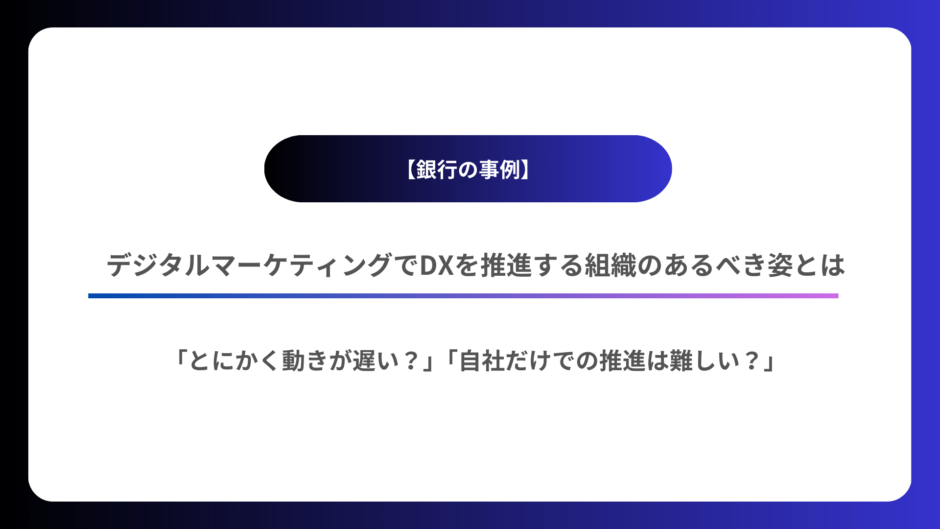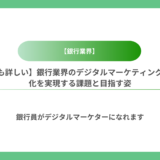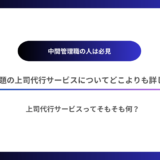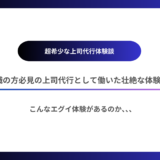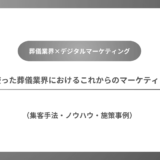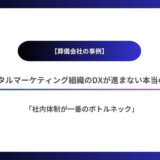皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本日は銀行の事例を元にデジタル組織のあるべき姿を「銀行内でマーケティングを推進していた担当が体験談を交えて」解説をしていきます。
- 1.銀行でデジタルマーケティング組織に属してる方
- 2.銀行で働いていて、デジタル推進をしなければならない方
- 3.デジタル推進が銀行内で遅れており外部の支援企業を探している方
銀行業界におけるデジタルマーケティングとDXの必要性
銀行業界は急速に変化するデジタル社会の波に対応しなければならない状況にあります。
フィンテック企業の台頭や顧客のデジタル志向の高まりにより、従来の対面型ビジネスモデルだけでは競争優位性を維持することが困難になっています。
しかし、銀行のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進は遅れがちであり、多くの組織がデジタルマーケティングの活用に苦戦しています。本章では「なぜ銀行のデジタル化が進まないのか」、その課題と可能性について解説します。
DX推進が遅れる銀行の現状|なぜデジタル化が進まないのか?
銀行業界におけるDX推進は一部の大手企業を除き、多くの組織で遅れています。
その要因として、まず挙げられるのがレガシーシステムの存在です。
日本の銀行の多くは、数十年前から運用されている基幹システムを使用しており、新しいデジタル技術との統合が難しい状況にあります。
これにより、データの一元管理やAPI連携などの近代的なシステム運用が難しくなり、デジタルマーケティングの高度化を妨げています。
また、DX推進に対する社内の抵抗も大きな課題です。
特に、上層部の多くがアナログ業務に慣れ親しんでおり、デジタルシフトの必要性を十分に理解していないケースが多く見受けられます。
「これまでの方法で問題なかった」という意識が根強く、新たなテクノロジー導入に対して慎重な姿勢を崩しません。
これが結果として、銀行のデジタルマーケティング戦略が停滞する要因となっています。
さらに、DX推進のための専門人材の不足も見逃せません。
デジタルマーケティングやデータ分析を推進するにはCRM(顧客管理ツール)やAIを活用できる専門知識が不可欠ですが、多くの銀行はそのような人材を確保できていません。
結果として外部の広告代理店やコンサルティング会社に依存しがちになり、内部にノウハウが蓄積されないままプロジェクトが進められることになります。
社内コンプライアンスがDX推進の足かせに?銀行特有の課題

顧客からすれば安心するかもしれませんが、銀行業界は他の業界と比べても厳格なコンプライアンス規制のもとで運営されています。
当たり前ですが個人情報の取り扱いや、金融商品の宣伝・販売におけるルールが厳しく設定されており、デジタルマーケティングを展開する際にもかなり慎重にならざるを得ません。(チェックフローがいくつもある場合もあります。)
例えばweb広告やKARTE等の接客ツール等でユーザーの行動データを基にしたターゲティング広告を行おうとすると「個人情報保護の観点から適切ではない」と判断されることが多く、施策の自由度が制限されてしまいます。
また、銀行内のコンプライアンス部門がマーケティング施策に対して強いチェック機能を持っていると、意思決定のスピードが遅くなるという問題もあります。
例えば、新たなデジタル広告キャンペーンを展開しようとしても、事前に何重もの承認プロセスを経なければならず、結果的に機会損失を生むケースが少なくありません。
さらに、内部監査やリスク管理の厳しさが影響し、デジタルツールの導入が制限されることもDX推進の障壁となっています。
(制限がされることに加えて、セキュリティ審査に時間がかかることが多いです)
マーケティングオートメーション(MA)ツールやCRM(顧客関係管理)システムを導入する際にも、「外部クラウドサービスのセキュリティリスク」を理由に導入が却下されることがあり、結果として業務効率化の機会を逃してしまうことになります。
デジタルマーケティングDXが銀行組織にもたらすメリット
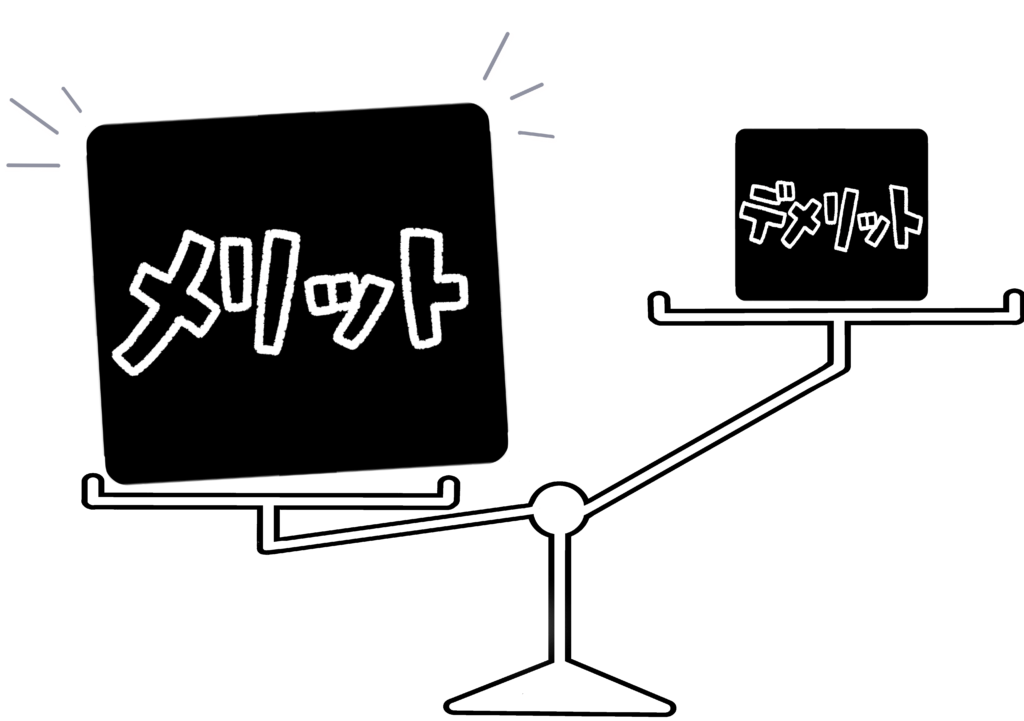
上記で記載したような課題や事情はありますが、銀行がデジタルマーケティングを活用してDXを推進することで得られるメリットは多岐にわたります。
まず、顧客体験の向上が挙げられます。
従来の銀行業務は窓口での対面対応や電話によるサポートが中心でしたが、デジタルマーケティングを活用することで、よりパーソナライズされた情報提供が可能になります。
例えば、シンプルな事案ですがチャットボットを活用することで顧客の問い合わせ対応を迅速化し、満足度を向上させることができます。
また、営業プロセスの効率化も期待できます。
デジタル広告やメールマーケティングを活用することで、銀行のサービスに興味を持つ潜在顧客を効率的に獲得し、CRMを通じて適切なフォローアップを行うことが可能になります。
特に住宅ローンや投資商品など、比較検討が必要な金融商品においてはデータ分析を活用したマーケティング戦略が大きな成果を生むことができます。
さらに、コスト削減の面でもメリットがあると言えます。
デジタル施策を強化することで、これまで人手に頼っていた業務を自動化し、効率化を図ることができます。
例えば、紙のDM(ダイレクトメール)に代えてデータを活用したパーソナライズドEメールを送ることで、コストを削減しながら効果的なマーケティングを実現することができます。
総じて、銀行業界におけるデジタルマーケティングのDX推進は顧客体験の向上、営業プロセスの最適化、業務効率化など、多方面でのメリットをもたらします。
しかし、そのためにはレガシーシステムの刷新、社内のデジタルリテラシー向上、コンプライアンスとのバランス調整といった課題を克服する必要があります。
銀行がこれらの課題に適切に対応し、デジタルマーケティングを最大限に活用することでDXの成功につなげることができるでしょう。
銀行のデジタル組織の課題とは?現場のリアルな悩み
銀行業界におけるデジタル変革は避けられないテーマですが、多くの金融機関ではその推進が難航しています。
本章では、銀行のデジタル組織が直面する現場のリアルな悩みについて詳しく掘り下げます。
変革を阻む「旧来型の組織体制」と「硬直的な意思決定」
銀行業界では長年培われたピラミッド型の組織体制がDX推進の大きな障害となっています。
意思決定がトップダウンで進められることが多く、デジタル変革を担う現場チームの裁量が極めて限定的です。
例えば、新しいマーケティングツールを導入したいと考えても、まず部門長の承認を得て、次に関連部署との調整を行い、最終的に経営層の決裁を経なければならないという煩雑なプロセスが存在します。
このようなフローではスピーディーな意思決定が求められるデジタル施策が機能しにくく、結果的に競争力が低下してしまいます。
また、多くの銀行では「失敗を許容しない文化」が根強く残っています。
DXは試行錯誤を繰り返しながら成長していくものですが、「前例のない取り組みは避ける」「ミスが許されない」といった文化が新しいチャレンジの機会を奪っています。
その結果、他の業界が次々とデジタルマーケティングの新しい手法を取り入れる中、銀行は旧来のマーケティング手法に固執し、顧客との接点を十分にデジタル化できていません。
DX人材が不足している|銀行におけるデジタル人材の確保が難しい理由

DXを推進する上で不可欠なのが、デジタル技術を理解し、適切な戦略を立案・実行できるDX人材の確保です。
しかし、銀行業界ではこのような人材の採用が非常に難しいのが現状です。
その理由の一つに、銀行業界特有の人事制度が挙げられます。
一般的に、銀行の人事制度は「総合職」としての採用が中心であり、専門性の高いデジタル人材を獲得するための施策が十分に整っていません。
そのため、データサイエンティストやマーケティングオートメーションの専門家といったDX人材が、銀行に魅力を感じることが少ないのです。
また、銀行は年功序列型の賃金体系を維持しているケースが多く、成果主義の報酬体系を好むデジタル人材にとっては、キャリアパスとしての魅力が薄れてしまいます。(働きやすさや専門性の観点からも銀行へ就職意欲が直結することが難しいこともあるようです)
さらに、銀行業務特有のコンプライアンスや規制の多さも、デジタル人材にとって参入の障壁になっています。
銀行は金融庁や日本銀行の規制を遵守しなければならないため、自由度の高いデジタル施策を打ち出しにくい環境にあります。
これにより、デジタルマーケティングの分野で活躍したい人材にとって、銀行は「制約が多く、スピード感がない業界」と映り、転職市場での競争力が低下しているのです。
人事異動の頻度が高すぎる?デジタル組織体制が安定しない理由
銀行のもう一つの特徴として、「定期的な人事異動」があります。これは、銀行全体の業務を幅広く経験させるという目的で行われていますが、デジタル組織にとっては逆効果になっていることが多いのが実情です。
(銀行にも寄りますが中途の専門職で入社した方は異動は対象外となることが多いようです)
例えば、デジタルマーケティングの専門知識を身につけた銀行の担当者が数年で別の部署に異動してしまうと、チーム内にノウハウが蓄積されにくくなります。
新しく配属された担当者はまた一から学び直さなければならず、結果的にDX推進のスピードが落ちてしまいます。これは、銀行全体でDXに対する専門職制度が確立されていないことが原因の一つです。
また、頻繁な人事異動により、「デジタル領域の専門性を深めたい」と考える社員が銀行を離れてしまうケースもあります。
長く同じ分野で経験を積むことで市場価値を高めたいと考えるデジタル人材にとって、銀行のような流動的な人事制度はキャリア形成の妨げになり得るのです。
そのため、優秀なデジタルマーケティング人材が定着しにくく、「いつまで経ってもデジタル組織が成熟しない」という課題を抱えています。
デジタル投資のハードル|ROIの見えにくさが導入を遅らせる
銀行がデジタル投資に慎重になる理由の一つに、「ROI(投資対効果)が見えにくい」という点があります。
デジタルマーケティングやDX施策は短期間で即効性のある成果が出るものばかりではなく、長期的な視点での取り組みが求められます。
しかし、銀行は伝統的に短期間での業績向上を求める文化が根付いており、数年後の成果を見越した投資判断が難しいのです。
例えば、データドリブンマーケティングを導入するためのCDP(カスタマーデータプラットフォーム)構築や、AIを活用したパーソナライズドマーケティングの実装は、初期投資が大きく、すぐに明確な利益につながらないことが少なくありません。
このため、経営層の理解を得にくく、「現状のやり方で十分」という判断が下されるケースが多くなります。
また、デジタルマーケティングのROIを正しく測定できるスキルセットが社内に不足していることも問題です。
KPIの設定や分析手法が確立されていないと、投資効果を説明できず、結果的にデジタル戦略が軽視されてしまいます。
このように、銀行業界ではデジタル投資を正しく評価するための体制が整っておらず、デジタル化の遅れにつながっているのです。
銀行のデジタル組織が直面する課題は、旧来型の組織文化、専門人材の不足、頻繁な人事異動、ROIの不透明性など、多岐にわたります。
これらの課題を解決するためには、専門職制度の導入、デジタル人材の採用強化、データドリブンな経営判断の促進といった改革が求められています。
銀行業界が本格的なDXを推進するためには、単なるシステム導入にとどまらず、組織全体の意識改革が不可欠です。
銀行のDXを加速させるためのデジタルマーケティング戦略|組織改革
銀行業界におけるDX推進はもはや選択肢ではなく今後5年10年に渡って必要不可欠な取り組みです。
しかし、多くの銀行では組織体制や人材の問題により、デジタルマーケティングの活用が思うように進んでいません。
本章では銀行がDXを加速させるためのデジタルマーケティング戦略と組織改革のポイントについて解説します。
デジタル専門チームの設置|銀行内のDX推進体制の構築方法
銀行のDXを成功させるためには明確なミッションを持つデジタル専門チーム・組織の設置が不可欠です。
従来の銀行の組織体制ではマーケティング、営業、ITがそれぞれ独立しており、デジタル施策が断片化しがちでした。
これを解消するためには、デジタル戦略を統括する専門チーム(デジタルハブとなるような部門)を設立し、各部署を横断的に連携させることが重要です。
(既に多くの企業・銀行においてもこのデジタルを一括で管理する部門が創設されていることが多いです)
さらに、経営層の理解を得るためのDX推進会議等を定期的に開催し、デジタル戦略の進捗や成果を可視化することも重要です。
デジタル専門チームは単なる施策実行部隊ではなく、銀行全体のDXをけん引する役割を担うべきです。
DX推進のカギを握る「デジタル戦略部門」の役割と設計
DXを本格的に推進するためには銀行内にデジタル戦略部門を設立することに加えてその役割を明確に定義する必要があります。
(この役割が明確に定義できていないと事業部門との連携が上手く取れず、単なるデジタル保守・管理機能としての役割に留まってしまう社内からの見え方になってしまいます)
このデジタル統括部門は単なるIT部門の延長ではなく、ビジネス視点を持ったDX推進のハブとして機能するべきです。
デジタル戦略部門の主な役割として、以下の点が挙げられます。(一例としてご紹介)
- データ活用戦略の策定:顧客データの統合・分析を行い、銀行サービスのパーソナライズ化を推進する。
- デジタルマーケティング施策の立案・実行:SEO、広告運用、コンテンツマーケティングなどを統括し、顧客獲得の効率化を図る。
- 社内のデジタルリテラシー向上:各部門のDX理解を促進し、デジタル施策を円滑に進めるための教育プログラムを実施する。
デジタル戦略部門の設計においては、従来の銀行業務とデジタル領域のバランスを取ることが重要です。経営層と現場の橋渡し役となることで、DX推進のスピードを加速させることができます。
デジタルマーケティングを成功させるための人材配置とチーム編成
そしてデジタルマーケティングを銀行に根付かせるためには、適切な人材配置とチーム編成が不可欠です。
銀行ではマーケティング部門とIT部門が分断されていることが多く、連携不足が課題となります。
そのため、デジタルマーケティングを推進するためには、両部門を横断するハイブリッド型の組織設計が求められます。
例えばデジタルマーケティングチームを「データ分析」「広告運用」「UX改善」「CRM戦略」などの専門分野ごとに分け、それぞれのスキルを活かせる環境を整えることが重要です。(多くの銀行はこの役割を代理店に依存しているケースが多いですが、
銀行のデジタルインハウス化は
プロストイックに事例実績が豊富です
外部パートナーの活用|代理店依存から脱却するためのバランスとは
銀行のデジタルマーケティングにおいては広告代理店やコンサルティングファームとの協業が一般的ですが、過度な依存はDXの自走力を低下させるリスクがあります。
代理店に丸投げするのではなく、戦略設計等一定部分は銀行内で行い、実行支援や運用を外部パートナーに任せる等バランスを取ることが重要です。
具体的には以下のような役割分担を考えるべきです。
- 銀行側:データ管理、顧客インサイトの分析、長期的なDX戦略の策定
- 外部パートナー:広告運用の最適化、マーケティングオートメーションの導入支援、最新技術の提供
このように役割を明確にすることで、銀行内にデジタルノウハウを蓄積しながら、外部の専門知識を最大限に活用することができます。
「銀行×デジタル人材」のミスマッチを防ぐために必要なこと
組織を創る上で人材の確保も必要不可欠な取り組みです。
銀行がデジタル人材を確保し定着させるためには「銀行文化」と「デジタル人材の働き方」のギャップを埋める取り組みが求められます。
多くの銀行では従来の年功序列や終身雇用の考え方が根強く、成果主義を重視するデジタル人材との価値観の違いがミスマッチを生む原因となっています。
これを解消するためには、キャリアの明確化と柔軟な働き方の導入が必要です。例えば、以下のような施策が考えられます。
- デジタル専門職のキャリアパスを整備し、長期的な成長を支援する。
- フレックスタイム制度やリモートワークを導入し、デジタル人材が働きやすい環境を整える。
- 成果ベースの評価制度を導入し、デジタル人材のモチベーションを向上させる。
これらは今日・明日でできる取り組みではないですがこうした取り組みにより、銀行におけるデジタル人材の定着率を高め、持続的なDX推進に繋がる取り組みの一例です。
デジタル組織事例 | COE機能の役割を担う銀行のデジタル部門
では上記で記載したようなデジタル・DX推進をしていくデジタル部門の役割としてどういったデジタル戦略があるのか具体的な例を交えて解説していきます。
銀行以外にも企業で導入されている事例は多いですが近年、銀行業界においてもデジタルマーケティングやDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するために、COE(センター・オブ・エクセレンス:Center of Excellence)という概念が注目されています。
COEとは企業内で特定の分野における高度な専門知識や技術を集約し、組織全体の業務改善やイノベーション推進を担う専門部門のことを指します。
銀行のデジタル部門がCOEの役割を担うことで、デジタル戦略の立案から実行、社内のデジタルリテラシー向上まで、さまざまな面で組織を支援することが可能になります。
銀行のデジタルCOEが担う主な役割
銀行におけるCOEの役割は多岐にわたりますが、主に以下のようなミッションが求められます。
- デジタル戦略の立案と推進
COEは銀行のDX戦略全体を統括し、マーケティング、IT、営業、カスタマーサポートなどの各部門と連携しながら、デジタル化を加速させる役割を担います。特に、デジタルマーケティングの最適化や、データドリブンな意思決定の推進などが重要な業務となります。 - データ分析と活用の支援
銀行が持つ膨大な顧客データを活用し、マーケティング施策の効果測定や、顧客の行動分析を行うのもCOEの役割の一つです。AIや機械学習を活用したパーソナライズドマーケティングの推進や、リアルタイムでのデータ分析により、より高度な金融サービスの提供が可能になります。 - 社内のデジタルリテラシー向上
銀行業界はレガシー(伝統的)な業務プロセスが根強く残っているため、デジタルスキルの格差が大きいことが課題です。COEは、研修プログラムの設計や、各部門に対するデジタル化のサポートを行うことで、組織全体のデジタルリテラシーを向上させる役割を果たします。 - 新技術の導入と実証実験(PoC)
フィンテック企業との連携やブロックチェーン、AI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの最新技術を導入する際、COEはその導入計画を策定し、実証実験(PoC)を主導します。特に、新しいデジタルサービスの開発や、オープンバンキング戦略の推進において、COEの存在が重要になります。
銀行COEの取り組み事例
一部の大手銀行ではデジタル部門をCOE化し、DXを加速させる取り組みが進んでいます。例えば、あるメガバンクではデジタルCOE機能をもつ部門を設立し、以下のような施策を展開しています。
- AIを活用した顧客対応の自動化:チャットボットやボイスボットを導入し、顧客対応の効率化を実現。
- データ分析基盤の構築:CRM(顧客関係管理)と連携し、顧客ごとに最適な金融商品を提案。
- デジタル人材育成プログラムの導入:社内のデジタルリテラシー向上を目的としたトレーニングの実施。(インナーマーケティング)
このように、銀行のデジタル部門がCOEの役割を担うことで、DX推進のスピードを加速し、組織全体のデジタル競争力を高めることが可能になります。
今後、デジタルマーケティングのさらなる高度化が求められる中で、銀行におけるCOEの重要性はますます高まるでしょう。
COEと堅苦しい表現をしていますが、実際は会社全体のデジタルを統括して推進できる役割の部門を設置すべきという概念になります。
大きな違いとしてはデジタル回りを「保守・管理」だけせず社内に浸透させることを役割としているのでどちらかというと「推進」をすることに重点を置いています。
銀行のCOE方針策定は
プロストイックが得意です
銀行組織の管理職やリーダーが推進したいデジタル施策
銀行業界ではデジタルマーケティングの活用が急務となっており、特に管理職やリーダー層にはDX推進の責任が求められています。
しかし、現場には依然としてアナログな業務プロセスや縦割りの組織体制が根強く残っており、スムーズなデジタル化が進まないケースも少なくありません。
本章では、銀行組織の管理職が推進すべきデジタル施策について解説します。
前提 | デジタルマーケティングに適した銀行の組織体制とは?
銀行がデジタルマーケティングを本格的に導入するためには、それに適した組織体制を構築する必要があります。
従来の銀行組織ではマーケティング、営業、IT部門がそれぞれ独立しており、情報共有や意思決定のスピードが遅くなる傾向にありました。
この課題を解決するために、先ほども提唱をした組織横断型のデジタル推進チームを設置し、マーケティング・IT・営業の各部門が連携しながら施策を進める体制を整えることが重要です。
以下は一例の組織構成と役割分担。
- マーケティング部門:広告運用、SEO、SNS戦略の立案・実施
- IT部門:データ管理、AI分析、マーケティングオートメーションの導入
- 営業部門:デジタル施策の結果を活用し、営業活動を最適化
このようなチーム体制を構築することで銀行全体のDX推進を加速させ、デジタルマーケティングの効果を最大化することができます。
銀行が取り組むべきデジタルマーケティング施策(広告・SEO・SNS・サイト改善)
銀行がデジタルマーケティングを推進するうえでまず着手すべき施策には、広告運用・SEO対策・SNSマーケティング等が挙げられます。
このデジタル施策は代理店へ丸投げをしている銀行様が多いですが、自社で実施をしないとノウハウが自社に貯まらないし何より自分達のデジタルスキルが向上しません。
プロストイックは銀行様のインハウス化実績もございますのでぜひ事例などを知りたい方はお問い合わせ頂ければ幸いです。
1. 広告運用(リスティング・ディスプレイ広告)
銀行の商品やサービスを効率的に訴求するために、Google広告やSNS広告を活用することが有効です。
特に、ターゲティング精度を高めた広告配信を行うことで、適切な顧客層にリーチできます。
2. SEO対策(検索エンジン最適化)
銀行業界ではローン、資産運用、クレジットカード、定期預金、金銭信託など、ユーザーが検索するキーワードに最適化したコンテンツを用意することが重要です。
たとえば、「住宅ローンの金利比較」「初心者向け資産運用ガイド」といったテーマの記事を作成し、検索流入を増やす施策が考えられます。
3. SNSマーケティング
X(旧Twitter)やtiktokなどのSNSを活用し、銀行のブランディングやユーザーとのコミュニケーションを強化することも有効です。
特に、若年層向けに金融リテラシーを高めるコンテンツを発信することで、新規顧客の獲得につなげることができます。また銀行が発信している情報ということもあり安心感が生まれます。
上司代行・外部リソース活用でデジタルスキルを補完する
銀行業界ではデジタルマーケティングの専門知識を持つ人材が不足しているケースが多く、社内リソースだけでは十分な施策を実行できないことが課題となっています。
この問題を解決するために、上司代行や外部リソースの活用が効果的な手段となります。
上司代行の活用
デジタルマーケティングの専門知識を持つ外部人材を一時的に管理職として迎え入れ、デジタル戦略の立案やプロジェクト推進をサポートすることができます。上司代行を導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 即戦力となる人材を確保できる:正社員採用ではなく、契約ベースで経験豊富な人材をアサインできる。
- 社内のデジタルリテラシー向上:外部の専門家がノウハウを提供し、銀行内のデジタルスキルを底上げできる。
- プロジェクト推進のスピード向上:デジタル施策の実行力が高まり、成果が出るまでの時間を短縮できる。
デジタルマーケティングの
現場管理職支援なら
プロストイックが強い
現場のデジタルリテラシーを底上げする教育・研修の重要性
デジタルマーケティングの施策を継続的に成功させるためには、現場のデジタルリテラシーを向上させることが不可欠です。銀行業界では、デジタル施策の理解が不足しているために、現場レベルでの導入が進まないことが課題となっています。
効果的なデジタル教育・研修プログラムを導入することで、以下のような成果を期待できます。
- 社員のデジタル活用力向上:基本的なデジタルツールの使い方やデータ分析手法を学ぶことで、業務の効率化が進む。
- デジタルマーケティングの理解促進:広告運用、SEO、SNSマーケティングの基礎を学び、実践的な知識を習得できる。
- DX推進の社内文化醸成:デジタル施策の重要性を理解し、積極的にDXを推進する風土が根付く。
また、デジタル教育を実施する際には、経営層・管理職・現場社員の全員が参加できる研修を設けることが重要です。
経営層がデジタルの重要性を理解し、管理職が適切に指導できる環境を整えることで、組織全体のデジタルリテラシーを底上げすることができます。
銀行業界がデジタルマーケティングを成功させるためには、組織体制の最適化、適切なデジタル施策の実施、上司代行・外部リソースの活用、デジタルリテラシーの向上が不可欠です。
管理職やリーダーが率先してDX推進をリードし、現場の意識を変えていくことで、銀行全体の競争力を高めることができるでしょう。
【事例紹介】デジタル化を成功させた銀行の具体的な取り組み
銀行業界におけるデジタル化の成功事例はDX推進のヒントを得るうえで非常に重要です。
本章では①代理店依存から脱却し内製化を実現した銀行、②デジタル組織体制の変革によってDX推進を加速させた銀行、③そして人事異動の影響を抑えつつ上司代行を活用し人材不足を解消した銀行の3つの成功事例を紹介します。
事例①:代理店依存から脱却し、内製化を実現した成功例
ある地方銀行は長年にわたりデジタルマーケティングの運用を外部の広告代理店に完全依存していました。しかし、代理店に任せきりの状態が続いたことで、広告のパフォーマンスが低下し、銀行側にノウハウが蓄積されないという問題が発生していました。加えて銀行員の方も代理店に丸投げ状態のため、自分達でデジタルスキルを培おうとしていなかった状態です。
この銀行はデジタルマーケティングの内製化を決断し、以下の3つの取り組みを実施しました。
- デジタル専門チームの設立
マーケティング部門内に、SEO・広告運用・データ分析を専門とする小規模なチームを編成。(ただ銀行内業務とは兼務) - 社内研修とスキルアップ支援
外部講師を招き、デジタル広告の基礎から運用最適化までを学ぶ研修を実施。 - 段階的な内製化の推進
最初は代理店と並行して運用し、徐々に自社運用へ移行する戦略を取ることでスムーズな移行を実現。
結果として、この銀行は広告運用コストを30%削減し、ROI(投資対効果)の向上に成功しました。
また、マーケティングチームが自ら運用データを分析できるようになり、PDCAを回すスピードが向上しました。
体験談としてお話をすると、銀行員の方も通常業務があり基本的には多忙です。なので、広告運用業務は基本的に自動化できるものは自動化する、平準化するものは平準化するなどのご支援を行っています。
加えてインハウス化支援の特徴はノウハウを貯めてから業務フローを整備するということです。結果が伴わないときに何が原因となりうる可能性があるのか。成果が出ている時に配信量を増やしてより獲得を強化していくのか。など判断軸まで平準化することが当社プロストイック支援の特徴です。
事例②:DX推進を加速させた組織体制の変革事例(インナーマーケティング)
あるメガバンクはDXの推進を掲げながらも、組織内における「縦割り文化」が障害となり、思うようにデジタル化が進まない状況にありました。一例を挙げるとデジタル部門とIT部門の連携不足が顕著で、顧客データの一元管理が困難な状況もありデジタル活用が他事業部、現場へ降りてきていない状況が続いていました。
この問題を解決するために、銀行は次のような組織体制の改革を行いました。
- 他部署連携のチームを設立
マーケティング、IT、営業の各部門から選出されたメンバーで構成されるDX推進チームを設置。(相互に部署間で連携できるようにするため) - インナーマーケティング(社内デジタル啓蒙)
各部門でデジタル活用したい内容の洗い出しやプラットフォーム(マイクロソフト環境を中心としたナレッジ蓄積や情報収集のためのポータルサイト)を整備
組織改革の結果、異なる部門間の連携が強化され、DX推進が加速しました。各部門の連携と各事業へのパイプ役を設置することでニーズの把握やスピード感のある連携が実現できます。
事例③:人事異動の影響を抑えて上司代行を活用し、人材不足を解消した事例
ある銀行では、頻繁な人事異動によって管理職の入れ替わりが激しく、デジタル戦略の一貫性が保てないという課題を抱えていました。
特に、マーケティング担当者が変わるたびに、施策の方向性がリセットされてしまい、業務の継続性が確保できない状態でした。
こちらの銀行は問題を解決するために上司代行サービスを活用し、デジタルマーケティングの継続性を確保しました。
- 上司代行の導入
デジタルマーケティング領域に精通した外部のプロフェッショナルを上司代行を(中間管理職のサポート役として)導入。現場のマネジメントや意思決定の手前までに必要な材料を集めて管理職業務を循環させることに従事。 - ノウハウの蓄積と共有
上司代行が施策の戦略立案を担当し、マーケティングの知見を社内に蓄積する仕組みを構築。 - 人事異動の影響を最小化
異動後の新任管理職がスムーズに業務を引き継げるよう、ドキュメント化されたマーケティング戦略を残す体制を確立。
具体の体制としては中間管理職の方のサポート役として1名、現場に近いリーダーや実行役の2名体制で支援を行っています。
この取り組みによって、銀行は人事異動の影響を抑えながら、デジタルマーケティングの継続性を確保することができました。
また、上司代行によるサポートを受けることで、社内のマーケティング担当者が短期間でスキルアップし、将来的には内製化を進めることが可能になりました。
銀行業界におけるデジタルマーケティングの成功事例を見ると、内製化の推進、組織改革、上司代行の活用が重要なポイントであることがわかります。
単にツールを導入するだけでなく、組織体制の整備やスキルの蓄積を並行して進めることで、持続可能なデジタル戦略を構築できます。
今後、銀行がDXを推進する上で、これらの成功事例を参考にしながら、最適な施策を検討することが求められるでしょう。
まとめ|銀行のDX推進とデジタルマーケティングの未来
デジタル化の波が金融業界にも押し寄せる中、銀行は従来の業務モデルを見直し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することが求められています。
最後にデジタルマーケティングを活用することで銀行が得られる競争優位性、DX成功のために今すぐ取り組むべきアクション、そして未来の銀行像について解説します。
デジタルマーケティングを活用することで銀行が得られる競争優位性
デジタルマーケティングは銀行が顧客との関係を強化し、収益性を向上させるための重要な手段です。
従来の対面営業や紙媒体中心のプロモーションだけでは、デジタルネイティブ世代にリーチすることが難しくなっています。
デジタルマーケティングの活用により銀行は単なる金融機関から「デジタル金融サービスプロバイダー」へと進化することが可能となります。
DXを成功させるために、銀行が今すぐ取り組むべきアクション
これまでのまとめとなりますが、銀行がDXを成功させるためには単なるデジタルツールの導入にとどまらず、組織改革や人材戦略の見直しが不可欠です。今すぐ取り組むべきアクションとして、以下の3つが挙げられます。
- デジタル専門チームの設立と育成
DX推進のためには、デジタルスキルを持つ人材が必要不可欠です。外部からの採用に頼るだけでなく、既存の社員をデジタルマーケティングやデータ分析に精通した人材へと育成する仕組みを整えることが重要です。定期的な研修やオンライン学習プログラムの導入、専門部署の設立などが効果的なアプローチとなります。 - 経営層の意識改革と組織全体のデジタルシフト
DXを推進する上で大きな壁となるのが「旧来型の意思決定プロセス」です。経営層がデジタルの重要性を理解し、DXを企業の戦略の中心に据えることが不可欠です。また、デジタル施策を各部署の部分最適ではなく、全社戦略の一環として推進する体制を整えることが求められます。 - 外部パートナーとの連携強化
銀行単体でDXを推進するには限界があります。テクノロジー企業やフィンテック企業、上司代行サービスなどの外部パートナーと連携し、専門知識を活用しながらデジタルシフトを進めることが、効率的かつ持続可能なDX推進につながります。
これらのアクションを迅速に実行することで、銀行はデジタル化の波に乗り遅れることなく、競争力を強化することができます。
未来の銀行像|デジタル組織の確立が生き残りの鍵となる
未来の銀行は、単なる金融サービスの提供者ではなく、顧客のライフスタイルに寄り添う「デジタル金融プラットフォーム」へと進化することが求められます。そのためには、以下のようなデジタル組織の確立が鍵を握ります。
- データドリブンな意思決定の標準化
これまで勘と経験に頼っていたマーケティング施策や経営判断を、データ分析を基盤としたアプローチにシフトすることが不可欠です。AIを活用した顧客分析や、自動化されたダッシュボードの導入により、リアルタイムでの意思決定が可能となります。 - 縦割りを打破する組織・チーム体制への転換
頻繁な人事異動や硬直的な組織体制がDXの足かせとなっている銀行は、よりアジャイルな組織運営へと転換することが必要です。プロジェクトベースのチーム編成や、部署間連携チーム・機能の導入など、社内の柔軟性を高めることで、デジタル人材の確保と定着を促進できます。 - 金融サービスのプラットフォーム化
これからの銀行は、単に融資や預金を提供するだけでなく、デジタル金融エコシステムの構築を進めることが求められます。例えば、フィンテック企業との連携によるスマートバンキングの実現や、APIを活用したオープンバンキングの推進などが挙げられます。 - 上司代行の活用によるマネジメント改革
デジタル変革を成功させるためには、組織の中間管理職が適切に機能することが不可欠です。しかし、DXの進展に伴い、伝統的な管理職の役割が変化してきています。ここで重要になるのが、上司代行サービスの活用です。上司代行を導入することで、デジタル領域の専門知識を持つプロフェッショナルが管理職の業務をサポートし、DX推進のスピードを加速させることが可能になります。
結論|銀行の未来はデジタル組織の確立にかかっている
銀行業界のDX推進は単なるデジタルツールの導入ではなく、組織全体の変革を伴う大きな挑戦です。
デジタルマーケティングを活用することで、銀行は新たな競争優位性を確立し、顧客との関係を強化することができます。また、DX成功のためには、組織体制の見直しや外部パートナーの活用など、多角的なアプローチが必要です。
そして広告代理店等に依存しているままではいつまでのデジタルスキルの蓄積、ノウハウは自社内に貯まりません。
未来の銀行はよりデジタルを活用してで柔軟な部署間連携を高めた組織へ変革し、デジタル金融のリーダーとしての地位を確立することが求められます。
そのために、今すぐ実行可能なアクションを積極的に取り入れ、デジタル時代に適応した組織づくりを進めていくことが不可欠です。
銀行内のデジタル組織強化
ならプロストイックへ
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック