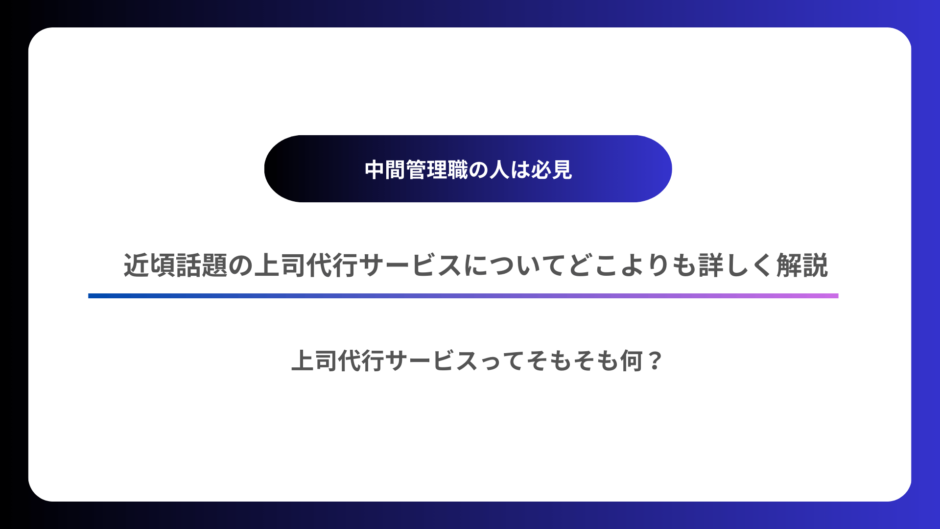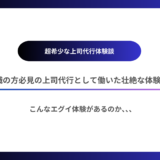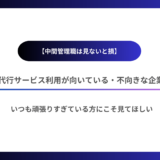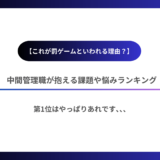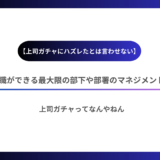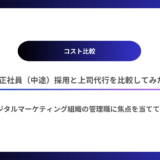皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本日はタイトルの通り、中間管理職(上司・プレイングマネージャー等)の方に向けて上司代行サービス(中間管理職支援)について解説していきます。
現在上司代行サービスについて多くの御依頼をいただいており、ご要望がございましたらまずはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
上司代行という言葉をどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、実態としてよくわからないという方が多いと思います。
今回はそう言った方々(主に中間管理職の方)に向けて詳しく解説をしていきます。
今回解説するのはあくまで当社プロストイックが支援している上司代行という形の支援内容・サービス内容となります
実は筆者も名前は違いますが、一部のクライアント様に「部長代理」としてオフィスにPCや社員証をお借りして業務をしていたことがありますので、その経験談もお伝えできればと思います。
体験談についてはこちらの記事で詳しくお伝えしていますのでぜひご覧下さい。
- 部下のマネジメントや上司からのプレッシャーに悩んでいる方
- 今現在プレイングマネージャーとして働いているが業務負荷が重くマネジメント業務ができていない方
- 上司代行に興味がある方
- マネジメントに関して相談できる相手がいない方
上司代行サービス(中間管理職支援)とは?
上司代行サービスとは一言で言ってしまえば
プレイングマネージャー化している管理職や部下の育成に手が回らないマネージャーを支援する”体制”を組織の中に構築して業務や体制を平準化する支援を行うものです。
後程も解説しますが、昨今進んでいるプレイングマネージャー化は一見「現場を理解していてキャリアもスキルもある管理職が現場を見てくれるから頼もしい」と思うかもしれませんが、これはあえて表現を大きく言えば「ドーピング」にすぎません。
プレイングマネージャー化によって上司がタスクを自身で行ってしまうと業務が属人化するばかりか難易度の高い業務はマネージャーがこなしてしまうので、部下のスキルが育ちません。そればかりか、本来すべき部下の育成・マネジメントに手が回らなくなるので、今は人手が足らないから仕方なくプレイングマネージャーをしているかもしれませんが数年後にはより組織が深刻化してしまいます。
この「上司を代行する」という概念・思想自体は潜在的に欲している方はいるものの「やりたくないけどやるか」「代わりにできる人もいないし」という状況で中間管理職を続けている方が多いとのことです。
補足をすると「上司代行」は上司の役割を代わりに担い今の上司が役割を降りるとか今の上司が降格する等というネガティブなものでは一切なく、今の上司(管理職)の方の右腕となる人材を組織の中に1~2名おいて目標達成に向けたアクション量を増やしたり・本来すべき業務に集中する体制を作ることです。(当社プロストイックの場合)
特に、業務の複雑化が進む現代の企業環境では中間管理職の役割が多くなり上層部と現場(部下)との間で板挟みになる方が多いとされています。
その点を解消するにあたって上司の役割を担える人材を活用することが、組織の効率化や心理的負担の軽減につながると期待されています。
中間管理職をサポートする新しい選択肢
中間管理職は現場の状況を理解しながらも経営陣の指示を遂行するという重要な立場にあります。
しかし、過剰な業務量や人間関係のストレスが彼らのパフォーマンスを低下させる要因となることも少なくありません。上司代行サービスはこうした課題を解決するための新しい選択肢として登場しているようです。
上司代行は一時的な支援にとどまらず、長期的な組織改善のきっかけとなるケースも増えています。
たとえば、プロジェクトの円滑な進行をサポートするために、経験豊富な専門家が現場でのリーダーシップを発揮することや若手社員の多くが管理職を敬遠する傾向がある中で、リーダー育成を支援する役割も果たします。
どんな場面で活用されているのか
当社プロストイックの事例では特に「人手不足が深刻な企業」や、「急速な組織拡大を進める企業」「人の入れ替わりが激しい企業」で導入が進んでいます。
たとえば、急な人事異動や退職で管理職が不在となった場合や特定のプロジェクトで専門性の高いリーダーが必要とされる場合などです。
また、組織内の人間関係に問題が生じた際にも、第三者としての視点を持つ代行者が介入することで良いクッションとなりハレーションの防止はもちろん、逆に組織文化を一緒に作ったり、現場の雰囲気を良くして生産性を上げることができます。
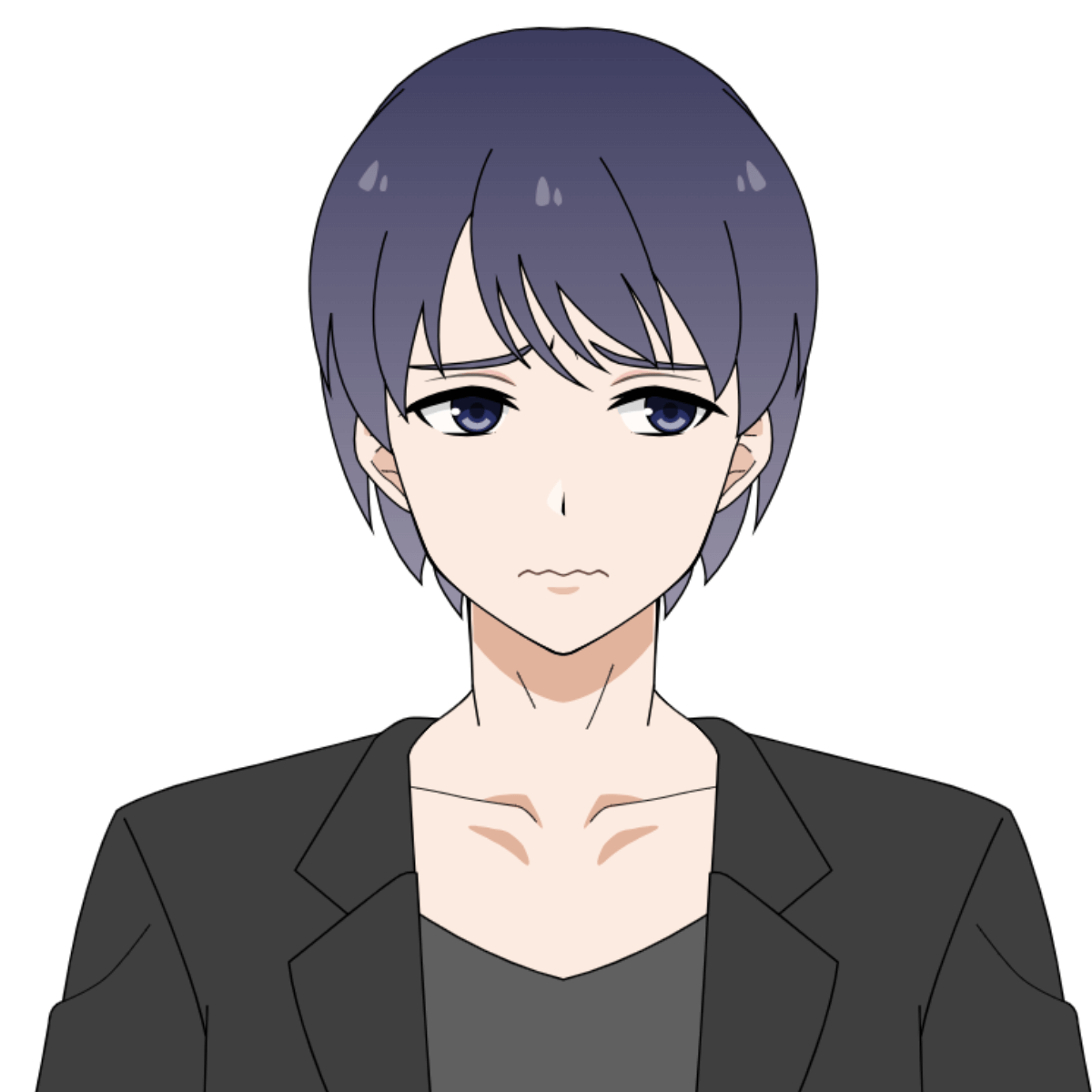
確かに何かうまくいかないときって新しい人入れて変わることも大きくありそうね
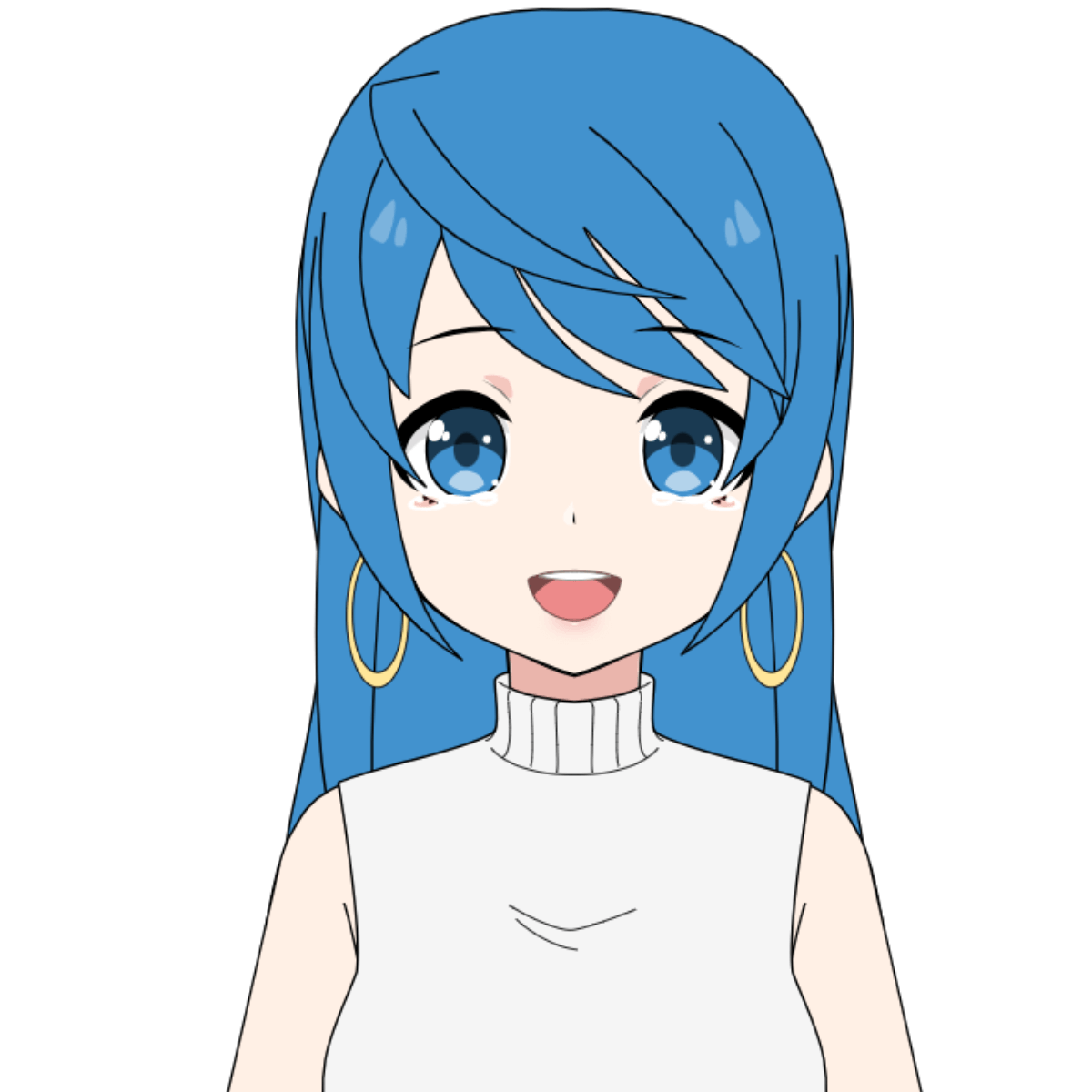
昨今AIが人の仕事を奪うと騒がれてるけどやっぱり組織における中心は人なんだわ
さらに、新しい働き方改革の流れを受けて、リモートワーク環境における管理職の負担を軽減する目的での利用も広がっています。これにより、従業員の満足度向上や生産性の向上といった効果も期待されています。
人を採用するだけが人手不足解決の選択肢ではない
従来、管理職や現場社員の不足を補うためには新たな人材を採用することが一般的でした。
しかし、採用には時間とコストがかかり、適切な人材を見つけるのも容易ではありません。ましてやミドル層となる中間管理職レベルの人材採用においては採用コストが300万円(給与とは別)を超えることもあります。
その点、上司代行サービスは即戦力となるプロを短期間で導入できるため、効率的な選択肢となります。
また、上司代行サービスを活用することで、既存の社員の育成や、組織内のマネジメント体制の見直しにもつながりボトルネックである人手不足の解決が可能です。これにより、長期的な組織の成長を支える基盤体制を築くことできます。
なぜ今「上司代行」(中間管理職支援)が求められているのか?
上司代行サービスが注目される理由のひとつには、働き方改革や多様化する職場環境の影響があります。
かつて「上司は育てられるもの」「現場を知る管理職こそが要」だと言われた時代から、働き方は大きく変わりました。
組織内の指揮命令系統における重要な役割を担いながら、部下に仕事を託したいけど「定時で帰りたいと言っている」「あまり過度なことをするとパワハラ・モラハラなどと言われる」「それで退職されたらさらに人手不足&自分の評価が下がる」「実は陰で上司ガチャ外れたとXでつぶやかれてる」などなど、多くの懸念があり心身ともに疲労困憊の方も多いようです。
急激な人員不足、世代間ギャップ、心理的安全性の重視。そんな時代において、経営上層部と現場社員の間で最も板挟みにされ、最も疲弊しているのが中間管理職です。
そこで人間関係の板挟み(マネジメント業務)や業務過多(プレイヤー業務)に苦しむ中間管理職を支援する新しい選択肢として上司代行サービスは注目されています。
特に、企業が人材不足に悩まされる中で、即戦力としての上司代行は貴重なリソースとなっています。
また、ストレスの多い現代の職場において、メンタルヘルスの重要性が高まる中、上司代行は中間管理職の心理的負担を軽減する有効な手段として認識されています。
(注意:コメントをいただいたので追記をしますが上司代行(中間管理職支援)は決して「上司の役割を放棄する」とか、「楽をするために逃げる」というネガティブなものではないですし、導入企業様の管理職をされている方々に一切そういった感情や狙いはないです。
むしろ深刻な人手不足によって数年後の組織図を思い描いたミッション・目標を達成するために奔走している中で即戦力を自分の部署の中に置き体制を組んで一緒に目標達成に向けて動いています。
中間管理職の負担増加が問題で上司が消滅しかけてる
昔は「早く出世したい」「給料を上げてお金を稼ぎたい」という意思を持つ方が多かったようですが、昨今では働き方も多様化していて
「定時で帰りたい」「責任取りたくないし出世したくない」「6時以降の趣味や副業に時間を費やしたい」
などで会社の若手社員の出世意欲が依然と比べて下がっているようです。
また「うちの課長、最近ずっと不機嫌なんです」「課長自身もつらそうなのに誰も助けてくれない」――そんな声を、企業の人事や部門長から頻繁に聞くようになり中間管理職が潰れかけている職場は少なくありません。
上司本人も組織を回しながら部下の育成、会議対応、上層部への報告、時にはクレーム処理やメンタルケアまで一手に抱えて疲弊しきっています。そんな状況で「うまくやれ」と言われても、無理な話です。
結果として、「せめて一時的にでも代わってくれたら…」「この上司に任せるのは今は厳しい」と、上司代行サービスを求める声が現場レベルで噴出しているのです。
中間管理職の業務量・ストレスが限界を超えている
マネジメント業務はただの“管理”ではありません。感情、対話、説得、育成、時に叱責と人間関係の総合格闘技とも言えます。そして現代の職場ではその複雑さに拍車がかかっています。
たとえばかなりディープな働き方をしている管理職の方の事例ですが、課長クラスが1人で10名以上の部下を持ち、週10本以上の会議をこなしながら、評価や業務進捗、採用面接まで担っていました。当然家に帰るのは深夜で土日も採用面接等で仕事をしていることも日常茶飯事でした。当然メンタルの不調も出始め、体調も崩しがちとなってしましました。このように管理職の健康リスクは現実の問題になっています。
中間管理職のストレスの質は「プレイヤー時代のような成果で自分を測れない不安」や、「上層部からの期待と、現場のリアルとのズレ」など、自分ではどうにもならない構造的な苦しみも多いです。
「上司ガチャ」「部下ガチャ」による職場のミスマッチ
3月、4月になるとSNS上でも賑わういわゆる「上司ガチャ」についてです。(まぁ上司からすれば部下ガチャともいえます)。
新入社員の間では「配属された上司によって運命が決まる」という意味で“上司ガチャ”という言葉が広まっています。
逆に、これも当たり前ですが管理職側も「この部下、どう扱えばいいのかわからない」という“部下ガチャ”に悩まされています。
これはつまり何が言いたいかというと、職場におけるミスマッチが増えているということです。
価値観の違い、働き方の期待値のズレ、言語化の難しい感情のすれ違い……。たった一人の不一致が、チーム全体の空気を悪くし、離職・パフォーマンス低下という深刻な問題を引き起こしています。
中規模・小規模の会社であれば採用面接時に直属の上司となる方と面接することでミスマッチの防止などを図れますが、大手企業となるとそうはいきません。
この「合わない関係性」を無理やり続けさせるのではなく、一度“代行者”というクッションを入れることで関係性をフラットする手段が、上司代行です。
適材適所が叶うまでのつなぎ役、信頼関係の再構築のきっかけとして、導入され始めている理由がここにあります。
部下と上司の板挟み状態とは?
中間管理職の典型的な悩みのひとつが、「部下と上司の板挟み状態」です。
彼らは部下の意見や要望を吸い上げつつ、経営陣の方針を現場に浸透させる役割を担います。
しかし、この両者の要求が必ずしも一致するとは限りません。
経営層からは「数字を出せ」「リスクを抑えろ」と言われ、部下からは「もっと聞いてくれ」「成長の機会がない」と求められる――その真ん中に立たされる苦しさは想像以上です。
その結果、板挟み状態となりストレスやモチベーションの低下を引き起こします。
たとえば、極端な例かもしれませんが部下が提案したプロジェクトが経営陣の意向にそぐわなくて却下された場合、中間管理職は部下のモチベーション調整、プロジェクトの代理進行、現場マネジメント、上層部からの「もっと現場のレベルを引き上げろとの命令」等に多くの時間とエネルギーを費やすことになります。
こうした状況が続けば、当然心がすり減ります。感情を押し殺してマネジメントを続ける管理職に、心からの指導はできません。この状態を打破するために、第三者的な「上司代行」という存在が求められているのです。
日本の中間管理職は役割が過多すぎる(構造的課題)
もっと広い範囲で見渡すと日本の中間管理職は他国と比べてその役割が過多であると言われています。
具体的には部下のマネジメントに加えて業務全体の進捗管理、経営層との連携、さらには現場作業までを一手に引き受けるケースが多いです。このような状況は「オーバーワーク」を招きやすく、結果的に中間管理職のメンタルヘルスや仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。
さらに、日本企業特有の年功序列文化や曖昧な役割分担が、管理職に対する負担を増加させている要因として挙げられます。
たとえば、全員が納得する意思決定プロセスを重視する文化があるため、中間管理職が調整役として過剰な時間と労力を割かなければならない場合が多いのです。
日本と海外の中間管理職の役割の違い
日本の中間管理職と海外のそれを比較すると、その役割や業務範囲に大きな違いが見られます。
たとえば、欧米諸国では、業務内容がより専門化されており、個々の管理職が担う役割が明確化されています。なので、定められた範囲でのみ責任を全うすることが組織構造として存在します。(いわゆるピラミッド型の組織構造ですね)
一方で、日本では「何でも屋」としての側面が強く、プレイングマネージャーとしての役割が強調され、自らも業務をこなしながら部下の指導や組織運営を行うことが求められ、困ったことや誰のタスク線引きがあいまいな場合にとりあえず中間管理職に仕事が降ってくることが少なくありません。←管理職なら一度は経験があるはずです。
この違いは企業文化や働き方の価値観にも起因しています。
欧米では、効率や専門性を重視する文化が根付いており、チーム全体で業務を分担する仕組みが整備されています。一方で、日本では調和や勤勉さが評価されるため、一人の管理職に過剰な期待が寄せられることが一般的です。
それゆえに、長時間労働や過重な業務負担が常態化しており、これが中間管理職のストレスやバーンアウトの原因となっています。実際、ロバート・ウォルターズ・ジャパンの調査によれば、日本の会社員の56%が職場でバーンアウトの症状を感じており、そのうち60%が私生活にも影響が出ていると回答しています。
プレイングマネージャー化により本来の業務ができない
先ほどからも口にしているように日本の中間管理職はプレイングマネージャーとしての役割を担うことが多く、自らも業務をこなしながら部下の指導や組織運営を行う必要があります。
このような状況ではマネジメント業務に十分な時間を割くことができず、部下の育成や組織の戦略的な運営が疎かになります。プレイヤーとしての業務もこなしながらマネージャーとしての部署の文化作りや戦略、社員の育成などをこなすことはほぼほぼ不可能です。
このような問題を解決するためには、業務の適切な分担や、マネジメント業務に専念できる環境の整備が求められます。
海外ではマネージャーとプレイヤーの役割が明確に分かれている
日本の企業ではプレイングマネージャーとして、マネジメント業務と実務の双方を担うことが一般的です。
しかし、特に欧米諸国ではマネージャーとプレイヤーの役割が明確に分かれています。マネージャーは戦略立案やチームの指導・育成に専念し、プレイヤーは専門的な業務に集中する体制が整っています。
このような役割分担によりマネージャーは組織全体のパフォーマンス向上に注力でき、プレイヤーは自身の専門性を高めることが可能となります。
つまりマネージャーはマネジメントの、プレイヤーは現場業務の専門性を役割をもって極めている(極められる)体制を取れているということです。
結果として組織全体の効率性や生産性が向上し、従業員の満足度も高まっています。
【現場の上司必見】若手社員が中間管理職を避ける理由
今、企業現場では「次の管理職がいない」という深刻な問題が広がり始めています。
↑この問題をかなり軽視している企業が多いですが、本当に数年後には深刻になります。
ベテランの上司や現管理職が退職しても、ポストを引き継ぐ人材が現れない。もしくは、推薦しても若手が明確に“断る”。その背景には、「中間管理職=罰ゲーム(仕事だけ増えて給料が上がらない)」というような、役職に対する否定的な認識が根付いているからです。
中間管理職を目指すことが前向きに評価されていた時代とは状況が大きく変わりました。特にZ世代の価値観とのギャップ、収入や働き方への疑問がその傾向を後押ししています。
では実際にどのような中間管理職の仕事が罰ゲームと感じることが多いのでしょうか。
その理由として挙げられる一番の理由は、「責任が重い割に見合った報酬や評価が得られない」といった不満です。また、ストレスフルな環境が、キャリア形成の妨げになると感じる若手も多いです。
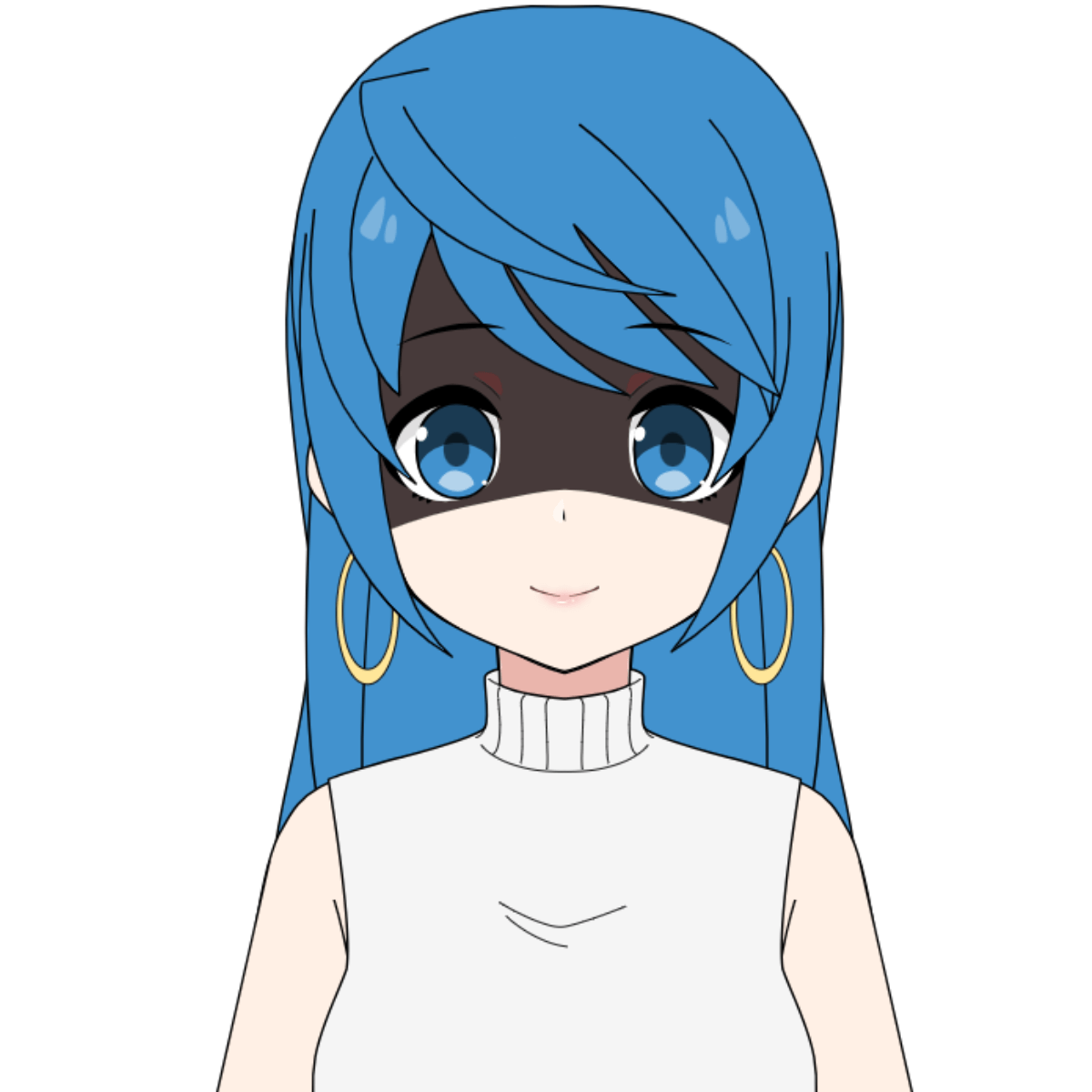
ふみと君、この記事がPV数伸びなかったらあなたの責任よ
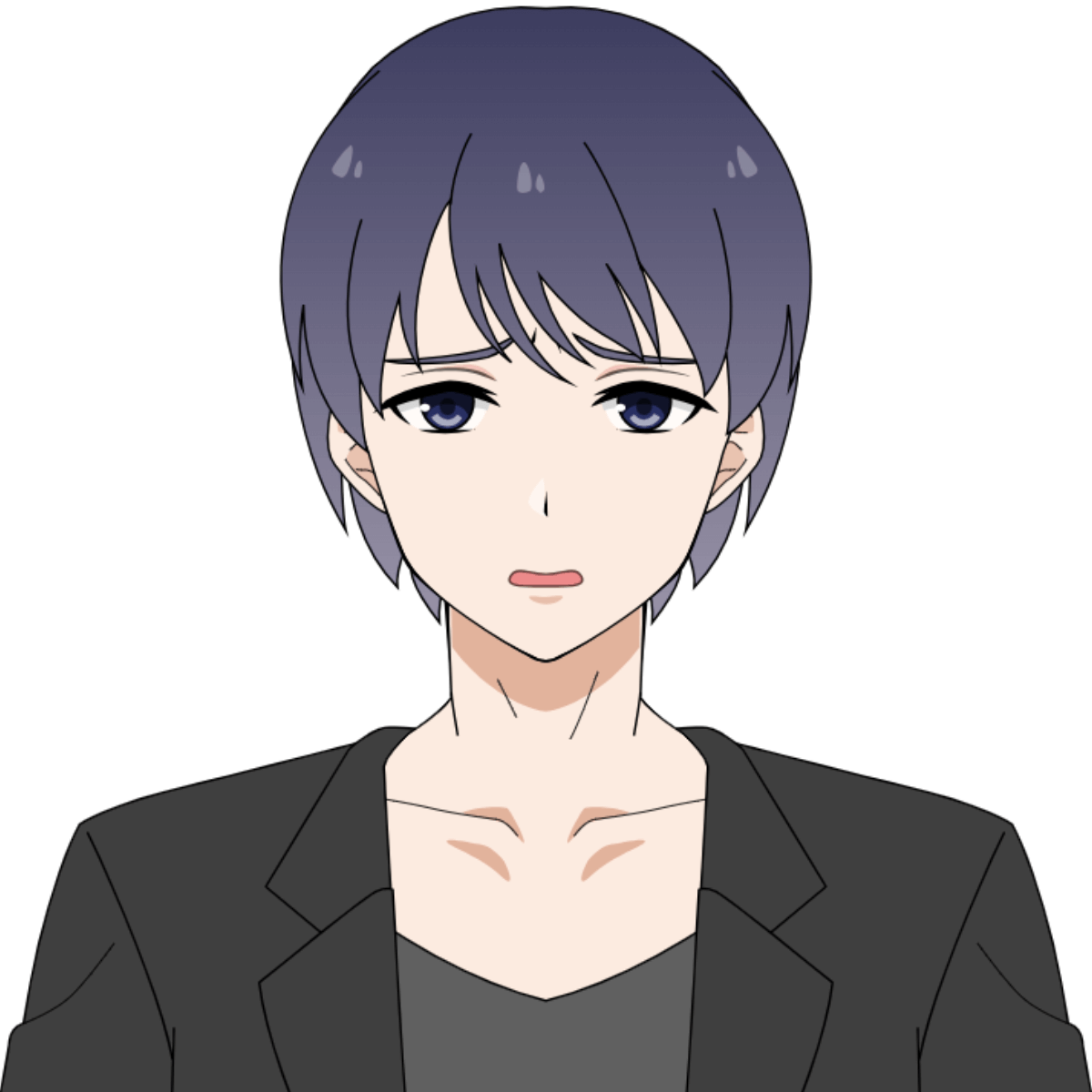
え、構成や執筆したのは僕じゃないですよ
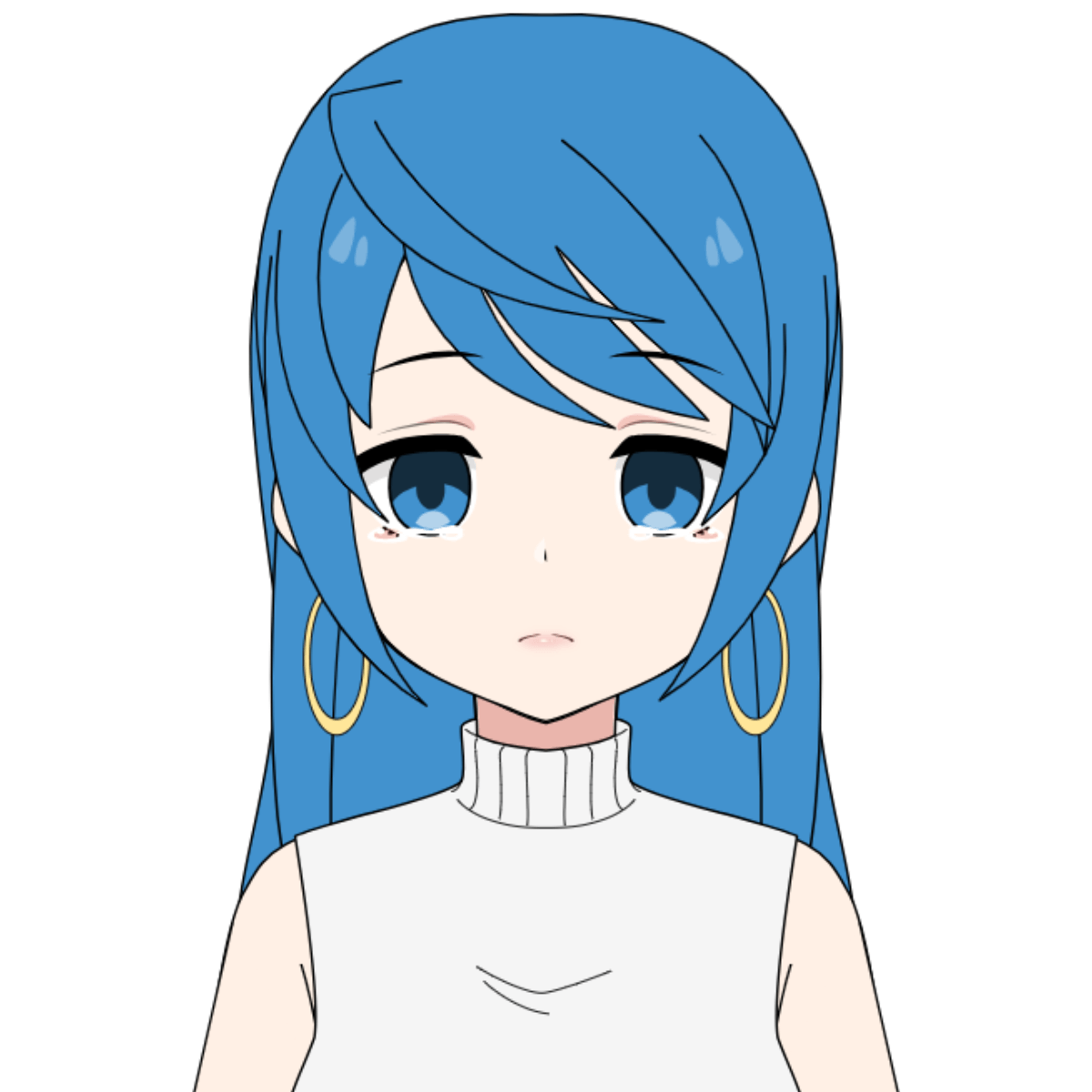
でもあなたが責任担当者よね
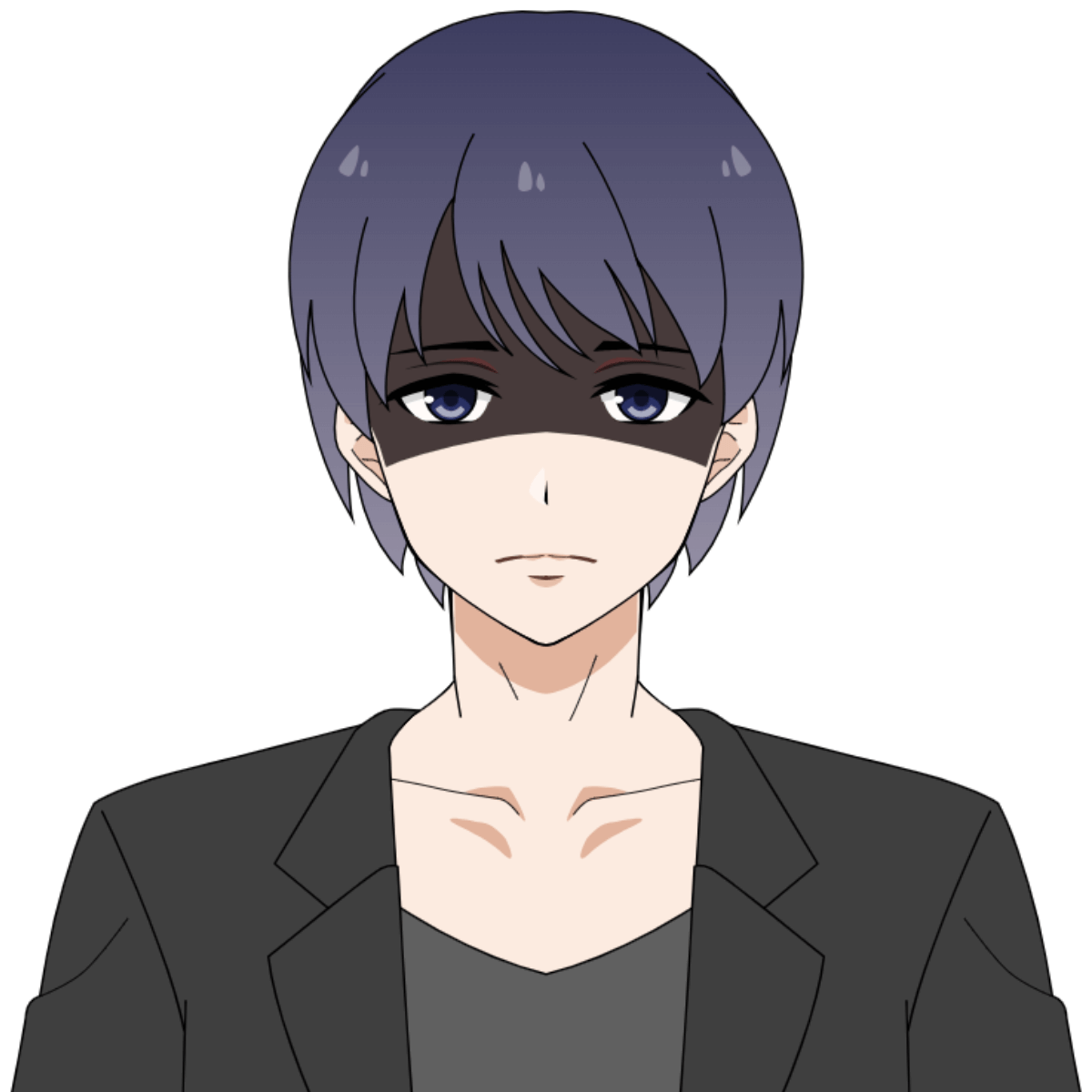
すいません、会社辞めていいですか
上記のやり取りはあくまで一例ですが、実際に現場でも起きているような例です。このような問題に対処するため、上司代行サービスは中間管理職が果たすべき役割を分担し、より魅力的な職場環境を提供するサポート(部署の文化作りやマネジメントサポート)を行っています。
この章ではなぜ若手が「上司」や「管理職」を避けるのか、その理由を現場目線で掘り下げていきます。
Z世代とミドル層の価値観ギャップ
Z世代(1990年代後半〜2010年生まれ)の多くは「仕事=生きがい」よりも「仕事=手段」と捉えています。彼らにとって大切なのは、評価よりも「自由度」や「自己裁量」、そして「心理的な負荷の少なさ」です。
一方でミドル層の管理職は組織への忠誠心や長時間労働を前提とした成果主義を経験してきた世代。プロパーで入社して転職せず生涯を最初に入社した会社で終えるという方も多いです。こうした違いが、日々の働き方の中でも顕著に現れています。
たとえばZ世代は「成長よりも自分らしさ」「指示よりも対話」を重視しますがミドル層の上司がその価値観に合わせられないと、関係がうまく築けません。
その結果「あんなふうにはなりたくない」と思われ、管理職が目指されなくなるのです。
これは決して若者の甘えではなく、時代背景と価値観のズレによるものです。
このズレを理解しないまま次期リーダーを育てようとしても、空回りするだけです。
中間管理職は罰ゲーム!?
「中間管理職は罰ゲーム」という表現を一度は聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この表現がSNSやメディアで話題になるほど、この「中間管理職」というポジションが抱えるプレッシャーは深刻です。
多くの中間管理職が業務過多や精神的な負担によって過度なストレス(場合によってはうつ病になり休職や退職)に陥るケースが増えています。
そして近年の若手社員からも「課長になりたい」「出世したい」と公言する若手は少なくなっており最近では「静かな退職」という言葉も流行ってきているようです。
静かな退職:必要な業務は行い何かを言われるまで何もせず定時まで密かに過ごすこと
若者にとって管理職に昇進することが「やりがい」よりも「負担」や「不安」の象徴になっているからです。
彼らにとって中間管理職とは
- 責任ばかり重く、裁量はない
- 上にも下にも気を使うだけで疲弊する
- 自分の仕事ができず、残業が増える
- 失敗すれば、矢面に立たされる
という“罰ゲーム”のような存在。現場でも「主任になった瞬間、仕事が倍になった」「課長になってからずっと寝不足が続いている」「課長になっても給料は上がらない」といった声がリアルに上がっています。
こうした実態を目の当たりにしている若手が「自分はそこには行きたくない」と感じるのはある意味当然です。
中間管理職が“魅力のない役割”に見えている限り、誰もそのポジションに手を挙げようとしないのです。
このような状況を改善するためには、業務の一部を外部に委託する柔軟な選択肢が必要です。上司代行サービスは、まさにこうしたニーズに応えるためにあります。
部下から見れば上司ガチャ・上司から見れば部下ガチャ
「中間管理職は罰ゲーム」と同様に「上司ガチャ」「部下ガチャ」という言葉も昨今横行していました。この言葉が示す通り、上司と部下の関係は必ずしも理想的な形で成立するわけではありません。
合う合わない上司・部下がそれぞれいるわけです。
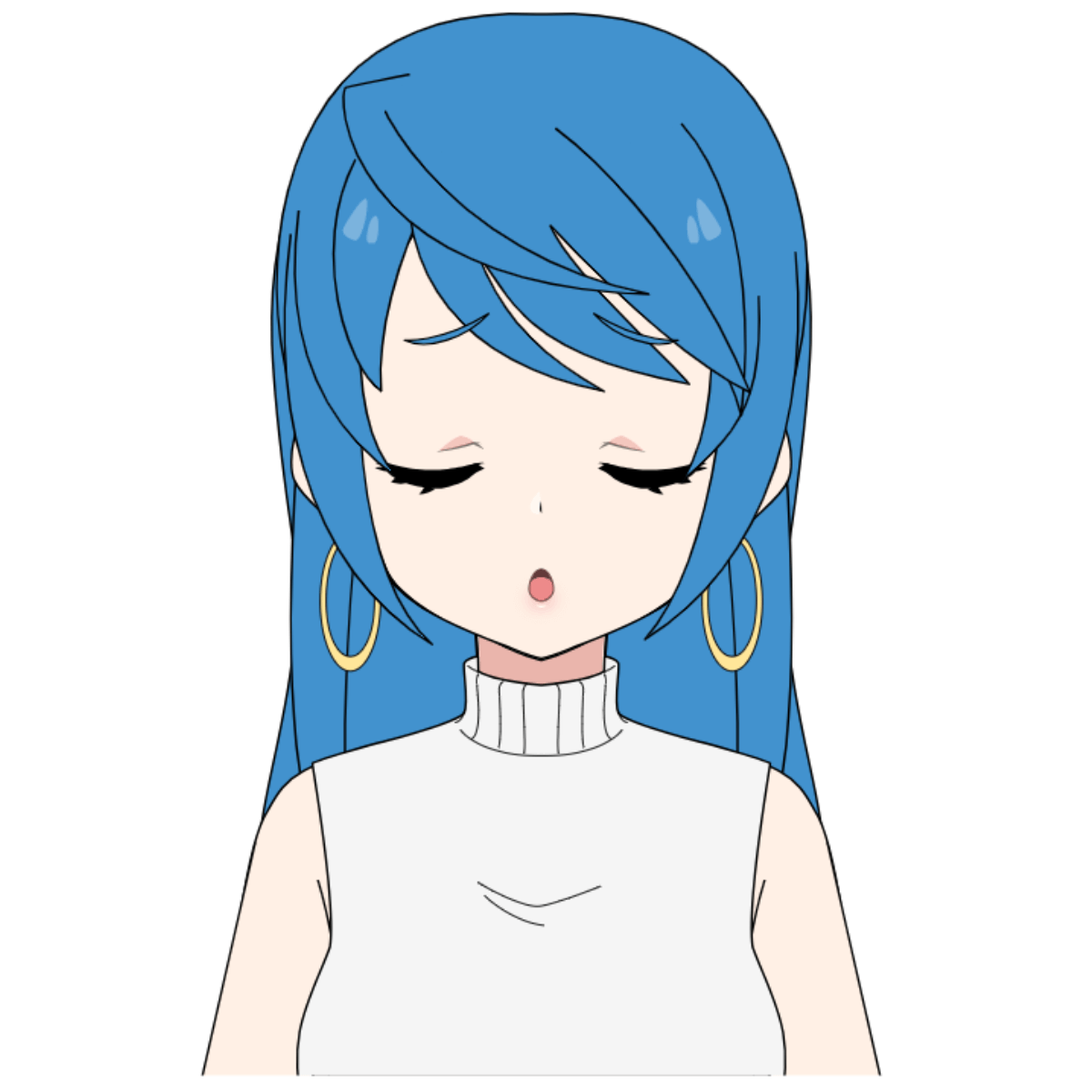
確かに私にだけ当たりが強い上司の人が昔いたわ
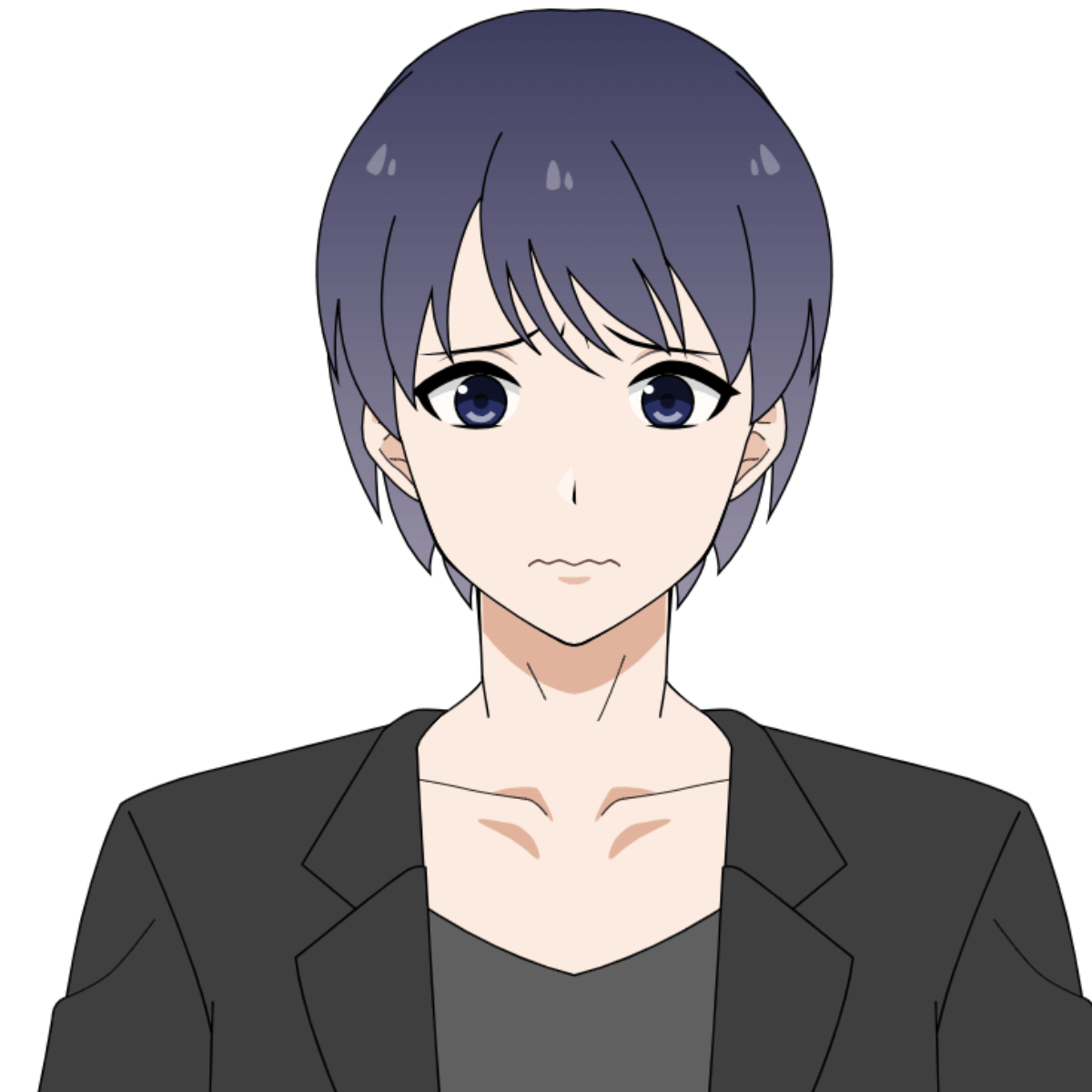
やっぱりどこにでもいるんですよね
このミスマッチが原因で、職場の雰囲気が悪化するケースもあります。
上司代行サービスはこのような課題を解決し、職場の調和を保つための有力な手段として機能します。
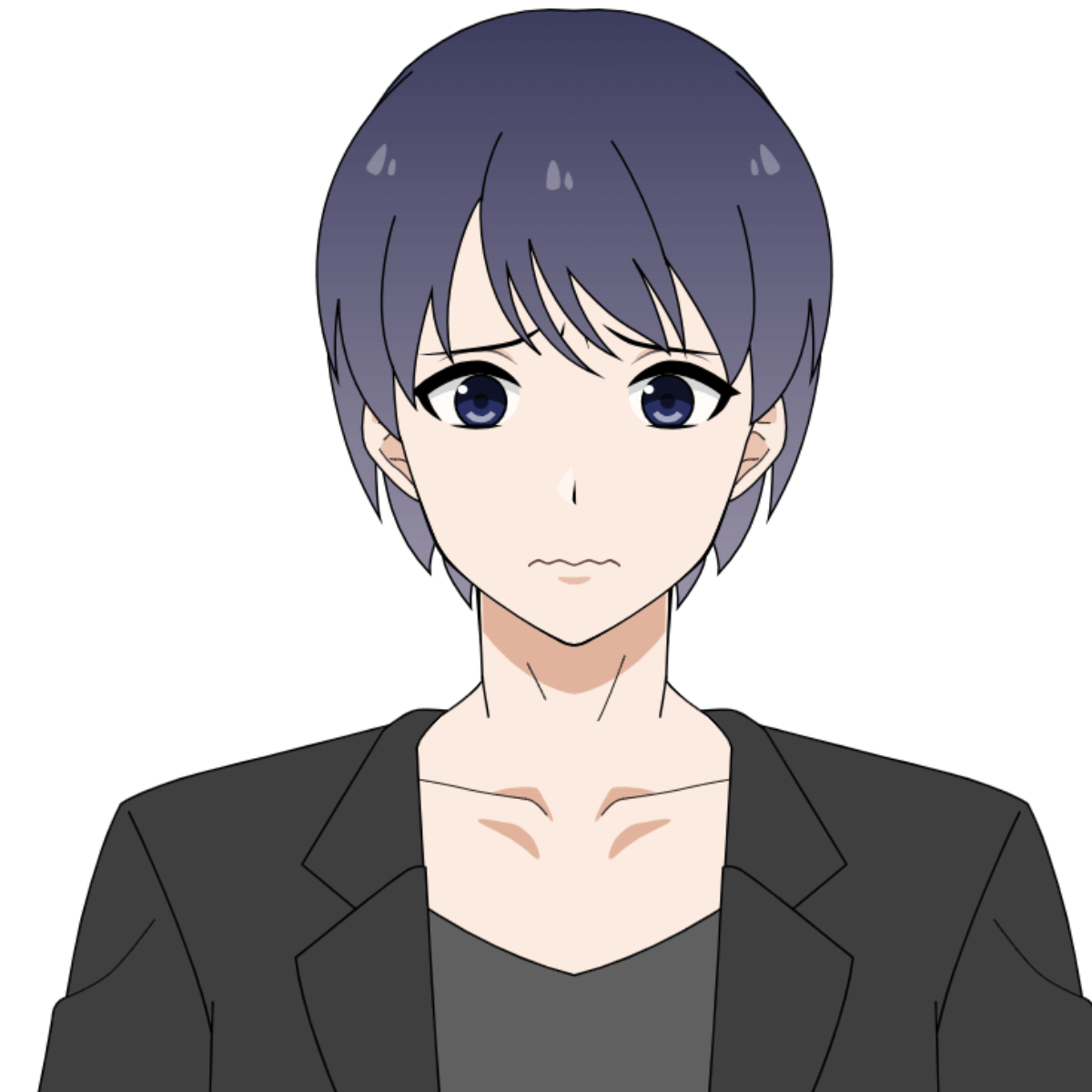
間に人を挟むことで直接やり取りする回数が減ったり、クッションの役割になったりするのは確かにいいですね
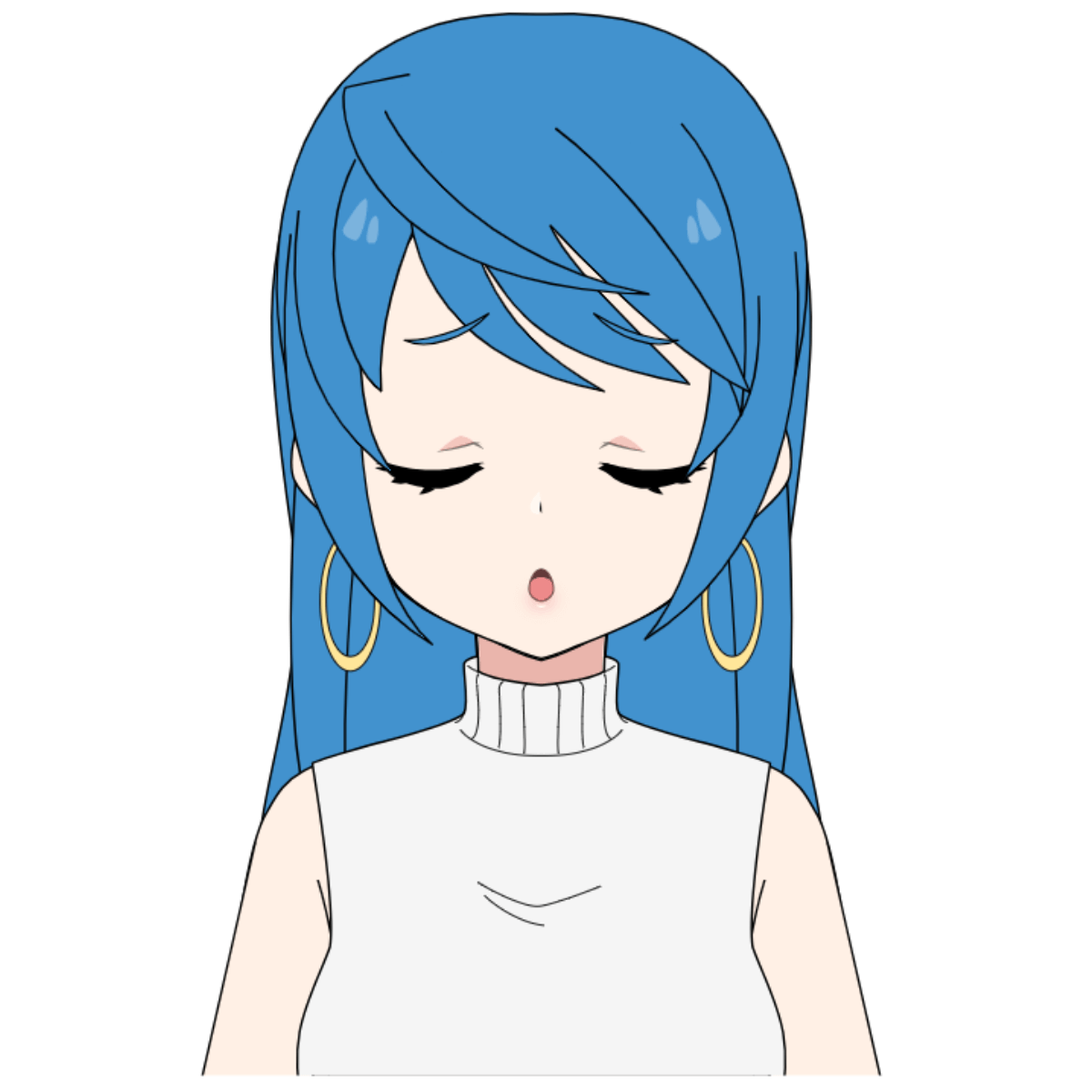
人間関係って確かに難しいわよね。仕事じゃ直接やり取りしないわけにもいかないから、第三者が入るって実は良い選択肢だと思うわ。
管理職になれば手取りが減る構造的な罠
多くの若手社員が社会に出ると気づいてしまう「管理職=昇給ではない」という事実です。もちろん、銀行や老舗のメーカー、外資系企業など年功序列や役職による手当がきちんと用意されている企業では役職によって昇給します。しかし多くの中小企業ではこの逆です。
実際には、“名ばかり管理職”になった瞬間に残業代がつかなくなり、実働時間が増え、実質的に手取りが減るというケースが非常に多く厚生労働省の調査でも、主任や係長などの一般的な管理職層では「非管理職時代よりも実収入が下がった」と答える人が約4割に上るという報告があります(※厚労省 令和4年度賃金構造基本統計調査より)。
つまり、キャリアを積むことで生活が豊かになるどころか「責任とストレスは増え、手取りは減る」という構造になっているのです。
この仕組みにメスを入れない限り、若手が「管理職になりたい」と思うはずがありません。
むしろ、「いかに管理職にならずに済むか」が彼らのキャリア設計の基準になりつつあるのが現実です。
【警鈴】今から次の管理職候補を育成できなければ数年後には本当に深刻になる
今、現場の中間管理職が多忙で若手育成どころではないという声も理解できます。
しかし、「そのまま放置していい」とはなりません。
なぜなら、今育てていない若手は数年後の中間管理職不在を招くからです。
現に、日本経済新聞が報じた調査によると、40代後半から50代前半のミドル層の退職が加速しており、2023年には管理職の人材不足が顕著になっている企業が増加しているという調査結果もでています。
問題は退職が始まってからではもう手遅れになるということ。だからこそ今、以下のような仕組みを持つ必要があります。
- 無理に昇進させるのではなく、段階的なロールモデルを見せる
- 育成よりも“育つ場”を意図的に用意する
- 若手が「こういう上司になりたい」と思える存在を見せる
管理職というポジションに“希望”を持たせる工夫をしなければ、いずれ組織は“リーダー不在”の危機に陥ります。
中間管理職は組織の要である一方、最も理解されず、最も苦しんでいる層でもあります。
そのポジションを魅力的な役割に変えるには、「価値観の更新」と「制度設計の見直し」が不可欠です。
次章では、こうした状況の打開策として注目されている「上司代行」サービスの実践的な活用法と導入時のポイントについて掘り下げていきます。
上司代行サービスで依頼できる主な業務内容
上司代行サービスは管理職の業務負担を軽減し、組織全体の効率を向上させる新たな手段として注目されています。特に中間管理職の役割が多岐にわたる日本の職場では、その必要性が高まっています。
「上司代行」という名前や表現に違和感があり
「自分の役割を代行してもらうなんてかっこ悪い」「使うこと自体に気がひける」
と感じている方は一度本記事を最後までぜひお読みください。実は「上司代行」という表現が出る以前から業務委託としておはいって同じようなサービスが実は存在するので、かっこ悪くもなく、気を引く必要もありません。
上司代行サービスの具体的な内容と種類
上司代行サービスは、管理職の業務を一部または全面的に代行することで、組織の効率化と職場環境の改善を図るサービスです。具体的には、以下のような業務が主な対象となることが多いです。
- 業務指示・進捗管理:部下への業務指示や進捗の確認を代行し、プロジェクトの円滑な進行をサポートします。
- 現場業務の支援:現場業務に手が回っておらずプレイングマネージャー化している状態を解決します。
- 部署の文化作り:組織の雰囲気や目標、部署のカルチャー作りを行います。
- マネジメントサポート:従業員の1on1やフィードバックを行い、モチベーションの維持・向上に寄与します。
- 会議のファシリテーション:会議の進行役を務め、議論の活性化や意思決定の迅速化を図ります。
- ハラスメント対応:職場内のハラスメント問題に対処し、健全な職場環境の維持を支援します。
いずれの支援も外側から意見をいうだけのコンサルではなく、組織の中に入って一緒に作っていくことが共通の特徴となる支援バリューです。
企業によって上司(中間管理職)の役割はそれぞれ異なる(企業によっては外向けの営業活動が加わったり人事回りの仕事も含まれる等)のですが、上記の中でどの部分の役割を担うのかをすり合わせをして上司代行サービスを使うか検討を進めます。
なので、今の業務課題としてチームマネジメントが追い付いていないのであればその役割を誰かに託すとか、クライアント対応が回らないのであればフロント対応を外部に委託するなどして応対を検討した方がよいでしょう。
上司代行うんぬん以前に業務過多な状態は一時的にでも解決すべき
上司代行は今後広がる可能性があるサービスですが本質としては「準社員」(業務委託ではなくあたかも支援先企業の社員となりきってアドバイスに加えて手を動かす人材)として動くので、課題に応じてどの役割を担うのか、どんな人にどんな業務を任せたいのかを事前にすり合わせる必要があります。
中間管理職の業務を代行することで、組織の円滑な運営が可能となり、中間管理職が抱えるプレッシャーを軽減できます。
(こうした打診をすると上長の方は「それはお前の役割だろ」と言われることもあるかもしれません。しかし業務が回っていない以上、誰かに業務を分散することは仕事を円滑に進める上で正しい判断ですし、社内にその役割を任せられる人がいなければ外部に託すことも選択肢に入る余地はあると思います)
まずは管理職のプレイヤーを平準化することがプロストイックの解決策
管理職の業務負担を軽減するためにはまずプレイヤーの業務平準化が重要です。
当社プロストイックでもプレイングマネージャーの支援に入る時の多くはプレイヤー業務の巻取りから行い今いるマネージャー・管理職の方がマネジメント業務や本来すべき業務に集中できる環境を作ります。
特定の管理職に業務が集中すると属人化が加速すると同時に過労やストレスの原因となり組織全体のパフォーマンス低下を招きます。
上司代行サービスを活用することで業務の分散化が可能となり、各管理職の負担を均等にすることができます。これにより組織内のバランスが取れ、持続可能な運営が実現します。
上司代行(中間管理職支援)はどんな企業に向いているサービスか
端的に言えば上司代行サービスは特に以下のような企業に非常に適しています。
- 人材不足に悩む中小企業
- 急成長中でリーダーが不足している企業
- 人間関係の課題を抱える職場
- 社員を雇うことにネックを感じている企業
特に、マネジメント層のリソース不足や業務過多、ハラスメントリスクの高まりなど、現代の職場が抱える複雑な問題に対して、外部の専門家が一時的または継続的にサポートを提供することで、組織全体の健全性と生産性を維持・向上させることが可能です。
いずれか1つでも当てはまるものがあればトライアルで一度導入することも検討してみてはいかがでしょうか。
これらの企業にとって上司代行は業務負担を分散し、チーム全体の効率を高めるための有力なツールとなります。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
上司代行が提供する価値とメリット
上司代行サービスの導入には以下のような価値とメリットがあります。
- 業務効率の向上:専門的なスキルを持つ代行者が業務を担当することで、業務の質とスピードが向上します。
- 管理職の負担軽減:業務の一部を代行することで、管理職の負担が軽減され、ストレスの軽減やモチベーションの向上につながります。
- 組織の柔軟性向上:必要に応じて代行サービスを活用することで、組織の柔軟性が高まり、変化に対応しやすくなります。
- 人材育成の促進:代行者からのフィードバックや指導を通じて、部下のスキル向上やキャリア形成が促進されます。
ただ、実際に支援している中でクライアント様からよく言われる一番の言葉は「外からアドバイスするだけではなくて組織の中に入って部署の業務を一緒に行ってくれることが一番ありがたい」と言っていただきます。一つのチーム・同じ部署の仲間として見てくれていることが非常にありがたいお言葉です。
社員を雇うよりもリスクは少ない
労働基準法によって社員の雇用は守られている(欧米と異なりいきなり解雇などができない)ので、雇用した以上は実質的に「雇い続けなければならない」状態が続くということです。
もちろんマッチしなければ自分から退職を申し出てくれますが、居座り続けた場合可能性として長期にわたってそのポジションにいる可能性があります。そうなると組織運営やマネジメントなど多々に渡って課題が新たに発生したり、業務が停滞する可能性があります。
その点、上司代行となれば雇用関係というより業務委託なので区切りの良いタイミングや課題が解決したらそこで区切ることも可能です。
最大のリスクであるハラスメント対策にも有効なのが上司代行
上司・中間管理職の方々が抱える一番の悩みの1つが「ハラスメント」です。パワハラ、セクハラ、モラハラなど様々な用語がSNSで飛び交い、部下のマネジメントに悩みを抱えている方もいるかと思います。
上司代行はこういったセクハラ対策にも有効です。基本的には部下への指示命令系統を上司代行の会社へ移管するので間接的な会話や指示はあれど直接業務指南をすることは減るのでハラスメントのリスクも軽減されます。
上司代行サービスはハラスメント対策にも有効な手段となります。
ハラスメント対策をメインとして利用するというより副次的な目的として対策をしてほしいというご依頼が多いのが当社の現状ですが代行者が中立的な立場で業務を担当することで、ハラスメントの発生リスクを低減し、健全な職場環境の維持が可能となります。
また、ハラスメントに関する相談や対応も代行者が行うことで、従業員が安心して働ける環境が整います。
上司代行サービスは管理職の業務負担軽減だけでなく、組織全体の健全性向上にも寄与する有効な手段です。導入を検討する際は自社の課題やニーズを明確にし、最適なサービスを選択することが重要です。
上司代行サービス(中間管理職支援)利用料金の相場は?
続いては上司代行サービスにおける料金・費用の相場についてです。
上司代行サービスの費用は依頼する業務の内容や範囲によって大きく変動します。
例えば、日常的な業務のサポートやスケジュール管理、会議のファシリテーションなどの工数がある程度予測できる業務であれば、比較的低コストで依頼することが可能です。
一方で、組織改革の推進や現場の中に入って支援、ハラスメント対応など、専門性や責任が伴う業務を依頼する場合は費用が高額になる傾向があります。
また、業務の緊急性や対応時間帯によっても費用が変動することがあります。例えば、夜間や週末の対応が必要な場合や、短期間での成果が求められるプロジェクトでは、追加料金が発生することがあります。そのため、依頼する業務の内容と求める成果を明確にすることが重要です。
業務内容によって費用は大きく変動する可能性も
上司代行サービスの料金体系は「業務内容が固定で決まっているか」「柔軟にこの役割・ポジションで入ってほしい」かによって大きく変わってきます。
大きくは稼働時間や業務難易度によって費用が変動することが多いです。
またどんな業務内容を担うかによってそれにマッチした人材のスキルセットや体制などが変わります。
概算で相場をお伝えするのであれば50万~200万円/月前後がおおよその目安でしょう
いずれにしてもなんの役割を担い、どの程度稼働が発生するのか、スキルセットが必要なのかによって変わってきますので、一度問い合わせをしてみるのが良いと思います。
支援会社を比較して選ぶコツ
料金プランを選ぶ際は、まず自社の課題を明確にすることが重要です。
適切な支援会社を選ぶためには、以下のポイントを押さえて比較検討することが重要です。
コミュニケーションの取りやすさ:担当者との連絡がスムーズで、柔軟な対応が可能かを確認しましょう。
業務範囲と専門性の確認:依頼したい業務内容に対して、支援会社がどの程度の専門性を持って対応できるかを確認しましょう。
勤務形態:フリーランスなのか、会社単位の支援体制なのか。(フリーランスの場合、会社の情報を預けることが非常に危険なのでできる業務に制限はかかります。)
実績と評判の確認:過去の導入事例や顧客の声を参考に、支援会社の信頼性や実績を評価しましょう。
上司代行サービス(中間管理職支援)を利用する際の注意点
上司代行サービスを利用する際には料金だけでなく契約内容も重要です。
またただし、外部の支援者を“上司の役割”(またはそれに近い役割)として導入する以上、一定の前提条件や準備を怠ると、期待した効果が出ないどころか、現場に混乱を招くリスクすらあります。
サービス提供範囲や追加料金の条件を明確に理解し、不明点があれば事前に確認することが必要です。
また、急な変更やトラブル時の対応についても、契約時に確認しておくと安心です。
このように、慎重な比較と確認を行うことで、最適な上司代行サービスを選ぶことが可能になります。
業務の課題や範囲はある程度事前に明確にする
上司代行サービスを利用する際に最も注意すべき点の1つ目は、事前に業務範囲や期待する成果を明確に伝えることが重要です。
既に中間管理職の方々の業務範囲が多岐に渡っているケースが多くどの業務を切り分けて依頼をしたいのかはすり合わせが必要です。
「とりあえず中間管理職がいないから入ってくれ」というケースもあるのですが、きちんと整理をしないと後々トラブルになってしまうケースがあります。
法的な話をすると準委任契約であれば業務範囲にある程度バッファーを持たせて対応可能ですが、派遣契約でないと契約が難しいということであれば業務範囲が事前に定められている範囲の中で対応するため柔軟な対応は厳しいのである程度事前に課題や業務範囲を明確にしておく必要があります。
また、定期的なミーティングを通じて進捗を確認し、問題が発生した際には迅速に対処する体制を整えることが求められます。
特に重要なのは、「何を任せるか」と「どうやって関わってもらうか」を事前に明確にしておくこと。そして、現場への説明や信頼構築のステップを丁寧に踏むことです。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
現場とのコミュニケーション設計を怠らない(人事・労務経由での導入の場合)
現場の方から直接管理職のサポート役として入る場合は明確な役割がわかっているので問題ないのですが、人事や労務など別の部署から現場の支援を依頼する場合は注意が必要です。
上司代行サービスを別部署から現場へ導入される場合、現場とのコミュニケーション設計を怠ると、「外部の人間が急に上司のように話してくる」という反発や混乱を生みやすくなります。
たとえば、現場メンバーにとっては
- 「この人はどんな役割で来ているのか」
- 「元の上司は今どこまで関与しているのか」
- 「この人からの指示はどの程度正式なものか」
といった情報が不透明だと、動きづらさと不信感が募ります。
これを防ぐには
- 導入前に関係部署やチームにしっかり背景を説明する
- 質問や不安に答える時間を設ける
- 最初の数週間は“紹介者”が同席して信頼構築をサポートする
といった丁寧なコミュニケーション設計が不可欠です。
また、「代行者は“監視者”ではなく、あくまでサポート役である」ことを明確にしないと、部下側が過度に萎縮してしまう場合もあるため、心理的安全性にも配慮が必要です。
上司代行を利用するうえでの個人情報の取り扱い範囲について
リスク感応度が高い方はお気づきかもしれませんが上司代行サービスの利用に際しては、個人情報の取り扱いに関する懸念が浮上するかと思います。
当社プロストイックでは取り扱っていないですが外部のフリーランスや委託業者に業務を依頼する場合、情報漏洩のリスクや契約上の問題が発生する可能性があります。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、事前の確認と適切な対策が不可欠です。
基本的な基本情報プライバシー保護については秘密保持契約書(NDA)を結ぶ(基本契約書の中に入ってるケースが近年は多いし弊社も同様)ことが多いですが、扱いには十分に注意しましょう。
ちなみに当社プロストイックの場合は自社PC端末での個人情報の取り扱いは禁止しており、クライアント様からお借りしたPCでかつ、定められた場所でのみ対応を可能としています。
フリーランスに企業情報を預ける危険性
当社プロストイックではフリーランス登録あるいはフリーランスへの業務委託を取り扱っていないですが、上司代行を利用するにあたってフリーランスに企業情報を預ける際には以下のリスクが考えられます。
- 情報漏洩のリスク: フリーランスが使用するデバイスやネットワークのセキュリティが不十分な場合、企業の機密情報が漏洩する可能性があります。
- 契約違反の可能性: フリーランスが契約内容を十分に理解していない場合、意図せず契約違反となる行為を行うことがあります。
- 法的責任の所在: 情報漏洩や契約違反が発生した場合、企業側が法的責任を問われる可能性があります。
企業としていざという時になんのリカバリーもできない状態では非常に危険です。
昨今では情報漏洩の件数も増えており、いざ漏洩してしまえば取引先との信用問題に発展します。
上司代行について中間管理職の方は前向きに捉えるべき
ここまで上司代行サービスの支援内容や注意点などをお伝えしてきましたが、実際に中間管理職の業務は多岐に渡っていることが多く、一人で抱えてしまうと過度なストレスに繋がったり業務が回らなくなることも多いです。
上司代行サービスを利用することに対して、一部の人はネガティブなイメージを抱くかもしれませんがしかし、これは単なる問題解決の手段ではなく、組織の成長を促進するポジティブな取り組みです。
しかし外部の専門家に業務の一部を委託することで、コア業務に集中することが可能になります。
また、上司代行を通じて新たな視点やノウハウを組織に取り入れることができ、組織の成長や変革を促進する効果も期待でき感覚としては「いつでも解雇ができる中途採用」に近いようなイメージです。
正社員ではなく、業務委託契約で同じ環境(PC・オフィス)で働くので本当に社員と変わらないです。しかもミスマッチであればいつでも契約満了ができるので企業としてもリスクが低く非常にコストパフォーマンスが高いです。
なので中間管理職の方々は今のご自身の課題や部署の課題を抱えすぎず、上司代行サービスを前向きに捉え、自身の業務改善や部署の目標達成を確実にするための手段として活用することが望ましいでしょう。
上司代行という名前に違和感を覚えるかもしれないが同じようなサービスは違う名前で実はある
上司代行サービスと似たようなサービスは、実は違う名前で既に多くの企業で活用されています。たとえば、「伴走支援型支援」や「プロジェクトマネジメント支援」などがその一例です。
しかしこれらも業務範囲が広告の運用だったり、実際に手を動かさないでアドバイスのみというのが結構多いので「実行まで含めた伴走支援」というのはかなり限られた企業のみが行っています。
このような既存のサービスと比較することで、上司代行サービスの特長や利点をより深く理解することができます。また、これらの類似サービスを組み合わせることで、より柔軟で効果的な解決策を構築することも可能です。
筆者の上司代行経験談
実は筆者自身も過去に上司代行サービスを「実行した側」として経験があります。
概要をお伝えすると、支援先のマーケティング部社員の多くが退職してしまい部署業務が回っていない状況でした。
部にはマーケティング未経験の方1名と社員のリーダー職の方が1名いてあとは本部長のみでした。
既に社員の方は深夜まで対応をしていてとにかく火の車状態でした。
そこに上司代行(その際そういった名前ではなく伴走半常駐支援でしたが)としてアサインされて業務の整理や組み立て、実行までを担いました。
弊社からトータル2名程度人をいれましたが、部のコンディションは劇的に改善しました。
具体的には本部長や社員の方と連携を図りマーケティング部としての方針が明確に定まり、年間予算や年間目標などを明確に定めることができ、部として具体の施策として取り組むものや分業制の体制を組むことができたので、目標達成のための改善のサイクルを構築できました。
この企業様は正社員雇用は考えていたのですが、なかなか業界的にも採用が難しく外部から人を入れることを選択肢として入れました。上司代行サービスは、その有効性を証明する一例と言えるでしょう。
体験談についてはこちらの記事で続きと詳しい内容を赤裸々にお伝えしています。
【未来について】中間管理職の働き方改革への影響(重要)
これまで「上司」や「管理職」は、現場を束ねる役割として当然のように存在してきました。
しかし、時代の変化とともにそのあり方は大きく揺らぎ始めています。中間管理職は今、過重な責任、働き方の硬直化、そして人間関係の板挟みといった三重苦に直面しており、もはや従来の体制では立ち行かなくなりつつあります。
このような時代背景の中でただ「がんばれ」と精神論を押しつけるのではなく、構造的な見直しが必要です。
上司代行サービスがもたらす可能性
上司代行サービスは単なる「代理業務」ではなく中間管理職の働き方そのものを大きく改善する可能性を秘めている点にあります。
たとえば、現場におけるマネジメントの偏りを是正するために、一部の業務を外部のプロに託すことで、内部の人材は自分の強みに集中できます。
これにより「苦手なマネジメントに悩む時間」が減り、「得意を活かして価値を出す時間」が増やすことができます
繰り返しになりますが、上司代行なんてサービス使わなくても正社員育てればできるし、今の中間管理職の仕事でしょ?
と思うかもしれませんが、理屈通りに上手くいく企業もそう多くありません。
正社員も退職リスクがあるし、採用するのにも採用費用(年収の25~35%がマージン相場:700万円の場合175万円~245万円がマージンで人材会社へ支払う)がかかりますし、社会保険料も会社が半分負担しています。(年収の15%が会社負担の目安なので年収700万円の場合、年間で105万円は会社が負担する計算)
特に、業務負担の軽減や心理的なサポートを通じて、働きやすい職場環境の構築に寄与します。また、これにより中間管理職の離職率が低下し、長期的には組織全体の安定と成長が期待されます。
これからの時代、すべてを内部リソースで完結させる発想は非効率でリスキーです。むしろ、「必要な部分を外に預ける勇気」こそが、持続可能な組織づくりに求められているのです。
採用に困っている企業にこそ上司代行は真価を発揮
慢性的な人材不足に悩む中小企業や地方企業にとって「管理職を担える人材の確保」は最もハードルが高い課題です。
候補者がいても経験不足で任せきれない、採用コストをかけても定着しない、といった悪循環に陥っているケースは少なくありません。
こうした背景を持つ企業にこそ、上司代行サービスの活用は極めて合理的な選択肢です。
なぜなら、必要なタイミング・必要な期間だけ・必要な業務だけ、マネジメント機能を外注できるからです。これは、常勤採用よりもリスクが低く、スピード感も早いため、組織の変化に柔軟に対応できる構造が作れます。
特に、社内の成長途上にある若手メンバーに対して、代行者が“見本”となるマネジメントを見せることで、次世代育成にもつながるという好循環も生まれます。
つまり、上司代行とは単に「人が足りない穴埋め」ではなく、未来に向けた「マネジメントの投資」でもあるのです。
経営者にとって社員同様に働く上司代行はコスパが良い
日本の雇用は労働基準法によってかなり守られていて容易に人事を入れ替える(退職や解雇)ができません。それゆえに正社員を抱えることは非常にリスクです。
その点、上司代行は契約の規制はあれどプロジェクトが落ち着いたり、役割として終えれば契約満了なども柔軟に対応できます。
プロジェクトやタスクは社内の人事状況も踏まえて流動的に変わる可能性があり、この際にリソースが足らないからタスクが進行しないのでは本末転倒です。
タスクを実行することや中間管理職の方の手助けになるようなメンバーがいればご自身の業務負荷軽減だけではなく評価向上にも繋がります。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
いかがだったでしょうか。本記事では中間管理職が抱える悩みや今後成長余地がある上司代行というサービスについて解説をしました。
また新しい世代やトレンドがくるとともに中間管理職の役割や悩みは大きく変化してきます。
悩んでいることや不安になっていることがあればぜひご相談いただけますと幸いです。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック