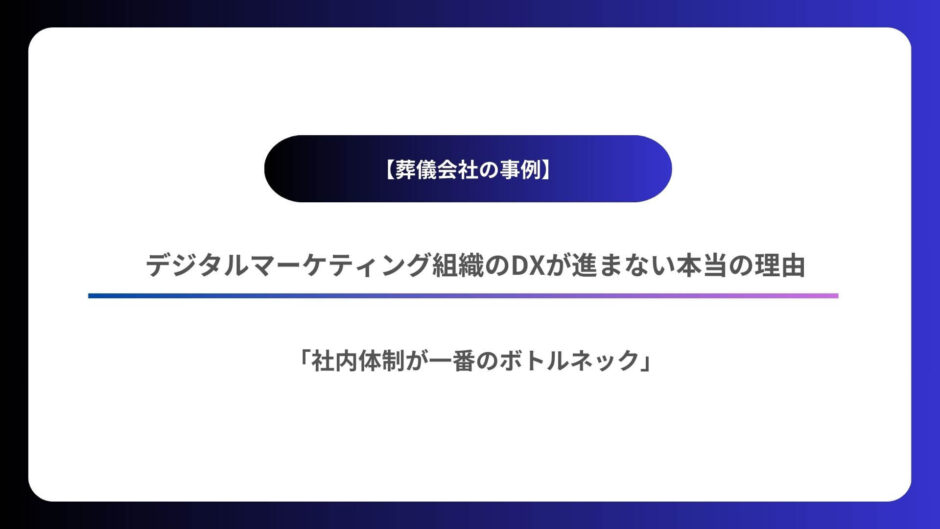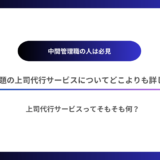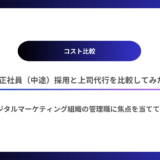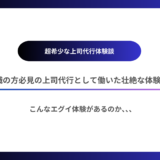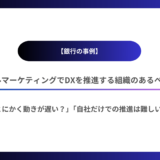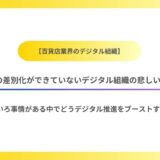皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本日は葬儀会社の事例を元にデジタル組織のあるべき姿について解説を進めていきます。
- 1.銀行でデジタルマーケティング組織に属してる方
- 2.銀行で働いていて、デジタル推進をしなければならない方
- 3.デジタル推進が銀行内で遅れており外部の支援企業を探している方
葬儀業界におけるデジタルマーケティングDXの壁とは

葬儀業界において、デジタルマーケティングやDXの必要性は広く認識されています。
しかし、実際に導入・活用できている企業はごく一部にとどまり、多くの企業ではデジタル化が進んでいません。これは、業界特有の商習慣や顧客層の特徴、さらには組織体制の問題などが複雑に絡み合っているためです。本章では、葬儀業界のデジタルマーケティングが抱える課題について詳しく解説します。
デジタル化の必要性を理解しながらも進まない理由
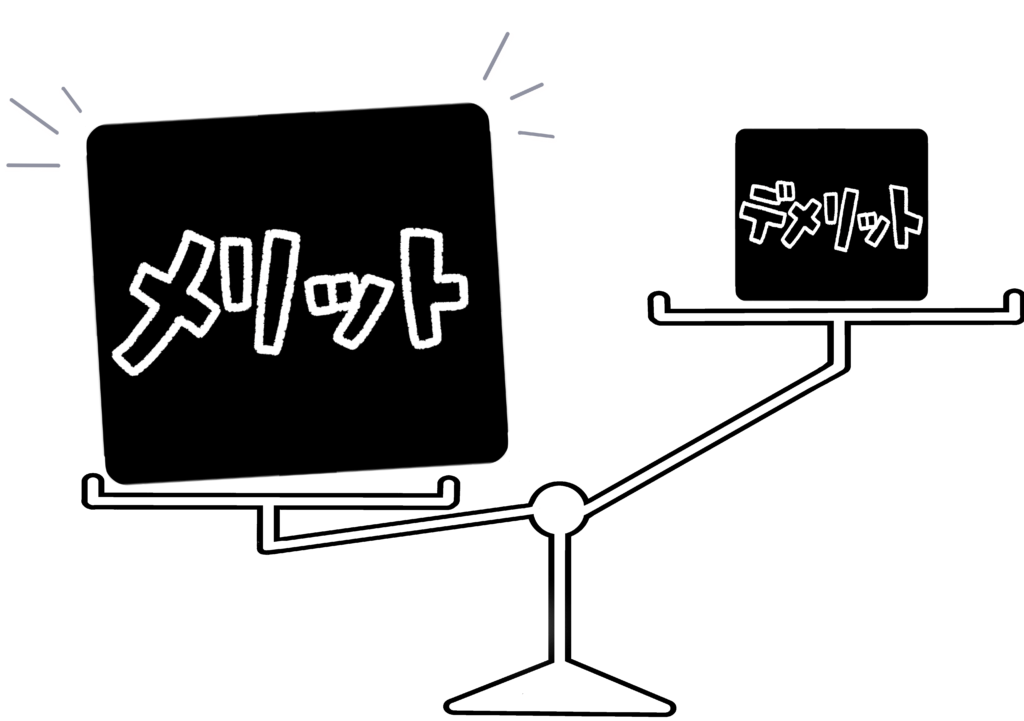
多くの葬儀会社ではDXの必要性を理解しながらも、実際の導入には至っていません。
色々は葬儀会社の事情がありますが、まとめるとその最大の理由は、「変革に対する抵抗感」と「デジタルスキルを持つ人材不足」です。
葬儀業界は長年にわたり、地域密着型のアナログな営業手法が主流でした。
顧客との関係構築も対面が基本であり、デジタル施策を導入する文化が根付いていません。
そのため、企業の経営層や現場担当者の間で、「デジタル化しても意味がない」「これまでのやり方で十分」といった認識が根強く残っています。
また、デジタルマーケティングを推進するにはSEO、広告運用、SNS戦略、データ分析などの専門知識が必要です。
しかし、葬儀業界にはこれらのスキルを持つ人材が相対的に少なく採用も難航しがちです。その結果、デジタル戦略を立てても、実際の運用が追いつかないケースが多発しています。
顧客の高齢化とオンライン施策のミスマッチ

葬儀業界の顧客層は高齢者が中心であり、デジタル施策と親和性が低いと多くの方が未だに考えられています。
故にチラシやテレビなどは特に地方でまだまだ主流の広告媒体でオンライン広告やSNS戦略に投資しても、高齢者層にリーチできるのかという疑問を抱く企業は少なくありません。
確かに、従来の紙媒体やテレビ・ラジオ広告と比べると、デジタル広告はシニア層の利用率が低い傾向にあります。
しかし、近年では高齢者のインターネット利用が増加し特に50代~60代の層はスマートフォンやSNSを活用するケースが増えています。そのため、デジタル施策の運用やターゲティング次第でマーケティング効果を高めることが可能です。
また、LINE公式アカウントやYouTube動画などを活用した情報発信も有効です。LINEはシニア層の利用率も高く、葬儀の流れやプランを手軽に相談できるツールとして活用できます。YouTubeでは、事前相談の流れや式場の紹介動画を掲載することで、視覚的な訴求力を高めることが可能です。
現場主導のマーケティングがデジタル移行を阻害
葬儀業界ではマーケティング戦略を現場のスタッフが主導するケースも多く見られます。
これは人手不足でリソースが足らないことも理由に挙げられますが地域密着型の営業が中心であるため、実際に顧客と接する現場の判断が重視される傾向が強いからです。
しかし、この現場主導型のマーケティングがデジタル移行の障壁になっている側面もあります。具体的には、以下のような問題が発生しています。
- 現場スタッフの業務負担が大きい
デジタルマーケティングを導入するには、ウェブサイトの更新や広告運用、SNS対応などの作業が発生します。しかし、現場のスタッフは葬儀の手配や顧客対応で多忙を極めており、新たな業務を負担する余裕がありません。 - デジタル施策の理解不足
デジタルマーケティングの効果を測定し、適切な改善を行うには、データ分析の知識が必要です。しかし、現場のスタッフはマーケティング専門の教育を受けていないため、効果的な戦略を立てるのが難しい状況です。 - 「アナログのほうが成果が出る」という固定観念
これまで地域密着の営業が成功していた経験から、デジタル化に対する疑念を持つケースが多く見られます。特に、長年アナログ営業で成功してきたベテランスタッフほど、新しい手法に対する抵抗感が強い傾向があります。
DXを成功させるために必要な視点
社内の動きが遅かったり、経営がデジタルに対する変革に腰が重い中、葬儀業界がデジタルマーケティングを活用しDXを成功させるには単なる技術導入ではなく、組織全体の意識改革が不可欠です。
そのためには、以下のようなアプローチが求められます。
- 上司代行サービスの活用
人手不足が深刻な企業では、上司代行を導入し、デジタルマーケティング戦略を専門家に任せることが有効です。これにより、現場スタッフの負担を軽減しつつ、専門的なノウハウを活用できます。(後程解説) - デジタル教育の推進
社員向けのデジタルマーケティング研修を実施し、組織全体のリテラシーを向上させることが重要です。特に、データ分析やSNS活用に関する基礎知識を持つことで、現場の意識も変わっていきます。 - 段階的なデジタル移行
いきなりすべての業務をデジタル化するのではなく、まずはLINEやウェブ広告の活用など、導入しやすい施策から始めるのが効果的です。少しずつ成功体験を積み重ねることで、組織全体のDX推進が加速します。
葬儀業界におけるデジタルマーケティングのDXは多くの課題を抱えながらも、今後の競争力強化には不可欠な取り組みです。
高齢化社会が進む中で、ターゲットの変化に対応し、効率的な集客やブランディングを行うためには、デジタル戦略そしてデジタルを推進する「体制」を社内に作ることが欠かせません。
現場主導のマーケティングから脱却し、組織全体でデジタル化を推進するためには今こそ葬儀業界もDXの波に乗り、持続可能な経営体制を確立するタイミングといえるでしょう。
葬儀業界で実績豊富なプロストイックへの
広告やマーケティングの相談はこちらから
葬儀業界の人材・組織課題がDX推進を妨げる現実
葬儀業界におけるDX推進の遅れは単なる技術的な課題だけでなく、人材や組織の構造的な問題にも起因しています。
多くの企業ではデジタルマーケティングやDXに関する専門部署が存在せず、知識の属人化や社内教育の不足が深刻な課題となっています。
(葬儀業界の企業を見渡すとデジタル部署はあるけど、色々な業務と兼務しながらマーケティング施策を実行していることがほとんどです。故に運用が疎かになってしまうことが多いです)
本章では葬儀業界におけるDX推進を阻害する具体的な戦略課題・人材・組織課題について詳しく解説します。
デジタル専門部署の不在が成長の足かせに
葬儀業界の多くの企業ではデジタル専門部署が存在せず、DX推進が組織的に行われていません。(あくまで弊社が支援した企業様を中心に考察していますが、厳密にはデジタルの専門部署はあるのですが、様々な業務と兼務していることが多く体系的にデジタルを推進している企業がまだまだ少ないように感じます)
マーケティング部門があったとしても、従来の紙媒体広告や営業支援が中心であり、デジタル領域には十分なリソースが割かれていないのが実情です。
また、デジタル戦略が経営層の意思決定に組み込まれていない企業も多く、「デジタル化は必要だが、誰がやるのか分からない」という状況に陥っています。
その結果、ウェブサイトの更新やSNS運用が後回しになり、競争力を失う要因となっています。
デジタル専門部署を設置し、マーケティングとIT部門が連携する体制を整えることが、葬儀業界のDX推進には不可欠です。
社内教育不足でデジタル施策が浸透しない
DXを成功させるには、経営層だけでなく、現場スタッフのデジタルリテラシー向上が不可欠です。
しかし、多くの葬儀社では社内教育の機会が乏しく、育成の機会やデジタルツールの活用が進んでいません。
例えば、ホームページの更新やGoogle広告の運用が外部業者任せになっており、社内に知見が蓄積されていない企業が多く見られます。
デジタル施策を推進するには、社員が最低限のマーケティング知識を持ち、データを基にした判断ができるようになる必要があります。
そのためには、自社で運用できる体制を構築することが求められます。しかし人手が不足しているという状況の企業様がほとんどなのでツールなどを入れますがこれも運用するのにまた工数を取られます。
なので、外部のアウトソースはしますが、自社内にノウハウが貯まる内製体制の組織を使うことがオススメです。プロストイックでは中間管理職が業務過多になっている場合に業務を巻き取り推進する「上司代行(中間管理職支援)」と現場にノウハウを貯めるために代理店に依存せず自分たちだけで運用できるスキルと体制を創る「インハウス化支援」の2軸でご支援をしています。
なのでデジタル戦略の基盤を築く支援を受けるのも一つの手段です。
デジタル知識が一部の社員に属人化している
また人手不足が慢性化している企業に多く見受けられますが、仮に社内にデジタル施策を担当する社員がいたとしても、その知識やスキルが特定の個人に依存してしまうケースが多く見られます。これは、以下のような問題を引き起こします。
- 担当者が退職すると、デジタル施策が完全に停止する
- 他の社員がデジタルツールを使えず、業務が属人化する(結果的に業務過多になる)
- データ分析や広告運用のノウハウが共有されず、継続的な改善ができない
特に葬儀業界においてデジタルリテラシーが高い従業員とそうでない方の知識格差が広がりやすい傾向にあります。
そのため、属人化を防ぐには、チーム全体でデジタルスキルを共有し、複数名が担当できる体制を整えることが重要です。
プロストイックではデジタル施策の属人化を防ぐ手段として、「上司代行」を活用し、組織的なデジタルマネジメントの仕組みを構築を支援しています
葬儀業界で実績豊富なプロストイックへの
広告やマーケティングの相談はこちらから
結局は広告代理店に頼りきりのデジタルマーケティング(自社にノウハウが貯まらない)
葬儀業界の企業はデジタルマーケティングを自社で運用するのが難しいため、多くの企業が広告代理店に頼っています。しかし、代理店に丸投げするだけでは、長期的に見て大きな課題が残ります。
- ノウハウが社内に蓄積されない
広告代理店に運用を委託すると、データの分析や改善策の提案が代理店任せになり、社内でPDCAサイクルを回す力が養われません。そのため、代理店を変更した際にゼロからやり直しになりがちです。 - コストが継続的に発生する
広告運用を外部に委託すると、成果が出なくても一定の運用コストが発生します。社内に最低限の運用ノウハウがあれば、広告の最適化や代理店の選定を自社で判断できるようになります。 - 戦略の主導権を握れない
代理店はクライアントの利益を第一に考えるとは限らず、自社のビジネスモデルに適したマーケティング戦略を立てるには、社内の意思決定者がデジタル施策を理解していることが不可欠です。
そのため、広告代理店に依存しすぎず、デジタル人材の育成や上司代行の活用によるインハウス運用の強化を進めることが、DX推進の鍵となります。
葬儀業界のDX推進を妨げる最大の要因は、単なる技術の問題ではなく、人材・組織の課題にあることが明らかです。
デジタル専門部署がなく、社内教育も不足しているため、デジタル施策が定着せず、属人化が進んでいる現状では、真のDXは実現できません。
この状況を打開するには、以下のような施策が有効です。(あくまで一例です)
- デジタル専門部署の設置と、経営層の積極的な関与
- 社内教育を強化し、デジタルリテラシーを向上させる
- 属人化を防ぎ、チームでデジタルマーケティングを運用する体制を作る
- 上司代行を活用し、外部の専門家と協力しながらDXを推進する
特に、上司代行の活用は、限られたリソースの中でデジタル戦略を実行する有効な手段となります。人材不足に悩む葬儀業界こそ、外部の専門知識を活用し、組織全体でデジタル戦闘力を高めるべき時代に突入しているといえるでしょう。
葬儀業界の企業がデジタル組織の戦闘力を上げるためには
葬儀業界におけるデジタルマーケティングやDX推進にはデジタル組織の強化が不可欠です。
しかし、従来の業務に依存し続けてきた業界特有の事情から、多くの企業がデジタル組織の立ち上げや運用に苦戦しています。
本章ではDX推進に必要なデジタル人材の確保、スムーズな組織立ち上げのロードマップ、上司代行の活用による組織力強化について詳しく解説します。
DX推進に必要なデジタル人材とは?採用・育成のポイント
DXを推進するためには単にITスキルを持つ人材を採用するだけでは不十分です。
葬儀業界の理解は大前提ではありますが、DX推進をしていくデジタル人材になるには、最低限として以下のような3つのスキルセットが求められます。
- デジタルマーケティングの知識
ウェブ広告、SEO、SNS運用、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティング全般に関する知見が必要です。特に葬儀業界では高齢者層の顧客が多いため、ターゲットに合わせた戦略を理解することが求められます。 - データ分析・活用スキル
DXの本質は、データを活用して業務効率やマーケティング効果を向上させることにあります。GoogleアナリティクスやCRMツールを駆使し、施策の効果を測定・改善する能力が必要です。 - 業界特有の知識と柔軟な対応力
デジタルの知識だけでなく、葬儀業界特有のビジネスモデルや慣習を理解し、現場とスムーズに連携できるスキルが求められます。現場の意見を尊重しつつ、デジタル施策を導入できるバランス感覚も重要です。
人材確保の方法としては、即戦力となるデジタルマーケティング経験者の採用と、既存社員のデジタルスキル育成の両輪が必要です。
デジタル組織をスムーズに立ち上げるためのロードマップ
デジタル組織を立ち上げる際、いきなり大掛かりなDX改革を進めようとすると、現場の混乱を招く可能性があります。そのため、段階的なアプローチが重要になります。
以下はあくまで一例ですが上流の設計から組織の体制と役割、そして現場での実行とPDCAを回すことを繰り返していくことが求められます。
1. デジタル戦略の明確化
まず、自社がDXによって達成したい目標を設定します。例えば、「オンライン相談の導入」「SEO対策の強化」「広告運用の最適化」など、具体的な方向性を定めることが必要です。
2. デジタル人材の配置・育成
前述したようにデジタル施策を推進するための人材を確保します。既存のスタッフの育成と並行して、外部からデジタルマーケティングの専門家を招くのも有効です。
3. ツールの選定と導入
DX推進には適切なツールの活用が欠かせません。CMS(コンテンツ管理システム)、広告管理ツール、CRM(顧客管理システム)などを導入し、業務の効率化を進めます。
4. 小規模な施策からテスト運用
全社的な導入前に一部の業務や部門で試験的にデジタル施策を実施します。例えば、「1カ月間、オンライン相談を試験導入する」「特定エリアでのGoogle広告を運用する」など、スモールスタートを行います。
5. PDCAを回しながら本格導入
テスト運用の結果を分析し、改善を加えながら本格導入へ進みます。このプロセスを繰り返しながら、組織全体にデジタル施策を定着させていきます。
上司代行を活用してデジタル組織の戦闘力を上げる

DXを進める上で多くの企業が課題となる一つが「現場とデジタル戦略の橋渡しができる人材の不足」です。ここで有効な手段の一つが「上司代行」の活用です。
上司代行とはデジタルマーケティングの知見を持つ外部の専門家が、主にプレイングマネージャーを対象として中間管理職が抱える「プレイヤー業務」あるいは「マネージャー業務」を巻き取り組織の目標達成する体制を創る・推進する仕組みです。
上司代行を活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 中間管理職が本来すべき業務に集中できる
「プレイヤー業務」と「マネージャー業務」の兼務は相当カロリーが高く業務負荷が高いです。プロストイックでは「プレイヤー業務(手を動かす系)」をまず巻き取り負荷を軽減します。 - 社内のデジタルリテラシー向上につながる
上司代行がノウハウを提供することで、社員のスキルアップにも寄与します。 - 部署の目標達成が可能
意思決定のスピードや施策実行の速度が上がるため必然的にPDCAが多く周り目標達成へ近づきます - 心理的な負荷が大幅に軽減
業務負荷が減るだけで心理的な負担が軽減可能。加えて部下とのミスコミニケーションなども中間に入ることで部署内のコミュニケーションが円滑になります。
自社社員だけでは得られないノウハウを上司代行で蓄積
DXを成功させるためには外部の知見を取り入れながら、自社にノウハウを蓄積することが重要です。
しかし、デジタルマーケティングの経験がない企業が独力で学びながら実践するのは、時間とコストの面で大きなハードルとなります。
上司代行を導入することで、最新のマーケティング手法やDXのノウハウを、現場の業務に即した形で学ぶことが可能になります。
例えば、広告運用の最適化やデータ分析の手法、SEO対策の改善ポイントなど、実践的なスキルを社内に残すことができるのです。
また、上司代行は単なる外部アドバイザーではなく、企業の一員としてチームの中に入り込み、実務レベルで支援を行う点が特徴です。これにより、単発のコンサルティングとは異なり、持続的な成長につながる知見が組織内に蓄積されます。
葬儀業界の企業がデジタル組織を強化するためには、デジタル人材の確保と育成、スムーズな組織立ち上げ、上司代行の活用が不可欠です。特に、DX推進を本格化させるには、外部リソースの適切な活用が鍵となります。
上司代行を活用することで、社内にデジタルノウハウを蓄積しながら、無理なくDXを推進できる体制を構築することが可能です。今後の競争環境を見据え、デジタル戦略の確立に向けた第一歩を踏み出しましょう。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
経営層含めた会社全体の意識改革がカギ|トップダウンで進めるDX戦略
デジタルマーケティングとDXの推進には経営層の意識改革が不可欠です。
特に葬儀業界ではこれまでの対面営業や紹介ビジネスに頼ってきた企業が多く、デジタルへのシフトに慎重な姿勢を取るケースが目立ちます。
しかし、消費者の行動がオンラインへと移行し、情報収集の手段が変化する中で、デジタル戦略の強化は避けて通れません。DXを成功させるためには、経営層が主体となり、トップダウンでデジタル改革を推し進める必要があります。
葬儀会社の社員もデジタルマーケティングのノウハウが貯まる体制を組むべき
葬儀業界におけるデジタルマーケティングの導入は単なる「集客手段」ではなく、企業の競争力を高めるための重要な要素です。
しかし、よくある失敗の一つが「代理店にすべて丸投げしてしまい、社内にノウハウが蓄積されない」という問題です。(本当に多いです)
例えば、ウェブ広告を活用した集客を始めたものの、代理店に運用を完全に依存してしまい、どの広告が成果を生んでいるのか、どう改善すべきなのかを社内で分析できないといったケースは少なくありません。
その結果、マーケティング施策の改善が遅れ、代理店の方針に振り回されることになります。
これを防ぐためには、デジタルマーケティングの基本的な知識を社内に蓄積し、担当者が一定の運用スキルを持つことが重要です。具体的には、以下のような体制を整えることが効果的です。
- ウェブ広告、SEO、SNS運用など、デジタル施策に関する定期的な社内研修を実施する
- 社員がマーケティングツールを活用できるように、まずは簡単なダッシュボードやレポートを作成する
- 支援企業と協力しながら運用する形を取り、「学びながら実践する」環境を整える
また、デジタル施策を実際に運用する人材を育てることで、広告運用の最適化やコンテンツマーケティングの強化など、施策の精度を向上させることができます。
中間管理職がデジタルをリードする体制を組むべき
DX推進において経営層の意識改革と並行して、中間管理職がデジタル戦略のリーダーシップを発揮できる体制を作ることが必要です。
これは葬儀業界問わずですが現場のスタッフと経営陣の間に立つ中間管理職がデジタル施策の橋渡し役として機能することで、組織全体の変革を加速できます。
しかし、多くの企業では、中間管理職が日々の業務に追われ、デジタル戦略にまで手が回らないのが実情です。その結果、「DXは経営層の指示で進めるもの」となり、現場レベルでの理解や実行が追いつかないという課題が発生します。
これを解決するためには、中間管理職に対して以下のようなサポート体制を整えることが重要です。
- デジタル施策に関する基礎研修を受けさせ、「デジタルに強い管理職」を育成する
- 上司代行などの外部専門家を活用し、管理職がデジタル施策のサポートを受けられる環境を作る
- 具体的なKPIを設定し、中間管理職がデジタルマーケティングの成果を管理できるようにする
例えば、「毎月の問い合わせ件数を◯%増加させる」「ウェブサイトの訪問数を◯%向上させる」といった具体的な指標を設定することで、デジタル施策の成果を可視化し、管理職が関与しやすくすることができます。
中間管理職がデジタルに関心を持ち、リーダーシップを発揮できる環境を整えることで、デジタルマーケティングの成功確率が飛躍的に高まります。
現場と経営陣のギャップを埋める組織作りとは
DX推進が失敗する原因の一つに、現場と経営陣の認識のギャップがあります。経営層は「デジタル化を進めなければならない」と考える一方、現場のスタッフは「本当に必要なのか?」と疑問を抱いているケースが少なくありません。
例えば、経営層が「SNSを活用した集客を強化しよう」と指示を出したとしても、現場のスタッフが「葬儀の集客にSNSが本当に有効なのか?」と疑問を持っている場合、施策が形骸化してしまいます。
このギャップを埋めるためには、経営層と現場の間でデジタル施策の重要性を共有し、実際の業務に落とし込むことが重要です。具体的な方法として、以下のような取り組みが考えられます。
- 経営層が現場スタッフと定期的に意見交換を行い、デジタル施策の目的や効果について説明する
- デジタル施策の導入を進める際に、現場の意見を反映させる仕組みを作る
- 「デジタル担当者=経営陣」ではなく、現場と経営の橋渡し役として中間管理職を活用する
また、上司代行を活用することで、デジタル施策の進行をスムーズにし、現場と経営陣の間の調整役として機能させることも有効です。デジタルの専門家が介在することで、施策の意図がより明確になり、現場の理解を得やすくなります。
葬儀業界のDX推進を成功させるためには経営層がデジタル化の必要性を理解し、中間管理職がデジタル戦略のリードを行いマネジメントを行い現場がそれを実現するアクションをとる組織全体の連携がが必要不可欠です。
デジタルマーケティングのノウハウを社内に蓄積し、管理職がデジタル施策を推進する環境を整えることで、長期的なDX成功の土台が築かれます。また、上司代行を活用することで、経営と現場の間をスムーズにつなぎ、実行力を強化することも重要なポイントです。
デジタル化が進む今葬儀業界においてもDXは避けて通れない課題です。早い段階で体制を整え、持続的に成果を生むデジタル組織へと進化するための取り組みを始めましょう。
まとめ | 葬儀会社が今後生き残るためのデジタルDX体制
デジタル化の波がさまざまな業界に押し寄せる中、葬儀業界も例外ではありません。
従来の紹介や口コミに頼った集客方法だけでは、今後の競争を勝ち抜くことは難しくなっています。
そのため、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、デジタルマーケティングを活用することが、企業の成長と持続可能性を確保する鍵となります。
葬儀会社の今後にデジタルDX活用は必須
近年、消費者の情報収集手段は大きく変化しています。以前は家族や知人の紹介で葬儀会社を選ぶことが一般的でしたが、現在ではインターネット検索やSNS、比較サイトを利用するケースが増えています。
そのため、デジタルマーケティングの活用は、今後の葬儀業界にとって不可欠な要素となっています。
特に以下のような変化が見られます。
- 検索エンジンでの情報収集:消費者は「葬儀会社 地域名」や「家族葬 費用」などのキーワードで検索し、信頼できる企業を選ぶようになっている。
- SNSや口コミの影響:実際に葬儀を利用した人々のレビューや体験談が、次の利用者の判断材料となるケースが増加。
- オンラインでの問い合わせ・契約が増加:特に若年層やビジネスパーソンは、時間を節約するためにオンラインで葬儀の相談を進める傾向がある。
これらの動向を踏まえると、デジタルDXを導入・推進しない葬儀会社は、市場競争から取り残されるリスクが高まると言えます。
また、自治体や病院などの紹介ルートだけに依存するのではなく、自社で集客チャネルを確立し、安定した経営基盤を築くことが重要です。デジタルを活用した情報発信を強化することで、新たな顧客層の獲得が可能となり、競争力の向上につながります。
自社内でデジタルマーケティング体制を構築するために今からできること
デジタルマーケティングを自社で運用するためには戦略的な体制構築が必要です。
特に葬儀業界では「専門知識を持ったデジタル人材がいない」「何から手をつければいいのかわからない」といった課題を抱える企業が多く見受けられます。しかし、これらの課題は適切なステップを踏むことで解決できます。
1. デジタルマーケティング担当者を育成する
まず、社内にデジタル施策を実行できる人材を確保することが不可欠です。既存の社員の中で、デジタルマーケティングに興味を持つ人材を見つけ、教育プログラムを実施するのが現実的なアプローチとなります。
2. デジタルマーケティングの基礎施策を自社で開始する
いきなり大規模な施策を実行するのではなく、小さく始めて効果を見ながら改善することが重要です。例えば、以下のような手順で進めるのが有効です。
- 自社サイトのSEO対策を行い、検索結果で上位表示されるようにする
- SNS(特にFacebookやInstagram)を活用し、葬儀の情報を発信する
- Google広告を使って、地域ターゲットに絞った集客施策を実施する
これらを実践することで、デジタルマーケティングの基礎を確立し、ノウハウを蓄積することが可能になります。
3. 上司代行を活用し、専門知識を補完する
デジタルマーケティングの導入にあたり、すべてを社内で完結させようとすると、大きな負担がかかる可能性があります。特に、マーケティング経験がない管理職がすべてを担うのは非現実的です。
そこで有効なのが上司代行の活用です。上司代行とは、デジタルマーケティングの知識やマネジメントスキルを持つ専門家が、企業の中間管理職の役割をサポートするサービスです。
上司代行を活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 即戦力のデジタルマーケティング知識を導入できる
- 社内のデジタル人材育成をサポートしてもらえる
- 経営層と現場の橋渡し役として機能し、DX推進を加速できる
特に、初めてデジタルマーケティングに取り組む企業にとって、経験豊富な専門家のサポートは大きな武器となります。
4. 経営層がデジタルマーケティングを理解し、全社で取り組む意識を持つ
DXを推進する上で、経営層の理解と協力は不可欠です。「デジタルマーケティングはマーケ部門の仕事」「IT担当者だけがやればいい」といった認識では、組織全体の変革にはつながりません。
経営層自らがデジタルマーケティングの意義を理解し、組織全体で取り組む姿勢を示すことで、社内の意識改革が進み、DX推進がスムーズになります。
葬儀業界のDXは待ったなし!今すぐデジタルマーケティング体制の構築を
葬儀業界が今後も競争力を維持し、成長を続けるためには、デジタルマーケティングの導入が不可欠です。単に広告を出すだけでなく、社内にノウハウを蓄積し、継続的に成果を生み出せる体制を整えることが重要です。
今からできることとして、以下を実践していきましょう。
- 社員のデジタルマーケティングスキルを向上させる
- 小規模な施策からスタートし、効果を見ながら改善を重ねる
- 上司代行を活用し、デジタル専門知識を補完する
- 経営層がデジタルの重要性を理解し、組織全体で取り組む
今後、デジタル化を積極的に進めた企業が、葬儀業界でも生き残る時代になります。今こそ、デジタルDX体制を構築し、競争優位性を高めていきましょう。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック