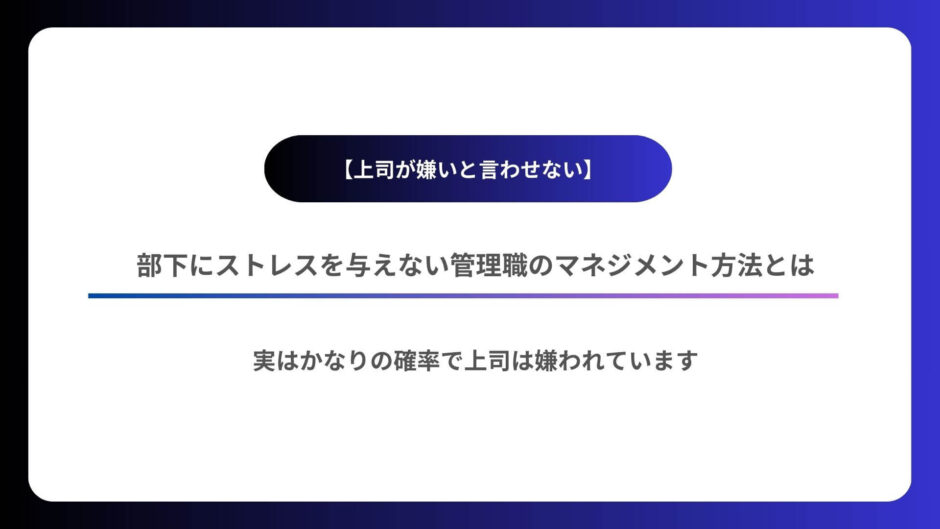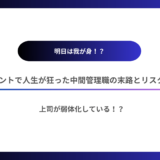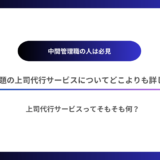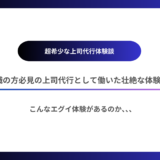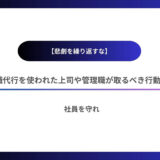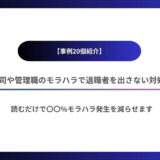皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本日は「嫌われている上司必見」の内容となっています。
「当たり前の内容が書いてる」と思うかもしれませんが、できていない方が非常に多く、むしろ「自分はできているから大丈夫!」という方にこそ「声に出して」読んでいただきたいです。
- 自分が管理職・上司をやっているが部下や周りのメンバーに嫌われている
- 部下との職場での良好な関係を築きたい
- きちんと部下を育成できていないことに自覚を持っている
当サイトでは上司のマネジメント系に関する悩みの記事が非常に多く読まれています。
当サイトでは上司のマネジメント系に関する悩みの記事が非常に多く読まれています。人事など向けではなく、現場の管理職に多く読んでいただいている内容となっております。
【嫌われている上司必見】なぜそもそも上司は嫌われるのか

「上司が嫌いです」、「上司がパワハラまがいのことしてくるんだけどうざい」—これはネット掲示板やSNS、口コミサイトなど、どこを見ても見かける言葉です。
組織内で避けては通れない“上下関係”の中で、部下が感じるストレスや不信感は多くの場合、「上司との関係性」から生まれています。
では、なぜ上司はこれほどまでに嫌いと言われてしまうのでしょうか?
それは単なる性格の不一致ではなく、マネジメントのやり方や、日々の言動に無自覚な“すれ違い”が積み重なっているからです。
この記事では部下の声や実際の退職理由にも挙がるようなリアルな「嫌われる理由」にフォーカスし、管理職として今すぐ見直すべきポイントを整理していきます。
無意識のうちにストレスを与えてしまっていないか、自分のふるまいを見つめ直すきっかけとしてぜひ活用してください。
無理な要求を現場の部下にしてくる
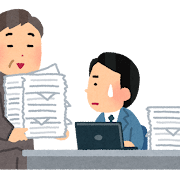
「今すぐこれ、やっといてくれ」「残業してでも終わらせてくれないと困る」——こうした発言に、部下がどれほど強いストレスを感じているか。管理職になると、現場の感覚よりも上層部の意向やKPI重視の視点に偏りがちですが、そこで生まれるのが「無理な要求」です。
たとえばこれは筆者が以前働いていたブラック職場での例ですが、営業部のマネージャーが売上目標を達成するために部下に“飛び込み訪問100件”を命じました。
しかし現場では、感染症対策で訪問が難しく、テレアポすら冷たくあしらわれる状況。にもかかわらず、「とにかく数を回せ」という指示が降り、部下は精神的に追い詰められ、1人が休職にまで至りました。
ここで重要なのは「結果を出せ」と言うのは上司の役割でもある反面、部下の現実や負荷を想像できない言動は確実に“嫌いな上司”への道を進むということです。
部下は「無理なことを押し付けられる」ことそのものよりも、「こちらの状況を理解しようとしない姿勢」に対してストレスを感じます。
上司としての指示が“現場感覚からズレていないか”、今一度見直すことが信頼回復の第一歩です。
無自覚な高圧的な態度や振る舞い
「俺の若い頃はもっとやってた」「それくらい、常識で考えろよ」——このような言葉が口ぐせになっていないでしょうか? 一見、アドバイスや指導のつもりでも、こうした発言は部下にとっては高圧的で一方的に映ります。
そして何より厄介なのは、言っている本人がそのことに“気づいていない”という点です。
筆者が相談を受けた20代の社員は直属の課長に何を話しても「で?結論は?」「それ、お前の主観でしょ」と言われ、話すこと自体が怖くなったと言います。←そもそも慣れ親しい中でもないのに上司から「お前」って言われること自体うざいと思います。
課長は「論理的に話してほしい」と指導しているつもりでしたが、実際には部下の意見を潰すコミュニケーションになっていたのです。
また、無意識のうちに「ため息」「眉をひそめる」「腕を組んで見下ろす」など、非言語の圧力も存在します。これらは本人にとってはクセでも、受け手にとっては「話しかけにくい」「怒られそう」と感じさせ、心理的距離を生む最大要因となります。
管理職として大切なのは「自分はどう接しているか」よりも「相手がどう感じているか」という視点を持つことです。
上司が無自覚に発している言葉や態度が、どれだけ部下のモチベーションや安心感を左右するか。その影響力の大きさにもっと自覚的であるべきです。
「聞く耳がない」「相談できない」のが最大のストレス
「こんなこと相談しても無駄だと思ってしまった」「どうせ聞いてもらえないから黙っていた」—このような言葉が部下から出たとしたら、それは上司としての“危険信号”です。
部下にとって、「話しかけてもいい」と思える空気がないことほど、働くうえでのストレスになるものはありません。
特に、忙しそうにしている上司、常にピリピリしている上司、または“すぐに否定から入る”タイプの上司は、部下から見て「壁のような存在」になります。
そして相談しづらい雰囲気が積み重なれば、そのうち本当に大事な問題も共有されなくなります。
筆者が支援している企業に聞いたケースでは部下が悩みを抱えながら誰にも言えず、最終的に退職代行を使って会社を去ったという事例がありました。
後から上司が「そんなに悩んでたなんて知らなかった」と言ったところで、時すでに遅しです。
退職代行についての上司の対応マニュアルがこちらです。
逆に、何でも相談できる上司は指導が多少厳しくても“嫌われない”傾向にあります。部下にとって重要なのは「この人なら聞いてくれる」「話をさえぎらずに受け止めてくれる」という信頼感と安心感なのです。
「聞く力」は管理職にとって最強のスキルです。
質問にすぐ答える力より、部下の言葉を最後まで受け止める力の方が、チームの安定には何倍も価値があるということを、今一度思い出してください。
部下に「嫌い」と言わせないためには、上司・管理職としてのふるまいを“正す”というより、“見直す”という視点が必要です。
中間管理職支援は
プロストイックが強い
部下に「嫌い」と言われない上司・管理職の共通点
「上司が嫌い」「話したくない」「顔色をうかがうのが疲れる」—こうした本音が、職場における離職や生産性低下の背景にあります。
一方で、「この上司なら信頼できる」「厳しくてもついていきたい」と思われる存在も確かにいます。その違いはどこにあるのか。
本見出しでは、部下に「嫌い」と言われない上司に共通するふるまいを掘り下げます。
特別なスキルやカリスマ性があるわけではありません。ただ、日常の中でのちょっとした接し方、言葉の選び方、感情の扱い方に“違い”があるのです。ストレスを与えず、信頼を築く管理職の具体的な行動を知ることが、明日からのマネジメント改善につながります。
日常的に感謝とフィードバックを伝えている

信頼される上司ほど、日常的に「ありがとう」「助かった」といった言葉を部下に伝えています。
それは決して特別な成果に対してだけではなく、「報告してくれて助かる」「早めに相談してくれてありがとう」など、小さな行動に対する感謝の積み重ねです。
あるIT企業のリーダーは毎朝の朝礼で「昨日○○さんが助けてくれたことで進捗が早まった」といった具体的なエピソードを紹介することを習慣にしています。
それを聞いた他の部下も、「認められる文化がある」と感じてチームの雰囲気が明るくなったといいます。
また、信頼される上司は「指摘」だけでなく「フィードバック」も忘れません。
間違いや改善点を伝える際にも「どうしてこうしたのか教えて」「ここまではよかった、あとはこうした方がもっと良くなる」という伝え方をすることで、部下にストレスを与えず、前向きな修正を促すことができます。
「上司が嫌い」と言われる人の多くは“ダメ出しだけで終わる”“成果は当然だと思っている”という状態になっています。日常の中で部下の努力を認め、言葉にして返すことが、信頼関係のベースになります。
指示ではなく対話で動かすマネジメント

優れた管理職に共通しているのは「命令」ではなく「対話」によって部下を動かしているという点です。
業務指示の場面でも「これやって」ではなく、「どう思う?やってみたい?」と問いかけを重ねながら、部下に主体性を持たせるアプローチを取っています。
当社が支援している銀行のマネージャーは指示を出す前に必ず「このプロジェクト、どんな形で関わりたい?」と聞くそうです。
それだけで部下の意見を聞く姿勢と対話が生まれ、結果的に質もスピードも、責任感も上がるといいます。
一方「俺が言った通りにやれ」「細かい説明はいらない、言われた通り動け」といった上司は高確率で“嫌われる”道をたどります。なぜなら、そこに対話の余地がなく、部下の意思が存在しないからです。
今求められているのは従来の「管理型」ではなく、「対話型」のマネジメントです。部下の中にある“考える力”や“選ぶ自由”を尊重することで、信頼とやる気が生まれる職場ができていきます。
感情をコントロールできる大人の振る舞い
どれだけ能力が高くても、感情のコントロールができない上司はすぐに「怖い」「近寄りたくない」と言われてしまいます。逆に、ピンチのときこそ冷静に振る舞い、怒りよりも対話を優先する上司には自然と信頼が集まります。
たとえば、トラブル対応の場面で「何やってるんだ!」と怒鳴る上司と「今の状況を一緒に整理しよう」と落ち着いて寄り添う上司。
どちらに相談したいかは明白です。
あるベテラン管理職は「感情をぶつける前に、一歩引いて考える。部下のせいにしたくなるときほど、自分の説明不足を振り返る」と語っていました。これはまさに“管理職の成熟度”を示す振る舞いです。
怒りや苛立ちが湧くのは自然なことですが、それを職場にそのままぶつけるのはリーダーとしての未熟さの表れです。部下にストレスを与えず、安心感を持たせるには、「感情の自制」が必須スキルだと認識すべきです。(感情を押さえつけるのではなく、コントロールするというのが難しいポイントです)
上司代行などのパートナーをうまく活用している

本音を言えば、すべての部下と良好な関係を築くのは簡単ではありません。
性格の相性もあれば、価値観のズレ、仕事のスピード感の違いもあります。そこで最近注目されているのが、「上司代行」「中間管理職支援」といった外部のサポートパートナーの活用です。
たとえば、上司代行サービス(中間管理職支援)では、社外の専門家がg現場に入って部下との面談を代行したり、マネジメントのアドバイスを上司に提供したりすることで、「部下の本音が上司に届かない」「自分の接し方がわからない」といった悩みを解消してくれます。
実際に導入した企業では、「本音を外部に吐き出すことで部下のストレスが減り、結果的に関係が改善された」という声も多く、上司が一人で抱え込まない風土づくりにも貢献しています。
加えて現場の業務にも入ってくれるので上辺だけのアドバイスではなく現場の従業員としても働き上司と部下の仕事でのすれ違いを実体験をもって理解した上で組織内のクッション役・ハブとして機能してくれます
信頼される上司は「全部自分でやる」のではなく、「適切に頼る」力も持っています。
部下にとっては、“完璧な上司”より、“頼れる味方を持つ上司”の方が安心感があるのです。嫌われない上司は支援を柔軟に取り入れる“しなやかさ”を持っているというのも、今の時代において大きな強みです。
「上司が嫌い」と言われないために必要なのは、特殊な能力ではありません。
日々の小さな言葉、姿勢、感情の扱い方に気を配れるかどうか。そこに気づき、改善を重ねていくことが、部下との信頼を積み上げる一番の近道です。
中間管理職支援は
プロストイックが強い
管理職が実践すべき“ストレスを与えない”マネジメント
管理職としての役割は成果を上げることだけではありません。
チームメンバーが安心して力を発揮できる環境を整え、日々の仕事に“無用なストレス”を感じさせないように配慮することも、現代の上司にとって不可欠なスキルです。
この記事のこのパートでは、部下から「この上司は信頼できる」と思われるための、“ストレスを与えない”マネジメント手法に焦点を当てます。
単なる気配りではなく、実際のマネジメントにどう組み込むか。
具体的な行動指針と共に、再現性のある形で整理していきます。「上司が嫌い」「管理職がプレッシャーの元」と言われないために、日々どんな視点と習慣が必要か、今一度立ち止まって見つめ直しましょう。
タスクよりも人を見てマネジメントする
「この仕事、終わってる?」「この件、対応した?」と、ついタスクベースでの確認が増えてしまうことは多くの管理職が経験していることです。
しかし、その“管理”が行き過ぎると、部下は「作業ロボット扱いされている」「信頼されていない」と感じ、やがてモチベーションを失ってしまいます。
信頼される上司ほど、タスクそのものより、“タスクをやっている人間”をちゃんと見ているという共通点があります。
たとえば「最近、表情が暗いけど大丈夫?」「このタスク、無理していない?」というひと言を添えるだけで、部下の心理的な負担は大きく軽減されます。
ある企業の事例では進捗確認の際に「業務の進み具合+気持ちの状態」をワンセットで聞くようにマネージャーが習慣づけたところ、体調不良による突発的な離脱が減ったそうです。これはまさに、タスク管理の中に“人を見る視点”を持ち込んだ成果です。
仕事をするのは人であり、人は感情を持つ存在です。だからこそ、数字や期限だけを追いかけるのではなく、「その人の今」に目を向けるマネジメントこそが、ストレスを与えない関わり方の原点なのです。
自分の常識を押しつけないコミュニケーション術
「これくらい言わなくてもわかるだろう」「普通はこうするものだ」——このような発言が、どれだけ部下にストレスを与えているかを理解している上司は、実は少数派です。問題は、それが“良かれと思っている”ところにあります。
今の職場は世代も背景も価値観も異なる人材が混在する多様な環境です。昭和型の“根性論”や“察して文化”は、今の部下には通用しません。むしろ、「自分の常識を押しつけてくる管理職」は、真っ先に“嫌われる上司”になってしまいます。
一部の企業では新任マネージャーに対して「相手の言葉で理解するトレーニング」が導入されています。
具体的には、自分が言いたいことを一旦脇に置き、まずは相手が使った言葉でその背景や意図を確認するという習慣を徹底するのです。結果的に、ミスコミュニケーションが激減し、会議の質も向上したといいます。
「自分にとっての当たり前は、相手にとっての異常かもしれない」——そう考えてコミュニケーションをとる姿勢が、ストレスのない信頼関係の第一歩です。伝え方ではなく、「受け止め方を尊重する力」が、今の時代に求められる上司の姿勢です。
上司代行等の外部パートナーを加えて直接的な対話を意図的に調整する
どんなに経験を積んだ管理職でも、部下とどうしても噛み合わない、あるいは「自分が言えばプレッシャーになってしまう」と感じる場面があります。そこで近年注目されているのが、「上司代行」や「中間管理職支援サービス」の活用です。
これは、外部の組織コンサルタントやが上司と部下の中間に立ち、本音のヒアリングや感情の調整役を担うサービスです。
対話が成立しづらい関係性でも、間に信頼できる第三者が入ることで、誤解が解けたり、改善の糸口が見えるケースも増えています。
管理職としては「全部自分で解決しなければ」と思い込みがちですが、第一歩目は「全て自分で解決することは無理」と現状をきちんと把握することです。時には第三者の視点を取り入れることが、最善の選択になることもあります。
外部の支援を“負け”ではなく、“チーム全体を守る知恵”と捉えることが、ストレスを軽減する柔軟かつ組織の成果を上げるマネジメントにつながります。
失敗を責めない、成長の機会と捉える思考法
部下が失敗したとき、それをどう受け止め、どうフィードバックするか。ここに管理職の“器”が問われます。信頼される上司は、ミスに対して責任を問うよりも、「そこから何を学ぶか」にフォーカスして話を進めます。
たとえば、「なぜこうなったのか」ではなく、「どうしたら次はうまくいくと思う?」と問いかけるだけで、部下は責められるのではなく、“自分の成長に向き合う機会”として失敗を受け止めやすくなります。
筆者が印象に残っているのは、ある製造業のベテラン課長がこう語ったことです。「ミスを責めると、部下は黙る。ミスから学ばせると、自分で考えるようになる。それだけでチームの質は変わる」。これはまさに、“叱る”のではなく“育てる”という本質を突いたマネジメントです。
「またやったのか」「前にも言ったよな」といった言葉は短期的な抑止にはなっても、長期的な信頼や成長にはつながりません。上司の役割は“失敗の追及者”ではなく、“成長の支援者”であるという認識を持つことで、部下はプレッシャーよりも安心感の中で力を発揮できるようになります。
“ストレスを与えないマネジメント”は、管理職としての本質的な力を試される分野です。しかし、それは決して難しいことではありません。「人を見る」「違いを受け入れる」「支援を頼る」「失敗に寄り添う」——この4つの姿勢を持ち続けることで、部下から信頼される上司への道は確実に拓けていきます。
次の見出しでは、これらのマネジメントをどう日常業務に組み込むか、その仕組みづくりと習慣化のポイントについてお伝えします。
嫌われる上司にならないための自己チェックリスト

どんなに能力が高く、仕事ができても、「この上司、正直嫌いです」と部下に思われてしまうと、マネジメントは機能しません。部下の本音が出てこない、報告が減る、指示が通らない——これらはすべて「信頼の崩れ」から始まる現象です。
では、どうすれば嫌われない上司になれるのか。答えはシンプルで、自分自身の言動を定期的に振り返ることです。本見出しでは、嫌われる上司に共通する“無自覚なNG行動”と、それを防ぐための自己チェックのポイントを整理していきます。
あなたのマネジメントが無意識のうちに部下にストレスを与えていないか? 管理職としての自覚を持っているつもりでも、細部にこそ本質が出ます。今のうちに“嫌われる兆候”を摘み取っておきましょう。
無意識にやっていないか?5つのNG行動

管理職の中には「自分はそこまで悪いことをしているつもりはない」と思っていても、部下からは“ストレスの源”と見られているケースが少なくありません。特に厄介なのは、自覚がないまま繰り返しているNG行動です。
以下は、筆者が多くの企業取材でよく聞く、「嫌われる上司」が無意識にやってしまっている典型的な言動です。
- 会話がすべて“業務の話”で終わる(人としての関心がないように感じる)
- 指摘はするが、褒めることがない(成果を出してもスルー)
- 機嫌の良し悪しが態度に出る(部下が気をつかう)
- 部下のアイデアに「でも」「それは違う」と否定から入る
- 自分のミスは曖昧にし、部下には厳しく責任追及する
一つでも心当たりがあるならかなり要注意です。こうした行動は、毎日少しずつ部下の信頼を削っていき、やがて「この上司、嫌いだな…」という感情に発展します。
部下は上司の一挙手一投足をよく見ています。だからこそ、「言っていない」「そんなつもりじゃない」では済まされないのです。まずは自分の行動を丁寧に振り返ることから、ストレスを与えない上司づくりは始まります。
自分の発言・態度を客観視する方法
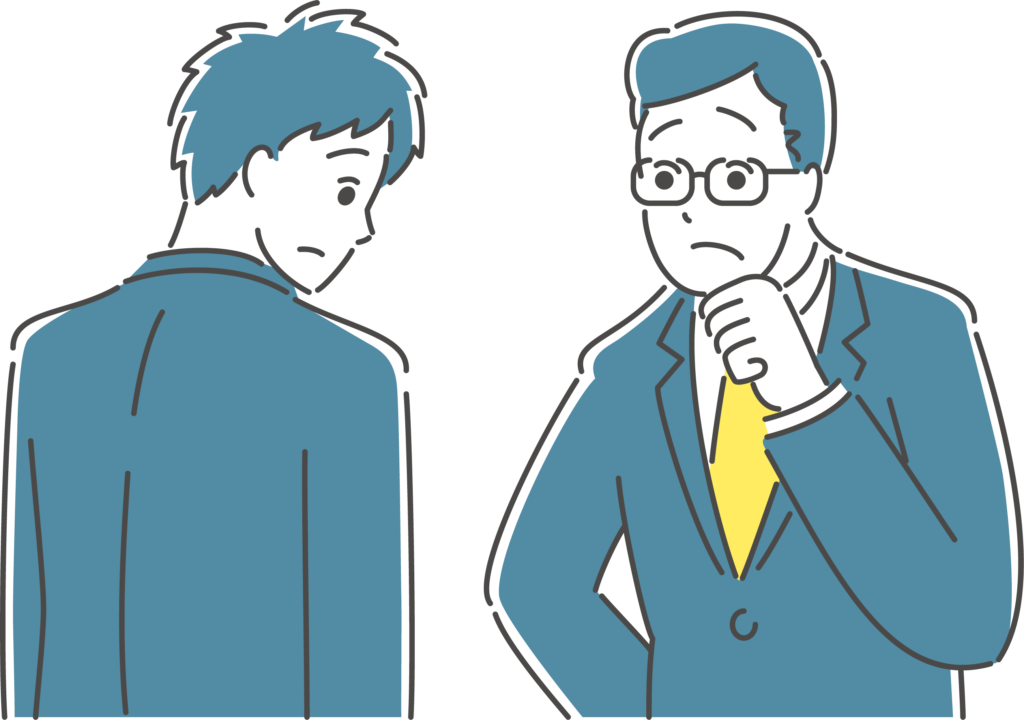
上司として最も難しいのは、自分自身の言動を客観的に見ること(メタ認知)です。なぜなら、人は自分の行動を“正当化”する傾向があり、「自分は悪くない」と感じるように脳が働いてしまうからです。
そのため、意識的に“外の視点”を取り入れる仕組みが必要です。以下は、実際に企業現場で効果があった自己客観化の方法です。
- 業務日報に「自分が今日した発言で気になったこと」を1つ書く
- 定期的に部下アンケートを取り、匿名でフィードバックをもらう
- 1on1面談の録音・録画を振り返り、自分の口調や間合いを確認する
- 信頼できる同僚マネージャーと、お互いのマネジメントをレビューし合う
たとえばある企業では、月に1度“フィードバック・フォーラム”という簡易セッションを実施し、部下が上司に対して「ありがたかった言動」と「ちょっと気になった点」をシェアできる場を設けています。
それを聞いた上司の一人は「普段使っていた言葉が意外と威圧的に伝わっていたと初めて知った」と語っていました。
大切なのは“自分の目では見えない自分”をどう知るかです。客観視の仕組みづくりは嫌われない上司になるための基礎体力といえます。
部下との距離感の取り方で注意すべき点

部下との関係をよくしようとするあまり、距離の取り方を間違えてしまう管理職も少なくありません。距離が近すぎると「なれなれしい」「線引きがあいまい」と感じられ、遠すぎると「冷たい」「怖い」と感じられる。このバランスこそ、上司の力量が試されるポイントです。
ありがちな失敗例は「フランクに接すれば信頼される」と考えて、あだ名で呼んだり、プライベートに踏み込みすぎたりするケース。
部下がそれを歓迎していればいいですが、内心で「距離の詰め方が急すぎて疲れる」と感じていることもあります。←だいたいいきなり呼び方を変える上司は距離感を間違えていることが多いです。
逆に、何でもメールやチャットで済ませ、雑談ゼロ、声かけゼロという“ドライすぎる上司”もいます。これでは「存在感はあるのに人間味がない」「報告しづらい」といった印象を持たれやすく、信頼構築が難しくなります。
適切な距離感とは、仕事に必要なことはしっかり伝える一方で、“心の余白”を残した接し方をすることです。
たとえば、「最近どう?」「今日は大変そうだったね」といった小さな気遣いを、タイミングよく入れるだけで、部下は「気にかけてもらっている」と感じ、心理的安全性が高まります。
「近すぎず、遠すぎず」。この距離感は一度で習得できるものではなく、日々の観察と試行錯誤の中で掴んでいく感覚です。部下によって“ちょうどいい距離”も違うため、常にアンテナを張り続ける姿勢が求められます。
上司が「嫌われない」存在であることは、単なる人気取りではありません。
部下が安心して働ける環境をつくり、組織全体の生産性と雰囲気を底上げする土台そのものです。今回紹介したチェックリストをもとに、ぜひ一度自分自身のマネジメントを見直してみてください。
管理職が知っておきたい“部下のホンネ”
部下がどんなふうに上司を見ているか、日々の表情や態度からなんとなく察しているつもりでも、実際の“ホンネ”までは届いていないことが多いものです。
「特に不満を言ってこないから大丈夫だろう」「部下とは適度な距離を取っているから問題ない」——そう考えている管理職こそ、気づかないうちに部下から「この上司、正直キツい」と思われている可能性があります。
ここでは、部下が上司に対してどんなときに「嫌い」と感じるのか、そしてその感情がチーム全体にどんな影響をもたらすのかを、実例とデータを交えて解説していきます。マネジメントにおける“見えない地雷”を踏まないために、まずは部下の視点で職場を捉え直すことがスタートラインです。
部下はどんな瞬間に「この上司無理」と思うのか
「この上司、ほんと無理」——その一言が出る瞬間には、必ずきっかけがあります。決して派手な事件やトラブルが原因とは限りません。むしろ、日常のささいな言動の積み重ねこそが、部下の中で“不信感”を育て、「嫌い」という感情に変わっていきます。
たとえば次のような場面です。
- 自分の話ばかりで、こちらの話を聞いていない
- 失敗を叱るだけで、フォローも励ましもない
- 口では「いつでも相談して」と言うのに、実際には忙しそうで近づけない
- チームの成果は自分の手柄にするのに、ミスは部下のせいにする
- 「気にするな」と言いつつ、その後態度がよそよそしくなる
これらはすべて、筆者がヒアリングした中で実際に出てきた事例です。
特徴的なのは、上司本人はまったく悪意なくやっているということ。つまり、部下が「無理」と思った瞬間、上司側にはその自覚がないことが多いのです。
だからこそ、「怒っていないから大丈夫」「何も言われていないから問題ない」という思い込みは非常に危険です。部下は“辞める寸前”まで何も言わないことがあります。そして、その沈黙の裏には、上司に対する“我慢の限界”が潜んでいるのです。
嫌いという感情が職場全体に与える悪影響
「上司が嫌い」という感情が生まれたとき、それが部下個人の中に留まっていればまだマシです。問題は、その感情が職場内でじわじわと広がっていくことにあります。誰か一人の不満やストレスが、やがてチーム全体に影響を及ぼす“空気感染”のような現象が起こるのです。
ある企業で実際にあった例では、若手社員が「上司が信用できない」と感じていたことを同僚にこぼすようになり、数ヶ月後にはチーム全体に「この上司には報告しにくいよね」という雰囲気が蔓延。結果、情報共有の質が下がり、連携が取りづらくなり、最終的にはプロジェクトの遅延にまで発展しました。
このように、上司と部下の関係の歪みは、業務効率や成果に直結します。さらに厄介なのは、「何が原因でこうなったのかが見えづらい」点です。表面的には仕事が回っているように見えても、実際には部下が“言いたいことを言えないまま働いている”という状態が続いている場合もあります。
職場における感情の空気は無視できません。
上司への“嫌悪感”は、部下の成長機会を奪い、報連相を滞らせ、組織全体の生産性を下げる“見えない損失”を生みます。だからこそ、「嫌われない上司」であることは、チームの未来を守るための経営的な判断でもあるのです。
実際のアンケートに見る「嫌われる上司像」
2023年に実施されたとある人材系企業の調査では「今まで出会った中で、最も嫌いだった上司の特徴は?」という質問に対し、以下のような回答が多く集まりました(複数回答)。
- 1位:感情的に怒鳴る・機嫌で態度を変える(68%)
- 2位:人によって態度を変える(54%)
- 3位:部下の意見を一切聞かない(49%)
- 4位:責任を取らず、人のせいにする(43%)
- 5位:プライベートに土足で踏み込んでくる(36%)
これらは、いずれも“上司としての行動”というより、“人としての信頼”を損なう言動ばかりです。つまり、部下が嫌うのは「厳しさ」そのものではなく、人としての敬意が感じられないふるまいに対してなのです。
一方、同じ調査で「尊敬できる上司」に挙がった特徴は
- 話を最後まで聞いてくれる
- ミスを責めずに一緒にリカバリーを考えてくれる
- 成果をきちんと評価してくれる
- 部下一人ひとりに合った接し方をしてくれる
というものでした。ここから見えてくるのは部下は“完璧な上司”を求めているわけではないということ。むしろ、“人間として信頼できる存在”を上司に求めているのです。
このようなリアルなデータを知っておくことで「自分が今、どう見られているか」の想像力が深まります。そしてそれは、日々のマネジメントを見直す大きなヒントになります。嫌われない上司になることは努力と意識で誰にでも可能なことなのです。
部下のホンネに目を向けることは、管理職としての責任のひとつです。
「自分は大丈夫」と思っているうちに、気づけば信頼を失っていた……そんな事態を避けるために、まずは部下の目線を知ること。そして、その声をマネジメントに反映させること。
中間管理職支援は
プロストイックが強い
まとめ:現代の管理職に求められるマネジメントとは
かつての管理職に求められていたのは「命令すること」「統率すること」でした。しかし現代の職場ではその在り方が通用しなくなりつつあります。今の時代に必要なのはトップダウン型のマネジメントではなく、組織全体で成果と信頼関係の両立を目指す姿勢です。
今回の記事では、「上司が嫌い」と言われる構造、その理由、対処法、改善事例、そして具体的なマネジメントスキルに至るまで、多角的に掘り下げてきました。最後に、これからの時代に上司・管理職が持つべき覚悟と選択肢について整理し、締めくくりとします。
嫌いと尊敬は紙一重と上司は腹をくくるべし
「嫌われたくない」——これは多くの上司が抱える本音でしょう。
しかし、部下との関係において、「嫌い」と「尊敬」は実は紙一重です。
一見厳しく映る上司でも、「この人は本気で自分の成長を考えてくれている」と伝われば、やがてそれは深い信頼に変わります。
逆に、優しいだけで距離を取り、問題に踏み込まない上司は、長期的には「頼りない」「無関心」として嫌われることもあります。
つまり、上司に求められるのは「好かれること」ではなく、“信頼されること”です。
そのためには、ときに腹をくくって言いづらいことも伝え、ときに一歩引いて部下の言葉を受け止める覚悟が必要です。
筆者が取材したある管理職は「嫌われるかもしれないけど、それでもチームのために言うべきことは言う」と決めてから、部下との関係が逆に安定したと語っていました。「自分の言葉にブレがなくなったことが信頼に変わった」とのことです。
嫌われたくないとビクビクするのではなく、「どう伝えれば伝わるか」「この人のために、どこまで寄り添えるか」を考える。その積み重ねこそが、“尊敬される上司”への最短距離です。
上司代行を活用して強固なマネジメント体制を創る
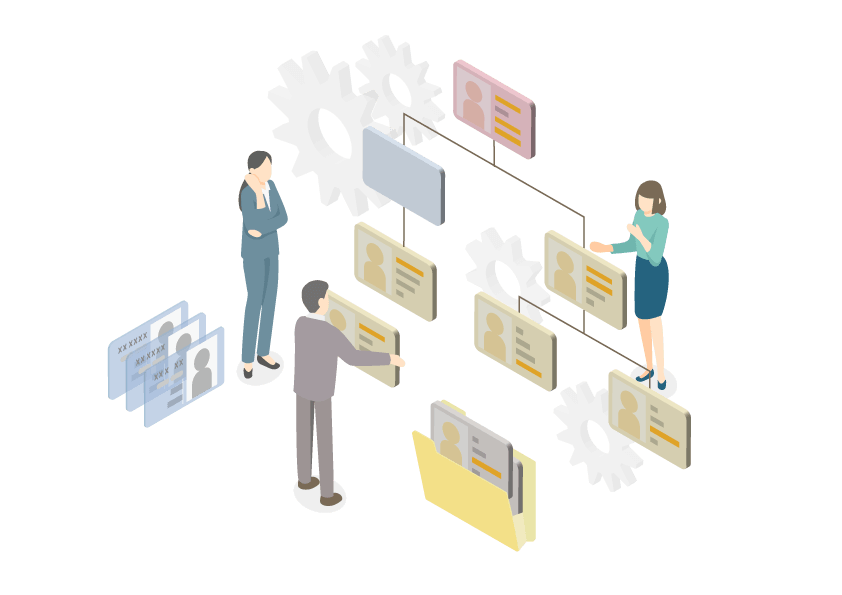
どれだけ経験豊富な管理職でも、すべての部下と完璧な関係を築けるわけではありません。
人間同士ですから、相性や立場、価値観の違いもあります。そこで注目されているのが、「上司代行」や「中間管理職支援」といった外部パートナーとの連携です。
上司代行は専門の第三者が部下とのコミュニケーションの橋渡しをしたり、管理職自身のマネジメントの質を高めるためのフィードバックを提供したりするサービスです。これにより、直接的な関係では生まれづらい信頼や安心感を補完することができます。
ある企業では、上司代行を取り入れたことで、上司と話すのが苦手だった若手社員が初めてキャリアの悩みを打ち明けることができ、配置転換につながった例もあります。結果的にモチベーションが回復し、離職を回避できたとのことです。
「部下のことは上司が全部面倒を見るべき」という考え方はもはや時代遅れです。これからは、“支えられる上司”であることが強さになる時代です。必要なときに適切なリソースを呼び込み、部下の可能性を最大化すること。そのための選択肢として、上司代行の活用はますます重要性を増していくでしょう。
時代が変わり、働き方が多様化する中で、管理職に求められる役割もまた、大きく変わっています。
ただ業務を指示し、結果を追うだけのマネジメントは通用しません。これからの管理職には、部下を信じ、支え、共に成長していく柔軟さと覚悟が求められています。
「嫌い」と言われるのを恐れるのではなく、「信頼される存在であれるか」を問い続けること。
それが、現代のマネジメントにおいて最も大切なスタンスです。そしてそれは、一人ではなくチームで築くもの。だからこそ、外部の力もうまく取り入れながら、“強く、しなやかな管理職”を目指していきましょう。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック