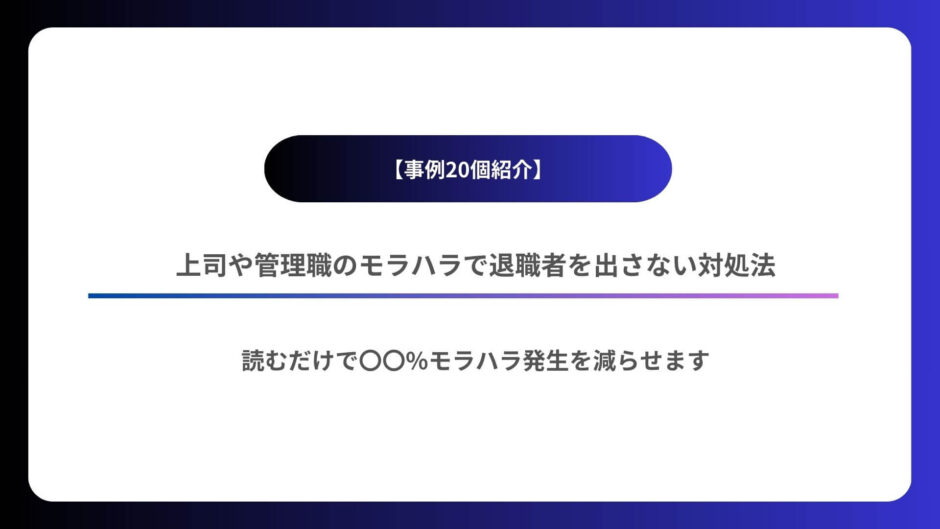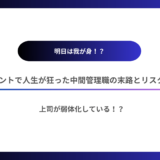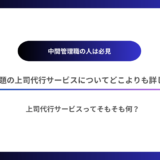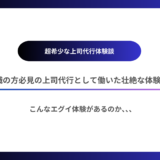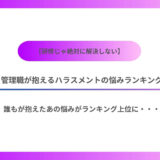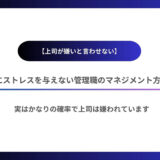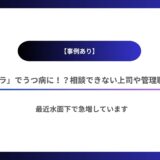皆さんこんにちは。株式会社プロストイックです。
本日は「モラハラ疑惑のある上司」の方や「モラハラをされているかも?と思う社員の方」必見の内容となっています。
会社員として努めている方は一度は絶対に目を通しておきたい内容となっているので目次で気になる箇所だけでも読むことをおすすめします。
- 自分が管理職・上司をやっているがモラハラをしている疑惑がある
- 上司にモラハラをされていて、悩んでいる
- モラハラが社内で横行していて、組織がこのままだとまずい状況
当サイトでは上司のマネジメント系に関する悩みの記事が非常に多く読まれています。人事など向けではなく、現場の管理職に多く読んでいただいている内容となっております。
上司や管理職のモラハラとは
「モラハラ(モラルハラスメント)」という言葉は近年ますます社会で浸透してきていますが、実際の職場ではまだまだ見過ごされているケースが多く存在します。
特に上司や管理職によるモラハラはその権限や影響力があるがゆえに、相談窓口などを設けても部下が声を上げづらく、深刻化しやすい傾向にあります。
(企業によっては相談窓口が機能していないこともあり、実質的に声を挙げられないケースもあります)
この記事では職場で起きがちなモラハラの実態や背景、そして部下が受けるストレスの構造、さらには組織に与える長期的な悪影響を明らかにしながら、具体的な対処法や未然に防ぐ仕組みづくりについて掘り下げていきます。
最初のステップとして、まずは「モラハラとは何か」を正しく理解し、指導との違いを認識することが必要です。
ちなみにご自身が絶対にモラハラをしないと自負している方こそ非常に危険です。
多くの職場では水面下で起きている
モラハラはパワハラのような身体的な攻撃ではなく、”言葉や態度、無視、無関心といった“見えにくい暴力”として現れるのが特徴です。そのため表面化しにくく、企業側や他の社員が気づくまでに時間がかかることがほとんどです。
とくに上司からのモラハラは「性格的なものだろう」「仕事だから仕方ない」と周囲も受け流しがちで、部下は孤立しやすくなります。たとえば以下のようなケースが実際に報告されています。
- 頻繁にため息をつきながら部下を無言で見下す
- 会議で意図的に発言させず、存在を無視する
- 「あいつはできないやつ」と陰で悪評を流す
- 必要な情報を与えず、業務で失敗させる構造をつくる
こうした行動が日常的に繰り返されると、受け手は「自分が悪いのではないか」と思い込み、心身に不調をきたすことになります。そして最悪の場合、退職やメンタル疾患にまで発展します。
モラハラは表面化しづらく記録にも残りづらい。
そのため、当事者が声を上げられない限り、周囲も見て見ぬふりをしてしまいがちです。しかしその沈黙が、組織にとっては“見えない損失”となって積み重なっていきます。
上司のモラハラによって組織の生産性が低下
「ひとりの問題」として片づけられがちなモラハラですが、実際には職場全体に深刻な悪影響を及ぼします。最も顕著なのは生産性の低下です。
たとえば、モラハラを受けた部下は常に萎縮して仕事に取り組むようになります。
自分の意見を出すのをためらい、指示待ちの姿勢になり、ミスを恐れて積極的な行動が取れなくなる。
結果、業務のスピードと質の両方が落ちていきます。
さらに、モラハラの存在を他の社員が知ると、「自分もいつターゲットにされるかもしれない」という不安が広がり、職場の心理的安全性が壊れていきます。
誰もが本音を言えず建設的な議論が避けられるようになり、組織全体が“縮こまった空気”に包まれるのです。
筆者が現在支援していた中堅のメーカー様では、過去にある管理職のモラハラにより半年間で4人の若手が立て続けに退職。採用コストだけでなく、教育にかけたリソースも無駄になり、チーム再建に1年以上かかったとのことでした。
1人採用するのに100万円かかっているとしたら400万円(+時間的コスト)もムダにしたことになります
このように、上司のモラハラは「本人と部下だけの問題」ではありません。それは組織の信頼、士気、そして未来を蝕むリスクです。だからこそ経営層や人事部門はモラハラを“個人間の揉め事”と見なさず、組織課題として向き合う必要があります。
「指導」と「ハラスメント」の線引きはどこか
上司として部下を育成し、業務を円滑に進めるために指導するのは当然の役割です。しかし、その指導が“行き過ぎ”たときに、モラハラと化してしまうことがあります。問題は、その境界線が非常にあいまいであるという点です。
「厳しく指導しているつもりだった」「本人のためを思って言った」——こうした言い分は加害側からよく聞かれます。しかし、ハラスメントの定義は「受け手がどう感じたか」に重きを置くため、“善意”や“教育のつもり”でも成立してしまうのが現実です。
線引きの一例として、以下の観点が参考になります。
- 「人格」を否定していないか(例:「ダメだな」→×、「このやり方だと伝わらない」→◯)
- 「個別指導」と称して長時間の説教になっていないか
- 「その人だけ」に極端に厳しくしていないか
- 「言い方」「タイミング」「頻度」が適切だったか
これらを意識するだけでも、指導とモラハラの境界は見えてきます。
大切なのは“正しさ”よりも“伝え方”に配慮する視点です。
特に、感情をぶつける形の指導はすべてモラハラの入り口だと考えた方がよいでしょう。
また、指導がうまくいかないとき、外部のマネジメント研修や1on1の進行役を依頼するなど、第三者の力を借りる選択肢も検討すべきです。
上司個人の善意や努力だけで解決できない時代だからこそ、「伝える力」と「配慮する力」は、管理職にとって欠かせないスキルなのです。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
【実録】上司・管理職のモラハラ事例20選
ここでは事例を20個紹介しているので、上司の方は「自分の行動に該当するものがないか」を。「社員の方は自分が受けているものはないか」、そして人事の方は「これらの問題が発生したときに対処できる対応策を用意しているか」を確認してみてください。
モラハラと一口に言っても、その形態はさまざまです。
言葉によるもの、態度によるもの、業務の振り方でのプレッシャーなど、受け手によって感じ方も大きく異なります。上司や管理職の立場にある人が気づかないうちに、部下にストレスを与え、追い詰めているケースも珍しくありません。
モラハラの種類・パターン
ここでは職場で実際に起きたモラハラを20のパターンに分類し具体的な事例として紹介していきます。もちろんこれ以外もあると思いますが、傾向として多いタイプをピックアップしております。
ちなみに以下のパターンに分類してそれぞれのモラハラをご紹介しております。
- 無視排除型:声かけ・挨拶など基本的な接触を断つ行為
- 攻撃威圧型:言葉・態度で威圧、責め立てる
- 負荷過多型:不適切な業務量・無理な期限を与える
- 業務調整型:仕事を与えない、もしくは意図的に外す
- 差別・不公平型:人によって扱いを変える
- プライバシー侵害型:私生活への過剰な干渉
- 支配型:選択肢を与えず強制的に従わせる
- 仲間外れ・人間関係操作型:孤立させるような空気を作る
- 手柄横取り型:成果を自分のものにする
- 人格否定型:能力や存在そのものを否定する発言
おそらく読み進めているうちに上司の方の場合、「え?これもダメなの?」、「じゃあどうすればええねん」という内容が頭をよぎるかもしれません。
しかし意識を変えるにはここで挙げている例は他人事ではないということをまず認識すべきです。
対応するべき内容は後半にきちんとまとめているので、まずは読み進めていただけると幸いです。
1. 無視・挨拶を返さない(無視排除型)
1つ目は無視・排除型です。
これはある中堅商社でのお話です。30代の男性社員が部長に挨拶をしても無視され続けるという状態が1ヶ月以上続いていました。
もちろん必要な依頼は向こうからしてくるのですが、こちらからの会話や確認などは何度も無視されて、ゼロ距離で聞いてようやく対話に応じてくれる状況で、あきらかに意図的な無視行為が続いていました。
これは部長だけではなく徐々に部署全体に広がり始めました。
はじめは「たまたま聞こえなかったのかも」と受け取っていましたが、他の社員とは普通にニコニコしながら会話している様子を見て、自分だけが意図的に排除されていることに気づきました。(突然飲み会にも誘われなくなったし、自分を除いたチャットグループがあることも後から知りました)
これまでの行動を振り返ると以前部長に強めに意見を言ってから部長の行動が変わっていることに気づきました。
おそらく部長は「強めに意見を言うとパワハラになるからあえて無視をしている。最低限仕事の会話だけはして」のだと思いました。(←ただ、これはモラハラです。)
挨拶を無視され続けることで当該社員は「存在を否定されているような感覚」になり、職場にもいずらくなり精神的に大きなストレスを抱え、結果的に体調を崩して退職しました。
この行為はモラハラの可能性があり、たとえ言葉を発していなくても「無視」という態度で相手を傷つける立派なハラスメントに該当します。そもそも上司という立場なのに無視をするという幼稚な行動にモラルが伴っているわけありませんよね。
なので必要最低限仕事の会話はしていても挨拶を無視したり、意図的に距離をおいて相手を遠ざげる行為は絶対にしないでください。
2. 仕事を与えない(業務調整型)
こちらはある製造業で働く女性社員が直属の上司から突然ほとんどの業務を外され、やることがない日が続いたというケースです。
こちらも先程と同様に過去上司に対して意見をしたことが気に障ったのか(決して強く意見したとか反抗したわけではない)、ある日から突然、上司からの仕事の指示がゼロに。
進捗会議や部内MTGでも名前さえ呼ばれず、メールにも上司は一切返信しない。“職場にいながら存在を無視される”状態が続き、当該社員は精神的に追い詰められ、心療内科に通うことになりました。
以前は同僚と同じように業務を担当していたにも関わらず、「君はもうそんなに責任あることを任せられない」と言われ、明確な理由もないまま仕事が消えました。
やることがない状況が続くのは、仕事を振りすぎることと同じくらい残酷です。周囲からも「何してるの?」と不審がられ、居場所を失った彼女は数ヶ月後に部署異動を願い出ました。
これは典型的な「干す」行為であると同時に明確な業務妨害であり、陰湿なモラハラの極地です。排除と支配の両方を含むモラハラの一種です。
似たように「干す」行為ではあるものの、こちらは懲罰的な意味合いが強いケースです。
勘違いしている上司の方が多いのが残念ですが、何かあったときに「手を出したらパワハラになるから何もさせない」ことがまかり通るわけではありません。
3. 放置(業務調整型・支配型)
似たように「干す」行為ではあるものの、こちらはモラハラも含めたマネジメント不届きな意味合いが強いケースです。
まだ中小規模の企業の中で「経験を積ませる」と言いながら、同時に3件のプロジェクトを丸投げ。
周囲のサポートもなく、「自分で考えろ」としか言わない。納期に間に合わないと叱責、遅れれば「やっぱり無理だったか」と皮肉を言う。これは業務調整を利用したモラハラの代表例です。
それに加えてプロジェクト管理をしていないマネージャーとしての資格や責任も果たしていないので、典型的にマネージャーとしてダメなケースです。(もちろんマネージャーが忙しいケースもありますが、一番ダメなのは最後の「叱責」と「やっぱり無理だったか」の一言です。ここまで放置しておいてその一言はさすがに許されません)
4. 会議で意図的に発言の機会を奪う(仲間外れ・人間関係操作型)
とある食品メーカーで起きた事例。最初は部下が会議のファシリテーションをしていましたが途中から会議の進行をすべて上司が握り、特定の部下には発言のタイミングを与えず、話しかけても「今はいいから」と制されることが続いていました。
周囲からも「いつもあの人だけ話してない」と見られたり「あいつは会議の空気を壊す」と言われました。発言の自由を奪う行為もですが、そのような「差別的行為」は組織の心理的安全性を破壊します。
次第に本人も発言を諦めていきました。その結果、業務提案の場がなくなり、評価にも影響し、自信喪失に至りました。
確かに部下の方はまだ会議のファシリテーションや意見だしが得意ではなかったのかもしれませんが、事前に経験を積ませるとか、練習をさせるとか上司として部下を育成する機会と方針を明確にすべき例です。
これは意図的な発言封じみなされる場合があり、職場での存在感を奪う&育成放棄となるモラハラと認定される可能性があるケースです。
5. ミスを大げさに責め立てる(攻撃威圧型)
これはいまだに多い例です。報告ミスがあった若手社員に対して、上司がその場で机を叩き、「何回言えばわかるんだ!」「これで信用ゼロだな」と大声で怒鳴ったという事例が報告されています。
しかも他の社員が見ている前で繰り返し糾弾され、「このままじゃ終わりだぞ」と脅されるような言動まであったそうです。
これは典型的な威圧・恫喝型モラハラです。
周囲に人がいる場での叱責や恫喝はモラハラに加えてパワハラにも該当します。
これは指導とは言い難く、人格に対する圧力行為にあたり企業によっては訓戒(注意)ではすまされず、懲戒(懲戒解雇ではなく)になるケースもあります。
6. 能力を否定する言葉を繰り返す(人格否定型)
これもいまだに非常に多い例です。「君って本当に向いてないね」「なんでまだこの程度なの?」といった言葉を、1日に何度も投げかけられていたという女性社員の事例。
最初は「厳しい人なんだ」と思っていたが、毎日繰り返されるうちに、「自分が無能でしかない」と思い込むようになり、最終的にはうつ状態で休職しました。
これは完全に人格そのものを否定するモラハラであり、最も危険な形態のひとつです。
また特に営業系の組織で聞くケースが多いですが何か月も目標未達の部下に対して「無能だなほんとに」「ほんと何やってるの毎月」「お前給与泥棒だろ」等と部下に圧力をかけるケースです。
これも同様に人格そのものを否定するモラハラであり、あってはいけない発言です。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
7. 目の前でため息をつく・舌打ち(無視排除型・威圧型)
これは断続的な嫌がらせに近いモラハラになる可能性があるケースです。
直接的な言葉がなくても、毎回レポートにいくたびに「ため息」「舌打ち」などをされることで、「自分は迷惑をかけている存在なのか」と感じさせるケース。
ため息後は普通のフィードバックが返ってくるので何か一種の癖かと思いましたが、特定の部下だけにやっていることが後から発覚しました(本人は無自覚)。たしかにその部下のレポートはまだまだ足りない部分が多かったのですが、静まり返ったオフィス内でため息なんてつかれたら周りの目も気になってしまいます。
これを3ヶ月以上受け続けた20代社員は、体調を崩して離職しました。
行動に言葉が伴わなくても、態度そのものが攻撃になるという典型例です。
加害者が「そんなつもりなかった」と言うケースが多く、意識の乏しさも問題となります。これが上司目線ではモラハラに該当する。
8. 自分の機嫌で態度を変える(支配型)
非常に多い例です。
昨日まで優しく話していた上司(課長)が今日は無言、明日は怒鳴る——という不安定な態度が続くと、部下は上司の機嫌を読むことに疲弊します。
いわゆる上司(課長)が情緒不安定、メンタル不安系のパターンです。
こうなると非常にやっかいで、もう社員からしたらどうしようもありません。そのまた上の上司(部長)は現場を見ない人なので、気づかないし、人事も現場なんて見てくれません。
こういう情緒不安定系上司に限って上のレイヤーと話すときは情緒が安定している最悪のパターンです。
とある30代営業職の男性社員は「一日の始まりが上司の顔色で決まる」と語っていました。
こうした振る舞いは感情的支配によるストレス構造であり、部下のメンタルにじわじわと悪影響を与えます。
自分の機嫌で態度が変わること自体がモラハラではありませんが、これはいずれモラハラに繋がる確率が非常に高いケースです。情緒の不安定化によって感情を制御できずいずれ上司が自滅していくことが多いです。
9. 過剰な業務量を一人に集中させる(負荷過多型)
「頼れるから」と言われて、複数人で分担すべき業務を1人で任され続けたケース。
納期に追われる毎日が半年続き、残業続きで体調を崩した女性社員が、最終的に過労で倒れ、医師から「うつの一歩手前」と診断されました。
これは賞賛に見せかけた過重労働の押し付けであり、モラハラの一種です。「お前ならできる」がプレッシャーになることもあると、管理職は理解すべきです。
これも過重労働自体がモラハラではありませんが、そのような状況はモラハラに非常に繋がりやすいです。
労働時間が長いとストレスが蓄積されて部下への罵倒や叱責、恫喝などが多いケースがいくつも報告されています。
10. 休暇や有給を取らせない(支配型・不公平型)
これは完全にアウトなモラハラ例です。
「今それどころじゃないでしょ」「みんな我慢してるよ」と、有給申請を事実上却下する上司のもとでは、社員がプライベートを犠牲にするしかありません。
最近はオープンに言えるようになっているケースも多いですが、一部の職場ではまだまだ浸透していないので改めて言うと「有給は労働者の権利」です。
休む権利を奪うことも立派なモラハラであり、管理職が最も気をつけるべき行動のひとつです。
社員によっては録音しているケースもありますし管理職は平然と有休を取らせない態度を改めるべきですし、社員の方もそのような上司・管理職を変えるにはやりたくないかもしれませんが、きちんと証拠を残しておくことが重要です。
11. 他部署へ不本意な異動を強要(業務調整型・支配型)
家電メーカーで働く30代の女性が直属の上司と意見が対立した一方的に人事に掛け合われ、まったく経験のない管理部門へ異動させられたという事例があります。
異動の理由は明確にされず、本人の希望も無視され「逃げられないように環境を変えられた」と精神的に大きな打撃を受けたそうです。
この方は上司とキャリア面談をしたばかりで、明確なキャリアを示したばかりなのに、まったく意図しない人事配置をさせられて非常に憤りを覚えていたケースです。
これは「異動」という制度を利用した圧力型モラハラ(職権乱用)です。業務命令に見せかけた排除行為として、非常に悪質なパターンに該当します。
12. 成績や成果を認めない(手柄横取り型)
これも一部の組織では水面下で多い例です。
営業職で成果を出した若手社員が、社内報告の場で「上司のサポートが大きかったからな」とすべての功績を上司に持っていかれたケース。しかも本人の名前すら出さないという扱いでした。
(さらに始末が悪い例としてさらに上のレイヤーには「上司の成果」として報告していて上司は昇給したが部下の評価には全く反映されていないというケースもあります。)
「認められない」どころか、「なかったことにされる」屈辱を受け、モチベーションは大きく低下。やがてその社員は他社へ転職しました。
このような手柄の横取りは、実績主義の職場でこそ大問題になります。本人のやる気を潰し、チーム全体の信頼関係を壊す典型的なモラハラ行為です。
13. えこひいきで差をつける(差別・不公平型)
この事例はかなり水面下で発生している例が多いです。
ある旅行代理店の支店では同じ仕事をしているにもかかわらず、上司の“お気に入り”には簡単な仕事を回し、苦手な部下には常に雑務とノルマの押し付けがされていました。
評価や報酬にまで不公平さが現れると、「頑張っても報われない」という不満が蔓延し、職場は完全に二極化。結果、離職者が相次ぎ、業績も悪化しました。
ちなみに筆者の前の上司は「お気に入りの女子」には甘く条件に良いタスクや案件を割り当てて、それ以外の気に入っていないメンバーに問題が山積みの案件を押し付けていて非常に顕著に態度や仕事に出るタイプでした。
ただえこひいき自体の違法性が低く何かに訴えるというより現状では態度を改善させるということしか組織内ではできないのが現状です。(明確な法令違反や社内ルールに反していない限り役割で分けているといわれてしまえばそれまでのことも多い)
えこひいきもモラハラに該当するケースもありますがそれ以上にえこひいきは組織の信頼を壊す非常に悪質な行為です。部下はきちんと、上司の態度や一貫性を見ています。
14. 評価を意図的に下げる(評価操作型)
「お前はもう伸びしろがないから、このくらいで妥当だろ」と一方的に評価を下げられ、上申も却下されたという事例。
成績は悪くなかったにもかかわらず、「態度が気に入らない」という理由で評価を落とされていたのです。
これは評価基準を加味せずに私情を評価に混ぜ込んだ明確なハラスメントであり、評価制度そのものを揺るがす行為です。
モラハラの本質は“力を利用した嫌がらせ”にあります。それゆえにほとんどのモラハラは「上司と部下の間」で発生します。
評価を私物化することほど組織にとって有害なモラハラはありません。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
15. 私的なことまで干渉してくる(プライバシー侵害型)
「結婚はまだ?」「彼氏と別れたのか?」など、仕事と関係のないプライベートに毎日のように踏み込んでくる男性上司(既婚)に困っていた女性社員のケース。←キモイ。
言葉は柔らかくても、明確に境界を越えてくる言動はモラハラに該当しますしこの結婚とか彼氏とかそういった発言はセクハラにも該当します(どちらかというとセクハラになるケースが多い)。
もういい加減このような発言は無くなってほしいし、パーソナルスペースをわきまえてほしいです。
こういったプライベートな話はセクハラ、モラハラに繋がるケースが非常に多く距離感を考えないでそういった発言をすること自体ナンセンスです。いい年したおっさんが街中でナンパしてるのとほぼ同じです。
上司の方にお伝えしたい予防線としては「飲み会にいかない」のが一番安全で行ったとしても「お酒を飲まない」ことです。
こういったプライベートな話で盛り上がるのはオフィスでの勤務中ではなく、多くが飲み会の場などで発生します。
これはプライバシー侵害型モラハラの典型例であり、昨今ではセクハラとも重なる極めて危険な行為になるので、もういい加減やめましょう。そんな会話をしても距離なんて縮みません。
むしろ上司・管理職としてマネジメントする立場なら部下から自発的にそういったプライベートな話が出てくるように組織や場を上手くマネージしてください。
16. LINEや私用連絡で監視する(支配型・私生活干渉型)
休日や夜間でも、LINEで「今どこにいるの?」「返信遅いね」と送ってくる上司。←これも普通にダメですよね。
しかも業務とは関係のない内容で、“常に監視されているようなプレッシャー”を感じていたという20代社員の体験談があります。
私用連絡ツールを使って部下をコントロールしようとするのは、明確な支配行動です。オン・オフの線引きを壊し、常に緊張感を強いる行為は、重いモラハラと見なされますし男女間であればセクハラやストーカーに該当する行為です。
17. 個人情報を勝手に話す(プライバシー侵害型)
これは本当に残念な上司・管理職の方が犯した最低な行為の例です。
同じ部署の女性社員が不妊治療中であることを、上司が社内で“気軽に”話していたというケース。「本人が言ってたから」と主張していたが、実際は一対一の会話で話しただけで、公にしていいとは一言も言っていなかったとのこと。←情報がセンシティブすぎる内容なことをきちんと理解していないダメ上司の典型です。
こうした行動は、重大な個人情報の漏洩であり、職場の信頼関係を崩す一因になります。上司の軽率さが招く深刻なモラハラの一つです。
18. 悪口を他の社員に吹き込む(人間関係操作型)
「○○は陰でサボってる」「あいつと仕事組まない方がいい」といった内容を上司が新人に“忠告”として伝えていたというケース。実際には根拠もない誇張で、本人にとっては知らないうちに職場で孤立する結果となりました。
これは、情報操作によって部下の人間関係を操作するモラハラ行為です。管理職の発言には影響力があるからこそ、誤った言葉は“毒”になります。
19. 飲み会への強制参加(支配型・プライベート干渉型)
これも未だに一部の企業で起こっていますが、毎週金曜日の飲み会に「行かないと評価に響くよ」と言われ、断れずに通い続けた若手社員。実はアルコールが体質的に苦手だったにもかかわらず、無理をして参加していたとのこと。
飲み会にいかないと評価に響くというのはそもそも評価基準に即してるわけないですし、
私的なイベントへの参加を“業務の一部”のように強制するのは、プライベートの支配でありモラハラです。「飲みにケーション」の押し付けが苦痛になっている若手は非常に多いのが現実です。
20. 部下の発言をとにかく否定する(人格否定型)
会議で部下が提案した内容を、上司が「いや、それはこういうことでしょ」と、とにかく真っ向から否定していくるタイプの上司。—こうした行動は意外に多く報告されています。
否定した割に翌週とかになると、過去部下が提案した内容で進める事になっているというパターンです。
それをあたかも自分が提案したかのように進め自分の手柄とするかなりうざいタイプの上司です。
これにより、部下は「どうせ何を言っても否定される」「自分は不要」と感じてしまい、意見を出すのをやめてしまいます。これは発言の奪取=存在意義の否定につながる、深刻なモラハラです。
「自分は正しい」と信じ込む上司の危険性
ここまでご紹介したすべての事例に共通しているのは上司や管理職が「自分は正しい」と信じて疑わない態度にあります。
「指導の一環だ」「厳しくしてやってるんだ」「昔はもっと大変だった」——そうした思い込みが、無自覚のまま他者を傷つける“加害”に変わる瞬間です。
上司が「俺は悪くない」と思っている時点で、部下との信頼関係はもう壊れ始めています。
モラハラを防ぐ第一歩は、「自分の言動は相手にどう伝わるか?」を問い直すこと。管理職は常に自らの権限の強さと影響力を慎重に扱う責任を持たなければなりません。
上司のモラハラを見抜くチェックポイント

モラハラは目に見える暴力や大声ではなく、”日常の言葉や態度に紛れた“静かな攻撃”として行われることが多いのが特徴です。
特に上司や管理職からのモラハラは部下が声を上げづらく、第三者が気づく頃にはすでに手遅れになっていることもあります。
職場で突然「辞めます」と言われて慌てたことがある方、もしくは「最近雰囲気が悪いな」と感じている方は要注意です。
モラハラは、“何かおかしい”という違和感の先に潜んでいます。
部下が黙って辞めていく職場の特徴
モラハラが潜んでいる職場には、共通する“静かなサイン”があります。
その代表が「突然の退職者が多いあるいは休みがちな人が多い職場」です。
特に、退職理由をはっきり語らずに去っていく社員が多い場合、それは上司との関係が原因だった可能性が極めて高いと考えられます。
例えば、以下のような傾向が見られる職場では注意が必要です。
- 退職者が理由を「一身上の都合」としか言わない
- 突然休みがちになる社員がいる
- 若手社員が長く定着せず、1年以内で辞めていく
- チーム内に「〇〇さんとは関わらない方がいい」という暗黙の空気がある
これらの現象は、部下が「何を言っても変わらない」と感じて黙って去る心理の表れです。
モラハラの被害者は、「訴えるだけ無駄」と感じてしまうことで沈黙を選びます。
そして、沈黙の退職が続くということは、組織に「声をあげられない雰囲気」が蔓延している証拠でもあります。
黙って辞める部下が多い職場こそ、上司や管理職のふるまいを疑ってみるべきシグナルなのです。
日常の言動に潜むモラハラサイン

上司自身が「特別なことはしていない」「普通に接している」と思っていても、実は部下にとっては日々の言動がモラハラになっているケースは少なくありません。
気づかないうちに、威圧的、排他的、不公平なふるまいを繰り返していないか、日常の中に潜む“サイン”を点検することが必要です。
たとえば、以下のような言動が頻繁に見られる場合は要注意です。部下の様子やご自身の言動をここで一度見返して見てください。
いそがしかったり、部署の社員が多く一人ひとりにケアをしてあげられない場合は普段から観察できないと思うのでこの機会にぜひチェックしてみてください。
- 部下が話しかけづらそうにしている
- 会議で特定の部下だけ発言機会が少ない
- 上司が成果を褒めず、ミスばかり指摘している
- 上司が曖昧な指示で「察して動け」と求めてしまう
- 上司が私生活や家庭のことに過剰に立ち入る
- 指示や態度がその日の気分で大きく変わる
これらはすべて、表面的には問題なく見えるけれど、受け手にとってはストレスとなる振る舞いです。特に「何を考えているのか分からない」「機嫌がコロコロ変わる」上司の存在は、部下にとって大きなプレッシャーとなります。
重要なのは、“指導”と“支配”を履き違えていないかという視点です。「管理職として当然」と思っている行動こそが、モラハラの温床になっている可能性があります。
アンケートや面談で見える兆候とは

モラハラを可視化し、早期に察知するために有効なのが、「社内アンケート」や「1on1面談」の活用です。ただし、形式的に実施するだけでは意味がありません。回答や会話の中に含まれる“違和感”をどう読み解くかがカギとなります。
たとえば、社員アンケートで以下のような傾向が見られた場合は注意が必要です。
- 「上司との関係性」に関する設問の満足度が極端に低い
- 「職場の心理的安全性」に関する設問に空欄が多い
- フリーコメント欄が無記入、あるいは内容が抽象的
これらは、“本当のことが書けない”“何を書いても変わらない”という諦めのサインです。
また、1on1面談でも、「最近どう?」という質問に「まあまあです」としか返ってこない、目を合わせない、話を切り上げたがるなどの反応が見られたら、それは上司に対する信頼感が薄れている兆候かもしれません。←まぁまぁです自体も「なにか違和感があるな」と疑ったほうがよいでしょう。
本音が出ない場でモラハラの芽を潰すには、聞き手側が「本当に耳を傾ける姿勢」を持つことが大切です。表面の言葉よりも、その背景にある感情や沈黙に注意を払いましょう。
モラハラは“気づけなかった”では済まされない問題です。
部下が辞めてから後悔するのではなく、日常の言動と現場の空気から“兆候”を見抜く感度が、現代の管理職には求められています。
次のセクションではこうしたモラハラの兆候を見逃さずに、退職や職場崩壊を防ぐための具体的な対処法と改善のステップについてご紹介していきます。
モラハラ上司・管理職への具体的な対処法
「まさか自社でそんなことが」と思いたくなるのが上司・管理職によるモラハラですが、現実には静かに、しかし確実に職場の空気を壊していきます。いくら面談やアンケートで兆候を掴んでも、明確な対処策を講じなければ“見て見ぬふり”と同じ結果になります。
ここでは、実際に社内で発生したモラハラに対し、どう動くべきか、企業や人事が取り得る実効性ある対応策を3つのステップで解説します。いずれも「部下を守る」「職場を守る」「上司自身を正す」ためのバランスを取ったアプローチです。
第三者を交えた面談を設定する
モラハラの疑いが浮上した段階で、いきなり加害者とされる上司を処分するのではなく、まずすべきは第三者を交えた客観的な面談の場を持つことです。ここでいう第三者とは、人事担当、外部の専門家、メンタルヘルスのカウンセラーなどを指します。
重要なのは、当事者同士での“言った・言わない”の水掛け論にしないことです。例えば、部下が上司に「態度が冷たくて精神的に苦痛です」と訴えたとしても、上司が「そんなつもりはなかった」と返して終わってしまうようなやりとりでは、問題の根は何も改善されません。
面談では以下の点を整理する必要があります。
- 部下が感じた具体的な言動(例:毎朝の無視、報告の遮断など)
- それが継続的だったかどうか
- 上司の認識・言い分
- 職場全体の空気への影響
こうした面談の場は、加害者・被害者の両方にとって“確認と気づきの機会”になります。上司の中には「そんなつもりはなかった」と本当に無自覚な場合もあります。逆に、明らかなパワーバランス利用であると判明した場合は、次のステップで処分や是正措置に進むことができます。
また、面談の記録は必ず残すことが大切です。感情ではなく事実に基づいた判断ができる環境整備こそ、組織の信用を守る第一歩です。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
就業規則・ハラスメントポリシーの整備
そもそも多くの企業では、「何がモラハラに該当するのか」について明文化されていないのが現状です。そのため、上司側が「自分はルールを破っていない」と感じてしまい、改善が進まないのです。
この問題を解決するには、就業規則や社内のハラスメントポリシーに、以下のような項目を具体的に盛り込むことが必要です。
- 「人格否定、威圧的な態度、無視などもハラスメントと見なす」
- 「部下とのコミュニケーションにおける推奨行動・禁止行動」
- 「ハラスメント通報時の対応プロセスと保護措置」
- 「加害が確認された場合の処分方針」
たとえば、外資系企業では「上司による個人の能力否定発言は禁止」と明記されており、違反した場合には警告→改善プログラム→降格・異動といった流れが明文化されています。
またこういったガイドラインを作っても一部の企業では「管理職や上司にのみ共有」されるのですが、逆で現場社員の方にいきわたるようにしないと意味がありません。
こうしたガイドラインがあるだけで、管理職は言動に対して自覚的になり、部下も安心して報告できるようになります。また、制度として存在することで、「社内全体がモラハラに対して真剣に向き合っている」というメッセージにもなります。
異動・降格など具体的な処分の基準作り
最後に必要なのは、行為の重大性に応じた処分を定めることです。
多くの企業で問題になるのが、モラハラをしていたことが認定されたにもかかわらず、「口頭注意で終了」「曖昧な対応で終わる」という事例です。
それでは、部下も納得できず、同様の問題が繰り返される原因になります。そこで必要になるのが、処分ルールの明確化です。
処分は段階的に考えるのが原則です。
- 初回 → 警告・改善指導(記録付き)
- 改善なし → 評価引き下げ・異動・昇進停止
- 再発・悪質 → 降格・懲戒処分・配置転換
また、改善指導の際には行動改善プログラムやマネジメント研修などを必須とし、「上司として再起する道も残すが、見過ごさない」というスタンスを取ることが大切です。
こうした仕組みが明文化されることで、加害者本人にも「自分の立場が危うい」という実感が生まれ、再発の抑止力になります。
モラハラは、見て見ぬふりをする組織文化がある限り、なくなりません。そして本当に組織を守るのは、「問題が起きない職場」ではなく、「問題が起きたときに正しく対応できる仕組み」です。
次回は、このような制度整備を進めながら、“そもそもモラハラが起きない組織文化”をつくるにはどうすればよいか、実践的な取り組みをご紹介していきます。モラハラを個人の問題で終わらせず、組織としての強さへと変えていく視点が求められます。
モラハラ上司の被害者を守るために組織ができること
モラハラが職場で発生したとき、被害者が最も求めているのは「安心して働ける環境」と「正当な対処」です。
しかし、現実には通報しても何も変わらなかったり、逆に報復を恐れて黙るしかなかったりと、組織の対応の甘さがさらなるストレスと退職を招くケースが後を絶ちません。
そうして組織が何もしてくれないことにより本人の退職、それに加えてその周りの社員にも悪影響が広がるという悪循環が出来上がってしまいます。(繰り返しになりますが、影響を受けるのはモラハラを受けた当人だけではなく、その周りの社員にも伝染します)
ここでは、上司や管理職によるモラハラから部下を守るために、企業や組織が取るべき具体的な仕組みと体制づくりについて紹介します。単なるマニュアル対応ではなく、実効性のある“守るための行動”が求められています。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
声を上げやすい通報ルートの整備
モラハラが表面化しない最大の理由は「相談してもムダ」「誰にも言えない」という空気です。特に加害者が管理職や上司である場合、部下はその上下関係に萎縮し、被害を“なかったこと”にしがちです。
そこで重要になるのが、「このルートなら安心して声を上げられる」と社員に感じさせる通報体制の整備です。以下のような取り組みが有効です。
- 社外の第三者(外部窓口)を含めた通報先の選択肢を用意する
- 匿名でも通報可能な仕組みを導入する(内部通報システムや専用フォーム)
- 「報復行為があった場合は即時調査・処分する」と明文化する
- 通報者のプライバシー保護と守秘義務を徹底する
ポイントは、「通報=不利益になる」という恐れを払拭することです。既に通報の窓口を表面的に設置している企業は多いですが「機能していない」ものが非常に多いです。
通報件数が増えることを“問題の証拠”と捉えるのではなく、「社員が安心して声を上げられる環境が整っている」とポジティブに評価すべきです。
通報の数こそ、心理的安全性のバロメーターと考える視点が今の組織には求められています。
【重要】上司代行(管理職支援)の活用
「モラハラをしている上司と顔を合わせ続けるのがつらい」「でもすぐに配置転換ができるわけでもない」――そんなケースで有効なのが、上司代行サービスや中間管理職支援の導入です。
これは、特定のチームや社員と距離を取りたい場合に、第三者のマネージャーや支援者が一時的にマネジメントや現場業務を代行・サポートする仕組みです。実際に次のような活用例があります。
- モラハラ上司のもとでストレスを抱えていた部下が、代行者を介して意思疎通を取り直すことで関係が改善
- 上司自身がフィードバックを受けることで、自分の態度の問題点を認識
- 管理職研修を兼ねた“サポート付き改善期間”として、再発を防止する環境整備が実現
用途はモラハラ対策だけではなく、現場の組織課題(業務過多・人手不足)が深刻な場合やマネジメント課題として部下の育成や組織の業務平準化に手が回っていないなどのケースにも有効です。
今回はモラハラでの活用を前提として話を進めると上司代行は上司本人が行う役割を切り捨てたり100%役割を切り変えるのではなく、「育て直す」「対話を再構築する」時間を与える施策としても機能します。
現場の課題に対しては採用やツール導入などサポートがありますが、管理職に対してのサポートは薄くわりに業務量が多いというのが現状です。
“管理職も助けを求めていい”という空気がある会社は強い。上司代行の活用は、組織全体のマネジメント体質を健全化させるための一歩になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
中間管理職の現場支援は
プロストイックが強い
相談後の対応を明確化する仕組み
通報があってもその後の動きが曖昧だと、被害者は「結局、何もしてくれなかった」と失望します。
大事なのは通報後にどう対応するかのプロセスと基準を明文化することです。
理想的には相談から対処、再発防止策までの流れを以下のように整理すべきです。
- 相談受理(人事・外部窓口など)
- 事実確認・ヒアリング(加害者・被害者・周囲)
- 結果通知と対処(口頭注意・研修・異動・降格等)
- 被害者への対応(希望確認・部署移動・心理支援など)
- 再発防止に向けたフィードバックと改善策の実施
この流れを社内ポリシーとして共有し、誰でも確認できる状態にすることで、「相談すればきちんと動いてくれる」という信頼感を構築できます。
また、対応内容を組織的にレビューする体制も必要です。「あの時の対応は適切だったか?」「同じようなケースが再発していないか?」を定期的に振り返ることで、制度はより機能するようになります。
加えて監督する人事や直属の上司自身が現場社員にきちんと説明をすることが非常に重要です。
「何かあったときにはこの相談窓口を使ってください」と管理職や監督する人事自ら口にすることできちんと機能する窓口ということを強くメッセージングできます。
逆に上司の方にお伝えしておくと通報窓口があるのにそのことを隠したり、使うなと遠回しに圧力をかける行為は後から必ず発覚して問題になるので絶対にやめましょう。
被害者へのフォローと環境改善の徹底
モラハラ対応で最も忘れてはいけないのが、被害者が受けた心のダメージを癒すケアです。たとえ加害者に処分を下しても、被害者がその後の職場で孤立したり、元の関係が修復されなければ、精神的ストレスは解消されません。
組織として以下のようなフォローを徹底することが必要です。
- 希望があれば部署移動や席替えなど、物理的距離をつくる
- 産業医やカウンセラーとの定期面談を設定
- 同僚からの無理解や噂を防ぐため、職場への正しい情報共有
- 職場環境そのものの改善(部内風土・上司の再教育など)
特に重要なのは、「被害者が悪い空気を持ち込んだ」と見なされることを防ぐこと。これは二次被害であり、再発防止どころか、職場の信頼をさらに破壊します。
モラハラを本気でなくすためには、“誰かが声を上げたら、それによって職場が良くなった”という成功体験をつくることが最も効果的です。そのためには、被害者への手厚いフォローが何より大切なのです。
モラハラは組織の「本気度」が試される問題です。
「見逃さない」だけでなく、「守る」「変える」「育て直す」までやりきる力こそ、今の時代に必要な組織力です。
次章では、こうした対応を通じて、モラハラを“起きない前提”にする職場文化の育て方について、さらに具体的な実践策を掘り下げていきます。
まとめ:モラハラが放置される職場に未来はない
モラハラは決して、当事者間だけの小さな問題ではありません。上司や管理職によるモラハラを放置するということは、職場の信頼関係を破壊し、社員のモチベーションを下げ、生産性の低下と退職者の増加を招く深刻な組織リスクに他なりません。
ここまでの記事ではモラハラの実態、兆候、具体的な事例、そして対処法まで幅広く解説してきました。最後に、職場からモラハラを本当に無くしていくために、これから組織がどうあるべきか、どんな行動をとるべきかを整理しておきます。
管理職の意識と行動が職場全体を変える
モラハラが起きない職場づくりの第一歩は、やはり管理職の意識改革です。部下からの信頼を得られる上司は、「自分が正しい」ではなく、「相手にどう伝わっているか」を常に考えています。
逆に、「昔はこれが普通だった」「厳しくしないと成長しない」といった古い価値観に固執する管理職が職場にいる限り、モラハラのリスクはなくなりません。管理職こそが“空気を変える主導者”であるべきです。
たとえば、日常的に感謝やフィードバックを伝えたり、指示ではなく対話で部下を動かしたりする姿勢。
それだけで、部下のストレスは大きく軽減され、心理的安全性が高まります。部下は「見てくれている」「理解しようとしてくれている」と感じた瞬間、上司に対して信頼を寄せはじめます。
つまり、管理職の小さな言動が職場の空気を左右するということです。
たったひとつの「ありがとう」が、退職を踏みとどまらせることすらあります。
退職者ゼロの職場にするために今すべきこと
「辞められてから動く」のでは遅すぎます。退職者が出るたびに現場は疲弊し、信頼は崩れ、採用コストは膨らみます。だからこそ、“今、辞めようとしている人”が出てくる前に打てる手を持っておくことが大切です。
そのためにできることはたくさんあります。たとえば、
- 1on1面談で本音を引き出す仕組み
- モラハラに関する匿名アンケートの定期実施
- 上司に対するフィードバック制度の導入
- 管理職研修の中で“無自覚モラハラ”への気づきの場を設ける
そして何より、部下が「辞めたい」と感じた時に、相談できる・訴えられる環境があるか。ここが整っていない限り、退職者ゼロは実現しません。
退職は、必ず前兆があります。それを見過ごさず、行動に移せるかどうかが、管理職として、組織としての“器の大きさ”です。
本質的には管理職だけが注意をするだけでは不十分
もちろん、モラハラを防ぐには管理職本人の自覚と行動が最重要です。しかし、それだけでは限界があります。そもそもモラハラは、「気づいていないうちに」「悪気なく」起こるケースも非常に多いのです。
だからこそ、組織全体としての仕組みが必要です。人事、経営層、現場リーダーが一体となって、モラハラのリスクを共有し、定期的にチェック・改善を行う文化を根づかせる。個人任せにせず、チームとして上司を支援・是正する構造が不可欠です。
「注意すれば変わるだろう」ではなく、「仕組みで変える」ことが求められています。責任を上司ひとりに押し付けるのではなく、みんなで“変わる空気”を育てていく視点が大切です。
上司代行の活用は悩んだタイミングがベスト
そして最後に、もし現場で「この上司、どうすればいいんだろう」「今すぐ配置転換は無理だけど、現場はもう限界」――そんな悩みがあるなら、上司代行の導入は“そのとき”がベストタイミングです。
上司代行は問題を“隠す”ためのものではなく、対話の再構築や組織改善を行う“戦略的な選択肢”です。
直接対立を避け、部下を守りながら、上司にも育成の機会を提供できる。その柔軟なアプローチは、現代のマネジメントにこそ必要な視点です。
悩んでから半年が経てば、部下は辞めています。悩んでから1年経てば、チームは崩れています。“相談したいと思った今”こそが、改善のチャンスです。
モラハラは静かに、確実に、組織を壊します。しかしそれを見抜き、止め、変えていく力もまた、組織の中にあるはずです。
上司は、変われます。職場も変えられます。その一歩は「気づくこと」そして「行動すること」。未来の職場は、今の小さな決断で変わります。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック