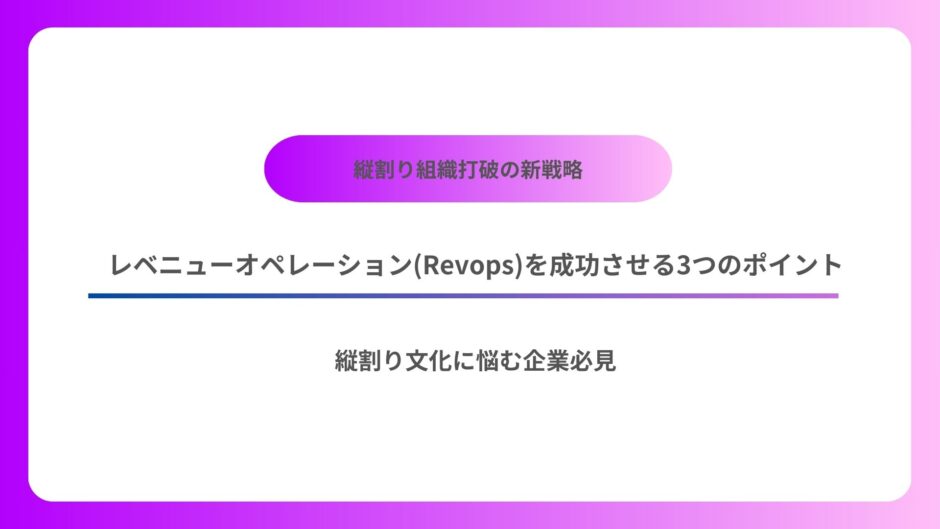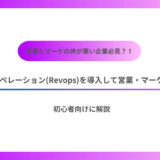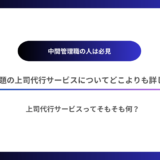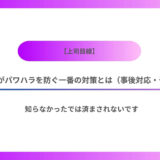皆さんこんにちは。株式会社プロストイックです。
今回は最近話題のレベニューオペレーション(通称でレブオプスやRevopsと言います)を成功させるポイントに一から詳しく解説をしていきます。
- 営業やマーケなど部署が連携すべきなのに「縦割り」で苦しんでいる
- 縦割りを打破したいがそのかじ取りをする人が社内にいない
- 部署それぞれの組織がうまく機能させたい
ちなみに前回は初心者の方向けにこちらの記事について解説をしました。
なぜBtoB企業にはレベニューオペレーションが必要なのか?

BtoBビジネスの現場では営業とマーケティングの連携不足が売上のボトルネックになっていることが多くあります。
各部門が別々に動き、それぞれの目標達成だけを意識してしまうと、組織全体としてのパフォーマンスはむしろ落ちてしまうからです。
とくにデジタル化が進むなかで、部門を横断したデータ活用やプロセスの統合が求められるようになってきました。
従来のような縦割り体制では、市場の変化に柔軟に対応できず、成果の出るマーケティング施策も、営業の努力も、うまく機能しないまま終わってしまうリスクがあります。
この課題を根本から解決する概念として注目されているのが「レベニューオペレーション(RevOps)」です。
レベニューオペレーション(RevOps)は営業・マーケティング・カスタマーサクセスをつなぎ、売上を組織全体で最適化していくための運営体制です。
ここからは、なぜ今の時代にBtoB企業がこの考え方を取り入れるべきなのかを営業・マーケのKPIのズレ、サイロ化の問題、そして全社的な売上最大化の観点から順を追って掘り下げていきます。
営業・マーケのKPIがバラバラ|非効率な組織の課題とは

BtoB企業では営業とマーケティングが異なる評価指標で管理されていることが珍しくありません。
マーケティング部門は「リード数」や「サイト訪問数」などの指標で評価される一方、営業部門は「商談数」や「受注額」など、より直接的な成果で評価されます。(実体験としていえば、より「顧客に直接的に向き合っているのは営業」というのが営業サイドからする感覚のようです)
このKPIのズレは組織の非効率さを引き起こす温床になります。
マーケティングが一生懸命に獲得したリードも、営業からすれば「質が低い」と見なされれば追わなくなりますし、営業が求める情報がマーケティングに伝わらなければ、見当違いなコンテンツや広告施策に予算が使われてしまいます。
結果として、せっかくの投資が成果につながらず、部門同士の不信感が募っていきます。
これがさらに各部門の独立志向を強めてしまい、いわゆる「組織のサイロ化」が進行します。
こうした課題を解消するために有効なのがレベニューオペレーションの導入です。
レベニューオペレーション(RevOps)では営業とマーケティングが共通のKPIを持ち、同じ方向を向いて動けるようにプロセスを統一します。
例えば「SQL(Sales Qualified Lead)からの受注率」や「顧客あたりのLTV」など、売上に直結する指標に全員がコミットすることで、施策の精度も連携も格段に上がります。
営業とマーケティングが連携できなければ、どれだけ優れた戦略を持っていても意味を成しません。
非効率を改善し、成果を上げるためにも、レベニューオペレーション(RevOps)という視点が今、必要とされています。
サイロ化した部署をつなげるRevOpsの役割
縦割り組織が抱える最大の問題は部門間で情報や目的が共有されず、施策が分断されてしまうことです。
マーケティングが生み出したリードの背景が営業に共有されなかったり、営業が受注した顧客情報がカスタマーサクセスにうまく引き渡されなかったりする場面は、現場でよく見かけます。
このようなサイロ化は属人化や責任の分散も引き起こします。
「これはマーケの責任だ」「営業が追わないから成果が出ない」といった責任転嫁が常態化し、現場はどんどん疲弊していきます。
ここでレベニューオペレーションが果たす役割は決定的です。
レベニューオペレーション(RevOps)は、各部門を貫く一つのレイヤーとして機能し、営業・マーケティング・カスタマーサクセスのプロセスとデータを統合します。
全員が共通のツール、共通のKPI、共通の指標をもとに動くことで、組織のバラバラな動きを整えることができるのです。
たとえばMA(マーケティングオートメーション)ツールとCRMを連携させることで、リードの獲得から受注・フォローまでの顧客情報が一本の線でつながります。
加えて、部門ごとの運用に頼らず、レベニューオペレーション(RevOps)チームが中立の立場からデータを評価・改善できるため、属人化も防ぎやすくなります。
最近ではこのRevOpsの立ち上げや運営を「上司代行」のような外部支援に委ねる動きも広がっています。
デジタル組織における中間管理職の役割を専門的に担うことで、内製化が難しい企業でもスムーズな導入が実現できます。
上司代行についての詳しい解説はこちら。
サイロを壊すには単なる「仲良しチーム」を作るのではなく、構造そのものを見直す必要があります。その仕組みとして、レベニューオペレーション(RevOps)の導入は非常に現実的かつ効果的な選択肢です。
組織全体で売上最大化を目指す考え方

営業は売上をつくる、マーケティングはリードをつくる。
かつてはそれぞれの役割が明確に分かれていました。
しかし現在のBtoB市場では、営業だけ、マーケティングだけでは売上を最大化することは難しくなっています。顧客の意思決定プロセスが複雑化し、受注後の継続的な関係構築まで含めた全体最適の視点が求められるからです。
この変化に対応するには「売上をつくるのは組織全体の責任である」という考え方が必要です。
レベニューオペレーションはまさにその思想を体現した仕組みです。
営業・マーケティング・カスタマーサクセスが一つのレベニューラインでつながり、データにもとづいて組織全体で売上を追いかけます。
たとえば、受注率が落ちていれば、それは営業だけの問題ではなく、リードの質や商談プロセス全体を見直す必要があります。成約後のチャーン率が高ければ、顧客との最初の接点やオンボーディングプロセスに課題があるかもしれません。
このような視点を社内に浸透させるには単なる方針転換だけでは不十分です。
データの可視化、KPIの統一、チーム間のハブとして機能するRevOps担当の配置、そして必要であれば、上司代行のような外部支援の活用が効果を発揮します。
組織が個別最適から脱却し、全体最適に向かって動くには、正しい仕組みと文化づくりが欠かせません。
次章ではレベニューオペレーションを定着・成功させるための具体的な3つのポイントを詳しく解説していきます。ここがまさに、縦割り組織を打破するための本質に迫る部分です。
組織間連携の実行支援は
プロストイックが強い
RevOps導入前に理解すべき縦割り組織の3つの根本課題

レベニューオペレーション(RevOps)を導入すれば、営業とマーケティングの連携が深まり、売上に直結する仕組みをつくることができます。
しかし、レベニューオペレーション(RevOps)が効果を発揮するためには、まず既存の組織が抱える構造的な課題を正しく理解しておく必要があります。
特にBtoBのデジタル組織においては、部門間の連携ミスではなく、根本的な設計そのものがボトルネックになっているケースが少なくありません。
導入効果を最大化するためには、どこにズレがあるのか、何が障害になっているのかを見極めることが欠かせません。
ここでは、レベニューオペレーション(RevOps)を導入する前段として知っておくべき「縦割り組織の3つの根本課題」について取り上げます。
これはすべてのBtoB企業に共通する可能性がある基本的な構造問題であり、これを無視したまま仕組みだけを変えても、成果にはつながりません。まずは現状の理解から始めていきましょう。
【1】目標・KPIが部署ごとにバラバラ

縦割り組織が機能しなくなる原因の一つは「目標設定のズレ」です。
営業部門は短期的な数字を追い、マーケティングはリード数や認知獲得を重視する。カスタマーサクセスに至っては解約率や継続率といった、また別のKPIで評価されていることが一般的です。
問題はこれらが相互にリンクしていないことです。
それぞれが「自部門の目標を達成すること」に集中するあまり、組織全体での成果に対する視点が欠落してしまいます。
結果的に施策はちぐはぐになり、営業が「このリード質悪い」と判断して追わず、マーケティングが「ちゃんと追ってないから数字にならない」と不満を持つ、といった悪循環が発生します。
本来、マーケティングも営業も、最終的には「売上」という同じゴールを持っているはずです。
それにもかかわらず、評価基準がバラバラであるがゆえに、動き方や優先順位がかみ合わないという状況が起こってしまいます。
こうしたKPIの分断は業務レベルの問題というより、組織設計の問題です。
だからこそ、レベニューオペレーションのような“全体最適”のフレームを導入することが、有効な打ち手になるわけですが、その前にまず「KPIがなぜ噛み合っていないのか」を見直す必要があります。
【2】部署間で顧客データが共有されていない
もう一つの大きな問題が顧客データの断絶です。
最近では共通のCRMつーるで管理していることも多いですがマーケティングが獲得したリードの情報、営業が商談で得たヒアリング内容、カスタマーサクセスが掴んでいる利用状況。これらの情報が各部門に分散し、連携されないまま属人的に管理されているケースは少なくありません。
この「分断された情報環境」は組織全体で顧客を正しく理解することを妨げます。
たとえば、営業がすでに提案済みの内容をマーケが再案内してしまったり、サポート履歴を知らない営業が間違ったフォローをしてしまったりすることで、信頼を損ねるリスクさえあります。
また、データが分散されていると分析や改善にも時間がかかります。
たとえば「なぜ今月は受注率が下がったのか」と考えたときに、リード獲得数・商談内容・成約プロセスがバラバラのツールに存在しているようでは、スピーディーな分析も意思決定もできません。
このような事態はレベニューオペレーションの導入によって一定解消が期待されますが、そもそもなぜ部門間で情報が共有されないのか、どこに壁があるのかという構造的な課題を押さえておかないと、形だけのデータ統合に終わってしまいます。
共有されていないデータの背景にある“組織文化”や“業務プロセスの設計”にも目を向ける必要があります。
【3】意思決定スピードが遅く、機会損失が発生している

最後の課題は「スピード」です。
デジタル時代においてBtoBビジネスでも顧客の検討スピードは加速しています。
数年前であれば半年がかりだった選定プロセスが今では1〜2か月で完結することも珍しくありません。
それにもかかわらず、社内の意思決定プロセスが旧態依然としていれば、機会を逃してしまうことになります。
この遅さは、縦割り構造そのものに起因しています。
何かを決めるたびに複数の部門の許可を取りに行き、社内調整に時間がかかる。
意思決定者が遠い、もしくはデータが統一されておらず議論が空中戦になる。
結果として「見送り」「後回し」が続き、競合にチャンスを奪われる。これは営業・マーケティング双方にとって深刻な損失です。
こうした状況において、最近注目されているのが「上司代行」のようなマネジメント支援の存在です。
あくまで当社プロストイックにおける上司代行(中間管理職支援)というのはミドルマネージャー、つまりプレイヤー業務(手を動かす業務)とマネージャー業務(管理・意思決定)を対象としてチーム体制で中間管理職の業務を支援するものになります。
業務負荷が高いタスクやプロジェクトがあればそれを支援したり、育成やマネジメントに困っていれば既存の管理職の方と「業務を分化」して「本来すべき業務」や「意思決定のスピードを上げる」体制を創ります
特にデジタル組織における中間管理職の役割を外部が担うことで、現場と経営の間に“判断と推進”のレイヤーをつくり、スピード感ある意思決定を支える体制が構築できます。
とはいえ、スピードを上げるためには仕組みだけでなく、「なぜこれほど遅れているのか」という組織のクセや慣習にも目を向ける必要があります。
レベニューオペレーション(RevOps)を成功させるためには、このスピードの課題を単なる業務改善ではなく、構造的な視点で捉えることが重要です。
上司代行支援なら
プロストイックが実績No,1
レベニューオペレーションを成功させる3つのポイント
レベニューオペレーション(RevOps)を導入するだけでは組織の変革や売上向上は実現しません。
ポイントは「どう運用するか」です。
従来の縦割り構造にレベニューオペレーション(RevOps)という名前だけを乗せても、実態が変わらなければ意味がありません。
特にBtoBのデジタル組織においては、営業・マーケティングのフローが複雑化しており、それぞれの部門が異なる指標、異なるツール、異なる目的意識で動いているケースが少なくありません。
その結果、足並みがそろわず施策のズレや機会損失が多発しているのが現実です。
そこで重要になるのが「KPIの統一」「データ基盤の連携」「組織設計の見直し」という3つの視点です。
レベニューオペレーション(RevOps)は単なる業務連携の枠を超えて、組織の根幹にまで踏み込むフレームです。この3つのポイントを押さえることが、成功と失敗の分岐点になります。
【ポイント①】KPIと指標の“統一”|共通ゴールを明確にする

RevOps導入の最初のステップはKPIと指標の統一です。
営業、マーケティング、それぞれが異なるゴールを持っている状態では、いくら部門間の連携を強化しても、戦略の整合性はとれません。
例えば、マーケティングがリード数ばかりを追っている一方で、営業が受注率や成約件数を評価されていれば、マーケは「とにかく数を稼ぐ」動きになり、営業は「質が低い」と嘆く。
そんな状況では、どちらも自分のKPIだけに最適化し、全体最適からはどんどん遠ざかります。
このような分断をなくすためにはマーケも営業も同じゴールを見据える必要があります。
たとえば「受注件数」「LTV(顧客生涯価値)」「パイプラインの成約率」など、売上に直結する指標を共通KPIとして設定することです。
また同じゴールを再定義する中で改めて「ペルソナ」や「カスタマージャーニー」の再設計をしてもよいでしょう。その場をリードする人が必要ですがワークショップなどを通じて意見を持ち寄ることによって改めて顧客の価値やすべきことなどを見直すことが可能です。
KPIを最終的に再定義する際には組織の成熟度や商材の特性に応じて調整が必要です。
SaaSモデルであれば獲得よりも継続に重きを置く指標設計が重要になります。こうした「KPI設計力」も、レベニューオペレーションの中核です。
KPIの再設計はいわば全社の意志統一。
ここを曖昧にしたままでは、レベニューオペレーション(RevOps)の枠組みだけ整えても機能しません。
【ポイント②】データ基盤の“連携”|CRM/MA/SFAを一気通貫で運用
レベニューオペレーション(RevOps)を実行に移す上で、データ基盤の整備は不可欠です。
とくにCRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援)の3つのツールが分断されている企業は、早急に「一気通貫の設計」が求められます。
なぜなら、顧客データの流れが断絶していると、営業とマーケティングの連携も噛み合わないからです。
マーケティングが生成したリード情報がSFAに連携されておらず、営業がゼロから関係構築を始める。
営業が収集したヒアリング内容がCRMに記録されないため、カスタマーサクセスが状況を把握できない。こういった分断は、企業にとって致命的です。
そのためには、各ツールがAPIで正しく連携していること、かつ運用ルールが部門横断で統一されていることが重要です。
データはつながっていても、入力ルールがバラバラでは正確な分析ができず、意思決定の精度も落ちます。
また、導入後の運用においては上司代行のようなマネジメント支援を活用することで、データ基盤の設計から活用支援までを推進する体制を整えることができます。
とくにデジタル組織においては、「現場と経営の間に立つ人材」が不足しているため、外部のプロによる横断的な調整が大きな支えになります。
ツールは目的ではなく手段です。CRM、MA、SFAの三位一体運用が、レベニューオペレーション(RevOps)を支える神経網になります。
【ポイント③】役割と責任の“再設計”|部門を横断するチーム体制へ
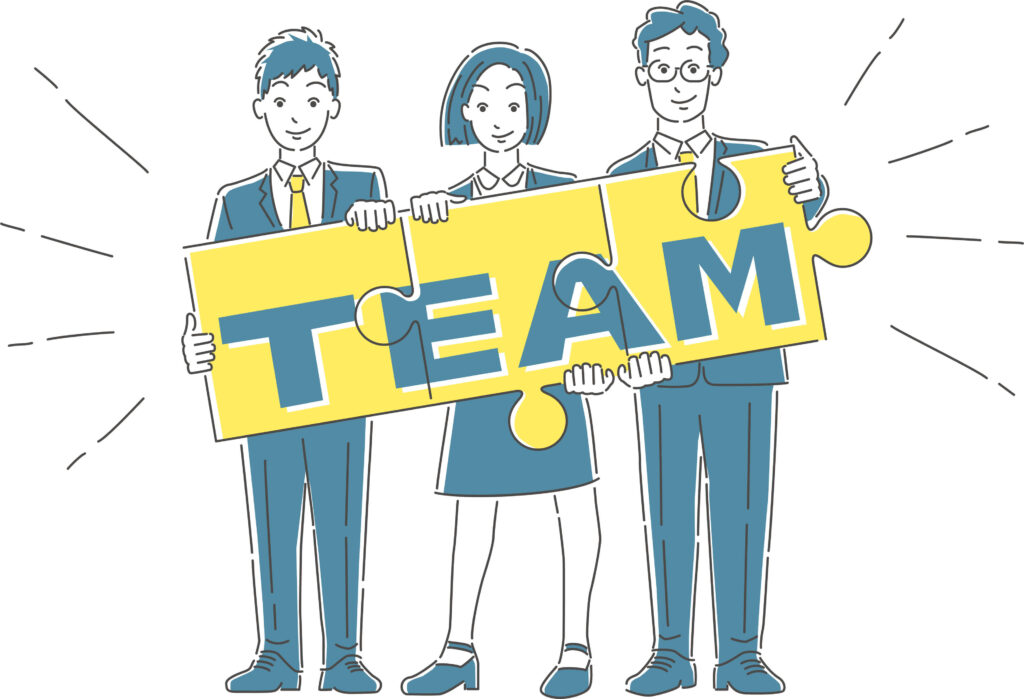
RevOpsの導入において見落とされがちなのが、人と組織の再設計です。仕組みやツールが整っても、結局は「誰が何をやるか」が曖昧なままでは機能しません。
特にBtoBの営業組織では営業は営業、マーケはマーケといった「役割の固定」が根深く残っています。ところが、顧客の購買行動は部門の境界などお構いなしに変化しており、これまでの役割分担では対応しきれなくなってきています。
たとえば、商談の初期段階での関係構築はマーケティングが担い、そのままインサイドセールスが引き継いで受注に持ち込む、といった流れが主流になる中で、「誰が主担当なのか」「どこで引き継ぐのか」が曖昧なままだと、責任の所在が不明確になります。
そこで重要なのが、部門横断での「チーム再編成」と「役割の再定義」です。
マーケ、営業、CSが混在したクロスファンクショナルなチームを編成し、それぞれのフェーズごとに責任を明確化する。これがレベニューオペレーション(RevOps)を機能させるうえで不可欠です。
この再設計を現場だけで進めるのは難易度が高く、感情的な摩擦も避けられません。
そこで有効なのが、上司代行のような外部ファシリテーターの活用です。社内調整に中立な立場で入り、横断的な議論をリードすることで、変革のスピードと精度を両立させることができます。
「人」の設計を変えない限り、どんなに仕組みを整えてもレベニューオペレーション(RevOps)は動きません。最後の鍵を握るのは、チームそのもののあり方です。
成功企業に学ぶ!RevOpsで縦割りを打破した実例
レベニューオペレーション(RevOps)は理論やフレームワークとして語られることが多い一方、実際に組織がどう変わるのか、現場でどんな効果が出るのかは見えにくいと感じている方も多いはずです。
特に営業やマーケティングといった実働部門では「本当にうちの会社でも機能するのか?」という懐疑的な声が上がることも珍しくありません。
しかし、実際にRevOpsを導入し、縦割り構造を打破して成果を上げている企業は少なくありません。
ここでは、BtoBの営業組織において従来の無駄や機会損失を見直し、明確な成果につなげた事例を紹介します。マーケティングと営業の連携、組織の意志決定プロセス、KPIの運用まで、具体的な変化とその裏側にある文化や仕組みを掘り下げていきます。
【事例】営業の“数打て精神”から「確度重視」へ転換|商談数15%減でも売上20%増
まず初めは大手IT企業の事例になります。多くの商品・サービスを扱っていたため営業から連携しなければならない部署が多くリードの管理や営業とマーケ、現場が連携することが難しい状況でした。
状況としては営業部門が“とにかく数を打つ”というスタイルを続けていました。
マーケティングからのリードを片っ端から追い、商談数を稼ぐことで数字を作ろうとしていたのです。しかし、案件の質にバラつきがあり、受注率が上がらないというジレンマに直面していました。
そこで導入されたのがレベニューオペレーション(RevOps)でした。
営業担当者がマーケデータを分析する文化が醸成
レベニューオペレーション(RevOps)チームが介入し、営業とマーケティングが共通のKPI(受注確度やLTV)に基づいて活動を設計。営業担当者には、MAツールで得られたスコアリングや行動履歴などの顧客データが共有されるようになりました。
最初はデータを読み解くことに戸惑いを見せていた営業チームも、マーケと連携しながら進めることにより徐々に「数字の裏にある顧客の意思」を読む力を身につけていきました。
結果として低確度のリードを無理に追うことが減り、逆に高確度の案件への集中が可能になりました。
マーケティングの文脈で作られたデータが営業の現場で活かされ、受注率が向上。
商談数は前年比で15%減ったものの、売上は20%増加するという成果につながりました。質を追うことで組織全体の業務も効率化されてマーケティングと営業が組織の枠を超えて“共通言語”で語り合う文化が、着実に根付き始めた好例です。
無駄打ち削減で商談準備時間が1件あたり平均30分短縮
同じ企業でレベニューオペレーション(RevOps)導入によってもう一つ大きな効果がありました。それは「商談準備時間の短縮」です。
これまでは営業担当が商談前に顧客の情報を複数のツールやファイルから手動でかき集めていたため、1件あたり平均60〜90分を費やしていました。
過去のやりとり、Web閲覧履歴、ダウンロードした資料などが社内に点在し、必要な情報を探すだけで疲弊していたのです。
ところがレベニューオペレーション(RevOps)によって、CRM・MA・SFAが連携し、顧客情報が一元化。
提案前の段階で「このリードはどのページを見て、どの資料を開いて、どういう問い合わせをしてきたか」が即座に確認できるようになりました。
これにより、商談準備時間が平均30分短縮され、営業担当者は空いた時間を他の案件への対応や顧客との対話に使えるようになりました。
生産性の向上は数値以上のインパクトを持ち、「商談前の情報武装」が営業の質を高める武器になったのです。
データがつながることはただの効率化ではなく、営業活動そのもののあり方を根本から変える力を持っています。
まさに、レベニューオペレーション(RevOps)がBtoB営業組織の文化を変えた好例です。
組織間連携の実行支援は
プロストイックが実績No,1
【事例】RevOpsチーム設置で意思決定が2週間→3日に短縮
別のBtoB企業の事例では、レベニューオペレーション(RevOps)の導入によって「意思決定のスピード」が劇的に改善しました。以前は、営業部門から上申された情報が上長→部長→役員へと段階的に上がり、判断が下るまでに平均で2週間かかっていました。市場変化のスピードについていけず、商談機会を逃すことも多かったのです。
従来の「営業→上長→役員」フローが“現場主導”型に
そこで、レベニューオペレーション(RevOps)専門チームを立ち上げ、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが日次で情報共有を行う体制に刷新。ツールで集約されたデータをもとに、現場主導での意思決定が許容される文化に変えていきました。
今では、意思決定に必要な情報がその場で可視化されるため、緊急度の高い判断であれば3日以内に方針が決まるようになっています。従来の階層的なフローから、フラットかつ迅速な体制への転換が、レベニューオペレーション(RevOps)によって実現されたのです。
予算調整・KPI修正が月次→週次に切り替わりPDCAが加速
この企業ではもう一つ、運用のサイクルにも大きな変化がありました。以前は月次で行っていたKPIのレビューや予算調整が、週次ベースへと切り替わったのです。
これまでは、月次レビューのタイミングでようやく「ズレ」に気づくという状況でしたが、レベニューオペレーション(RevOps)チームが週次でデータをレビューし、部門横断で進捗を確認する体制が構築されてからは、軌道修正がその場で行えるようになりました。
PDCAの回転数が上がったことで、施策の精度とスピードがともに向上。たとえば、Web広告の反応が悪ければ即座に予算を修正し、成果が出ているチャネルに配分し直すなどの柔軟な対応が可能になっています。
このような動きの中では、現場レベルだけでなくマネジメント支援の体制も重要です。
上司代行のような立場で、部門をまたいで動く役割を担う人材がいることで、現場の実行と経営判断の橋渡しがスムーズになります。
レベニューオペレーション(RevOps)は単なるツールやチームではなく、「意思決定の質と速さ」を変えるための構造改革です。
この企業のように、組織の文化そのものを変えた事例は、今後の導入企業にとって大きなヒントになるはずです。
レベニューオペレーションを定着させるために必要な文化と人材

ここまでは組織の課題やレベニューオペレーション(RevOps)を実現する上での大前提や実際に実現した事例を解説してきました。
ここまでの解説で「これはうちの組織じゃ無理だな」「うちの会社はほんとに営業とマーケが連携できないから」などと思われている方も多いと思います。
その通りで皆さんが感じている違和感やトライアルバリアを言語化すると
レベニューオペレーション(RevOps)は単に仕組みを導入すれば成果が出るわけではありません。むしろ本質的な難しさは組織に定着させる「文化」と、それを推進する「人材」の側にあります。
特にBtoBのデジタル組織では営業やマーケティング、カスタマーサクセスといった部門が独自の文化や常識を持っており、それらがぶつかることも少なくありません。
レベニューオペレーション(RevOps)の導入はそうした部門間の溝を埋め「組織としての売上最大化」という共通ゴールに向かって全体を動かしていくプロセスです。(結局は組織というより人とどう向き合うのかです)
そのためには、役割を超えて協働するマインドを育てること、変革の中核を担う人材を配置すること、そして小さな成功を積み上げて信頼を勝ち取ることが欠かせません。
以下ではレベニューオペレーションを現場に定着させるための文化的・人的な観点を深掘りしていきます。
役職を超えた“協働マインド”をどう育てるか

レベニューオペレーションの根幹にあるのは部門の壁を超えて“協働”する文化です。
営業・マーケティング・カスタマーサクセスの各部門が従来の縦割り意識を捨て、横断的に課題解決に向き合うことが求められます。
しかし、現実には役職や業務領域へのこだわりが根強く、互いの仕事に口を出すことを敬遠する空気があるのも事実です。
こうした文化を変えるにはトップダウンとボトムアップの両面からのアプローチが必要です。まず経営層が「個別最適ではなく全体最適を重視する」というメッセージを明確に発信し、評価制度もそれに連動させる必要があります。
部門単位ではなく「チーム全体としての成果」に対して評価がなされれば、自然と部門をまたいだ連携が促進されます。
また現場では、小さな協働の成功体験を積み重ねることが重要です。
たとえば、マーケティングから営業へ渡すリード情報をカスタマイズしたり、営業からカスタマーサクセスへ顧客ニーズを共有したりといった、小さな連携から始めると抵抗感は少なくなります。
レベニューオペレーションを機能させるには協働マインドの醸成が不可欠です。
組織の中に「隣のチームの成果も、自分たちの仕事の延長にある」という意識を根付かせることが、最初の一歩です。
組織間連携の実行支援は
プロストイックが実績No,1
組織変革のキーマンは「レベニューリーダー」

レベニューオペレーションを導入するうえで欠かせないのが「レベニューリーダー」と呼ばれる役割の存在です。
これは、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど複数部門の理解を持ち、かつ経営視点でKPIや業務設計を捉えられるハイブリッドな人材です。
このレベニューリーダーは現場と経営の“翻訳者”のような役割を担います。
たとえば営業からの「リードの質が低い」という声を、マーケティング視点での施策見直しに変換したり、現場の感覚を数字に落とし込んで経営層に報告したりします。縦にも横にも信頼関係を築けることが求められるポジションです。
「そんな人材社内にいないよ」という声が大半なのですが、ぜひ当社プロストイックの上司代行(管理職支援)をご活用下さい。
上司代行のように、中間管理職の業務を代行・支援する立場からレベニューオペレーション(RevOps)をリードするケースも増えてきています。
特にデジタル組織では、従来型の管理職では対応しきれない部門間の調整やデータドリブンな判断が求められる場面が多く、外部の知見を持つ人材が重要な役割を果たします。
レベニューオペレーション(RevOps)の要となるのは、戦略と現場の両方に精通した人材の配置です。こうした人材がいることで、混乱を抑えつつスムーズに改革を進めることができます。
小さく始めて、徐々に成果を“見える化”する運用がカギ
レベニューオペレーション(RevOps)は一朝一夕に完了する取り組みではありません。
むしろ「大きな改革」を掲げすぎると、現場は反発や疲弊を招き、途中で頓挫してしまうリスクがあります。そこで重要なのが、「小さく始めて成果を見える化する」という段階的なアプローチです。
たとえば、まずは営業とマーケティングの一部チームだけで、共通のKPIを設定し、1〜2ヶ月の実証実験を行ってみる。あるいは、特定の商材に限定してCRMとMAツールを連携させ、成果の変化を検証する。こうした取り組みを続けることで、徐々に組織全体へと展開していくのが理想です。
また、成果を「定量・定性」の両面から共有することも重要です。売上や商談数の変化だけでなく、現場の担当者がどのように業務の効率や意識の変化を感じたかといった声を収集し、社内に発信することで、改革への理解と納得を広げることができます。
特に組織全体を巻き込むには、「見える成功体験」が欠かせません。
レベニューオペレーション(RevOps)の導入は社内の慣習や文化と向き合う地道な活動です。
だからこそ、まずは身近な範囲で一つの成功モデルを作り、それを起点に信頼を得ていくことが、定着に向けた近道となります。
まとめ|縦割りを壊すなら、今こそRevOpsという選択を
ここまでいかがだったでしょうか。「難しい」「これならできそう」「難しいけどやる必要がありそう」など様々なご意見があると思います。
最後にこれまでの総括をまとめていますので、ここまでのサマリー(要約)としてご活用下さい。
組織構造が変われば、売上も変わる
いくら優秀な人材を揃えても、組織構造が非効率なままでは力を発揮できません。
営業とマーケティングが別々のKPIで動き、データが分断され、意思決定に時間がかかる縦割りの状態では、努力が売上に結びつきづらくなります。BtoB企業において、こうした構造上の課題が成長のボトルネックになっているケースは珍しくありません。
そこで注目すべきなのがレベニューオペレーション(RevOps)という考え方です。
これは、営業・マーケティング・カスタマーサクセスといった収益に関わる部門を統合的にマネジメントし、「組織として売上最大化を実現する」ための仕組みです。
役割の重複や連携ミスを減らし、各部門が同じゴールに向かって動く構造をつくることで、本来のポテンシャルを引き出します。
実際、組織構造をRevOps型に転換した企業では、商談数は減っても売上が増える、意思決定が迅速になって市場対応力が向上する、といった成果が報告されています。
単なる業務効率化ではなく、「成果の出る組織」に生まれ変わること。それがレベニューオペレーション(RevOps)導入の真の意味です。
部門の壁を超えて一つの“レベニューチーム”を作ろう
レベニューオペレーションの本質は「組織をまたぐチームづくり」です。
営業、マーケティング、カスタマーサクセスという異なる部門を、単なる連携先としてではなく、“一つのチーム”として捉える視点が重要です。
この転換には時間も労力もかかります。文化の違いや業務プロセスの違いを乗り越えるには、信頼関係と共通理解が不可欠です。
しかしその壁を越えられたとき、部門間の連携は「調整」ではなく「協働」へと進化します。情報の流れが滑らかになり、現場が判断を下せるスピードが生まれます。
このような“レベニューチーム”が機能し始めると、各部門が自部門の成果だけでなく、会社全体の成長に関心を持つようになります。
たとえば営業がマーケティングのキャンペーン設計に関わったり、カスタマーサクセスが見込み客のフィードバックを提供したりといった動きが自然に生まれます。
上司代行サービスなど、外部からチームビルディング支援を受けるのも有効です。
特にデジタル組織では、自前でこの体制を整えるには限界があります。専門家の支援を受けることで、部門横断チームの立ち上げがスムーズになります。
BtoB企業が次の成長を目指すなら、RevOpsは不可欠な戦略
市場環境が不安定で、顧客のニーズが高度化・複雑化する現代において、旧来の縦割り型組織ではもう限界があります。BtoB企業が競争優位を築き、継続的に成長していくためには、組織自体をアップデートする必要があります。その答えの一つが、レベニューオペレーション(RevOps)です。
単にツールを導入するだけではありません。KPIの再設計、データ基盤の連携、役割分担の見直し、文化の変革といった一連の流れを、組織全体で丁寧に取り組む必要があります。簡単ではないですが、だからこそ差がつきます。
RevOpsは目先の売上向上施策ではなく、「組織の売上力を根本から強化する戦略」です。
そしてそれは、BtoB企業が次のステージへ進むための強力なレバレッジになります。いまのやり方で限界を感じているなら、組織の在り方自体を見直すタイミングかもしれません。
縦割り構造を打破し、部門の壁を越えて一つのゴールを追いかける。レベニューオペレーション(RevOps)という選択肢は、まさにその第一歩です。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック