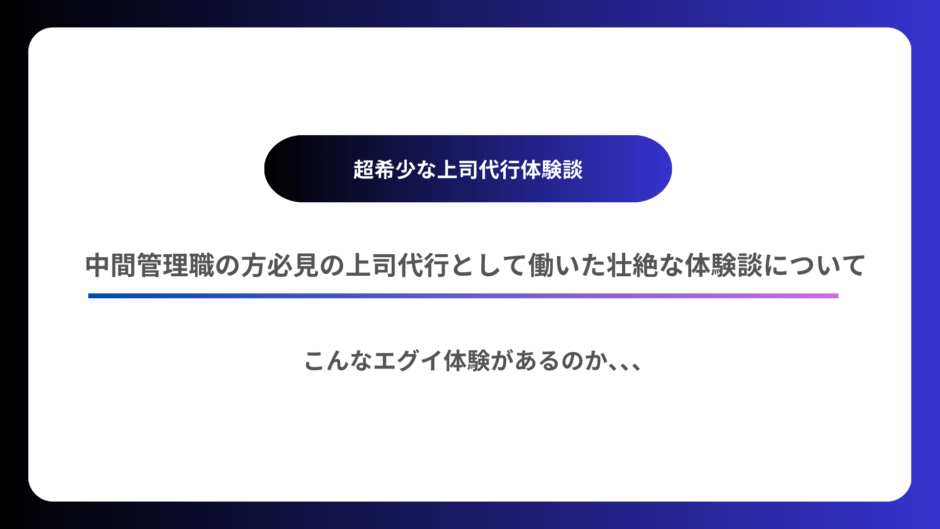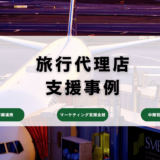皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本記事を閲覧いただいた方は以下に該当する方が多いのではないでしょうか。
- 中間管理職として働いているが悩みを抱えている
- 仕事が多すぎて誰か信頼できる人に業務をパスしたい
- 上司について悩んでいる
本記事で解説する内容は一言で言えば「部下や中間管理職が業務過多で苦しんでいる部署を立て直した体験談」です。
「上司代行」という言葉を使ってはいますが企業の中に入り、同じような社員として一緒に汗水流して働き最高のチームを作り上げた事例となります。(当時は上司代行という名目というより業務委託で支援をしていましたが本記事ではわかりやすくするために命名を上司代行と呼びます)
中間管理職として日々の業務に奮闘されている皆様のプレッシャーとストレスにどれだけの方が共感して、理解しているでしょうか。
上司代行という特殊な役割を通じて、筆者は中間管理職の置かれている現実の過酷さ、そしてその裏に存在する社内課題や人間関係の問題に深く向き合う機会を得ました。
本記事では上司代行として働いた経験談を中心に、中間管理職の方々に向けた新たな選択肢をお届けします。
中間管理職として日々責任の重圧や業務の過密スケジュールに追われる方は少なくありません。
その中で、上司代行という新しいサービスが注目されています。筆者が上司代行として働いた実際の体験談を通じて、中間管理職の厳しい現実とその解決策について深掘りしていきます。
ちなみに前回は上司代行の概要について解説しました。上司代行の現状やサービスの詳細、料金などについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
上司代行経験者が語る企業の中間管理職が直面する過酷な現実
筆者自身、上司代行として働く中で中間管理職が直面する現実を肌で感じてきました。
特に、上司と部下の間に挟まれる苦悩や、責任とストレスの重圧が浮き彫りになります。まず本章では、中間管理職がそもそも抱える課題について整理をしたいと思います。
上司と部下の板挟みで苦悩する日々
本当によく聞く声の一つとして挙がるのは中間管理職にとって最大の苦悩の一つは、上司と部下の板挟み状態です。
上司からは売上目標や成果を求められ、部下からは働きやすい環境を求められるため、相反する要求に応える必要があります。
例えば、上層部から無理な納期を設定された場合、それを部下に伝えることは大きなストレスとなります。
また、部下から上司への不満を吸収しつつ、上司の意向を部下に伝える必要があるため、心理的負担が増大します。
このような状況では、上司代行のような外部リソースを活用することで、一時的に負担を軽減することが可能です。
責任とストレスがのしかかる職場環境
周りの中間管理職の方で悲痛な声を挙げている方の職場環境を聞くとかなりタフな状況です。
「現場を把握していない上司」「外部から突然来て言うだけ言って手を動かさない役員」「株トレードばかりしている社長」などかなり色々な声が聞こえてきます。
多くの中間管理職は責任の重さと業務量の多さに日々直面しています。
特に、企業の成績が低迷した場合や部署目標が高いがリソース不足(人や予算が少ない)が深刻な部署は、その責任を一身に背負うことが求められるため、心理的な負担が増大します。
部下が失敗したプロジェクトの責任を中間管理職が負い、上層部への説明や改善策の立案に追われるようなことがあると過重労働に繋がり健康やモチベーションの低下につながる危険性もありますよね。この問題は日本全国で深刻なものとなっています。
上司のミスは部下の責任・部下の失敗は上司の責任
この見出し、実は多くの方が一度は聞いたことがあるかもしれませんが、実は、TBSドラマ「半沢直樹」に登場する大和田常務のセリフです。
実際問題として「上司のミスは部下の責任」「部下の失敗は上司の責任」という不条理な現実に直面することも少なくありません。中間管理職は、上下双方からの期待と責任を一手に引き受ける役割を担っています。
例えば、プロジェクトの進行中に発生したトラブルが、実際には上層部の不適切な指示に起因していたとしても、中間管理職がその責任を問われることがありました。このような矛盾した状況を改善するには、組織全体の理解とサポートが必要です。
サポートを求める中間管理職の声
実は多くの中間管理職が内心で適切なサポートを求める声を上げています。特に、外部リソースを活用した負担軽減策や、業務の効率化が求められています。
上司代行サービスは、こうした声に応える形で提供されるサービスであり、職場環境の改善や業務効率化に大きく貢献します。筆者の経験では、上司代行を導入したことで中間管理職の満足度が向上し、組織全体の生産性が上がった事例が数多く存在します。
上司代行として体験した壮絶なエピソードを語ります
早速ですが、ここからは筆者(プロストイックのメンバー)が上司代行として活躍していたエピソードをお伝えします。
(厳密に当時は「上司代行」とい名前で支援をしていたわけではなく半常駐という形でクライアント様のオフィスにPCや社員証をお借りして準社員のように業務を行っていた内容になります。ただ役割としてはほとんど上司を代行してプロジェクト進行や意思決定までのプロセスを可視化するなど部長の役割を全うしていました)
背景をわかりやすくお伝えすると社員の退職が続いてしまい、もともと10名程度いたマーケティングの部署に社員が1名になってしまい業務が全く回らない状況になってしまいました。
役割としては部長代理というポジションで本部長と連携して部署の方針を決めたり、取締役会用の資料作成、現場の運用業務など全て多岐に渡り意思決定から実行までを行うというものでした。(そもそも部長も辞めてしまっていて本部長(3か月前に入社)と社員2名しかいない状況でした。その内1名は1か月前に入社した正社員の方)
ここからはトラブルやイレギュラーの連続で現状の解像度を上げれば上げるほど不可解な実態が浮き彫りになってきました。
本章では筆者が体験した壮絶なエピソードを通じて、上司代行の現実とその意義について語ります。
話を進めていくにあたり先方本部長の他、社員さんが2名登場しますが元から5年程度勤めていた社員さんをAさん、1か月前に入社した人をBさんと呼ぶことにします。
初日から予想外のトラブル対応
事前ヒアリングでおおよその概要は聞いていたのですが手が回っていない状況で詳しい内容は現場に入ってから確認していく流れでした。
契約書の手続きも本来かかる期間からかなり急ピッチで対応して急遽支援体制を組みました。
ちなみに上司代行として働く初月は必ずと言っていいほど予想外のトラブルに直面します。
今回筆者が経験したケースはかなり稀有でここまでのレベルはなかなかないですが参考例としてご紹介します。
早速お伝えしてしまうとまず、第一のトラブルは筆者が来る(支援に入る)ことを現場社員に知らされていませんでした。
なので、何の準備もされておらずPCはおろか社員証もなかったので、外部との応接室で挨拶やMTGをすることになりました。
知らされていないがゆえに現場の方々も既存の業務が手一杯なこともあり、我々に割ける時間は多くて1h/1日程度が限界でした。
とにかく何も準備がされていないためPCを手配していただき、自分達で情報を能動的にキャッチアップして全量を把握していくしかない状況でした。
この時、元からいる社員さんAは毎朝4時までMTGをしていてほとんど寝ていない状況でした。そんな状況でしたのでなんとか仕事を巻き取って負荷軽減をしてあげたいと思っていました。
現場メンバーとの信頼構築に四苦八苦
筆者は部長代理として支援に加わったので、実質的には上司代行として活動をするミッションを与えられていたのですが最初に直面する課題の一つが部下との信頼構築です。
特に、短期間でリーダーシップを発揮し、チームの一員として受け入れられることが重要です。
既存社員の方の中には過去のやり方を固辞する方もいますし新しい意見に消極的な方もいます。今回の例はまさにこの例に当てはまりました。
とはいえ上司代行という名目ではないので、上司部下という立場というよりも同じ部署の仲間としてどう部署機能を回復して業務を平準化していくのかという立回りをしていました。
ちなみに退職していった方々も適当なメモだけ残して辞めてしまったため前任者がほとんど引き継ぎを行わずに現場を去ったため、後行程を対応するこちらはかなり混乱が生じました。
(ここまで聞くとなぜこんな多くの方が辞めていったのか、何があったのか気になる方もいるかもしれませんが、そこについては読み進めてもらえば推察はできますが、今回は触れることができないのでご了承ください。)
しかし新しい風(人)が入るというのはストレスに感じる方もいます。今回がそのケースで元からいる社員さんAにとってはかなりストレスと感じていたようです。
その理由は次の見出しで解説します。
政治的な癒着で不透明な会計
タスクや会社の全容を把握しながら業務を進めていくと筆者に対して社員A(朝4時まで仕事している人)さんからの当たりがかなり強くなりました。
特に何もしていないどころか、朝4時まで仕事してるAさんを助けようと必死に動いていたつもりなのですが「これ以上仕事を巻き取らないでくれ」などと不可解な発言も飛び出しました。(この発言をされたときはほんとに意味が分からず困惑しました)
「これは何かある」と思い引き続き業務の把握を進めたところ、部署の販管費の使い方に不透明な実態がありました。
掘り下げて確認すると稼働していないのに異様に高い業務委託費用が発生していることが判明しました。
さりげなく社員Aさんに確認すると「過去正社員として勤務していた方に業務が回らないからという理由で作業を委託」しているということでした。
しかしプロストイック社員が勤務してから業務を委託している別の方の話なんぞ1ミリたりとも出てきていませんでした。加えて社員Aさんの手が回っていないのに湯水のようにオフィスにもいない、チャットにも顔を出していない方の業務委託費だけ流れって社内業務は溜まり溜まっていく一方でした。
これは元々正社員として勤務していたけど既に退職した人への業務委託費でした。
表向きは退職が一気に続いてツールの品質担保や何かあったときのリスクヘッジと言っていますが稼働実態がないのに費用を払っているので誤解覚悟で分かりやすい言葉を使うと「裏金」のようなものでした(実際には裏金ではありません)。
たまに稼働はしてたようですが、ただ月に数時間の稼働でかなりの月額費用(大手企業に勤める40代中盤の平均月収くらい)を払っていたので、これは相当闇が深いと感じました。
その実態は本部長も把握していなかったので報告をしてなんとか社員Aさんに理解をしてもらいその後和解というか普通にコミュニケーションをとることができました。
(平たく言えばAさんも昔の仲間に思い入れがありそこへの委託費用が止まってしまうことがやや心苦しいかったのか、朝4時まで働いて頭が正常ではなかったのかと思います)
上層部の高い要求に応えるプレッシャー
上司代行の現場では上層部からの高い要求に応えるプレッシャーも大きな課題です。特に、短期間で結果を出すことが求められる場面では、その重圧が一層強まります。
筆者が経験した事例では、業績改善のための新たな戦略を1週間以内に提案するよう求められました。
本部長は元々ビック4のコンサルファーム出身の方で労働時間なんて関係ない、上司からのメールや電話をいつでも取れる用意携帯電話を頭の額に置いて寝てる人でした
加えて取締役会が翌週にあるからマーケティング部としての方針も1週間以内に作成するようにと言われ筆者も多忙な日々が続いていきました(これはかなり極端な例なので上司代行サービスとしてここまでの負荷が必要なのかは契約時にすり合わせが必要です)
このような厳しい要求に対応するためには、過去のデータを素早く分析し、チームと協力して具体的な提案を作り上げる力が必要でした。
他部署やステークホルダーとの関係でアプリやwebなどの改善も難しい
社内の状況をさらに説明すると業務解像度を上げれば上げるほど隠れた制約が多くありました。
例えばWEBサイトの改善を図るに当たり何か画像や文字を変えようにもステークホルダー(いわゆる株主)からのチェックが入る可能性があると言われました。
かなり初めてのケースで筆者も困惑しましたが、以前は「なんで勝手に変えてるんだ」と連絡が来たこともあったようです(今回、ABテストという名目で進行して変えたところ変更パターンに当たらなかったのか、見てなかったのかはわかりませんが数回試しても連絡は来ませんでした)
また社内連携もかなり大変で、アプリグロースを支援する中でアプリのUIやキーワード変更に当たりエンジニアサイドとのすり合わせが必要なのですが変更に当たっての根拠や効果などなぜ工数を割くのかの議論だけでかなりの時間を費やしました(この議論してる間に変更して改善を図り効果検証した方が一番スムーズだと思うと誰もが思ってはいました)
といったディープな内容はあくまでほんとに一部の例ではありますが
お伝えしたかったことは中間管理職はこのようなイレギュラーな事態に対応を必然的に迫られ稼働をとられます。
本来はスムーズにいくはずですし、順調に進めばなんの問題もないのですが組織においてそこが上手くいかないことがかなりの確率で潜んでいます。そこを手助けするのが上司代行サービスの役割ととらえていただければと思います。
本体験談についてさらに詳しく知りたい方は、雑談ベースでもお話させていただきますのでぜひご連絡をいただけると幸いです。(上司代行サービスのご利用意向がなくても問題ありません)
時間を重ねて信頼関係を作ることが結論ベスト
最初は困惑したり、ストレスを感じていた社員さんも同じオフィスで同じPCを使い同じ時間・苦楽を共にすれば必然的に関係値は築くことができます。
筆者もそうしてプロジェクトを進めたり、部署の方々と連携を図っていき今では一緒に映画を見たり、仕事終わりにスニーカーを買いに行ったりしています。
上司代行業務の現場で見えた課題
また上司代行として働く中で、現場には多くの根本的な課題が存在することに気づきました。
ツールの運用や管理業務であれば利用マニュアルなどを用いて仕組化することはできるのですが、本記事をご覧の方々は職場のカオスな状態、複雑な人間関係の実態を経験しているかと思い一筋縄ではいかないことは既に感じていると思います。
特にコミュニケーション面(上司・部下・他部署・関連会社)においてはかなり苦労があるかとお察ししています。
このような状況を改善するには、適切なリーダーシップや効率的なプロセス構築、共通目標等が不可欠です。
職場の人間関係の複雑さと中間管理職へ飛び火する実態
職場の人間関係は業務の円滑な進行やチームの士気に大きく影響を与える要因です。
しかし、その複雑さゆえに、中間管理職への負担が増加することも珍しくありません。
中間管理職の方の中にはプロジェクト管理をする方もいるかと思いますが、プロジェクト管理表の中にはタスクのみがWBSとして組み込まれていますが、そこに人間関係の構築やハレーションなどは当初から組み込まれていません。
ゆえにコミュニケーションロスが発生するとスケジュールが順調に遅延するケースがあります。こういった際に中間管理職へ飛び火して業務を巻き取ったり、コミュニケーションの折衝をしたりすることがあります。
中間管理職の業務負担が生む悪循環
職場の人間関係が円滑でない場合、その調整に多くの時間と労力が費やされ中間管理職の業務負担が増加します。
この負担が蓄積されると本来の業務に支障をきたし、最終的には組織全体の効率低下を招くことになります。
例えば、今回体験談として取り上げている企業様の例ではないのですが、ある企業様では部下同士の対立が頻発し、タスクが進行せずその対応に追われた中間管理職が他の業務に十分な時間を割けなくなりました。
結局部下二人とも辞めてしまい中間管理職にタスクが全て降ってくるという超悪循環。(人間関係の問題はとても難しくただ最終的には中間管理職が苦労を飲み込まなくてはいけないバッド事例です)
このような状況では、上司代行(中間管理職の負荷を軽減するサービス)を活用して短期的な負担を軽減することが解決策の一つとなり得ます。
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
組織としてのサポート不足
ここでは少し見方を変えてみます。
実態として多くの職場では中間管理職への十分なサポート体制が整っていないことが課題となっています。
これは業務分担の話と体制の話などいろいろな見方がありますが、業務分担についてはスキルセットが他の人だと難しいという点で中間管理職が巻き取る形をとらされるケースが多く、体制については話を深堀すると根本的にリソースが足らないことが多いです。
加えてイレギュラー対応(本来の業務とは別件)が発生した場合、遅かれ早かれ中間管理職の方がその問題を対処することに追われます。
例えば、部下の教育やメンタルヘルスのサポートが不十分である場合、その責任(とまでは言いませんが対処することを)が中間管理職に押し付けられることがあります。
課題がある→スキルセットが足らない→リソースが足らない→でも対処しなきゃいけない→中間管理職の人頼みます(という悪循環)
リソースが根本的に不足しているので仕事を抱え込んでしまう
昨今、中間管理職に対する世間の目が冷ややかなのは一言で言ってしまうと「めんどくさい業務が全て中間管理職に来るから」です。
中間管理職は、上司と部下の間をつなぎ、チーム全体を円滑に運営する重要な役割を担っています。
しかし、業務が多岐にわたることもあるし多様に変化することもあり、柔軟な対応が求められる場面も複雑です。中間管理職はイレギュラー対応のためにいるのではなく、既存の業務をやりながらイレギュラー対応をするわけです。
100kgまでしか上がらないベンチプレスを突然、140kg上げてくれと言わんばかりに仕事が降ってくるので相当な負荷がかかります。仕組みで解決することも難しい問題も多いため、結局は残業で対処するしかありません。
また立場上横並びで同じ部署に中間管理職が何人もいるわけではないので、相談も難しく仕事を抱え込み、バッドサイクル(悪循環)に繋がってしまいます。
上司代行(中間管理職の支援)を機能させる重要なポイントと経験談
悪循環に入ってしまった(可能であれば入る前がベスト)中間管理職を支援するのが上司代行の役割です。
とはいえ中間管理職の方が管理するタスクが人間関係のものや他部署折衝の話であれば、短期で解決が難しいタスクや事案もあるのは確かです。
ここでは上司代行をどう活用するのかと機能させる重要なポイントについて解説していきます。
自分の限界を知ることの大切さ
中間管理職は多くの責任を抱え込むあまり、自分の限界を見失いがちです。(実際に自分がやらないと他に頼る人がいないが故に背負ってしまうことも確かです)
しかし、無理をし続けることで心身の健康を損なうリスクがあります。
なので自分の限界を知り、必要に応じて他者に助けを求めることもスキルの一つです。
筆者が体験したある事例では、業務量が膨大でありながら誰にも相談できない中間管理職の方がいました。
上司代行を導入したことで、仕事を適切に分担でき、結果的に職場全体の効率が上がりました。必要以上に負担を抱え込まず、リソースを適切に活用することが大切です。
効果的なコミュニケーションの重要性
中間管理職において、効果的なコミュニケーション能力は最も重要なスキルの一つです。
上司には部下の状況や意見を正確に伝え、部下には上層部の意向を的確に伝える必要があります。
このバランスが崩れると、職場全体に混乱が生じかねません。
筆者が上司代行として働いた際にも、まずはチームとの信頼関係を構築することから始めました。積極的に話をして共通点を見い出し、徐々に信頼を積みかなさねていきました。
一人ひとりの意見に耳を傾け、部下の課題を把握することで、スムーズな業務進行が可能になります。
具体的には定期的なミーティングや1対1の面談を通じて、情報共有の場を設けることが効果的でした。
上司代行の体験から得た提言
上司代行として多くの現場を経験する中で、中間管理職に共通する課題が見えてきました。
それは、「孤立感」と「不安感」です。多くの中間管理職の方とお話をして口には出しませんが共通して根本にある感情はこの2つでした。
やりたくない仕事をやらなくてはいけない二律背反な感情があり、上司や部下との板挟み、自分の仕事が終わらない、クライアント対応など多くの悩みを抱えている状況で孤独な立場にいるとても難しいポジションです。
これを解消するためには、定期的な会社からのケアやメンタルヘルスへの配慮が必要です。
また、上司代行の導入は短期的な負担軽減にとどまらず長期的な職場環境改善にも寄与します。
筆者が支援した企業様ではまず短期的には業務負荷は圧倒的に解決をしました。最初のインプットの時間は必要なのですが、業務を2つでも4つでも巻き取ることで相対的に社員、中間管理職の方が抱える業務負荷は減ります。
また会社、他部署から来た依頼も巻き取ることで物理的なタスク量だけではなく、心のメンタル負荷も軽減をすることができます(どちらかというとメンタル面の方が助かったという声が強かったです)。
中間管理職を支える仕組み作りの必要性
中間管理職が安心して働ける職場環境を整えることは、企業の成長に直結します。
本章では中間管理職の業務を改善する例を一部ご紹介させていただき上司代行サービスの活用法について解説します。
「とりあえずミーティングするか」の文化をなくす

よくありがちな中間管理職の1つに「カレンダーが埋まっている」という事象があります。
中間管理職は他部署からの相談や部下からのタスク相談、1on1などのMTG、経営上層部への報告など意思決定をする立場上多くの場面、議論の場に顔を出します。
故にMTGが多くなりがちで自分のタスクを消化する時間が無いことが多いです。
このMTGの文化は仕方がない側面もあります。多忙な日々を送る中で部下だけでは決められない事案や他部署の方からしてもこの部署の意思決定者を巻き込まないと話が進まないということも多くあるでしょう。
ただ、実際にそのMTG内で意思決定に関わる重要な時間・要素は1時間のMTGの内、何分くらいでしょうか。
もちろん部署メンバーや社内他部署の方々とのコミュニケーションの場でもあるのでただ単に意思決定だけする場としてMTGが存在しているわけではないのですが、
以前支援していた企業様ではとにかく現場レベルのタスク確認に部長や次長クラスの方々も入ってMTGをするという文化(実質的にマイクロマネジメント)がありました。その部長や室長の方は表面上言葉にしてはないのですが、とにかくMTGが大好きなようでした(暇ではないが忙しくもなく、主要なタスクは全て課長に丸投げしているという状況で逆に仕事がなくて現場レベルのMTGに介入するという悪循環な状況でした)。
いずれにしてもMTGをするにあたっては、中間管理職の方が参加する意義を事前明確にしておくことです。
MTGのゴールやアジェンダ、そのMTG内で意思決定をすることなど事前準備が非常に重要で、「とりあえず困ってるからMTG」というのは時間を浪費するだけです。
現在支援している会社様でかなり多忙な中間管理職の方がいますがその方と相談する中で「相談ごとは立ちながらやろう」という「立ちMTG」をプロトタイプで導入したことがありますが「かなり効果がありました」。
もちろん腰を据えて話すというのは大事な時間でもありますが、多忙な日々を送る中ではクイックに決める・確認するということも出てきます。そんな中で立ちながらMTGをするという文化の醸成はかなり面白く効果的な取り組みでした。
(余談ですが腰の高さ程度のロッカーの上にPCを置いて立ちながらMTGをすると20%程度MTG時間が長くなるという結果にもなりました)
また筆者が関わった企業では、働き方改革の一環として業務プロセスの見直しが行われました。これにより、従来の無駄な会議や重複したタスクが削減され、中間管理職が本来の業務に集中できるようになりました。
その他、中間管理職の業務についてお悩みが少しでもある方はぜひご相談下さい
上司代行サービスを有効活用する方法
上記でご紹介した事例のように上司代行は中間管理職の右腕のようなポジションにいます。
上司代行サービスを効果的に活用するには、導入の目的を明確にすることが重要です。
単なる業務負担の軽減ではなく、リーダーシップの強化や組織全体の改善を目指す視点が求められ、そこに伴走するパワーが自社内では足りていない企業様にはかなり有効です。
例えば、プロジェクトの立ち上げ時に上司代行を活用することで、リーダーシップが一時的に補強され、スムーズなスタートが切れたり、問題解決能力が高い代行者をアサインすることで、現場全体の課題解決が迅速に進みます。
中間管理職として頑張るあなたに知ってほしい上司代行
最後に上司代行としての経験を踏まえ、中間管理職の方々に対して上司代行の活用法とメッセージをお伝えさせてください。
中間管理職の皆様へメッセージ
中間管理職として日々奮闘する皆様にお伝えしたいのは、「一人で抱え込まないでください」ということです。必要な時には、上司代行サービスや外部リソースを活用し、自分の役割を果たすことに集中してください。
孤独感を抱えやすい中間管理職だからこそ、信頼できる仲間やサポート体制を整えることが大切です。そして、常に前向きな姿勢を持ち、自分自身を大切にしてください。
上司代行経験者だから伝えられるエール
上司代行として多くの現場を見てきた中で感じたのは、中間管理職の皆様の努力が、企業の成長に不可欠だということです。
中間管理職は「材料が揃っていないのに意思決定をしなければならない」こともあるし「部下の人生に影響を与える評価」、「インシデント発生時の対応」、「ミスの謝罪」、「上司からの叱責」などとにかく「やりたくない仕事をやらなければならない割合」が非常に多いです。
その一方で、その負担の大きさが見過ごされている現状もあります。だからこそ、自分を労り、適切なサポートを受けることを恐れないでください。
一時的にプロの助っ人を呼ぶことは正社員雇用よりも経営目線では最適
上司代行という選択肢は中間管理職の未来を切り開く一つの手段です。
経営目線の話をするとどの企業も中間管理職不足の悩みを抱えるタイミングがくる可能性があります。
「新卒を育成しても退職されてしまう」、「柔軟に動けて意思決定ができるメンバーがいない」などの悩みを抱えることがどこかのタイミングで来ます。
正社員雇用は自社の同じミッション、ビジョンを共有できる仲間ですが、プロストイックの上司代行サービスもそれは同じで志をもって取り組ませていただきております。
同じミッション、ビジョンを共有して同じゴールに向かって苦楽をともにすることは上司代行(中間管理職支援)の何よりの重要な使命です。
この新しいサービスを活用することで、職場全体がより効率的かつ健全に機能する可能性が広がります。
ぜひ、恐れずに頼れるパートナーを見つけてください。それが、中間管理職のご自身だけでなく、企業全体の成功に繋がる可能性があります。
本記事は以上となります。それでは本日もよい一日をお過ごしください!
中間管理職の業務過多に少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック