皆さんこんにちは。
本日は60代の方に絶対に知ってもらいたい「セカンドライフの過ごし方」について実際の体験談をもとに解説をしていきます。
- 既に60代だが、老後の自分が色々と不安(資産・健康・過ごし方)
- まだ40代だけど60代になった時のお金が心配
- 老後の過ごし方について全くイメージができていない方
60代からのセカンドライフとは?
60代の方々にお伺いまずお伺いしたいです。60代からの人生設計ってできていますか?
「60代になったら後はゆっくりするだけ」、「年金生活で選択肢もなにもない」、「もう寿命もないからそんなの考えない」
上記の質問をすると色々な反応が返ってきます。まずはじめに述べておくと「こうすべき」「老後は〇〇な風に過ごさなければいけない」などと断言はしませんし、色々な生き方・過ごし方があって良いと思います。
現在、定年も65歳から70歳に伸びていることや平均寿命が延び、健康寿命も伸びてきている現代において、60代からの暮らし方は多様化しています。
しかし最近は「60代からの人生をどう設計するか」「定年後に何を目標にして生きていくか」といった問いに向き合う方が増えてきており、“セカンドライフ”という言葉が改めて注目されています。
老後資金や仕事、健康、人間関係、趣味や地域とのつながりなど、見直すべきテーマは多岐にわたります。
この記事では、60代という人生の節目を迎えた方々に向けて、セカンドライフの意味とその背景、社会環境の変化、そしてこの年代ならではの転機について丁寧に整理していきます。
これからの人生を前向きに、そして安心して歩んでいくために、どんな準備が必要かを一緒に考えていきましょう。
セカンドライフの意味と背景
「セカンドライフ」という言葉は直訳すれば「第二の人生」ですが、近年では60代以降の生活全般を指す言葉として広く使われるようになってきました。
単なる“老後”や“隠居生活”というイメージとは異なり、より能動的で主体的に人生を楽しむ時間と捉えられています。
背景にはいくつかの社会的な変化があります。まず、人生100年時代といわれるように、定年を迎えたあとも20年〜30年にわたる期間があるという現実です。
厚生労働省のデータによれば、2023年時点での日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳とされています。これに対し、定年の平均年齢が60〜65歳とすると、その後の時間は実に20年以上にも及びます。
また、経済的な事情からも、働き続けることや新しい収入源を模索する60代が増加しています。
老後資金の目安が2,000万円とも言われるなか、貯蓄や年金だけでは不安を感じる方も少なくありません。こうした現実的な背景から、「セカンドライフ=引退」ではなく、「新しい人生の章」という認識に変わりつつあります。
さらに、子育てがひと段落し、ご家族の独立や生活スタイルの変化を機に「自分の時間」を再構築する時期として、60代は大きなターニングポイントになりやすい年代です。
今後の生活をどう過ごすかを考えるうえで、セカンドライフの捉え方が変わってきていると言えるでしょう。
定年延長・再雇用時代の「第二の人生」像
現在の日本では、多くの企業が定年の延長や再雇用制度を導入しており、「定年後に一度に仕事を辞める」という働き方が見直されつつあります。
2021年4月からは改正高年齢者雇用安定法も施行され、70歳まで働ける環境整備が企業に求められるようになりました。こうした制度の変化は、60代のライフプランに大きな影響を与えています。
再雇用で継続して働く方もいれば、フリーランスやパートタイムで新しい働き方に挑戦する方もいます。中には、自営業や地域活動、NPOへの参加など、自分らしいライフスタイルを模索しながら新たな社会的役割を見出す方もいます。つまり、60代のセカンドライフは「何もしない時間」ではなく、「新しい挑戦の時間」として捉えられているのです。
一方で、再雇用は収入や職責が大きく変わるケースもあり、仕事を通じての充実感や人間関係の変化に戸惑う方も少なくありません。
だからこそ、60代を迎える前後で「自分にとって働くとは何か」「これからの人生で大切にしたいことは何か」を一度立ち止まって考えてみることが大切です。
「セカンドライフ」はキャリアの延長線上にあるものではなく「自分の人生にもう一度舵を取る時間」として捉えることで、その意味合いがぐっと深まっていくのではないでしょうか。
60代は変化を受け入れながらも、これからの生き方を自分自身でデザインしていける貴重な時期だと考えられています。
60代が直面する主な転機(退職、年金受給開始、介護リスクなど)
60代になると生活のなかでさまざまな「転機」を迎える方が多くなります。
なかでも代表的なものとして、退職や年金の受給開始、親御さんやご自身の介護リスクなどが挙げられます。こうした転機は、ライフスタイルや価値観の見直しにもつながりやすいため、事前の備えが非常に重要とされています。
まず退職は多くの方にとって“人生の一つの節目”でもあり、時間の使い方や経済設計が大きく変わる瞬間です。特に会社中心の生活を送ってきた方にとってはアイデンティティの再構築を求められることもあります。
次に年金の受給。多くの方が65歳から受給を開始されますが、60歳からの繰上げ受給や70歳までの繰下げといった選択肢もあるため、年金の知識や活用方法について早めに学んでおくことが望ましいとされています。
そして見逃せないのが「介護」の問題です。
厚生労働省の調査によると、介護が必要になる平均年齢は女性で75歳、男性で78歳前後とされていますが、介護は突然始まることもあるため、60代のうちから介護保険や施設選び、家族との連携体制などについて考えておくことが求められます。
これらの転機はどれも避けることが難しい「現実的な節目」であり、セカンドライフの方向性を大きく左右する要素となります。
だからこそ、60代という時期は、未来の安心と楽しみのために、自分自身と向き合う絶好のチャンスなのです。
60代のセカンドライフに必要なお金とは?
セカンドライフを穏やかに、そして自分らしく過ごしていくためには、経済的な準備が欠かせません。60代という年代は、収入が大きく変わるタイミングであると同時に、今後の支出に対して現実的に備えていく必要がある時期でもあります。
定年後も働き続けるか、年金だけで暮らしていけるのか、どのくらい貯蓄があれば安心できるのかなど、お金に関する不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
特に「老後2,000万円問題」などが話題になったこともあり、「本当にそんなに必要なのか?」という声も根強くあります。
ここでは、60代からのセカンドライフに必要となる生活費の実態や、公的年金と貯蓄の使い方のバランス、さらに単身・夫婦それぞれの生活モデルにおける費用の目安など、現実に即した情報を整理していきます。「なんとなく不安」から、「だからこう備えよう」へと視点を変えるためのヒントになれば幸いです。
老後の生活費は月いくら?総額はどのくらい?
老後の生活費について、「毎月いくらくらい必要なのか」「何年分を想定しておけば安心なのか」は、セカンドライフ設計の基盤となる重要なテーマです。60代という年代では、まだ生活に現役時代の感覚が残っている方も多いため、生活費の再計算や見直しはこれからの計画に直結します。
総務省「家計調査報告(家計収支編)」によると、2023年時点における高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上・妻60歳以上)の毎月の平均支出はおよそ26万円となっています。これに対して、公的年金の受給額は平均で約20万円前後とされており、月々に5〜6万円の赤字が生じる構造です。
この差額を貯蓄や退職金などで補っていくことになりますが、「老後が20〜30年続く」と仮定すれば、月5万円の不足があった場合、単純計算でも年間60万円、20年で1,200万円が必要になる計算です。ここに突発的な出費や余裕資金として800万円を加えた概算が老後に2,000万円不足すると計算されているので「老後2,000万円問題」というのが浮上しました。
しかし老後2,000万円問は2019年6月に発表されたもので、そこから物価が急上昇しているため、2,000万円では足らないことが鮮明になりつつあります。
また、生活スタイルや住居の形態(賃貸か持ち家か)、趣味やレジャーにどのくらいお金をかけるかによって、必要な生活費は大きく異なります。
セカンドライフに向けた家計の設計は、「平均」ではなく「自分の場合」を基準に見直すことが、現実的な準備につながると考えられています。
2,000万円問題の再確認とリアルな目安
2019年に金融庁が報告書の中で「老後に2,000万円が不足する可能性がある」と記したことで、多くの人に衝撃を与えた「老後2,000万円問題」。この数字だけが独り歩きし、「そんなに貯められない」「どうせムリだから考えないようにしている」といった声も広がりました。
しかし、あらためて冷静に見てみると、この2,000万円という数字は「モデル世帯」が公的年金だけでは不足する金額を補うための目安であり、すべての人に共通するものではありません。
実際には、自宅が持ち家であるか、住宅ローンが完済されているか、地方に住んでいるか都市部かによっても必要金額は大きく変わってきます。たとえば、地方在住で自家用車を手放したことで支出が大きく減ったという例もありますし、逆に都市部で家賃を払い続けている方は3,000万円程度の備えが必要とされるケースもあります。
「2,000万円貯めなければならない」とプレッシャーを感じるよりも、「自分のライフスタイルに合わせた現実的な備えはどのくらいか?」を見極めることが、セカンドライフを安心して迎える第一歩になるのではないでしょうか。
60代からの年金と貯蓄、使い方のバランス
セカンドライフの資金設計においては、年金と貯蓄の“使い方のバランス”が極めて重要です。公的年金は基本的に毎月安定して入ってくる収入源である一方、貯蓄は取り崩すごとに減っていくため、「どこまでを年金で賄い、どのように貯蓄を活かすか」という視点が必要です。
【補足】まだ40代、50代の就業中の方を中心に補足をすると、年金生活に入ると入ってくる収入に上限がありお金が一方的に出ていくことが増えていきます。これ以上稼ぐこともできないので、お金の取り崩しが始まります。そうなるとどう「節約するか」ということにかなり目線が行きがちになり、投資などにリスクを取ることをためらう傾向にあります。なので、セカンドライフの資産設計は早めに考えることが推奨されます。
たとえば、年金で生活費の7〜8割をカバーできる場合、残りを貯蓄から補うといった考え方が主流です。ただし、住宅リフォーム費や医療・介護費、交際費や趣味など、イレギュラーな支出には柔軟に貯蓄を使うという姿勢が求められます。
また、60代はまだ比較的健康で動ける時期であるため、「旅行に行きたい」「新しいことに挑戦したい」という希望を実現するために、ある程度の自由資金を計画的に使っていくことも、精神的な充実感につながります。無理に節約一辺倒になるより、「使うときには使う」という姿勢も、セカンドライフにおいては大切な考え方とされています。
そして資産の運用という視点も重要です。年金だけでは不安な場合、60代でも比較的リスクの低い運用(債券中心の投資信託など)を取り入れるケースも見られます。ただし、運用は元本保証ではないため、実施する際は専門家と相談のうえ、無理のない範囲で検討するのが望ましいでしょう。
夫婦世帯・単身世帯の生活費モデル
セカンドライフにおける経済設計を考える上で、世帯構成は重要な要素となります。
60代の方々のなかには、夫婦二人で生活を送っている方もいれば、配偶者に先立たれた方や、初めからおひとりさまを選んでいる方もいらっしゃいます。こうしたライフスタイルの違いによって、必要な生活費も大きく異なってきます。
たとえば、総務省の家計調査によれば、夫婦高齢無職世帯の月間支出は平均で26万円前後。一方、単身高齢無職世帯では平均で16万円程度とされており、生活費に約10万円の差があると報告されています。
しかしながら、単身世帯のほうが支出が少ないとはいえ、光熱費や家賃、通信費などはひとりでも一定額がかかるため、「一人分だから楽」というわけではありません。むしろ、支出の固定費割合が高くなる傾向にあるため、予算管理の難易度が上がるという側面もあります。
また、夫婦世帯ではどちらかが先にお亡くなりになった場合、遺族年金を受け取ることで収入が一定程度維持される一方、支出は大きく減らないことも多く、将来的には単身世帯に移行することを見据えた準備が求められます。
このように、セカンドライフに必要なお金は「世帯のかたち」によっても変わるため、ご自身の状況や将来の見通しを踏まえた柔軟な設計がカギとなります。平均やモデルケースを参考にしつつも、「わたしの場合はどうだろう?」という視点で考えることが、安心と納得感のある生活設計につながっていくと考えられています。
資産運用と見直し|60代のセカンドライフに合った方法とは?
60代に入ると、現役時代のような「増やすための投資」から、「減らさない・上手に使う」ことを意識した資産運用へと価値観が変化していくケースが多く見られます。セカンドライフに向けた資産管理では、単純なリターン重視だけでなく、生活費の安定確保や将来の医療・介護費用への備えも含めたトータルな設計が求められます。
さらに2024年からは新NISA制度もスタートし、60代でも長期・積立・分散投資の選択肢が広がっています。また、不動産などの資産を「どう活かすか」も重要なテーマとなっており、持ち家の活用や住み替えによる生活設計の見直しを検討する方も増えてきています。
このパートでは60代が考えるべき資産運用の方向性やリスク回避の視点、制度を活かした選択肢、そして住まいを含めた“資産の使い方”にフォーカスして、より安心で納得感のあるセカンドライフ設計を後押しする情報をお届けします。
定年後の資産運用:守りと攻めのバランス
資産運用というと、リスクを取ってお金を「増やす」イメージが強いかもしれませんが、60代以降は「守る」意識も非常に大切になります。なぜなら、60代は現役世代と比べて収入の増加が見込めない一方、支出は一定以上かかり続けるからです。
60代での運用の基本は「生活資金に余裕を持たせつつ、インフレや長寿リスクに備える」こと。すべてを現金で持っておくとインフレに弱くなりますが、すべてをリスク資産に預けると暴落時に取り崩せないというジレンマがあります。
そのため、リスクとリターンのバランスを取った「守りと攻めのミックス戦略」が推奨されることが多いです。
たとえば、生活費2〜3年分は流動性の高い預貯金や短期国債に確保し、それ以外は安定的な配当が期待できる株式や債券型の投資信託、定期預金などで運用するという考え方です。
「60代の資産運用は守りが基本」と言われる一方で、あまりに守りすぎると資産の目減りリスクに対応できないという側面もあります。
だからこそ、セカンドライフでは「自分に合ったリスク許容度」を見極めながら、少しの“攻め”も取り入れていくことが、将来の安心につながるとされています。
60代でやってはいけない投資とは?
資産運用が注目される一方で、60代にとって注意すべき「やってはいけない投資」も存在します。特に定年退職後の退職金を元手に、短期間で大きなリターンを狙おうと無理をすることは、リスクが非常に高いとされています。
金融庁や消費者庁によると、近年は高齢者を狙った詐欺まがいの投資トラブルも増加しており、「絶対儲かる」「元本保証」といった誘い文句には警戒が必要です。
過去には「海外ファンドへの高利回り預託」や「未公開株の購入を持ちかける業者」といった事例も報告されています。
また、60代は時間的な回復余力が少ないため、ハイリスク・ハイリターン型のFX取引や仮想通貨などへの一括投資も慎重に判断する必要があります。
相場変動が激しく、精神的な負担も大きくなりやすい投資手法は、老後の安心を損なう可能性があるため、資産の一部にとどめておくのが現実的です。
一方で「すべての投資がダメ」というわけではありません。インデックス型の投資信託や、低コスト・長期運用型のサービスなど、リスクを抑えつつ安定的に資産形成ができる選択肢もあります。
大切なのは、「なぜ投資するのか」「何のために運用するのか」を明確にし、自分の生活設計と無理なく噛み合う方法を選ぶことです。
iDeCo・NISA・年金の併用術
2024年に制度が刷新された「新NISA」は60代の方にとっても活用できる長期投資の有力な選択肢として注目されています。特に年間投資枠の拡大(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)や、生涯非課税枠の導入などにより、資産運用の幅が広がっています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)もまた、節税効果の高い制度ですが、原則60歳までしか積立ができず、受け取り開始も60歳以降に限定されているため、60代での新規加入は年齢制限に注意が必要です。一方、すでに加入していた方は、受取方法(分割・一括)や受取時期を最適化することで、税制面でのメリットを最大限に活かすことが可能です。
新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能で、60代の方でもインフレ対策や老後の生活費補填に向けた運用が現実的になります。つみたてNISAの対象商品は、主に低リスク・長期分散型のインデックスファンドが中心であり、初心者でも取り組みやすい設計となっています。
年金と運用の併用においては、「年金は生活費のベース、NISAは将来の追加資金」という位置づけにすることで、生活の安心感と柔軟性を両立することができます。制度の活用には一定の知識が必要ですが、金融機関の窓口やファイナンシャルプランナーへの相談を通じて、自分に合った方法を見つけていくことが望ましいとされています。
持ち家 vs リースバック vs サ高住(資産の活用)
60代にとってもうひとつの大きな資産が、「住まい」です。長年住み続けた持ち家を今後どう活かしていくかは、セカンドライフ設計において非常に重要なテーマになります。
ちなみに「サ高住」とは、「サービス付き高齢者向け住宅」の略称で、高齢者が安心して生活ができるようんに、定期的な安否確認や日常の生活相談ができるなどのサービスが提供される賃貸住宅のことを指しています。
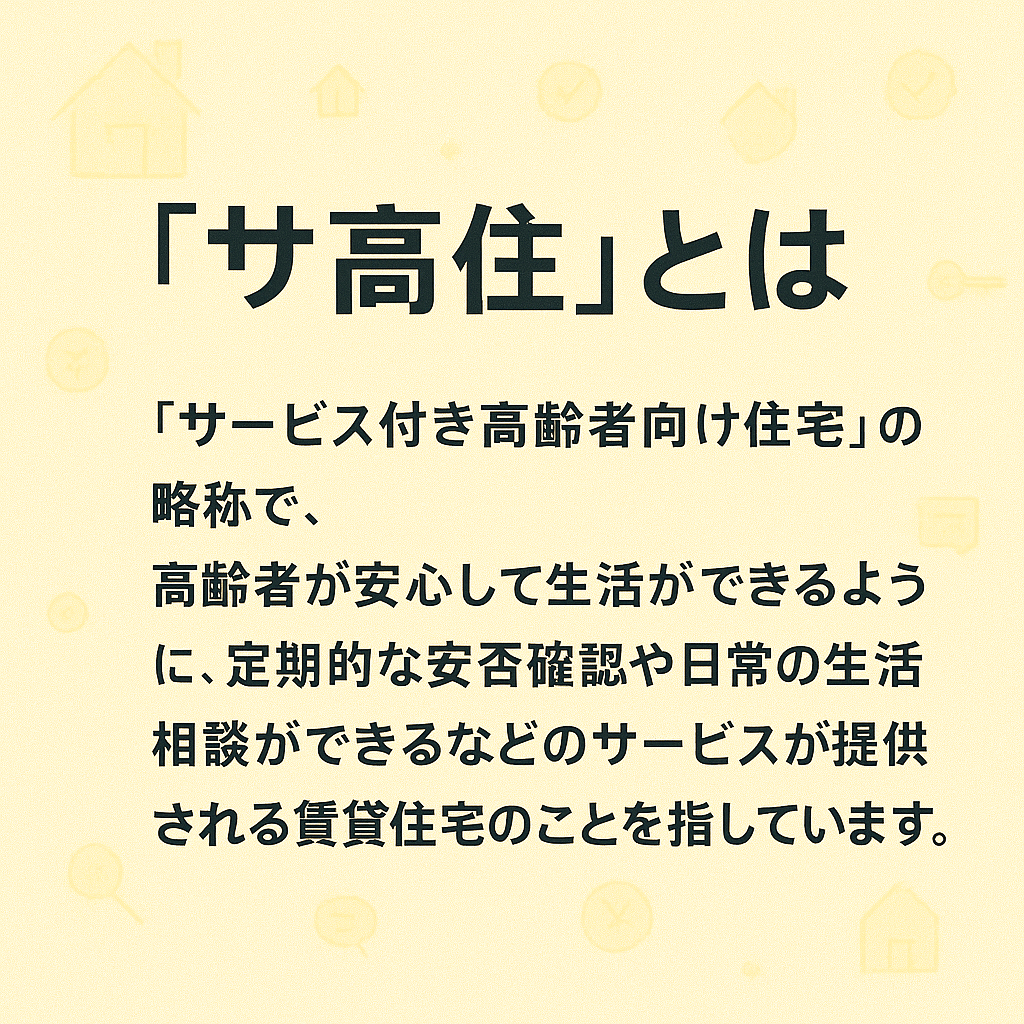
またリースバックとは第三者に所有資産を売却すると同時に賃借する取引方法です。
例えば、自宅を売却した上で、同居住物件を賃借することで、売却資金の確保と同時に住み続けることが可能になります。
まず、「持ち家をそのまま住み続ける」選択肢は安心感がある反面、修繕費や固定資産税といった費用も継続的に発生します。また、将来的に自宅での生活が難しくなった場合、住み替えや売却のタイミングを見極める必要が出てきます。
一方、「リースバック」は、持ち家を売却した後もそのまま住み続けられる仕組みで、まとまった資金を得ながら居住環境を維持できるという特徴があります。生活資金にゆとりがなくなったときの選択肢として注目されていますが、契約内容や賃料負担などには注意が必要です。
さらに、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」への住み替えも選択肢の一つです。
バリアフリー構造や見守りサービスが整っており、単身や高齢夫婦でも安心して暮らせる環境が提供されます。月額利用料は施設により異なりますが、家を処分して住み替えることで生活設計を見直すという動きも増えています。
それぞれの選択肢にはメリットと注意点がありますが、大切なのは「資産としての住まいをどう位置づけるか」「将来の変化にどう対応できるか」を、早い段階から考えておくことです。
セカンドライフの住まい方を見直すことは、安心感と経済的なゆとりの両方を得るための、大きな鍵になると考えられています。
次回の〈最終まとめパート〉では、ここまでの内容を総括し「60代の今だからこそ始められるセカンドライフ設計の実践ポイント」や、家族との情報共有、専門家との連携方法など、“実行に移すためのステップ”をご紹介していきます。未来への不安を、安心と楽しみへと変えていくヒントをぜひご期待ください。
60代から考える暮らし方と住まいの選択
セカンドライフをどこで、どのように過ごすか。それは、60代にとって重要なテーマです。
住まいは生活の基盤であると同時に、心身の健康や人とのつながりにも大きな影響を与える存在です。だからこそ、この時期に一度「本当に今の場所が自分に合っているのか?」「将来を見据えて住まいを変える選択肢はないか?」と見直してみることには大きな意義があります。
特に昨今では、地方移住や郊外への住み替え、コンパクトな暮らしへの関心も高まっており、定年後に住環境を変えることで新たな楽しみや生きがいを見つける方も増えています。一方で、医療や交通、コミュニティとの距離感などをどう考慮するかも課題として内在しています。
ここでは、60代以降の暮らし方の選択肢や、住み替えを検討する際のポイント、健康や安心とどう向き合うかについて、具体的に解説していきます。「住まいを選ぶこと」は、「これからの人生をどう生きるか」を考えることにもつながる時間です。
セカンドライフと移住(地方・郊外の可能性)
セカンドライフの充実を考えるなかで、「地方や郊外への移住」を検討する60代の方が増えてきています。広々とした自然環境、比較的ゆとりある住空間、物価の安さ、そして「人との距離感の心地よさ」などが理由として挙げられます。
実際、総務省が2023年に発表した移住動向調査では、地方移住を希望する層のうち、60代が約3割を占めているという結果が出ています。
リタイア後の時間を活かして、農的暮らしやスローライフを楽しみたいという希望や、都会の喧騒から離れて静かな環境で過ごしたいというニーズが、背景にあるようです。
ただし、地方移住には慎重な準備が必要です。医療機関へのアクセスや交通手段、生活インフラの整備状況など、現地での生活のしやすさを事前に確かめておくことが重要です。また、移住先の地域との相性(文化や人間関係)も、暮らしの満足度に大きく関わります。
最近では「お試し移住」や「移住体験住宅」を提供している自治体も増えており、いきなり拠点を変えるのではなく、段階的に移住を検討する方も増えています。
セカンドライフの一環としての地方移住はご自身にマッチすれば心身ともに豊かな生活をもたらしてくれる可能性がありますが、見落とされがちなリスクもあるため、下調べと現地訪問を通じて「リアルな暮らし」を体感することが推奨されています。
住み替えや終の住処の考え方
60代になると、今後の住まいについて考える機会が自然と増えてきます。
「いまの家に住み続けるべきか」「もっと暮らしやすい場所に住み替えるべきか」あるいは「介護が必要になったときのことを考えて施設に移るべきか」など、多くの選択肢と向き合う時期ともいえます。
特に、子育てが終わり、夫婦二人や単身世帯となった後の住まいは、広さや立地を見直すタイミングにもなります。管理が難しい戸建てからマンションへの住み替えや、階段のある住まいからバリアフリーな住宅への移行などは、安心感と生活効率を高める手段として注目されています。
また、最近では「終の住処(ついのすみか)」という言葉も広く使われるようになり、「最後まで自分らしく暮らせる場所はどこか」という視点が、60代からの住まい選びにおいて重要なテーマとなっています。
終の住処は必ずしも施設や特別な住宅を意味するわけではありません。
自宅をリフォームして住みやすくする、近くに住むご家族との距離感を見直すなども、立派な選択肢のひとつです。ポイントは「今の生活」と「10年後、20年後の生活」を両方想像したうえで、無理なく移行できる形を選ぶことです。
自分が年齢を重ねたとき、どのように過ごしたいか。そのイメージに合った住まい方を早めに描くことが、セカンドライフの安心感を高める備えにつながっていきます。
健康・医療アクセス・コミュニティについて検討すべきこと
住まいを選ぶうえで見逃せないのが「健康」「医療」「人とのつながり」といった、暮らしの質に直結する要素です。
特に60代以降は加齢に伴う体調の変化や介護への備えが現実的な課題となってくるため、住環境が心身の安心にどう影響するかを見極める視点が欠かせません。
まず、医療機関へのアクセスは非常に重要です。
日常的な通院が必要になった場合や、緊急時の対応を考えると、「近くにかかりつけ医がいるか」「夜間・休日に対応できる医療施設があるか」は大きな判断材料になります。
また、地域コミュニティへの参加やご近所との関係性も、セカンドライフの充実度を左右する要素のひとつです。孤立を避ける意味でも、「挨拶できる相手がいる」「ちょっとした困りごとを相談できる」関係性が築けるかどうかは、安心感のベースになります。
最近では地域包括ケアや高齢者支援センターといった自治体の取り組みも増えており、地域全体で支え合う仕組みが整いつつあります。
住まいを選ぶ際にはこうした“目に見えない安心”にも目を向けてみることが、セカンドライフを豊かにする大きなヒントになります。
移住や住み替えを検討する際も「ただ静かな環境で過ごせるかどうか」だけでなく、「健康面の安心や社会的つながりも保てるかどうか」に意識を向けておくと、後悔のない選択につながるのではないでしょうか。
60代で始める「やりがい」のあるセカンドライフ
セカンドライフという言葉には「余生」や「老後」といった消極的なイメージを持たれることもありますが、実際には“人生の再スタート”という前向きな意味合いを込めて使われることが増えてきました。特に60代は、仕事や子育てといった社会的な役割から一段落し、「自分のための時間」がようやく確保できるタイミングでもあります。
このタイミングで何かに打ち込める「やりがい」があると、日々の生活に活力が生まれ、心身の健康にも良い影響をもたらすと考えられています。もちろん、やりがいの形は人それぞれ。仕事をセーブしながらも働き続ける方、地域活動やボランティアに参加する方、長年の趣味を深める方、学び直しで新たな知識を吸収する方など、多彩なスタイルが存在します。
ここでは、60代からでも始めやすい「やりがい」のある選択肢や、自分らしいセカンドライフを見つけるためのヒントについて、いくつかの視点からご紹介していきます。
セミリタイア・週3勤務・ボランティアなどの選択肢
定年後、「すっぱり仕事を辞める」だけが選択肢ではありません。むしろ、近年は収入と自由のバランスを取りながら、週3日程度の勤務を続ける「セミリタイア」や、「短時間労働・地域貢献型の働き方」へとシフトする方が増えています。
厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」によれば、60代の再雇用率は年々上昇しており、多くの企業が65歳までの雇用延長や、再雇用制度を導入しています。また、最近では60代から新たな職場にチャレンジする人も増えており、シニア向けの就労マッチングサービスも活発化しています。
一方、ボランティア活動やNPO団体への参加も、心の充実感を得られる手段のひとつです。地域の子ども食堂や高齢者支援、環境保全など、関心分野に関わる活動を通じて、社会とのつながりや“誰かの役に立っている”という実感を得ることができます。
やりがいを持って働き続けることは、生活リズムや社会性を維持するうえでも非常に効果的です。
「週3日だけ働く」「好きなことを副業にしてみる」「地域の役に立つことに参加する」といった選択肢を柔軟に組み合わせることで、無理なく前向きなセカンドライフを築くことができるのではないでしょうか。
趣味や学び直し(リカレント教育)
「やりがい」は、仕事だけで得られるものではありません。60代以降は今まで忙しくてできなかった趣味にじっくりと取り組むチャンスでもあります。釣りやガーデニング、陶芸、旅行、写真、音楽など、これまで興味があったことに時間をかけることで、自分らしい時間の過ごし方を発見する方も多いようです。
また、注目されているのが「学び直し(リカレント教育)」です。文部科学省も近年、「学び直しによる再チャレンジの推進」を掲げており、60代から大学や専門学校に通う方も珍しくなくなってきました。オンライン講座の普及により、自宅で気軽に学べる環境も整いつつあります。
ある60代の男性は、退職後に通信制大学で心理学を学び直し、その後地域の福祉施設で相談員として活動を始めたそうです。「ただ学ぶ」のではなく、「学びを活かす」ことで、新しいやりがいと役割を見つけられるという好例と言えるでしょう。
また、趣味と学びはしばしばリンクしており、書道や語学、歴史などのカルチャースクールに通うことで、人との出会いや地域とのつながりが広がるというメリットもあります。60代は、自分の好奇心に素直に向き合うことが、心の豊かさにつながる時期なのかもしれません。
家族・パートナーとの関係性を再構築するには
仕事や家事、育児を優先してきた人生の前半とは異なり、60代以降は「家族」や「パートナー」と過ごす時間が長くなるタイミングでもあります。そのため、「いまさら改まって向き合うのも照れくさい」「どうやって関係性を築けばいいかわからない」と戸惑う方も少なくありません。
特に定年後に一緒に過ごす時間が増えた夫婦間では、コミュニケーション不足や生活リズムの違いが原因で、気持ちのすれ違いが起こることもあるようです。だからこそ、セカンドライフにおける「やりがい」や「楽しみ」をパートナーと共有することが、関係性の再構築につながるとされています。
たとえば、一緒にウォーキングや旅行を楽しむ、料理やガーデニングを共通の趣味にする、地域のサークルに夫婦で参加するなど、「一緒に新しい体験をする」ことで自然と対話が生まれやすくなります。また、お互いの時間を大切にしつつも、「今日はどうだった?」と日々の出来事を共有する時間を持つことも、関係の再構築に役立つと考えられています。
単身で暮らしている方にとっても、兄弟姉妹や親族、長年の友人との関係を見直すことは、セカンドライフの心の支えになります。「昔の友人に手紙を出してみる」「年に一度は顔を合わせる」など、小さな一歩から関係性は動き始めるものです。
家族やパートナーとの関係は、人生の土台であり安心感の源でもあります。これまでの感謝を伝えたり、新しい習慣を一緒に作ったりすることで、60代以降の暮らしはよりあたたかく、豊かなものへと変わっていくのではないでしょうか。
まとめ|今からでも間に合う、60代の備えと行動
ここまで、60代のセカンドライフに向けたお金・住まい・暮らし方・やりがいといったさまざまな視点を整理してきました。振り返ってみると、60代という年代は、「老後の入り口」ではなく、「これからの人生を自分でどう描いていくか」を決める再出発のタイミングとも言えるのではないでしょうか。
もちろん、これまでの人生の延長線上で計画がうまく立てられている方もいれば、「何もしていない」「不安しかない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。ですがご安心ください。セカンドライフの備えに“遅すぎる”ということはありません。
今できることに少しずつ取り組むことで、生活の安心感や心のゆとりが少しずつ広がっていきます。このまとめでは、今から始められる具体的な行動や、支援を受ける際のポイント、そしてセカンドライフを自分らしく生きるための心構えを、最後にもう一度振り返っていきましょう。
今すぐ始めるべき3つのこと(資金確認・生活設計・健康管理)
60代からセカンドライフの備えを始めるにあたって、「何から手をつけたらよいかわからない」という声はとても多く聞かれます。そこで、まず着手しやすい3つのステップとして、「資金確認」「生活設計」「健康管理」をご紹介します。
まずは資金確認。現在の預貯金や年金見込み額、退職金、保険など、保有している資産を一度リストアップしておくと、自分に必要な生活費とのギャップが見えてきます。「ねんきん定期便」や金融機関の通帳、保険証券などを整理し、「見える化」することが第一歩です。
次に生活設計。夫婦世帯か単身世帯か、住宅は持ち家か賃貸か、定年後も働く予定があるかどうかなど、自分のライフスタイルを前提に支出を見直し、「毎月いくら必要か」「どんな選択肢があり得るか」を把握していきましょう。
そして最後は健康管理です。健康でいることが、経済面でも精神面でも大きな財産となります。定期的な健康診断を受ける、運動習慣を取り入れる、睡眠や食事を見直すなど、小さな一歩が長く自立した生活につながっていきます。
この3つを軸に、自分の状況を整理してみると、やるべきことが見えてきて、セカンドライフへの不安も少しずつ軽減されていくはずです。
専門家の力を借りる(FP・不動産・年金窓口など)
60代の備えは、情報が多岐にわたるため、自分だけで判断するのが難しい場面も少なくありません。そんなときに頼りになるのが、各分野の専門家のサポートです。
たとえば、お金の面では**ファイナンシャルプランナー(FP)**に相談することで、年金・保険・資産運用・相続などの全体設計を第三者目線でアドバイスしてもらえます。独立系FPであれば、特定の金融機関に偏らず中立的な助言が受けられる可能性が高くなります。
住まいに関しては、不動産会社や住宅相談窓口に相談することで、持ち家の活用や住み替え、リースバックの可否など、生活に合った選択肢を検討する手助けになります。最近では高齢者住まいの専門資格を持つアドバイザーも登場しています。
また、年金については年金事務所や社会保険労務士が頼れる存在です。繰上げ・繰下げ受給、受給開始タイミング、加給年金など制度は複雑なため、自分の条件で最適な選択肢を一緒に検討してもらうと安心です。
こうした専門家の力を借りることは、「自分の知らなかった視点」を得ることにもつながります。自分だけで抱え込まず、信頼できる第三者に相談することで、セカンドライフへの道筋がより明確になるのではないでしょうか。
最後に伝えたいこと:後悔しないセカンドライフとは
「もっと早く準備しておけばよかった」「こんなはずじゃなかった」——そんな後悔を口にされる方も少なくありません。しかし、60代の今だからこそ気づけること、始められることはたくさんあります。これまで積み重ねてきた人生の上に、これからの時間をどう積み上げるか。そこにこそセカンドライフの本当の価値があるように思います。
後悔しないセカンドライフとは誰かと比較して「正解」を探すことではなく、「自分にとって納得できる選択肢」を一つずつ積み重ねていくことだと考えられています。
それは、無理なく、背伸びせず、でも“未来の自分”が少し微笑んでくれるような選び方です。
お金のことも、住まいのことも、健康のことも、そして人とのつながりも、完璧である必要はありません。「知って、考えて、動いてみる」——その繰り返しが、セカンドライフをゆたかにする道しるべになります。
60代は、まだまだこれから。どんなスタートであっても、遅くはありません。まずは、小さな一歩から始めてみてください。そして迷ったとき、不安なときは、専門家や家族、信頼できる人と一緒に考えていくことをおすすめします。
人生100年時代。これからの時間を、あなたらしく大切に育てていけることを心より願っています。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック 