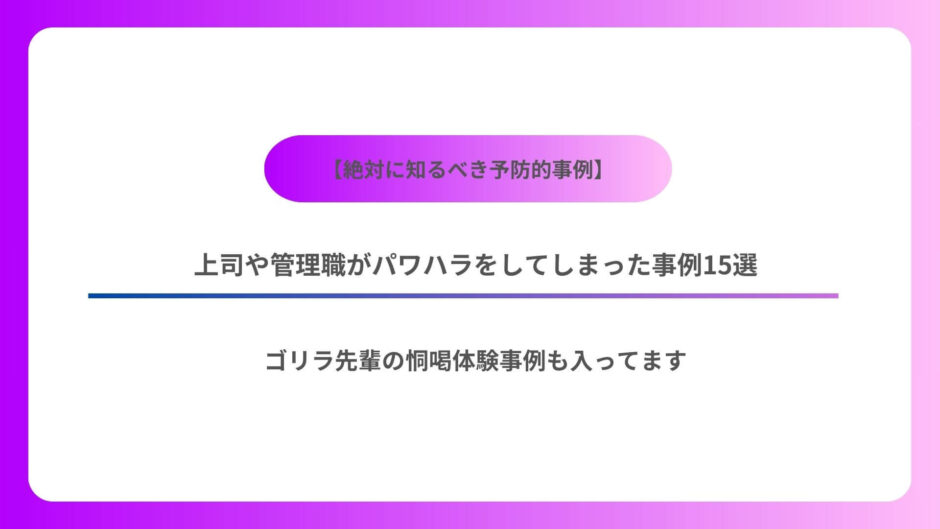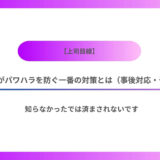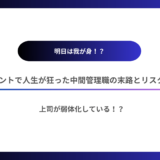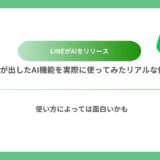皆さんこんにちは。株式会社プロストイックです。
今回のテーマは前回に続いてパワハラです。パワハラというのはかなりセンシティブな内容ですが、だからこそ困っている管理職の方がたくさんいるのを多く目にしています。対策として「防ぐにはどうすればいいのか」、「これってパワハラになるの?」「パワハラをしてしまった事後の対応ってどうすればいいのか」等皆さんが知るべきことについて解説をします。
また今回はパワハラの加害者になってしまう前に過去の失敗事例から逆算して失敗を防ぐための記事です。
- パワハラをしてしまうリスクが(無意識的にも)ある管理職に着任している方
- 周囲でパワハラの被害・加害が最近勃発している方
- パワハラのリスクを回避して管理職業務を行いたい方
ちなみに前回の記事はとしてこちらも読まれております。
なぜ今、パワハラの事例を学ぶべきなのか?

働き方改革やリモートワークの拡大、コンプライアンス意識の高まりなど、職場環境はここ数年で大きく変わりました。
しかしその一方で、「管理職の何気ない一言」がパワハラとみなされるケースが急増しています。
特に「上司だから」「管理職の立場だから」という過去の慣習に縛られてしまうと、知らぬ間にラインを越えてしまい、大きな問題へと発展する危険性があります。
このような背景から今、改めて「パワハラ」の具体的な事例を学ぶ意義が増しています。
単なる知識やルールだけでは防げない、リアルな現場の温度感や、失敗から得られる教訓にこそ価値があるのです。
そしてその一つひとつが予防と対応力を高めるヒントになります。
この記事では、実際にあった「パワハラ事例」15選を取り上げながら、上司としての立場を見つめ直す機会を提供します。
「パワハラ・上司・事例・管理職・上司代行」といったキーワードを軸に、ただの反面教師にとどまらない、“今後の動き”に役立つ視点を一緒に見ていきましょう。
管理職や上司の「うっかり言動」が取り返しのつかない事態に

パワハラという言葉を聞くと、怒鳴ったり無理な業務を押し付けたりする、いわゆる「わかりやすい」ものを想像しがちです。
しかし実際の現場では、もっと日常的で曖昧な言動が問題となっています。
たとえば、部下のアイデアを頭ごなしに否定する。あるいは、冗談のつもりで言った一言が、相手にとっては深く傷つく暴言だった。
こうした「うっかり」が、パワハラとして記録に残り、法的措置に発展する事例も出てきています。
ある企業では上司が「最近の若い子はやる気がない」と繰り返し発言していたことが、部下たちに心理的負担を与えていたと判断され、社内で正式に処分されたケースがありました。
本人は軽い愚痴のつもりだったそうですが、周囲からは「人格否定」と受け取られ、職場全体の士気が大きく低下したのです。
「上司代行」などの外部サポートが求められる背景にも、こうした“意図しないパワハラ”が急増している現実があります。
管理職という立場は、それだけ影響力が大きく、だからこそ、言葉や態度の一つひとつに対する自覚が必要です。パワハラは、故意だけでなく、無自覚にも起こりうるもの。だからこそ、「うっかり」を放置しない姿勢が重要です。
きつい言い方かもしれませんが、本当に本当に事後では遅く取返しが付かなくなるので言いますが、ハラスメントは予防が大事です。特に「日常的に部下との会話が上手くいっていないと感じる方」「ハラスメント疑惑があると思われる方」は必ず見てください
事例から学ぶことで“予防力”が高まる理由
「パワハラはしてはいけない」と知っていても、実際の現場では何がアウトで何がセーフなのか、判断に迷うことが少なくありません。だからこそ、実際に起きた「事例」から学ぶことが効果的です。
なぜなら、リアルな場面や言動を見ることで、自分自身の行動を具体的に照らし合わせられるからです。
例えば、会議中に部下の発言を遮り「話す資格はまだない」と発言した上司がパワハラで訴えられた事例があります。
これは指導の一環として本人は言ったつもりだったそうですが、第三者が見たときに「威圧的な態度」と判断されました。
こうした事例を知ることで、「自分が同じ状況に立ったとき、どうすべきか」という視点を持てるようになります。
また、事例を学ぶことは「予防力」だけでなく、チーム全体のマネジメント力の底上げにもつながります。上司代行のようなマネジメント支援を受ける現場でも、事例を共有する研修が行われることが多く、管理職としての意識改革が図られています。
言葉や行動の裏にある“受け手の心理”を理解することが、パワハラ防止の第一歩です。
教科書的な知識ではなく、「現実にあった話」だからこそ、自分ごととして捉えられるのです。
部下の離職・訴訟・SNS炎上…想定以上のリスク

パワハラが引き起こす問題は当事者間のトラブルにとどまりません。
企業全体、場合によっては社会的な信頼にも大きく関わるリスクです。部下が辞めてしまう、人事訴訟に発展する、さらにはSNSで実名や企業名とともに拡散されるなど、一つの言動が思わぬ大ごとに発展する可能性があります。
実際に、あるIT企業では上司の継続的な無視と人格否定に耐えかねた若手社員が退職し、匿名でX(旧Twitter)に投稿。その内容がバズり、会社名が特定されて謝罪に追い込まれた事例がありました。
わずか数行のポストが株価にまで影響したのです。
このような“想定外の拡大”は、今や珍しいことではありません。
特にデジタル組織においては、リスクは瞬時に拡散し、修復に時間がかかる傾向があります。だからこそ、管理職や上司は、単なる社内のトラブルとして片付けず、社会全体を意識した対応が求められるのです。
上司代行などを活用し、客観的な視点からマネジメントを見直す動きが広がっているのも、こうした背景があります。問題が起きてから動くのではなく、起こる前に防ぐ力——それが今、最も求められている視点です。
【タイプ別】管理職・上司によるパワハラ事例15選
パワハラという言葉が世間に広まった今もなお、実際の現場では“何がパワハラにあたるのか”が曖昧なまま放置されているケースが少なくありません。
特に管理職や上司という立場では、「指導」や「教育」の名のもとに、意図せずにハラスメント行為に踏み込んでしまう危険があります。
今回はパワハラを「タイプ別」に整理し、それぞれの典型的な事例を15個紹介していきます。
事例を通して、「こんなケースがあるのか」と自分自身を見つめ直す材料にしていただきたいと思います。
パワハラ、上司、管理職、上司代行といったキーワードに関係する現実的な事例を知ることは、今後のトラブルを未然に防ぐ最善の手段です。
【言葉の暴力】叱責がエスカレートしてしまった例

言葉は人を動かす力にも、人を傷つける凶器にもなります。
特に上司という立場では、部下の心にどれだけ響くかを意識せず、強い言葉を繰り返すことで深刻なパワハラとなることがあります。
ある製造業の事例では新人のミスが重なったことに対し、上司(管理職の部長)が「お前の存在が会社の迷惑なんだよ」と声を荒げたことで問題になりました。
最初は指導のつもりだったようですが、感情的になっていくうちに言葉がどんどん過激になり、最後には「辞めろ」とまで言ってしまったのです。この部下は精神的に不調をきたし、労災申請に至りました。
「叱責」は必要な場面もありますが、TPO(時間、場所、場面)を考慮しなかったり、言葉の選び方次第でパワハラになります。
特に管理職は感情のコントロールが求められるポジションです。
上司代行などの第三者的視点を取り入れることで、自分の言動が客観的にどう見えているかを定期的にチェックするのも予防策の一つです。
パワハラにおける「言葉の暴力」は、紙一重で誰でも踏み外す可能性があります。だからこそ、常に言葉の使い方を意識しておくことが重要です。
【無視・孤立】「教育の一環」のつもりが逆効果になったケース

一部の管理職の中には「自分で考えさせるために、あえて放置する」という教育方針を取る人がいます。
しかし、そのやり方が“無視”や“孤立”と受け取られた場合、それはパワハラとみなされかねません。
実際、あるベンチャー企業で起きたケースでは上司が「自立を促す」という理由で、新人にほとんど声をかけず、質問にも「まずは自分で調べろ」とだけ返すという対応を続けていました。
結果としてその新人は孤立感を深め、チーム内でも浮いた存在になってしまい、半年後に退職しました。
このように「教育の一環」という意図があっても、受け手側が“放置された”“無視された”と感じれば、それはパワハラになり得るのです。
無論このケースはハラスメント認定というよりも新人側のモチベーションが上がらない、成長を感じられないという理由で退職に繋がってしまうケースが多いです。
特に近年の若手社員は「聞きづらさ」を抱えたまま仕事をしていることも多く、そうした心理的な壁に対して敏感である必要があります。
上司代行のような外部サービスでもこうした「放置型パワハラ」の相談が増えているのが現状です。
管理職や上司は「教えないことが教育」と思い込まず、適切なフォローと距離感を持って接する必要があります。
【過度な業務】明確な基準なく無理を強いた結果どうなったか
「これくらい普通だろ」「自分の若い頃はもっとやってた」――こうした考えで部下に業務を押しつけてしまう管理職は今も一定数います。
しかし、基準の不明確な“過剰な期待”は、パワハラとして大きな問題を引き起こします。
ある広告代理店で上司が「成長させたいから」として、新人に通常の2倍の業務量を課していました。
指示内容も曖昧で、期限は「とにかく早く」というざっくりしたもの。結果、部下は過労で倒れ、労基署への相談にまで発展しました。
会社としては「熱意のある育成」と説明しましたが、世間には「ブラック体質」と報道され、企業イメージの失墜にもつながりました。
このような「過度な業務負担」は、管理職の経験値が裏目に出てしまう典型です。
パワハラの基準は“やらされた側がどう感じたか”で判断されることを忘れてはいけません。
上司代行など、マネジメントの基準を見直す支援を受けることで、「個人の感覚」ではなく「組織として妥当な負荷」を可視化できるようになります。感覚頼みのマネジメントこそ、パワハラを生む土壌になりやすいのです。
【プライベート侵害】飲み会強要やLINEの頻繁な連絡トラブル
こちらは信頼関係が築けずプライベートの話をしてしまいハラスメントに繋がってしまった事例です。
「これも仕事のうち」「チームの結束が深まる」――そんな言葉を盾に、部下のプライベートに土足で踏み込んでしまうケースがあります。中でも多いのが、飲み会の強要や、業務時間外のLINE連絡です。
実例として、ある中堅IT企業では、管理職が毎週末に飲み会を設定し、「参加は自由」と言いつつも、出席率の低い社員を評価で(結果的に)マイナスにするという実態が発覚しました。
また、日曜の深夜に「週明けの会議資料見ておいて」とLINEで送られてきたことにより、部下が睡眠障害を訴えたという例もあります。
このように、信頼関係が築けていないのにプライベートと業務の境界が曖昧になると、上司の言動が当事者目線ではハラスメント扱いされてしまいます。
たとえ親睦を深めたいという善意からでも、押しつけになれば逆効果です。
上司代行のような管理職をプレイヤー・マネジメントの両面からする支援は業務と私生活の切り分けが不十分な現場に対して、仕組みそのものを見直す手助けになります。今の時代、「距離感」がマネジメントスキルの一部です。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
【人前での叱責】公開処刑のような場面が職場の空気を一変
人前での叱責ほど、職場の空気を一瞬で冷やすものはありません。
特にオープンな場で強い言葉を浴びせられると、本人だけでなく周囲にも緊張感や不信感が広がり、チームの雰囲気を壊してしまいます。
あるコンサル会社での事例では上司が朝礼中に部下の資料ミスを取り上げ、「こんなレベルで仕事するなら帰ってくれ」と大声で叱責しました。
場は凍り付き、対象の社員はそのまま退職。
他の社員たちにも「いつ自分がターゲットになるか分からない」と恐怖が広がり、半年以内に4人が離職するという結果に。
上司の立場としては「その場で正したかった」意図があったかもしれませんが、その影響はあまりにも大きすぎました。
これも後から後悔するケースです。潜在的にハラスメントに繋がるリスクをはらんでいる方が上司の立場に経ってしまいその厳しい指導を乗り越えられる部下はいいですが、それ以外は「いてもらっても困る」とおっしゃるタイプの上司像ですね。
残念ながらこうした行為はパワハラの中でも特に深刻な部類とされ、訴訟に発展しやすいタイプです。
会社としては採用費に何百万円もかけて人を採用しているのに結果的にどんどん人が辞めてしまってはコストも時間も相当に無駄です。(この採用費も自分で払っているわけではないので目に見えずらいものがありますが、結果として会社の損害は非常に大きいです。結局人が足らなくなり、また採用のやり直しですからね)
【指導と圧力の境界】「俺の時代は…」が生んだパワハラ誤認ケース
いまだに聞く事例です。
「俺たちの頃はもっと厳しかった」「これくらい乗り越えられないようじゃダメだ」――こうした発言は、管理職としての“経験値”を伝えたいという気持ちから出ることも多いでしょう。しかし、現代の職場ではその感覚が通じず、パワハラと誤認されるケースが少なくありません。
実際に、ある中小企業で起きた例では、部下が業務でミスをした際、上司が「昔は殴られてでも覚えたもんだよ」と発言。
本人は冗談のつもりでしたが、部下はこれを“暴力を肯定する風潮”と受け止め、不信感が募って退職に至りました。
(え、こんなことで退職するの!?と思った方ほど注意です)
その後、社内アンケートを通じて他の社員も同様の発言に違和感を抱いていたことが判明し、組織全体でマネジメントの見直しが行われました。
ここでの教訓は、「過去の正解」が今も通用するとは限らないということです。
管理職としての“成功体験”が、今の価値観とズレている場合、その言動はパワハラとして機能してしまう可能性があります。上司代行のようなサービスが果たす役割は、そうしたズレを調整し、時代に合った指導法を再設計することにあります。
パワハラとは加害の意図がなくても成立するものです。だからこそ、時代との対話を怠らないことが、今の上司に求められています。
【成果主義の弊害】成果が出ない部下への過剰プレッシャー

成果主義は多くの企業で導入されている評価制度です。しかし、その導入が「成果を出さなければ人間としてダメだ」という空気にすり替わった瞬間、パワハラが発生します。
たとえば、ある営業会社ではノルマ未達成が3ヶ月続いた社員に対し、管理職が毎日の朝礼で「このままじゃチームの足を引っ張るぞ」と発言し続けました。
最初は励ましのつもりだったようですが、次第に部下の表情が硬くなり、最終的には休職に。第三者機関の調査では「継続的かつ精神的な圧力」が認定され、上司の発言がパワハラと判断されました。
成果を出させることが上司の役割であるのは間違いありません。
ただし、成果への期待を“恐怖”や“羞恥”といった負の感情で煽ることは逆効果です。上司代行によるマネジメントサポートでは成果に対する健全なモチベーション設計や、適切なフィードバックの出し方を含めて見直しが行われます。(後程詳しく解説)
パワハラと成果主義が結びつくと、職場は競争という名のプレッシャーに潰されてしまいます。だからこそ、上司は“人を動かす”視点を持ち続ける必要があります。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
【ジェンダー問題】“女だから”発言が招いた訴訟リスク
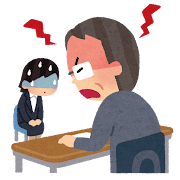
「女性にはこの仕事は難しいかも」「女の子に厳しくするのも気が引ける」――どれも一見“配慮”に見える言葉ですが、これがパワハラどころかジェンダーハラスメントとして訴訟リスクを生むことがあります。
とあるWeb制作会社では女性社員が重要案件から外された際に、上司が「結婚も近いし、無理させるわけにはいかない」と説明。本人に確認もなく決められたことに対し、当人が社内で抗議したものの状況は改善せず、最終的に弁護士を通じて労働相談へと発展しました。
ジェンダーを理由にした配慮や判断は本人の能力や意志を無視しており、結果的に機会の平等を奪う行為になります。
これは明確にパワハラの一種であり、企業の法的リスクを引き上げる要因でもあります。
管理職は「性別による思い込み」に無自覚であるケースが多く、上司代行などの第三者的支援によって、その視点をリセットするプロセスが不可欠です。パワハラを防ぐとは、つまり“公平性を守る”ことでもあるのです。
【年齢差別】若手・高齢者への扱いに潜む危険なバイアス

「最近の若い子は打たれ弱い」「年寄りにはこの仕事は無理」――これらの発言がいかに職場に蔓延しているかは誰もが少しは心当たりがあるのではないでしょうか。しかし、年齢に基づいた一括りの判断や言動は、立派なパワハラです。
実際、ある企業では若手社員に対し「ゆとり世代だから仕方ない」と言い放った上司が複数の社員から不満を受け、社内で処分されました。
また、逆に60代の再雇用社員に「もう引退してくれたほうがありがたい」と言ったことで訴訟に至ったケースもあります。年齢に関する発言は、地雷原のように取り扱い注意なのです。
上司や管理職にとって重要なのは、「世代」ではなく「個」を見ることです。年齢で判断するのではなく、その人の背景・強み・希望を尊重するマネジメントが求められます。
上司代行が支援するマネジメントの現場ではこうしたバイアスを意識的に排除し、年齢を問わず戦力として活かす方法に取り組んでいます。パワハラとは、思い込みから生まれることも多いという点を、忘れてはいけません。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
【昇進・異動絡み】人事権の濫用による圧力的な対応事例
昇進や異動といった人事の決定権は管理職や上司の手に委ねられている場合が多く、その分、権力のバランスが崩れるとパワハラに発展しやすい領域でもあります。
たとえば、ある大手企業では部下が上司の提案に異を唱えたことで「じゃあ君、地方の支店に飛ばすから」と発言したことが問題に。
実際に異動辞令が出され、部下が不服を申し立て、社外の労働機関に相談した結果、「報復的な人事異動」として正式にパワハラ認定されました。
こうした事例は、「黙って従わせるための異動」「昇進をチラつかせて従わせる」など、権限を使った心理的圧力が背景にあります。まさに典型的な管理職によるパワハラです。
パワハラの根源は「誰にも咎められない力」にあります。だからこそ、権限を持つ立場こそ、最も謙虚でなければならないのです。
上司代行(中間管理職支援)ではこうしたリスクをボトルネックから解消すべく組織の中に入り込んで部下とのコミュニケーションを現場業務を通じて支援しています。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
【見て見ぬふり】部下間のパワハラを放置した上司の責任
パワハラは上司から部下への一方的なものとは限りません。
むしろ最近では、部下同士のトラブルや“同僚によるハラスメント”が問題になるケースが増えています。そして見逃せないのが、それを「知っていながら何もしなかった」上司の責任です。
あるIT企業では、チーム内で特定の社員に対して陰口や無視といった行為が常態化していました。直属の上司は相談を受けていたにもかかわらず、「大げさにしないほうがいい」と放置。
その結果、被害者がメンタル不調により休職し、最終的に社内調査が入り、上司の対応も「パワハラ黙認」として処分されました。
管理職や上司がパワハラを「見て見ぬふり」した場合、それは“加担”とみなされることがあります。
上司代行など外部のマネジメント支援が介入していた場合、初期の段階での是正が可能だったという意見も出ており、初動対応の重要性が改めて注目されています。
職場内で何か違和感を感じたときに、目を背けない姿勢こそが、管理職としての資質です。パワハラの加害者になるのは、何も“声を荒げた人”だけではないという現実に向き合う必要があります。
【逆パワハラ対策失敗】部下からの訴えに過剰反応してしまった例
「上司からの圧力」はもちろん問題ですが、その反対――いわゆる“逆パワハラ”に対応する際も、冷静さを欠くと管理職の行動自体が問題になることがあります。特に最近では、部下がコンプライアンスを盾にするような言動も増えており、そのときにどう対応するかが問われます。
あるサービス業のケースでは、部下が上司の注意に対し「それパワハラじゃないですか?」と返答。
上司はそれに驚き、以後その社員に対して業務を回さなくなり関係が断絶。その対応を別の社員が報告し、結果として「不適切な対応」として上司が注意処分を受けました。
逆パワハラの可能性を疑うのは必要ですが、それによって上司が感情的・極端な行動に出てしまうと、それ自体が「管理職によるパワハラ」にすり替わってしまうことがあります。
上司代行のような第三者のサポートは、こうした微妙な力関係のバランスを客観的に調整し、対処の仕方を整える点でも重要です。
パワハラを恐れるあまり、「正しく指導できない上司」が増えている今、萎縮ではなく“整った対処力”が求められているのです。
【テレワーク時代】オンラインで起きた新たなパワハラ問題
テレワークの普及によって、働く環境が柔軟になる一方、見えづらくなった人間関係が生む新たなパワハラ問題が増えています。画面越しのやりとりでは、声のトーンや表情のニュアンスが伝わりにくく、誤解や一方的な受け取り方から深刻なトラブルに発展することもあります。
ある企業では上司がオンライン会議で部下に対し「理解できてる?」「なんで今も黙ってるの?」と詰問するような発言を繰り返したことで、部下が精神的に追い込まれました。
会議の記録を見直した結果、他のメンバーも「きつすぎる」と感じていたことが発覚し、パワハラとして社内で調査が行われました。
テレワーク下では、気軽なつもりのチャットやメールも、相手にとっては威圧やプレッシャーになることがあります。管理職や上司はリモート環境でも「伝え方」を意識しなければなりません。
見えない場所でこそ、人は過敏になります。パワハラを防ぐには、リアルよりさらに繊細な配慮が必要なのです。
【外国人労働者対応】文化的配慮を怠った管理職の対応ミス
グローバル化が進む中、日本の職場にも多くの外国人労働者が働くようになりました。こうした中で、文化や価値観の違いに無理解なまま接すると、それがパワハラとして問題になることがあります。
製造業の現場であった事例では上司が外国人労働者に対して「日本の常識を早く覚えろ」「郷に入れば郷に従え」と繰り返し指導。
日本人社員に比べて厳しく叱責する場面が多かったため、差別的だと受け止められ、当人から社内の相談窓口に通報が入りました。結果として、企業は外部講師を招いて文化理解の研修を行う事態になりました。
言葉の壁や表現の違いがあるなかで、同じ指導をしても“重く”響いてしまうことがあります。だからこそ、外国人労働者への対応は、「公平である」以上に「文化を理解したうえでの配慮」が求められます。
上司代行や外部マネジメント支援ではこうした多国籍環境への対応スキルを高めるプログラムも導入されています。グローバルな組織であればあるほど、管理職の配慮は“世界基準”であるべきです。
【社内研修での失言】教育の場が一転して不信感を生んだケース
社内研修は教育や意識改革のために行われる場ですが、発言一つで逆に信頼を失うこともあります。特に、研修を担当する立場の人が“無意識の偏見”を口にしてしまうと、それがパワハラ認定されることすらあるのです。
ある企業では管理職向け研修の中で講師を務めた上司が「今どきの若手は使えない」と発言。
冗談交じりのつもりでしたが、参加者に若手も含まれており、複数人が不快感を抱いて人事部に報告。後日、当該上司が注意処分を受け、社内の研修プログラムが一時中断されました。
研修という場は「教える側の発言が正しい」と受け止められやすく、それだけに発言には重みがあります。管理職がその自覚なく、場の空気に任せて不用意な言葉を発すると、むしろ逆効果となってしまうのです。
マネジメントでは「何を言ってはいけないか」よりも、「どうすれば伝わるか」を中心に考える必要があります。教育の場でこそ、謙虚さと自己チェックの視点が求められるのです。
【管理職は理解必須】事例に共通する“パワハラを生む3つの構造”と体験談
ここまで紹介してきたさまざまなパワハラ事例には実は共通して潜んでいる“構造的な問題”があります。
それは単なる個人の資質や感情の問題ではなく、組織全体の仕組みや環境が作り出している場合がほとんどです。
つまり、パワハラの原因はある日突然ふって湧くようなものではなく、職場の文化、評価制度、業務体制といった「土壌」がすでに存在しており、そこに上司や管理職のストレスや無自覚が重なることで起こってしまうのです。
この章では特に顕著に表れていた3つの構造的要因に焦点を当てて分析します。
パワハラ、上司、管理職、上司代行といったキーワードの背景にある“見えにくい原因”を整理することで、根本的な対策への理解が深まるはずです。
「成果主義」×「曖昧な評価基準」が招くマネジメントの暴走

成果主義自体は社員一人ひとりの努力を正当に評価するうえで重要な制度です。
しかし、この成果主義が“曖昧な評価基準”とセットになっていると、現場のマネジメントが暴走する温床になります。
例えば、数値目標だけが強調され「何をもって達成とみなすのか」「どのように評価するのか」といったプロセスの定義があいまいなまま、現場の管理職に丸投げされているケース。
すると、上司は“結果を出させなければならない”というプレッシャーから、部下に対して必要以上の叱責や圧力をかけてしまいます。
このような構造ではパワハラは「起きるべくして起きる」ものになります。制度そのものが、個々の判断に依存してしまう危うさを内包しているからです。
上司代行などの外部支援ではこうした“評価基準の再設計”を通じて、成果だけでなく「成長プロセス」を見える化する手法が導入されています。パワハラの発生を防ぐには、制度とマネジメントの間にある「評価のグレーゾーン」を見直すことが第一歩です。
管理職が孤立しやすい組織風土が暴言を引き起こす
意外に見落とされがちですがパワハラが起きる職場には「上司が孤立している」という特徴が見られます。
部下からの相談はあっても、自分自身が気軽に話せる相手がいない、悩みを共有できる場がない。そんな環境が、言葉の荒さや判断の偏りにつながっていくのです。
実際、ある製造業の中間管理職は日々のトラブル対応や業務調整に追われながらも、上層部からのフォローがなく、完全に“板挟み”の状態でした。
孤立感が限界に達したある日、部下に対して激しい叱責をしてしまい、社内でパワハラと認定。
本人は「自分を守る術がなかった」と後に語っています。
パワハラとは加害者側が精神的に余裕を失ったときに起こりやすいものです。そしてその背景には、「支えのなさ」「相談のなさ」という構造があるのです。
こうした孤立を防ぐ意味でも、上司代行のような外部マネジメント支援は有効です。上司代行という名称ですが、プロストイックの上司代行(管理職支援)は管理職の直下にチーム体制を敷いて「本来すべき業務に選択と集中」ができる体制をつくることにあります。
業務内容として「マネジメント(部下の育成やコミュニケーション)が急務課題」ということであればそこをフォローアップ。プレイヤー業務(現場の品質管理や部下の作業フォロー)が急務であればそれを対応するなど「プレイヤー業務」と「マネジメント業務」の二重不可である管理職を属人化を排除した盤石な体制で実働フォローするのがプロストイックの上司代行(管理職支援)です
つまり単に部下を管理するのではなく、管理職自身も“守られるべき存在”であるという意識が、組織全体の健全化には不可欠です。
パワハラに“気づけない”職場の空気とは
最も根深いパワハラの構造的要因のひとつが「パワハラがパワハラとして認識されない空気」です。
つまり、職場全体が無意識のうちにハラスメントを容認してしまう文化や慣習を持っている場合、それが“当たり前”になってしまうのです。
たとえば、「上司に叱られるのは成長の証」「怒鳴られて一人前」といった考えが根強い職場では、被害を受けた本人ですら「自分が悪いのでは」と感じ、声を上げられません。結果として問題が放置され、後になって深刻なメンタル不調や退職者を出すことになります。
こうした空気の中では、誰も「おかしい」と言えないのです。だからこそ、外部の視点が不可欠になります。次の体験談でその詳細を詳しくお話します。
筆者のハラスメント体験談事例(ゴリラ先輩からのパワハラ)

筆者の体験談を言うと、実際にまだパワハラがここまで世間に浸透するやや手前のタイミングでした。
営業職だったので、毎月の目標を課されて未達が視えると、上司(ここからはこの上司を「ゴリラ先輩」とします)から「今月何件電話した?」「なんで周りは達成しているのにお前だけ未達なの?」、「やる気あるの?」など鋭い言葉の数々が周囲の目もある前で「1人の上司」から飛んできていました。
そのゴリラ先輩はオンとオフがとても激しい先輩でした。厳しく叱責するときはしていて、逆に何も無い時は普通に優しい先輩でした。
しかしその「歪み」が周囲を狂わせていました。つまり業務中にそこまで圧力をかけることも「これは業務指導の一貫だ」「未達なのは会社にとってマイナスだし厳しい言葉を罰せられるのは未達のお前が悪い」という雰囲気が醸成されてゴリラ先輩の言うことを止める人は誰もいませんでした。
もっとわかりやすく言うと「この厳しいさは愛情だ」という認識がされていて、さらにその上の上司(この上司を「マスターゴリラ」とします)に
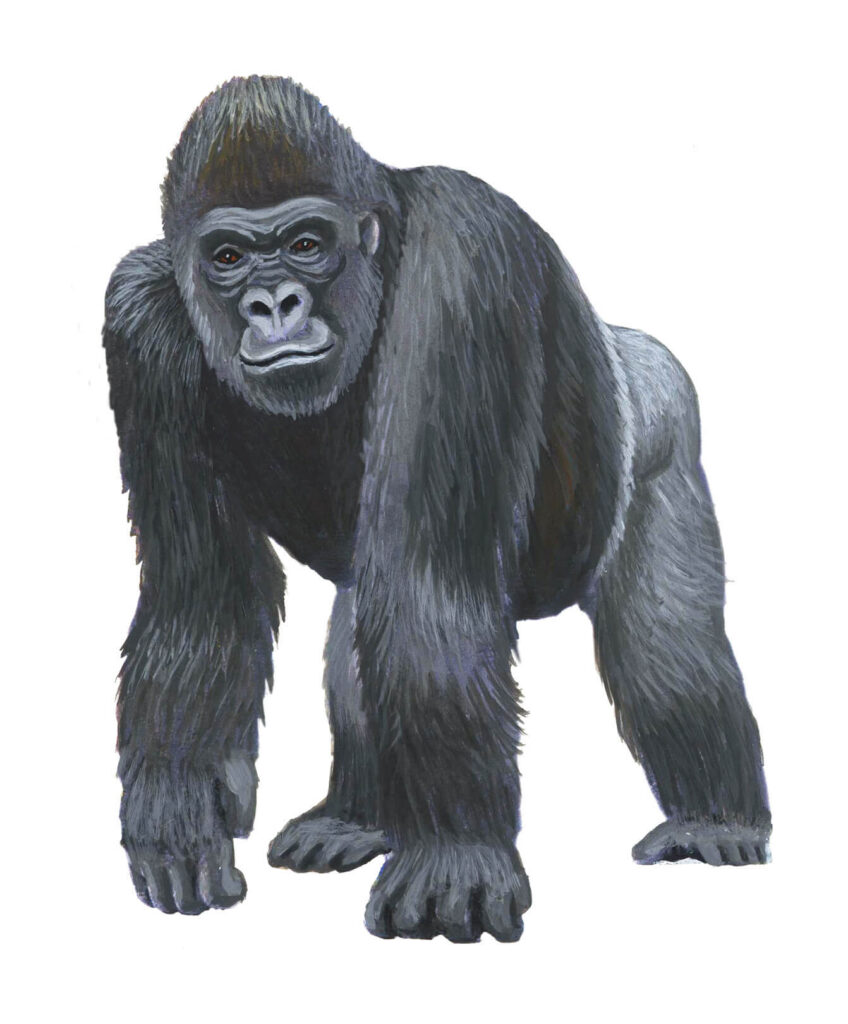
「ちょっとあの先輩厳しすぎるんですが」とやんわり相談しても、「あいつも言いたくて言ってるわけではない」、「目標を君に達成してほしいから、成長してほしいから言っている」などと完全に相手陣営に取り込まれていました。
今思えばふざけたマスターゴリラですね。相談しても君の主観でものを語るべきではないんですよ。
(おっと失礼しました。つい失言が、、、)
と、まぁ今はもうどうでもいいですが、当時は本当に奴らに苦しめられて夜は寝れないし土日もサービス残業をしていて(このサービス残業もその上司は知ってて黙認していたので懲戒食らわせてやりたいですが)本当に大変でした。
皆さんには同じ思いをしてほしくないし、管理職の方にもこんなことはさせたくないので結構生々しい事例をお話しました。
上司代行のようなサービスでは第三者的に現場のやり取りを観察・分析し、「当たり前にされているが、実は危ない言動」を可視化することが可能です。
パワハラの予防は、「見える化」から始まります。気づけないまま進行するほど、リスクは高くなるということを忘れてはなりません。
管理職が業務過多・多忙な体制が問題であれば上司代行活用を検討

最後に、パワハラを生む構造として極めて現実的なのが、「管理職の過剰な業務負担」です。プレイヤーとしての業務を持ちながら、部下のマネジメント、人事評価、トラブル対応……すべてを一人で背負っていては、どんなに優秀な人でも余裕をなくし、言動が荒れてしまうのは時間の問題です。
特にスタートアップや中小企業、急成長中の組織などでは、人手不足の中で「プレイングマネージャー」が当たり前になっています。その結果、指導が粗雑になり、部下との信頼関係が崩れ、パワハラと見なされるケースが増えています。
このような状況にある企業は上司代行サービスの導入を前向きに検討するべきです。
上司代行とは、マネジメントの一部(または全体)をプロが担うことで、業務の偏りを解消し、上司本来の役割に集中できる体制を整える仕組みです。
パワハラを“未然に防ぐ組織”を作るには、個人の努力だけでは限界があります。構造を変えなければ、問題は繰り返されます。だからこそ、管理職に過度な負荷をかけない仕組みそのものを見直す視点が、今最も求められているのです。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
上司・管理職が今日からできる!パワハラ予防アクション
ここまでで、さまざまなパワハラ事例やその背景にある構造を明らかにしてきました。では、現場で管理職や上司が「今すぐできること」は何なのか?それがこの見出しのテーマです。
パワハラを防ぐには大げさな制度変更や研修だけが手段ではありません。むしろ、日々の業務の中での“ちょっとした意識の切り替え”や“習慣化”こそが最も効果的な予防策になります。
このパートでは明日からでも取り組める実践的なアクションに焦点を当ててご紹介します。
パワハラ、上司、管理職、上司代行というキーワードに共通するのは、「人を動かす立場としての影響力」。その力を、より良い方向に活かしていくヒントをお届けします。
1on1や面談で「相手視点」を意識する管理職の会話術
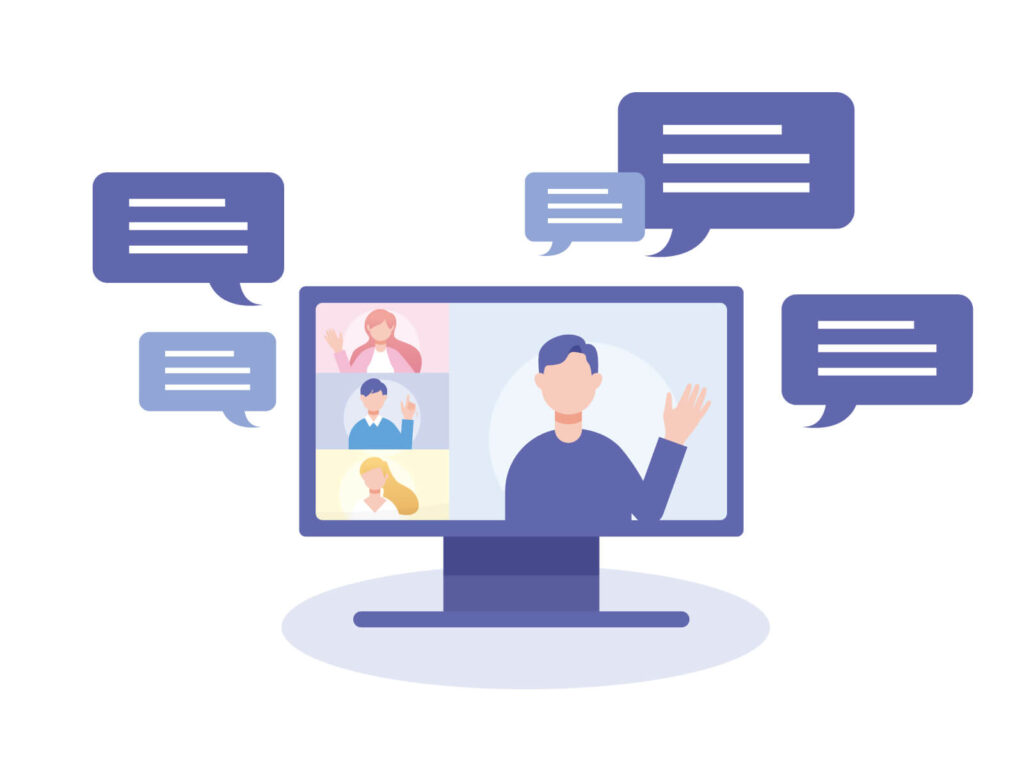
1on1や個別面談は部下と本音で向き合える貴重な場ですが、管理職側の意識次第でその効果は大きく変わります。
特に重要なのが「相手視点」を持って会話をすること。これができていないと、面談が単なる指導や報告の場に終わってしまい、逆にプレッシャーを与える場になってしまいます。
ある企業で実施された1on1研修では「上司が話す割合を減らし、相手に話させる」を徹底したところ、部下の満足度が2倍以上に向上したというデータもあります。
(実際のこれは相手が無口であれば「難しい」と感じていしまうことが多いので「会話を引き出す力が要求されます。)
部下の目線に立ち、感情・意図・背景をくみ取ろうとする姿勢が、信頼関係の礎になります。
「最近どう?」のような雑談的な入り方でも構いません。大切なのは、“自分が主導権を握る”のではなく、“相手の思考を引き出す”というスタンスに切り替えること。これだけで、パワハラ予防につながる効果的な対話になります。
上司代行でも、こうした「対話力の強化」は必須のスキルとして重視されています。管理職は会話を通じて、信頼も不信も生み出す立場であることを忘れてはいけません。
管理職自身の言動をチェックする“モニタリング習慣”

管理職は、日々さまざまな判断と発言を繰り返しています。
だからこそ、その“慣れ”が怖い。無意識に部下を追い詰めたり、意図せず圧力をかけてしまうこともあるため、言動を“モニタリングする習慣”を持つことが、パワハラ予防の基本となります。
具体的には1日の終わりに「今日の発言で部下に不快感を与えた可能性はなかったか?」「伝え方は適切だったか?」と自己点検すること。もし難しければ、月に一度程度、同僚や他の管理職に「最近の自分の言動で気になる点はあったか」と聞いてみるのも有効です。
そしてこういった時間を多忙な中間管理職が意図的に作れないので、上司代行を活用して「歪み」を改善します。
ある企業では、「上司モニタリングシート」という簡易のチェック表を導入した結果、ハラスメント相談件数が前年比で30%減少したという実績もあります。見直すのは“行動”ではなく“習慣”であるという意識が鍵です。
上司代行を活用する際も、このモニタリングの視点は極めて重視されます。組織にとって強い上司とは、「見られている自覚」を持ち続ける人なのです。
管理職同士と連携して「ひとりで抱えない」体制をつくる

管理職というポジションは孤独です。これは管理職を経験したことがある方なら一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
特に部下に関する判断やトラブルの対応を“全部一人で背負ってしまう”人は多いです。
しかしそれこそが、判断ミスや感情の爆発を引き起こし、パワハラへとつながる原因になります。
大切なのは、「ひとりで抱え込まない」という体制を職場全体でつくることです。
たとえば、「部下の評価については必ず他の管理職と共有・相談する」「トラブル時にはチームで対応方針を決める」といったルールがあれば、上司の負荷も判断の偏りも防げます。
ある企業では「管理職限定の情報交換会」を月1で実施したところ、孤立感の軽減に加えて、部下とのコミュニケーションの質も上がったという結果が出ています。連携は、管理職自身を守るだけでなく、職場全体を柔らかくする効果があります。
上司代行を使う企業では、管理職支援の一環として「相談のハブ」や「方針のファシリテーター」として機能させている例もあり、孤立の解消は制度でも実現可能です。
上司の“相談力”が、職場のパワハラリスクを左右するのです。
上司・管理職代行を活用して効率的かつマネジメントできる体制を創る

パワハラを防ぎながら、チームを成果に導くには、管理職に過剰な負荷をかけない体制づくりが欠かせません。現場の忙しさや人手不足の中で、すべてのマネジメントを完璧にこなすのは現実的ではない――その課題を根本から支えるのが、上司・管理職代行という選択肢です。
上司代行とは単なる人手の補填ではありません。
デジタル組織に特化し、業務支援・マネジメント・チームビルディングなどを第三者的な立場から担うことで、現場の負荷を軽減し、管理職が本来の役割に集中できる環境を整えます。
たとえば、あるスタートアップ企業ではプロジェクトリーダーが業務に追われていたため、上司代行を導入。
1on1や進捗管理、フィードバック業務を代行したことで、リーダーは戦略立案に集中でき、チームの成果も向上しました。同時に、パワハラリスクも抑えられたのです。
「組織を守る」ことは、管理職を支えることから始まります。効率的で柔軟なマネジメント体制を整える選択肢として、上司代行の活用はこれからの時代に不可欠な手段です。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
まとめ|管理職が事例から学ぶ“防げたパワハラ”を次の一手に
この記事ではパワハラに関する実例をもとに、管理職や上司が陥りがちな落とし穴、そこからどう抜け出すべきかについて詳しく見てきました。
大切なのは「起きてしまったパワハラを悔やむ」ことではなく、「起きる前に気づく力」を養うことです。
パワハラを引き起こすのは、悪意ある人間ばかりではありません。
むしろ多くの場合、指導のつもりだった、配慮のつもりだった、という善意が裏目に出てしまった事例が目立ちます。だからこそ、他者の経験を自分ごととして受け取り、次の行動につなげる姿勢が重要になります。
ここでは、この記事の最後の締めくくりとして、管理職や上司が「パワハラを防げる存在」になるための視点を再確認していきましょう。パワハラ、上司、管理職、上司代行といったキーワードの先にある“未来の職場の形”を想像しながら、次の一歩を踏み出すためのまとめをお届けします。
一つの失敗から得られる組織改革のヒント

パワハラの事例を見ていると、「なぜ防げなかったのか」「どうすれば違う結末になったのか」と思う場面が多々あります
しかし裏を返せば、それは「防げたかもしれない」からこそ、学びがあるということです。一つの失敗は、組織全体の進化にとって貴重な材料となります。
たとえば、部下への言葉が原因で訴訟に至った事例も、見方を変えれば、「上司の言葉の重み」「部下の受け取り方」「組織としての対応力」の3点を見直すきっかけになります。このように、一つのトラブルが明らかにするのは、個人のミス以上に“組織の構造的な盲点”なのです。
上司代行のような外部サービスが注目される背景にも、この「失敗を個人のせいにしない視点」があります。むしろ、そうした事例を共有し、仕組みのほうを見直していく柔軟性を持つことこそ、組織改革の第一歩です。
パワハラを“止める力”は、決して責任追及ではなく、“仕組みを変える力”として使われるべきです。
管理職自身が「変わろうとすること」こそ最大の対策
どれだけ制度やルールを整えても、それを運用する「人」が変わらなければ、パワハラは根絶できません。
つまり、最も効果的な対策は、管理職自身が「自分も変わるべき存在だ」と気づくこと。これができるかどうかで、組織の空気は大きく変わります。(そしてこれが自主的に変わるのがなかなか難しいのが人というものなので「きっかけ作り」として管理職支援(上司代行)というものがあります)。
まず大前提として変わることは必ずしも「今までが間違っていた」と認めることではありません。
それよりも、「もっとよくなれるはず」「今の時代に合った関わり方をしたい」という前向きな意思の表れです。そして、その姿勢は必ず部下に伝わります。
ある企業では管理職が自ら「自分の対応で気になることがあれば言ってほしい」と部下に伝えることで、風通しが一気によくなり、相談件数も増加。結果としてトラブルの芽を早期に摘み取れる体制ができあがりました。こうした柔軟さこそ、現代のマネジメントに求められる本質です。
上司代行もまた、「変化に前向きな組織」を支える仕組みの一つです。自分が変わる姿を見せることが、部下の信頼を育み、パワハラを遠ざける最強の対策となるのです。
パワハラゼロを目指す組織の未来像とは
パワハラゼロを実現する組織はただ「静かな職場」ではありません。むしろ、安心して意見を言える、課題を共有できる、違和感を指摘できる――そんな“活発で健全なコミュニケーション”がある職場です。
パワハラがない職場とは、「我慢する人がいない職場」であり、同時に「誰かが抱え込まない職場」でもあります。
そのためには、管理職が独りで判断し、対処する体制では限界があります。
だからこそ、上司代行のような仕組みを活用し、役割を分散させ、全員が“支え合う前提”で動ける組織が強いのです。
未来のマネジメントには、“聴く力”“寄り添う力”“変わる勇気”が欠かせません。そして、これらの力を育てていける環境そのものが、パワハラのない未来をつくります。
パワハラ、上司、管理職というキーワードは、単なるリスクワードではなく、“組織の成長を支える柱”として、これからも見直されていくべきです。
管理職が一歩を踏み出せば、組織は必ず変わります。今日から始められるその一歩が、未来を変える鍵になるのです。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック