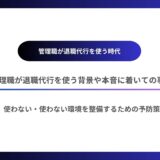皆さんこんにちは。
本日は近年世界で広がりつつあるDINKs(ディンクス)という生き方について「初心者向け」に解説をしていきます。
- DINKsという言葉を聞いたばかりでよくわかっていない
- 自分がDINKsという選択をしようか迷っている
- DINKsという生き方の体験談や世間の声について知りたい
ここでお伝えしているのはあくまで「世間からの意見」や「見え方」「変化」でありDINksという生き方を体現されているの方の実体験をベースとさせていただいております。
近年増えているDINKs(ディンクス)とは
ここ数年、ライフスタイルに関する価値観が大きく変わりつつある中で、ひとつの選択肢として注目を集めているのが「DINKs(ディンクス)」です。
DINKs(ディンクス)とは「Dual Income, No Kids」の略で、共働きで子どもを持たない夫婦のことを指します。
ちなみに誤認も多いのですが、この子どもを持たないというのも「持てない」ではなく「意識的に持たないと決めた夫婦」のことを指しているのが言葉の定義となっているようです。
DINKs(ディンクス)という言葉自体は決して新しい概念ではないものの日本では言葉自体は最近になって徐々に知られるようになっているようです。
海外(特にアメリカ)では以前より言葉は流通はしていて、最近ではDINKsであることを肯定的に捉えて、youtubeやtiktokなどで動画を挙げている方も少なくありません。
DINKs(ディンクス)はという生き方は「共働きで経済的な安定を重視する」。「時間やライフスタイルの自由を優先する」。「キャリアに集中する」。いずれも現代にフィットした考え方であり、DINKs(ディンクス)という生き方が新しい価値観として広がっている背景にあるようです。
この章ではそんなDINKs(ディンクス)というライフスタイルがなぜここまで広がっているのか。
その背景にある価値観の変化や、世代別の傾向など多面的な意見や世間からの認識を探っていきます。
「子どもを持たない人生」に対する価値観の多様化
近年では価値観の変化も多く、色々なライフプランがあります。
「結婚しても子どもを持たない人生」「夫婦ふたりの時間を長く大切にしたい」「そもそも親になることに向いていないと感じている」こうした考え方を持つ人が徐々に増えているという傾向もあるようです。
DINKsというライフスタイルはまさにこうした価値観の多様化から生まれた選択で、とくに女性のキャリア志向や、結婚後も仕事を続けたいという意欲が強くなっている現代において「子どもを持たないことで得られる選択肢」は多くの共働き夫婦にとって新しい選択肢の一つになっているようです。
また、「子どもを持たないからこそ、豊かな生活を送れている」という声もあるようです。
海外旅行、自己投資、住環境、ペットとの暮らしなど子育てとは別の形で人生の充実を感じている夫婦も一定数いるようです。
もちろん良い側面だけではなく、子供を持たないという選択肢に対しての懐疑の声や疑念がゼロというわけではありません。
いずれにしても「自分たちが納得できる人生を歩む」という価値観が多くの人にとって重要視されるようになったからこそ、DINKsという選択肢は新しい価値観として説得力を持ち始めたのです。
30代から40代を中心にDINKsが広がっている
DINKsというライフスタイルの中心層は30代から40代の共働き夫婦の間を中心に広がっているようです。
この世代は就職氷河期やリーマンショック、コロナ禍といった大きな社会変動をくぐり抜けてきたこともあり、生活や結婚に対して現実的な視点を持っているようです。
30代前後に差しかかると、周囲が子育てに追われ始める一方で「自分たちはこのままでいいのか」と立ち止まって考える機会もあります。
そのなかで「このままふたりの時間を大切にしたい」「経済的な余裕を削ってまで子育てを選びたくない」など色々な理由から、あえて子どもを持たないという選択をするケースがあります。
30代から40代はSNSなどの利用者も多く情報感度が高い世代でもあるため、SNSやライフスタイル雑誌やYouTubeでもDINKs夫婦のリアルな暮らしが取り上げられるようになり、「それ、興味あるかも」と感じた人が選択肢に加える流れもあるようです。
なぜDINKsを選ぶ夫婦が増えているのか
近年、「DINKs(ディンクス)」という言葉が改めて注目を集めるようになっています。
アメリカではtiktokやyoutubeを中心にDIKNsという生き方についてのアカウントも多く存在しています。参照はこちら
以前から存在していた概念ではあるものの、時代の変化とともにそのあり方がより明確かつ多様に、そして身近なものとして広がりつつあるようです。
特に都市部を中心に共働きで子どもを持たない夫婦の数は徐々に増えてきており、それを肯定的に捉える風潮も広がっているようです。
ではなぜ今、DINKsというライフスタイルを選ぶ人が増えているのでしょうか。その背景には経済的な現実や価値観の変化、社会の構造的課題など、さまざまな要因が絡んでいると考えられます。
この章では、DINKsという選択に至る理由のなかでも特に多く語られる側面—経済・キャリア・子育て不安などを切り口に、その傾向を解説します。
経済的な自由やライフスタイルの優先
DINKsを選ぶ理由のひとつとしては経済的な自由やライフスタイルを優先する意識の高まりです。
共働きで子どもを持たない夫婦は世帯収入が安定している一方で、子育てにかかる費用がないため、その分を旅行や自己投資、趣味、住宅ローンの早期返済などに回せるという経済的余裕があるケースが多いようです。
このような状況から「子どもがいないからこそ可能になる暮らし方」を好ましく感じる人が増えている傾向があります。
特に、都市部では生活コストが高く、教育費や住宅費の負担を考えると、子育てを選ばないという判断に至るのも不自然ではないと考える方も一定数いるようです。
また、物質的な満足だけでなく「二人の時間を大切にしたい」「自由な移動や生活拠点の選択肢を持ちたい」といった、時間的・精神的な余裕を重視するライフスタイル志向も見られます。こうした価値観は“贅沢”を意味するものではなく、“自分たちらしく無理なく暮らす”という考え方の延長にあるようです。
キャリアと自己実現を重視する流れ
特に女性の働き方や生き方が多様化したことはDINKsの増加に関係していると考えられます。
近年は、結婚後もフルタイムで働き続ける女性が増えキャリアアップや専門職への挑戦、資格取得といった道を選ぶ人も少なくないようです。
そうした中で「出産や育児によってキャリアを一時中断することに抵抗がある」「両立を考えると、自分のやりたいことが制限されそうだ」と感じる夫婦がDINKsという選択肢を視野に入れることもあるようです。
誤認をされる方もいるかもしれないので、念の為の記載ですがこれは決して子ども持つことを否定しているわけではなく「今の自分にとって何が大切か」を真剣に見極めたうえでの選択と言えるかもしれません。
また、男性側にも「自分の人生を仕事以外でも充実させたい」という意識が強まりつつあり、夫婦そろってキャリアやライフワークに重きを置くスタイルが成立しやすくなっているようです。
家庭と仕事のバランスを自分たちのペースで取りたいと考える人がDINKsという形に自然にフィットしていくという構図も見受けられます。
自己実現を追い求める生き方は以前であれば一部の人のものでしたが、今では生き方・価値観として広がりつつあるようです。その流れがDINKsの選択を「特別なこと」から「ひとつのあり方」へと見え方を変えているのかもしれません。
子育てへの不安や社会的なプレッシャーの変化
旧来のメディアニュース、アンケート調査などの傾向を見ていると子育てに対する不安や、子を持つことが“当然”とされていた社会的プレッシャーもあったようです。
しかし現在の日本では「教育費の高さ」や「待機児童の問題」、「育休制度の使いづらさ」など、子育てに関する課題が山積しており「本当にこの環境で子どもを育てられるのか」と疑問を抱く夫婦も多いようです。
子供を持つと一人当たり2,000万円~4,000万円(物価高の影響でさらに上がると推測されている)かかると言われている経済的な圧迫や夫婦間のすれ違いなどが起きてしまうことに不安を持つ夫婦も一定数いるようです。
また、SNSの普及によって子育ての“現実”が可視化されるようになったことで、「あの大変さを自分が担えるだろうか」と自問する人も出てきているようです。
これは子育てを否定しているわけではなく、自分の性格や体力、経済状況を冷静に見つめた結果、「今の自分たちには合わない」と判断するケースも含まれています。
こうした状況から、DINKsというライフスタイルが「逃げ」や「贅沢」といったネガティブな見方から離れ、「現実的かつ健全な選択肢」として認識される傾向が強まっているのかもしれません。
非選択的DINKs(晩婚・経済面・将来への不安)
非常にセンシティブな話ではありますが、DINKsのすべてが「意図的に子どもを持たない」と決めた夫婦とは限りません。
DINKs(Double Income No Kids)という言葉の定義を改めてお伝えしておくとDINKsとは「意識的に子どもをもたない選択をした共働き夫婦」のことを指します。しかし意識的にもたない選択をした背景は様々で、晩婚、年齢差結婚、経済面、将来への不安と責任など様々な理由があり「子どもを望んでいるものの、まだ子どもがいない夫婦」や「子供を望んではいるけど、これから子供や将来について考える」「子供はいないけど夫婦の片方しか働いていない」方たちとは異なる意味を持つので注意が必要です。
「結果として子どもを持たない人生になった」というDIKNs(本記事では“非選択的DINKs”と呼称)もいることをきちんと理解していただければ幸いです。たとえば、晩婚や長期赴任、治療の問題、キャリアの両立といった現実的な理由から、出産のタイミングを逃してしまったケースなどがそれにあたります。
晩婚化が進む中で、30代後半〜40代で結婚する夫婦にとっては、妊娠や出産のリスクが高まるのは避けられません。一方で、仕事の責任も大きくなる年代でもあるため、「今は家庭を安定させるほうが先」と考えているうちに、選択肢そのものが狭まっていく現実があります。
また、長期出張や海外赴任によって夫婦の時間が十分に取れない、転勤で生活基盤が安定しないなど、「環境が整わなかったために、結果的に子どもを持たない」という夫婦もいるようです。
こうした非選択的DINKsは見た目には自由に暮らしているように見えることもあるかもしれませんが、その裏には複雑な事情や、受け入れるまでに時間を要した感情があることも多いのです。
SNSなどではDINKsという言葉が“ポジティブな選択”として語られる一方、こうした“選べなかったDINKs”のリアルな声があることも忘れてはいけません。
人生には思い通りにいかない局面もあり、そうした現実もDINKsという枠組みの中に確かに存在しています。
お伝えしたいことは「価値観は多様化しており様々な生き方・選択肢がある」ということです。
DINKs夫婦のリアルな生活実態
DINKs(Dual Income, No Kids)というライフスタイルを選ぶ夫婦が増える一方で、その実際の暮らしぶりについては、外からはなかなか見えにくい部分もあるようです。
DINKsならではの時間の使い方や、趣味や日々の生活、そしてその裏に潜む葛藤など多面的な実情があるようです。
またDINKsというワードの認知度がまだまだ低いのもあり、その生活スタイルに対するイメージや見え方も、人によって大きく異なるようです。
「気ままで自由」といった声もあれば、「寂しくないのか」といった疑問を投げかけられる場面もあるかもしれません。
この章ではDINKs夫婦のリアルな生活実態を「時間の過ごし方」「お金の使い方」「感じやすい孤独感」といった3つの切り口から整理していきます。
DINKsという選択肢が実際にどのような毎日につながっているのか、その輪郭が少しずつ見えてくるかもしれません。
二人だけの時間が多く、生活満足度は高め
DINKs夫婦は、夫婦ふたりの時間を多く持てる傾向にあるようです。
朝や夜の時間に余裕があったり、週末の予定を自由に組めたりと、生活にある程度のゆとりを感じやすいといった声もよく聞かれます。(子育てをしていると朝は保育園や学校のお弁当作りでバタバタ。夜も子供のお世話や寝かしつけでバタバタ)
特に共働きで生活を支える構図の場合、役割分担も柔軟に決めやすく、家事や生活リズムのすり合わせがスムーズになるという声もあります。「夫婦というよりパートナーに近い感覚でいられる」といった声もあり、関係性をフラットに保ちやすいという側面もあるようです。
また、平日の夜にふたりで外食を楽しんだり、自宅で静かに過ごす時間に重きを置いたりと、日々の充実感を感じている夫婦も多いようです。こうした生活リズムが「満足度が高い」「毎日にストレスを感じにくい」といった感覚につながっている可能性もあります。
もちろん、生活満足度は夫婦それぞれの関係性や考え方に大きく左右されるため、一概にすべてのDINKsが「幸せそう」とは限らないかもしれませんが、全体的には「自分たちのペースで暮らせている」という実感を持つ人が少なくないようです。
趣味・旅行・自己投資にお金と時間を使える
DINKsであることの大きな特徴のひとつに、趣味や旅行、自己成長のための時間とお金を比較的自由に使える点が挙げられます。教育費や養育費がかからない分、可処分所得に余裕があり、そのぶん“今を楽しむ”という感覚を持つ人が多い傾向にあるようです。
たとえば、毎年のように海外旅行を楽しんでいたり、仕事終わりにジムやスクールに通う習慣があったりと、生活の中に「自分のための時間」をしっかり確保している夫婦もいるようです。近年では、DINKs世帯(世間でいうパワーカップルと言ったりもします)をターゲットにした高級マンションの販売や、趣味志向の強いサービスも登場しており、一定のニーズがあることがうかがえます。
また、子育てのために住環境や職場を妥協する必要がないため、自分たちの好みに合ったエリアやライフスタイルを優先しやすいという利点もあるようです。その結果、仕事に対するモチベーションが上がったり、日常生活に満足できたりすることもあるようです。
もちろん、全員が贅沢な生活をしているわけではありませんが「自分のための選択ができる自由さ」が、DINKsにおけるひとつの特徴になっているようです。
外からは理解されにくい孤独感もある
リアルなDINKsの生活実態について解説する記事のためネガティブな側面もあることに少し触れるとDINKsというライフスタイルは自由で快適な面がある一方で、周囲からの理解を得にくいと感じる場面もあるようです。特に「子どもを持たない選択」そのものが、“何か事情があるのでは”といった詮索や偏見の対象になってしまうこともあるようです。
実際、親族からは「子どもはまだ?」と聞かれたり、「老後どうするの?」と心配されたりすることがストレスになっているという声もあるようです。また、子育てをしている世代との会話に共通点が見つけにくく、地域や会社内での孤立感を覚えることもあるようです。
また老後にも関わってくることですが、夫婦のどちらかに体調不良や転職などの変化があった際に、「支え手が自分しかいない」と感じる場面もあるようで、老後に対しての備え(健康や交友関係)はDINksだからこそ重要と言えるのかもしれません。
そうした背景から、DINKsであることにポジティブな思いを持ちつつも、「どこか説明しにくい孤独感」や「理解してもらえない感覚」を抱えている人も少なからずいるようです。これはDINKsという生き方がまだ社会全体に完全に受け入れられているわけではないからかもしれません。
次章では、こうした実態を踏まえて、DINKsにおける具体的なメリットとデメリット、それぞれにどんな特徴があり、どんな影響を及ぼしているのかをさらに掘り下げていきます。ライフスタイルとしての“バランス”をどう捉えるかが、大きな鍵になるかもしれません。
DINKsのメリットとは
DINKsというライフスタイルには「子どもを意識的に持たない夫婦環境」によって経済的な自由度や趣味・趣向に対しての柔軟性があるとされており、その選択にはさまざまなメリットが感じられるようです。
もちろん、その価値は夫婦それぞれの人生観や置かれた状況によって大きく異なりますが「自分たちにとって無理のない生活」を目指すという点では、多くのDINKs夫婦に共通した感覚があるのではないかと思われます。
この章では、DINKsであることによって得られやすいとされる代表的なメリットを3つの視点から掘り下げていきます。
経済的な面、家庭内の人間関係、そして将来設計に関する考え方まで、それぞれの側面にどのような良さがあると捉えられているのかを具体的に整理してみます。
経済的なゆとりがある
DINKs夫婦は共働きであることが前提のため世帯収入が多く、しかも子どもにかかる教育費や養育費が発生しないため、相対的に「可処分所得が高め」である傾向があるようです。
実際、世帯収入が同等でも支出の構造が異なることから、貯蓄や資産形成がしやすいという声も見られます。
また、子どもの進学や習い事、将来の教育費を見越して長期的な家計計画を立てる必要がないぶん、住まい・保険・旅行・趣味といった部分に自由度を持たせやすいという側面もあるようです。
「欲しいものを自分のお金で買える」「ボーナスを夫婦で話し合って“投資”に回せる」といった意見も散見され、計画的にお金を使いやすい状況が整いやすい印象もあります。
もちろん、共働きの収入格差や突発的な支出リスクがまったくないわけではありませんが、全体として“長期的な経済の安定感”を重視しやすい家庭構成とも言えるかもしれません。
特に、日々の生活において「我慢しすぎない」ことで、精神的な満足感につながっているという声もあるようです。
人間関係や家庭内トラブルが少ない
子どもがいないことで、家族間の役割分担や教育方針に関するすれ違いが発生しにくく、家庭内の衝突が比較的少ない傾向があるようです。
特にDINKs夫婦の場合は共働きのため「どちらかが一方的に負担を抱える構造になりにくい」「対等な関係で話し合える」といった感覚を持っている人も少なくないようです。
また、育児をめぐる親族との関係性にまつわるストレスが少ない点も、精神的な安定につながっている可能性があります。「孫の顔を見たい」「子どもはまだか」という無言の圧力からある程度距離を取れることで、夫婦の価値観に集中した生活を送りやすくなるという声もあるようです。
もちろん、DINKsでも意見の食い違いや家庭内のストレスがまったくないわけではありません。ただ、家庭内における“決定事項”が相対的に少ないぶん、日常的なコミュニケーションがシンプルになりやすいという点で、「日々の生活が穏やかに保ちやすい」と傾向があるようです。
老後まで自分たちのペースで生活設計が可能
DINKs夫婦の多くは「ライフイベントが比較的自由に設計できる」という点に安心感を持っているケースがあるようです。
子育てがないことによって、住宅購入や転職、移住、資産形成といった人生の選択肢を、自分たちのペースとタイミングで検討できるため、将来に対する計画が立てやすいという側面があるようです。
また、「老後に備えて、今から資産運用を始めている」「老後もふたりで自由に過ごせるように、小さな家で無理なく暮らしている」といった話もあり、必要以上に大きなリスクを負わず、堅実に長期的な生活設計を組み立てている夫婦が多いようです。
ただ一方で、子どもがいないことに対する将来的な不安としてたとえば介護や老後の問題についてをまったく感じないわけではないようです。
だからこそ、「今のうちに資産と健康に投資しておく」「老後に頼れる仕組みを少しずつ準備している」といった慎重な動きが見られることもあるようです。
こうした生活設計の柔軟性はDINKsだからこそ可能になる部分もあるのかもしれません。
とくに人生100年時代を見据えるなかで「無理をせず、自分たちで選んでいける」という感覚が、生活全体の安定感につながっているようです。
次章では、こうしたメリットの裏側にあるDINKsの“悩み”や“迷い”についても客観的な意見について解説します。
DINKsという選択をより現実的に考えるためには、そのバランスを見極める視点も欠かせません。
DINKsのデメリットと見えにくいリスク
DINKs(Dual Income, No Kids)というライフスタイルには経済的自由や時間の柔軟性といったメリットがある一方で、表面からは見えにくい課題やリスクを抱える場面もあるようです。
子供を持たないことを「意識的に決定」することの裏側には将来の不安や人間関係の摩擦といった、長期的に向き合う必要のある要素が隠れていると考えられています。
また、DINKsというスタイルは年々増加はしていますがまだ少数派とも言われており、その選択が「理解されにくい」「説明が求められがち」といった社会的な摩擦を生むケースもあるようです。
夫婦としては納得して選んだ道であっても、外部からの視線や変化する価値観のズレによって、思いがけないストレスを感じることもあるかもしれません。
この章ではDINKsに伴うデメリットや注意点について、よく挙げられるテーマを中心に考察していきます。「今は良くても将来が不安」「周囲との違いに苦しむ」「夫婦の間でも価値観がずれてきた」などの声がどこから生まれているのかを、丁寧にひも解いていきます。
※
将来の孤独・介護・老後資金への不安
DINKs夫婦に共通して語られることのひとつが「老後の不安」についてです。
子どもがいないということは、将来的に身近に頼れる存在が少なくなる可能性があるという意味でもあり、「もしどちらかが先に亡くなったら」「病気や介護が必要になったときにどうするか」といった懸念を抱く場面が少なくないようです。
また、公的な介護制度や地域の支援体制が整ってきているとはいえ、「誰かに任せることの限界」や「お金がどれだけあっても解決しきれない不安」が残ると感じている人もいるようです。
特に高齢者単身世帯の増加が社会問題になっている中で、DINKs世帯が将来的に似たような課題に直面する可能性は高いと考えられています。
経済的に自立している場合でも「資産がある=安心」という構図が成り立つわけではありません。
お金の問題だけでなく、孤独感や生活の質の低下といった“メンタルのケア”が難しくなる局面もあるようです。
だからこそ、DINKsを選んだ夫婦の一部では、比較的早い段階から終活や老後の住まい、介護サービスの利用計画に取り組むケースも見られます。
将来への備えを「今から積み上げる」ことがDINKsの方たちは意識しやすいようです。
ただし、その不安はどこか漠然としていて、日常に大きな影を落とすわけではないものの、ふとした瞬間に頭をよぎる“見えない重さ”として存在しているようにも感じられます。
DINKsを選ぶ背景には消費志向というよりも、「将来に対する漠然とした不安を避けたい」「今の安心感を維持したい」といった、防衛的な動機も含まれている可能性があります。
周囲からの無言の圧力・偏見
DINKsという選択は自分たちにとって自然なものであっても、社会や周囲の価値観とすれ違う場面があるようです。
親族や職場、地域コミュニティといった比較的保守的な関係のなかでは「子どもを持たないのはなぜか」という無言の問いかけを感じることがあるようです。
DINKs夫婦になった事情や背景があるにもかかわらず、「子どもはまだ?」「そろそろ考えないと手遅れになるよ」など、意図的でなくとも価値観を押しつけるような言葉に傷ついた経験を語るDINKs夫婦は少なくありません。
また、育児を前提とした制度や社内文化のなかで、「蚊帳の外」に置かれるような感覚を持ったことがあるという人もいるようです。
特に、DINKsという選択がまだ少数派である場合、自分の立場を説明しなければならない状況に置かれることもあり、それが長期的な精神的負担になっているケースもあるようです。
もちろん、近年ではDINKsへの理解が進みつつあるという見方もありますが、いまだに「違和感を持たれやすい存在」であるという印象が本人たちのなかに残っている場合もあるようです。
夫婦間の価値観のすれ違いが顕在化しやすい
DINKsは「子どもを持たない」という一点では一致していても、その背景にある価値観がまったく同じとは限りません。「今は持たないけど、将来は考えたい」という思いが一方にある場合、時間の経過とともにそのズレが表面化してくる可能性もあるようです。
また、経済的・時間的に自由度が高い生活だからこそ、それぞれが「自分のやりたいこと」に集中しすぎてしまい、夫婦間のすり合わせがうまくいかなくなることもあるようです。仕事や趣味、交友関係などの方向性がすれ違ってきたときに、それを“育児”という共通の軸で繋ぎとめる構造がないぶん、価値観のズレがダイレクトに関係性に影響しやすいという意見もあります。
さらに、何か大きな転機(転職・病気・親の介護など)を迎えたとき、「こんなとき子どもがいたら違ったかも」と感じてしまう場面があるという話も耳にします。こうした感情がパートナー間に生まれたとき、きちんと夫婦間で健全な話し合いや対策ができる関係性が重要です。
DINKsに限らず、夫婦関係において価値観の一致とすり合わせは非常に重要ですが、DINKsの場合は関係の根幹を支える“共通の未来像”をどこに置くかがより鮮明に問われる局面があるのかもしれません。
【体験談】DINKs歴10年目の夫婦が語るリアル
DINKsという選択を実際に続けてきた夫婦の声は、ライフスタイルの表層だけでは見えにくい「内側のリアル」に触れるきっかけになることがあるようです。
DINKs歴が長くなるほど、さまざまなライフイベントや社会との接点に直面し、その都度、選択の意味を見つめ直す瞬間が訪れるといった話も耳にします。
今回は、30代前半でDINKsという生き方を選んだ、現在40代前半の共働き夫婦でDINKs歴10年というご夫婦の体験をもとに「信頼関係の深化」「周囲との関係性」「将来への向き合い方」といった観点から、時間をかけて育まれてきたDINKsの実像を探っていきます。ここで紹介する声は、あくまで一例ではあるものの、同じような道を選び、迷いながら歩いている方にとって、何かしらの参考になる部分があれば幸いです。
一緒に過ごす時間が多く、深まった信頼関係
DINKs歴10年の夫婦にとってDINKsというライフスタイルは「一緒にいる時間を丁寧に重ねていく」ことに繋がってきたようです。
共働きという前提はありつつも、子育ての時間に縛られないぶん、平日も休日もパートナー同士で過ごす時間を柔軟に持ててきたとのことです。現在もお互いの趣味の時間を大事にしつつも一緒に過ごす時間もきちんと作り互いに理解している生活を送っているようです。
忙しい中でも「週に一度は必ず外食をする」「お互いの趣味に付き合う時間をつくる」「家事は分担して協力して行う」といった、生活の中での小さなルールが自然と生まれ、それが結果的に信頼や理解の深まりに繋がってきたと語っています。
また、喧嘩や衝突の頻度も少ないようで、お互いに感情的になる場面が少ないという点にも触れており、これは「急いで何かを決めなければならない状況がなかったからではないか」と感じているようです。
時間制限のある意思決定が少ないことで、日々のコミュニケーションに余裕が生まれていた可能性があるとのことでした。(平日は忙しいし、土日もお互いの趣味に時間を費やしていることが多いので、お互いが自由に生きているけど、価値観は近くて老後も一緒に住めるパートナーという関係のようです)
周囲の出産ラッシュで感じた疎外感と葛藤
上記では落ち着いた生活を送っているようなご夫婦ですが、この10年の中には葛藤や疎外感といったことを感じた場面も多くあったようです。
DINKsを選ぶことには納得していたものの、周囲で次々と出産や育児の報告が相次いだ時期には「自分たちだけ取り残されたような感覚になった」と語っていました。
とくに30代前半には友人との会話が「子ども中心」になる場面も多く、共通の話題が見つけにくいと感じたこともあったそうで、徐々に友人と食事に行く機会も減ったとのことです。
さらに、親戚の集まりや実家に帰省した際「子どもはまだ?」と聞かれたときには、どこか心に引っかかるものがあったようで、戸惑った時期もあったとのことです。
こうした感情をきっかけに、「本当にこのままで良かったのか」と考え直すタイミングもあったようですが、夫婦で話し合いを重ねた結果、「やはり今の生活に無理がない」という共通認識に落ち着いていったようです。
葛藤がなかったわけではなく、むしろそれに直面したからこそ、「自分たちが納得して生きること」の大切さを再確認する機会になったと語っていました。
40代を迎えて話し合った「もしもの後悔」
DINKs生活10年目を迎えたこの夫婦も年数を重ねるまでに様々な話しあいをしています。「もし将来、子どもがいないことを後悔することがあったらどうしようか」「万が一、自分たちに健康や生活の変化があったときにどうしようか」などについてです。
このとき夫婦で出た答えは「後悔するかもしれないけれど、そのときどきに納得できる判断を積み重ねることが、未来への備えになるのではないか」と考えているようでした。
また、「万が一、自分たちに健康や生活の変化があったときに」についても話し合いをして、老後や介護への備えを互いにそれぞれ貯蓄を毎月一定額決めて早い段階から共有しているようです。
そして「後悔をゼロにする」のではなく、「後悔したときに一緒に受け止められる関係性を築いておく」という考え方がこの夫婦にとってのDINKs生活を支えるひとつの軸になっているようでした。
こうした長期的な視点に立って、DINKsという生き方をどのように設計し直せるか、夫婦間の対話や制度の活用、外部とのつながり方などを軸に、より持続的で安心感のある暮らし方を次のパートでは考えていきます。将来について考えることはDINKsに限らず、すべての家庭にとっての共通課題とも言えそうです。
DINKs夫婦が気をつけたい3つのこと
DINKsというライフスタイルは柔軟で自由な反面、長期的に見たときに自分たちの暮らしをどう設計していくかが重要になってくるようです。
また、周囲との違いやライフステージの進行に伴って、夫婦の間で感じ方や価値観にズレが生まれることもあるようです。そうした変化にどう気づき、どう向き合うかが、DINKs夫婦の安定感や満足度に影響を与える可能性があると考えられます。
ここでは、DINKsであることを前提により健やかで持続可能な関係を築いていくために意識しておきたい3つの視点を紹介します。どれもすぐに結論が出るものではありませんが、定期的に立ち止まって考えてみることで、将来の安心感につながるかもしれません。
長期視点でのライフプラン設計の重要性
DINKs夫婦にとって、長期的な生活設計は重要とされる傾向があります。子どもの教育資金や進学などの予定がない一方で、マンション・戸建ての購入やNISA・idecoなどの投資を「どこまで行うか」が老後の医療・介護といったライフイベントに向けての準備になります。
実際、40代以降になると「このままでいいのか」「何か見落としていないか」といった漠然とした不安を感じ始めるケースもあるようで、そのタイミングで初めてライフプランの必要性に気づく人も少なくないと言われています。
そのため、まだ体力や収入が安定している時期にこそ、老後資金、住まいの見直し、健康維持の仕組み、信頼できるサポート体制などについて早めに話し合っておくことが、精神的な安心感につながる可能性があります。
「いずれ考えよう」ではなく、「少しずつでも方向性を共有しておく」という姿勢が、DINKsという選択をより前向きに持続させていく鍵になるのかもしれません。
定期的に“価値観のすり合わせ”をする
DINKs夫婦にとって、“価値観の共通点”はとても大切な軸のようです。ただし、それは一度決めたら変わらないというものではなく、年齢や環境、社会の変化とともに揺らぐこともあるようです。
とくに仕事の状況や家族の健康、ライフスタイルの変化などをきっかけに、「これまでと違う考え方をするようになった」と気づく瞬間が訪れることもあるとされています。
そのようなズレを防ぐために、定期的に「今の暮らしに満足しているか」「将来に向けて気になることはないか」といったテーマで、夫婦でフラットに話し合う時間を持つことが推奨されています。
また、「本音を言いにくくなっていた」「なんとなく察しているつもりだった」といったすれ違いが表面化するタイミングもDINKsとして生活を続けているとくるようです。
だからこそ、小さな違和感を早めに拾い上げて話し合うことが、将来的な関係の安定につながると考えられています。
「同じ方向を向いているつもり」ではなく、「今も同じ方向を向けているかどうかを確認する」ことが、静かで安定した関係を保つうえで大切なポイントになってくるのかもしれません。
周囲と比較せず、自分たちの幸せを軸に決める
DINKsというスタイルは、まだまだ世間的に認知度が低いこともあるようで、人によっては周囲からの視線や意見に気持ちが揺れることもあるようです。
特に30〜40代のタイミングで、友人や同僚に子どもが生まれると、無意識に「自分たちはこれで良かったのか」と立ち止まってしまうケースもあるようです。
また、SNSなどで育児や家族の投稿を見かける機会が増えることで、必要以上に自分たちの生活と比較してしまう場面もあるかもしれません。
こうした“外からの情報”が、ふとした瞬間に心のざわつきを生むことがあるという話も聞かれます。
ただ、そのたびに思い出したいのは、「何を大切にしたいかは、夫婦ごとに違う」という前提です。
他人の幸せが自分の幸せと一致するとは限らず、自分たちが納得して選んだ道が、そのまま最適解になっているケースも多いようです。
自分たちにとって心地よい暮らしとは何か、どうすればふたりで気持ちよく過ごしていけるか。それをベースにして暮らしを選び続けていくことが、DINKsにとっての“ブレない軸”になってくるのではないでしょうか。
次章では、こうした視点を踏まえつつ、DINKsを取り巻く社会環境や制度の課題について触れながら、今後どうすれば安心してこの生き方を選びやすくなるのか、周囲の理解や仕組みづくりの観点から考えていきます。DINKsは個人の選択であると同時に、社会全体がどう支えるかも問われるテーマになりつつあるようです。
まとめ|DINKsという生き方に正解も不正解もない
DINKsという生き方は自由で柔軟である反面、理解されにくさや将来への不安といった独自の課題も抱えているようですが、それはどのような生き方にも共通する部分があるとも言えそうです。
子どもを持つ人生も、持たない人生も、それぞれに異なる責任と選択があり、いずれかが優れているわけではないという考え方が、少しずつ社会の中でも共有され始めているように見受けられます。
DINKsを選んだからといって、すべてが順風満帆というわけではない一方で、その決断の先に確かな満足や安定を感じている夫婦がいることもまた事実です。
周囲の声に惑わされるよりも、自分たちにとって「何が心地よく、何を大切にしたいのか」に耳を傾けていくことが、DINKsという生き方を前向きに続けるための土台になっていくようです。
ここでは、そんなDINKsという選択を通じて見えてくる、「幸せのかたちに正解はない」という視点から、最後に2つの大切な考え方を整理してみます。
選んだ道に責任を持てば、幸せは築ける
どんなライフスタイルにも、一長一短があります。
DINKsもまた、経済的な自由や時間の柔軟性というメリットを享受できる一方で、孤独や老後の不安といった“長い目で見たときの課題”を避けられない側面があるとされます。
しかし、重要なのは「選んだあとに、どうその道と向き合っていくか」ではないでしょうか。
たとえば、老後の計画を早めに立てる、外部とのつながりを意識して持ち続ける、ライフプランを夫婦で定期的に見直すといった行動を重ねることで、不安を具体的な安心材料に変えていける可能性があるようです。
どこかで迷いが生じたとしても、その選択を他人や環境のせいにせず、自分たちで納得できるように向き合っていく姿勢が、結果として長く幸せを感じられる関係を築く土台になるのかもしれません。
DINKsという生き方が特別なものではなく、「自分たちにとって自然な選択肢」であると受け止めることができれば、その選択はよりしなやかで持続的なものになっていく可能性があります。
「どう生きるか」を夫婦で対話し続けることが鍵
DINKsに限らず、どんな家庭にも共通するのは「価値観は時とともに変わる」という点かもしれません。
だからこそ、一度決めたから終わりではなく、定期的に立ち止まり、「今の自分たちがどうありたいのか」を確認することが大切になるようです。
特にDINKsの場合、育児などの明確なライフイベントが少ない分、「話し合う機会」が意識しないと減ってしまうこともあるようです。
そのため、意識的にパートナーと未来について話す習慣を持つことが、互いの価値観のズレや心の変化に気づくきっかけになり得ます。
例えば「今の働き方で満足している?」「老後はどこでどんなふうに暮らしたい?」といったテーマを、年に一度でも話し合っておくことが、将来の選択肢を狭めない工夫につながっていくのではないでしょうか。
「話し合いができる関係性」でいることこそが、DINKsという選択の中で最も大切な基盤になっているように思えます。夫婦の対話は、生活を守るツールであると同時に、未来への地図を描くためのコンパスのような存在かもしれません。
DINKsという生き方には、たしかに多くの自由と可能性がある一方で、答えのない問いに向き合い続ける覚悟も必要とされるようです。
ただ、「正解がない」からこそ、「自分たちの正解を一緒に探していける関係」であり続けることに、大きな意味があるのではないでしょうか。選んだ道を自分たちらしく歩めることこそが、何よりの豊かさにつながっていくように感じられます。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック