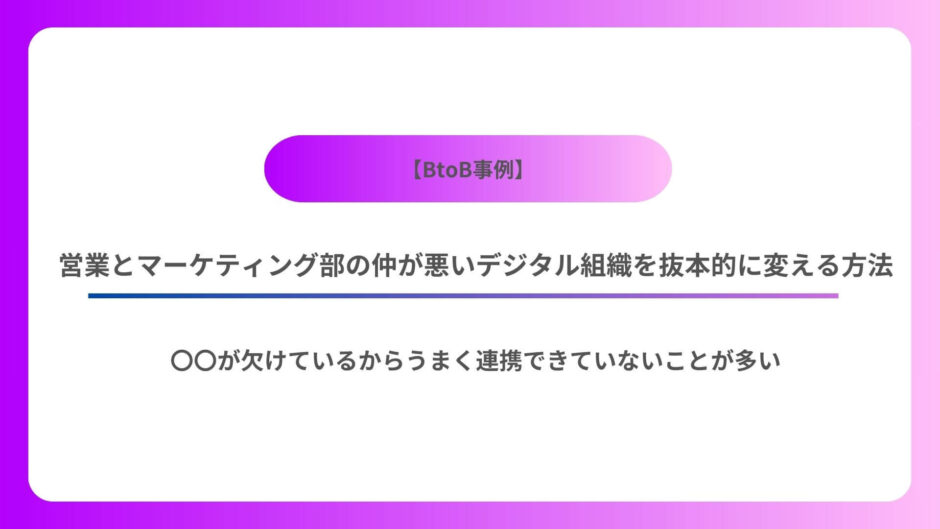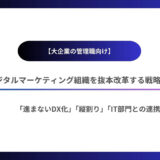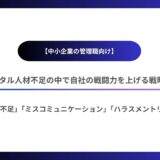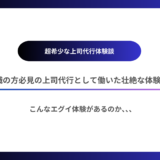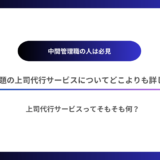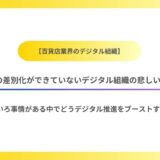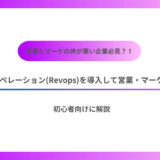皆さんこんにちは。プロストイックです。
本日は「BtoB企業」に所属している企業の方を対象に「デジタル組織を抜本的に変える方法」について解説をしていきます。
- BtoB系企業で営業やマーケティング部に所属してる方
- 社内の雰囲気があまり良くなく、職場の空気感をどうにかしたい方
- 営業やマーケティング部、商品開発部など部署間の連携ができておらず組織がうまく機能していない
ちなみに前回はこちらの記事を解説しました。
なぜBtoB企業では営業とマーケティング部が対立してしまうのか?
まずいきなり本題のテーマから入ります。皆様30秒だけ踏みとどまって考えてみてください。
見出しにも記載の通りではありますが、「なぜBtoB企業では営業とマーケティング部が対立してしまうのでしょうか?」
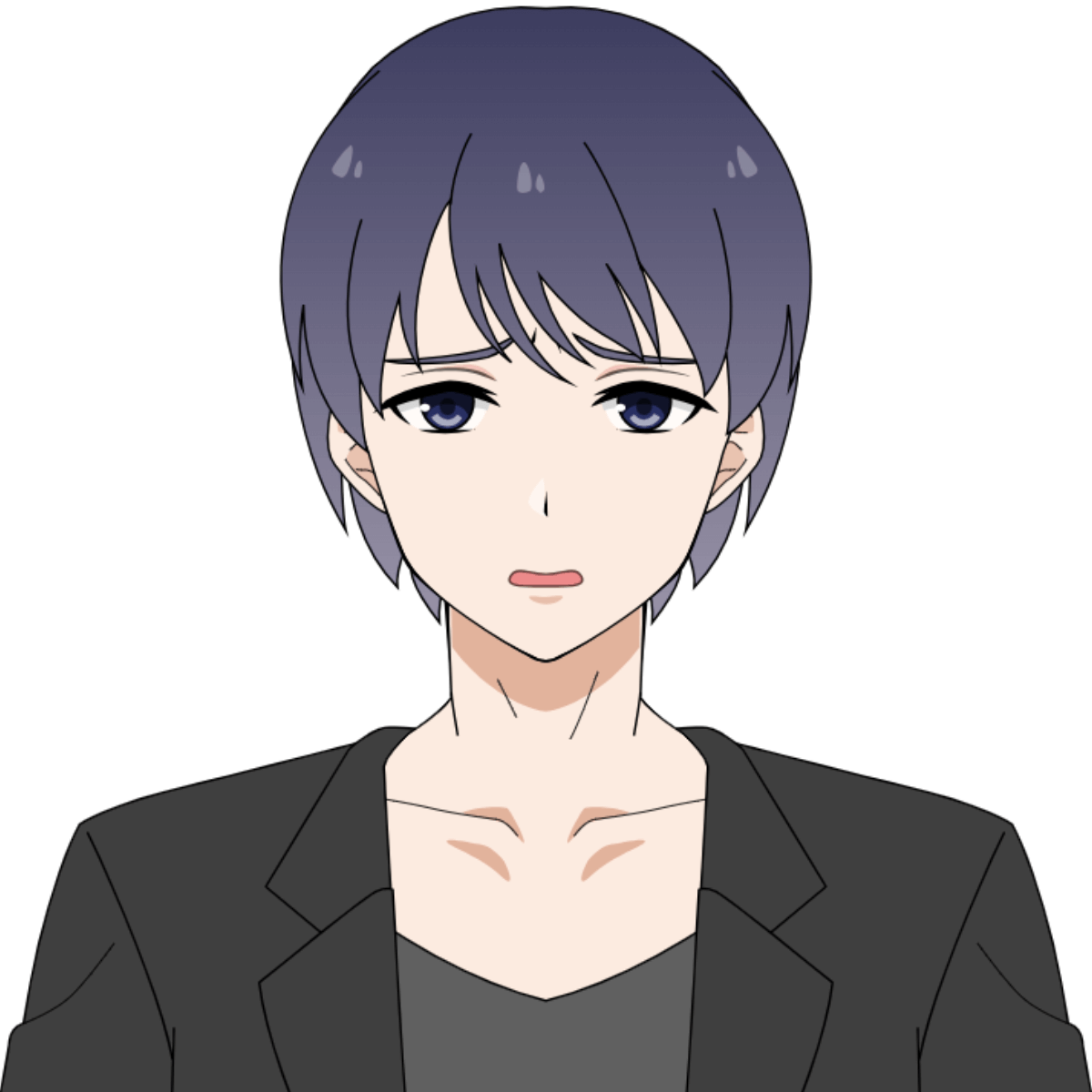
ん~なんでなんだろう?
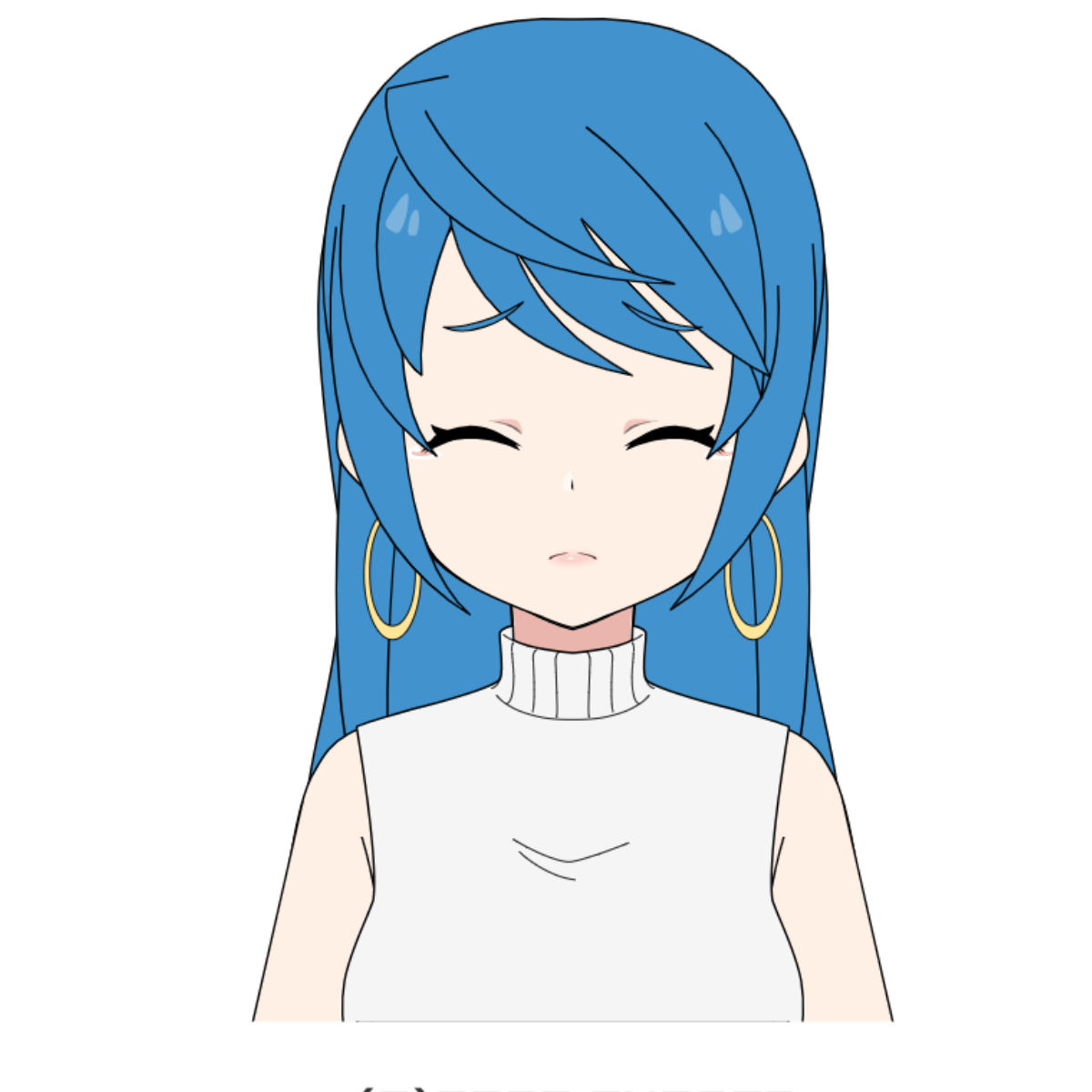
仲が悪いというより方針の違いやコミュニケーションのすれ違いもあるのかもしれないわ
実際にBtoB企業において営業とマーケティング部門の関係がうまくいかないのは珍しいことではありません。
(体験談ですが当社プロストイックがこれまでご支援してきた企業では仲が悪いというより意思疎通やコミュニケーションが部署間で上手く取れていなかった企業様が多いです。これはこれからお話をする内容が合致していたケースもありますし、純粋に部署の規模が大きくて部署の間に立って調整する人がいなかったことが原因なこともあります、
本来ならば同じ「売上向上」という目標を共有するはずの2つの部門が、互いに対立してしまう原因はどこにあるのでしょうか。
特に、デジタルマーケティングの活用が進む現代において、両部門の連携が不十分なままではDX(デジタルトランスフォーメーション)推進も難しくなります。
本章では営業とマーケティングが対立してしまう根本的な原因を掘り下げていきます。
追っている目標(KPI)が同じようで違う|営業は短期成果、マーケは中長期視点
まず1つ目の原因となりうる営業とマーケティングの間に生じる摩擦の大きな要因の一つは両者が追い求める目標(KPI)が根本的に異なる点にあります。
営業部門のKPIは基本的に短期的な売上達成に直結するものが多く、即効性のある施策を求めます。
例えば、営業チームは以下のような指標を重視します。
- 月次・四半期ごとの売上目標
- 新規顧客獲得数
- 受注率や成約件数
一方でマーケティング部門が重視するのは中長期的なブランド認知やリード(見込み顧客)の育成といった指標です。例えば以下のようなKPIを設定することが一般的です。
- SNSの更新やコンテンツSEOの記事数増加
- リードの獲得数やナーチャリング(育成)の進捗度
- ブランド認知度の向上
このように営業は「すぐに売れる顧客」を求めるのに対し、マーケティングは「時間をかけて育てる顧客」を重視するため、どうしても認識のズレが生まれます。(特にSNSやSEOは成果が出るまでに時間がかかる事が多く、「すぐに」目に見える数値に成果が反映されないことが多いです)
営業からすれば、「マーケティングが獲得したリードは質が低い」と不満を持ちやすく、一方のマーケティングは「せっかく育てたリードを営業がうまく活用していない」と感じることが多いのです。
また、営業部門は過去の成功体験を重視する傾向があり、従来のやり方(例えば、訪問営業やテレアポ)を継続したがります。
一方で、マーケティング部門はデジタル化を進めインバウンド施策(SEOやコンテンツマーケティングなど)による効率的な顧客獲得を目指すため、戦略の方向性が一致しないことも対立を生む原因となります。
こうしたギャップを埋めるにはKPIの統合と共有が必要です。(解決策や対策は本記事の後半パートで詳しく解説しております。)
経営層がマーケティングを軽視しがちなBtoBの現実
もう一つの大きな問題は経営層がマーケティングの重要性を十分に理解していない点です。
特にBtoB企業では「営業が売上を作る」という考え方が根強く、マーケティングは補助的な役割として見られがちです。
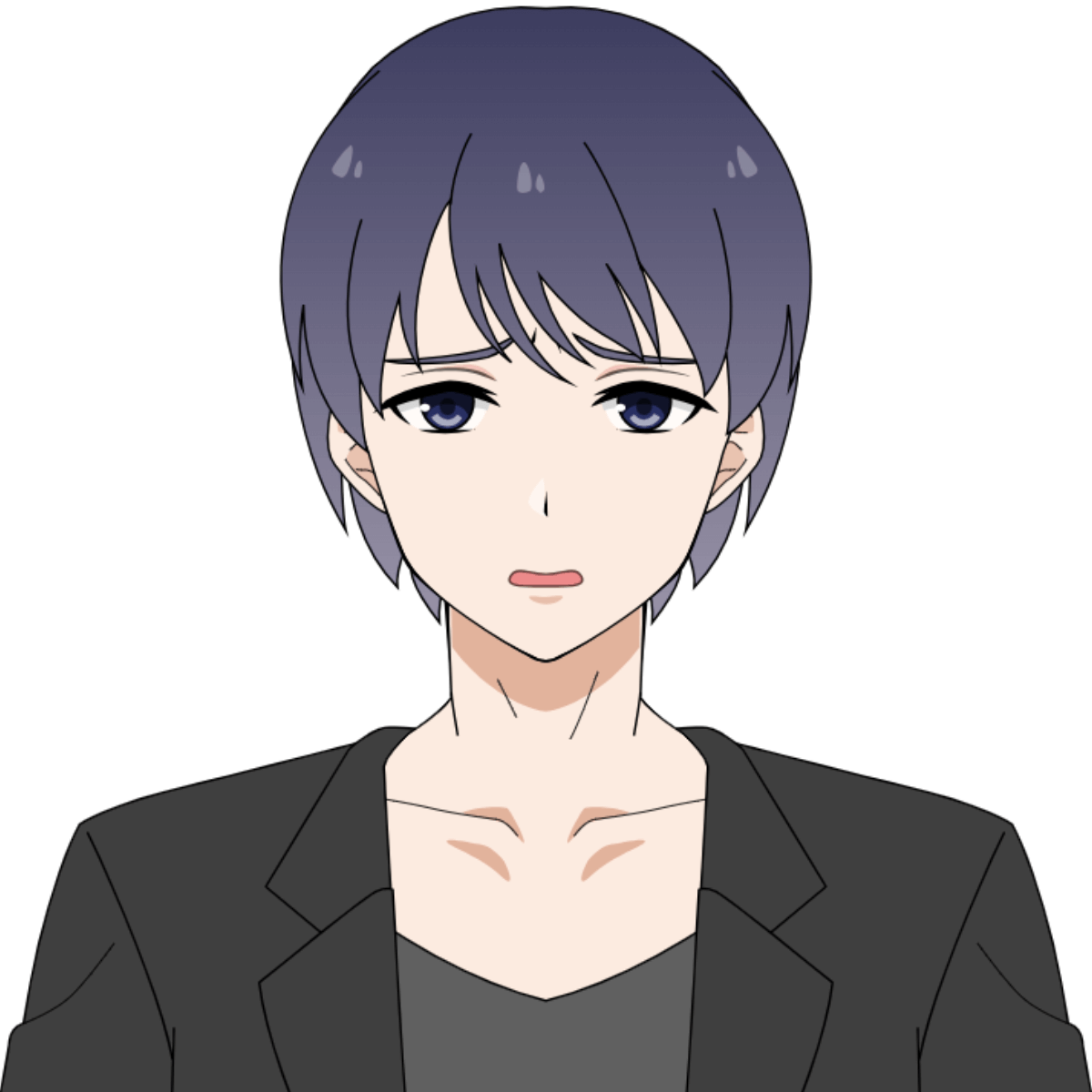
確かに一般消費者向けの商品やサービスじゃないとリーチできるターゲットも限られるもんね
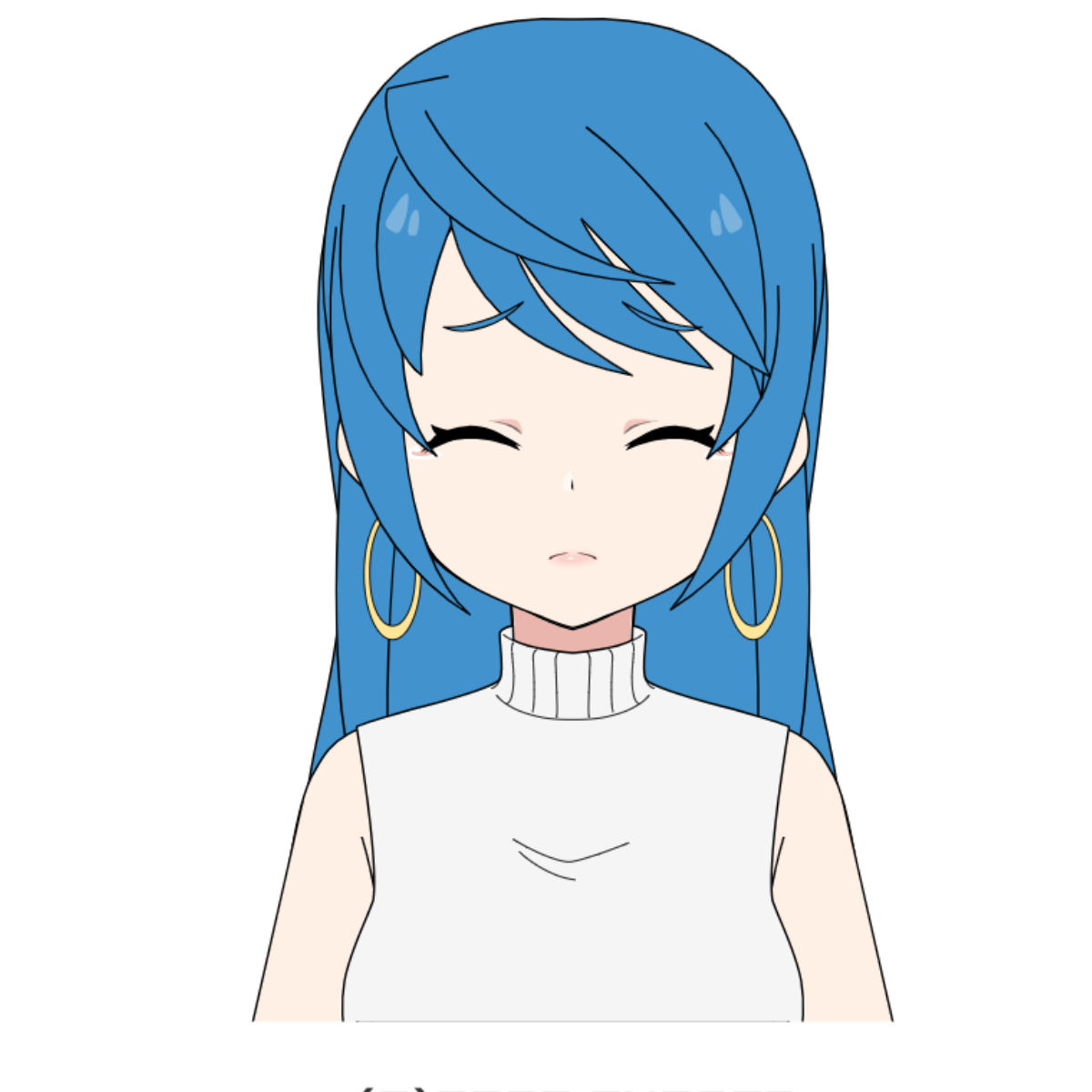
営業が架電や飛び込み営業、展示会などの手段がまだ一般的なのかもしれないわね
そのため、企業によってはマーケティング部門の予算が十分に確保されず、人員も不足しがちになります。
営業が根本的に強い組織の背景には、以下のような要因があります。
- 営業主導の企業文化が根付いている
BtoB企業は歴史的に営業主導のビジネスモデルで成長してきたケースが多く、「優秀な営業担当者がいれば売上は伸びる」という考えが経営層に浸透しています。結果としてマーケティングへの投資が後回しになり、営業のサポート役にとどまることが多いのです。 - マーケティングの効果が数字で見えにくい
営業活動は受注という明確な成果が出ますが、マーケティング施策は短期間では効果が見えにくいことがあります。例えば、SEO施策やコンテンツマーケティングは、成果が出るまでに数ヶ月以上かかることが一般的です。経営層が即効性を求める場合、マーケティングの価値を正しく評価できず、軽視してしまうことになります。
(これを社内に理解してもらうのが相当大変なことが体験談としては多いです) - BtoB企業のマーケティング部門は少人数で機能していることが多い
一般的なBtoC企業に比べ、BtoB企業のマーケティング部門は小規模な傾向があり、業務負担が集中しがちです。加えて、DX推進のための専門知識を持つ人材が不足しているため、デジタル施策の実行が思うように進まないケースもあります。
このような状況を改善するには、経営層がマーケティングの役割を正しく理解し、組織全体でDX推進を支援する体制を構築することが必要です。
さらにこの後、後半パートでお話をする上司代行を活用することで、BtoBマーケティングに精通した外部の専門家を導入し、社内の知見を強化する方法も効果的です。
マーケティング組織が機能するためには、適切なリーダーシップが求められますが、社内に適任者がいない場合、外部のプロフェッショナルを一時的に登用することで、施策の立案から実行までを円滑に進めることができます。
(またマーケティング部に人数が少ないと中間管理職やリーダーがプレイングマネージャーとなり手が回っていないことが非常に多く眼の前の降ってくる仕事をこなすだけで部署として本来すべきことや役割に注視できていないことが多いです)
BtoB企業において、営業とマーケティングの対立は珍しいことではありません。
しかし、この対立を放置するとDXの推進が滞りデジタルマーケティングの成果が十分に発揮されない状況に陥ります。
この問題を解決するには、以下のポイントが重要で後半パートで具体的な内容や解決策の詳細をお話します。
- マーケティングのKPIを経営層と共有し、ビジネスインパクト(マーケティングの効果)を可視化する
- 経営層がマーケティングの価値を正しく理解し、十分なリソースを確保する(結果で示す)
- マーケティング部が主動で営業を巻き込み組織全体をリードする役割(大義名分)を得る
- 上司代行などのリソースを活用し、マーケティング知見(ノウハウ)を組織内に蓄積する
これらの施策を実行することで、営業とマーケティングの関係性を改善し、BtoB企業のDX推進を加速させることができるでしょう。
「営業がマーケのリードを信用しない問題」の正体とは
BtoB企業において営業とマーケティング部門の関係がうまく機能しない理由の一つが「営業がマーケティングのリードを信用しない問題」です。
マーケティングが獲得したリードを営業が「質が悪い」と判断し、フォローを後回しにするケースが多く見られます。
この問題が放置されると、マーケティングの成果が正しく評価されず、結果として営業とマーケティングの対立が深まります。では、なぜこのような問題が発生するのでしょうか。本章では、その根本的な原因を掘り下げます。
「リードの質が悪い」vs「フォローが遅い」|終わらない責任の押し付け合い
営業とマーケティングが対立する際、よく聞かれるのが「マーケティングが取ってきたリードの質が悪い」という営業側の不満です。
一方で、マーケティング側は「せっかくリードを提供しても、営業が適切にフォローしない」と反論します。このように、お互いが相手に責任を押し付ける形になり、対立が深まってしまうのです。
営業が「リードの質が悪い」と感じるのには、いくつかの理由があります。
例えば、マーケティングが提供するリードが単なる資料請求者や情報収集段階の企業であり、今すぐ商談につながる可能性が低い場合、営業側は「このリードを追っても時間の無駄だ」と判断します。
一方で、マーケティングは「営業がリードを適切にフォローし、育てることで商談化の可能性は高まる」と考えているため、両者の認識にギャップが生まれるのです。
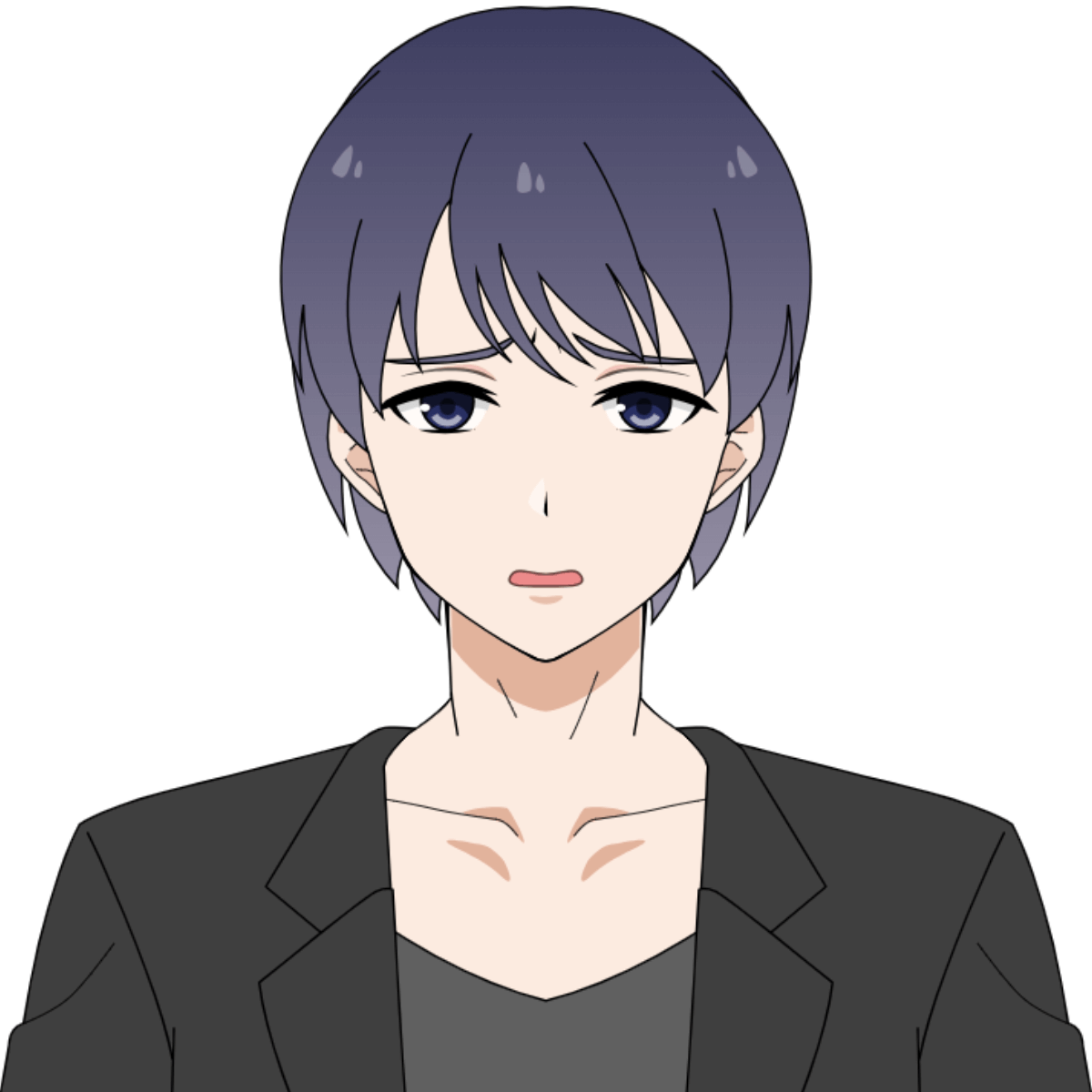
ん~なんかそんな話をよく聞くような、、、
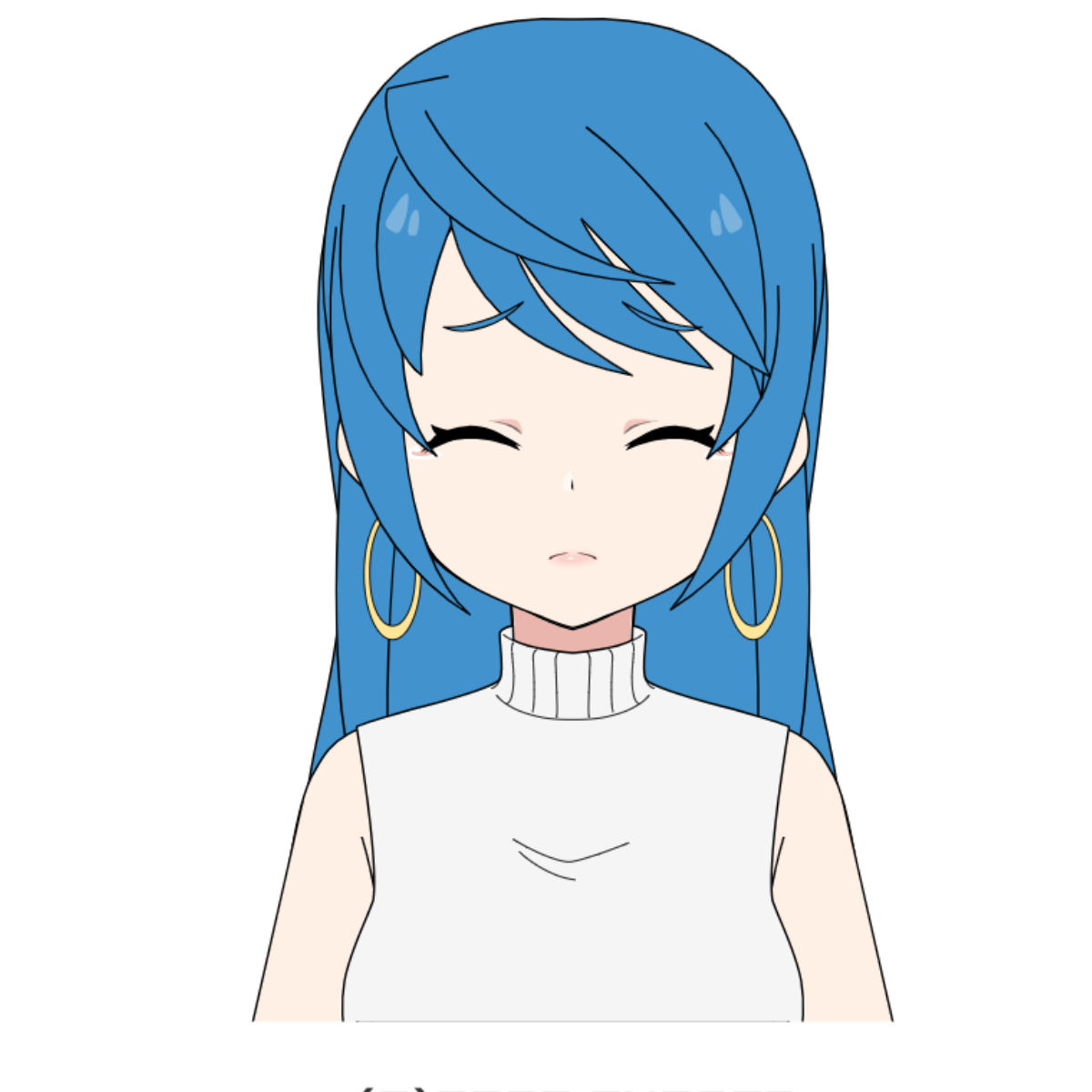
どちらの立場の言い分もわかるような気もするわ
また、営業のフォローが遅れることも問題の一因です。
特に、営業担当者が少数精鋭で回しているBtoB企業では、新しいリードをすぐに追う余裕がなく、後回しになりがちです。
リードの鮮度が落ちた頃にようやくアプローチをかけても、既に他社と商談が進んでいるか、顧客の関心が薄れてしまっていることが多く、「このリードは意味がなかった」と営業が判断するケースが発生します。
(この対応を知るとだいたいマーケ側は憤慨して「いや質の話ではなく対応の話じゃん」となります(体験談))
この責任の押し付け合いを解消するには、以下のような施策が必要です。
- リードのスコアリングを導入し、商談化の可能性が高いリードを優先して営業に提供する
- リードナーチャリング(育成)のプロセスを明確にし、営業とマーケティングの役割分担を整理する
- SFA(営業支援システム)やCRMを活用し、営業のフォロー状況を部署間で共通化・可視化する
こうした取り組みによって、リードの質と営業のフォロー体制を最適化し、両部門の認識ギャップを埋めることが可能になります。
「売る人」と「育てる人」|役割の違いが生む根本的なズレ
営業とマーケティングの関係を考える際に重要なのが、両者の役割の違いです。
営業は「売ること」が主な役割です。
商談を成立させ、契約を獲得することが営業の最終ゴールであり、目の前のターゲットに対して最も適切な提案を行うことが求められます。そのため、短期的な成果を最優先する傾向があります。
一方、マーケティングの役割は「顧客を育てること」です。
BtoBの購買プロセスは長期化することが多く、特に高額商材では顧客が導入を決定するまでに複数のステップを踏みます。(これが大手企業であればあるほど社内申請のフローが長く時間を要します)
マーケティングはこうした顧客に対して継続的な情報提供を行い、適切なタイミングで営業に引き渡すことが求められます。
このように、営業とマーケティングでは役割が大きく異なるため、以下のようなズレが生じます。(多少違うケースもあるかもしれませんが、言語化をすると以下のようなすれ違いなことが多いです)
- 営業は「すぐに売れる顧客」が欲しいが、マーケティングは「時間をかけて育てる顧客」を提供する
- 営業は「今すぐの売上」を重視するが、マーケティングは「中長期的な関係構築」を重視する
- 営業は「リードが少なくても質が高いほうがいい」と考えるが、マーケティングは「母数を増やして確率を上げる」と考える
このズレを解消するには、マーケティングが育成したリードを営業がどのように活用するかを、双方で共通理解を持つことが重要です。
例えば、マーケティングが提供するリードの種類(情報収集段階・検討段階・意思決定段階)を明確にし、営業のアプローチ方法を標準化することで、ミスコミュニケーションを防ぐことができます。
営業とマーケの体制や連携にも根本的かつ潜在的な課題が
まず営業とマーケティングの連携がうまくいかない背景には、組織体制やプロセスに根本的な問題があることが多いです。
例えば、連携が上手くいっていない企業の多くでは営業とマーケティングが別々の部門として運営されており、情報共有がスムーズに行われていません。(情報連携は形の上ではしていても、意思疎通や相互的な協力ができていないことが多いです)
これをもう少し掘り下げるとマーケティング側がどのようにリードを獲得し、どのタイミングで営業に引き渡すべきかが明確になっていないため、結果として「リードの質が悪い」「フォローが遅い」といった問題が発生しやすくなります。
また、経営層がマーケティングを単なる「営業サポート」と位置づけている企業では、マーケティングの役割が十分に発揮されず、営業との連携が進みません。営業部門が主導権を握り、マーケティングが後回しにされる構造では、DX推進も停滞してしまいます。
営業がマーケティングのリードを信用しない問題は単なる認識の違いではなく、組織体制やプロセスの設計ミスによって引き起こされることが多いです。
この課題を解決するには両部門が共通のKPIを持ち、連携を強化する必要があります。
BtoB企業の一般的な組織構造とデジタル組織の現状
BtoB企業におけるデジタルマーケティングの導入は企業の競争力を高める重要な要素となっています。
しかし、現実には多くのBtoB企業が従来の営業主導型の組織を維持しており、デジタル組織の構築に苦戦しているのが現状です。本章では、BtoB企業の典型的な組織構造を分析し、デジタル活用が進まない理由を探ります。
典型的なBtoB企業の営業主導型組織とは?
BtoB企業の多くは長年にわたって営業主導型の組織を形成してきました。
特に、日本企業では「足で稼ぐ営業」が文化として根付いており、営業担当者が顧客との関係を築きながら受注を獲得するスタイルが一般的です。(当然飛び込み営業なども実施しています。)
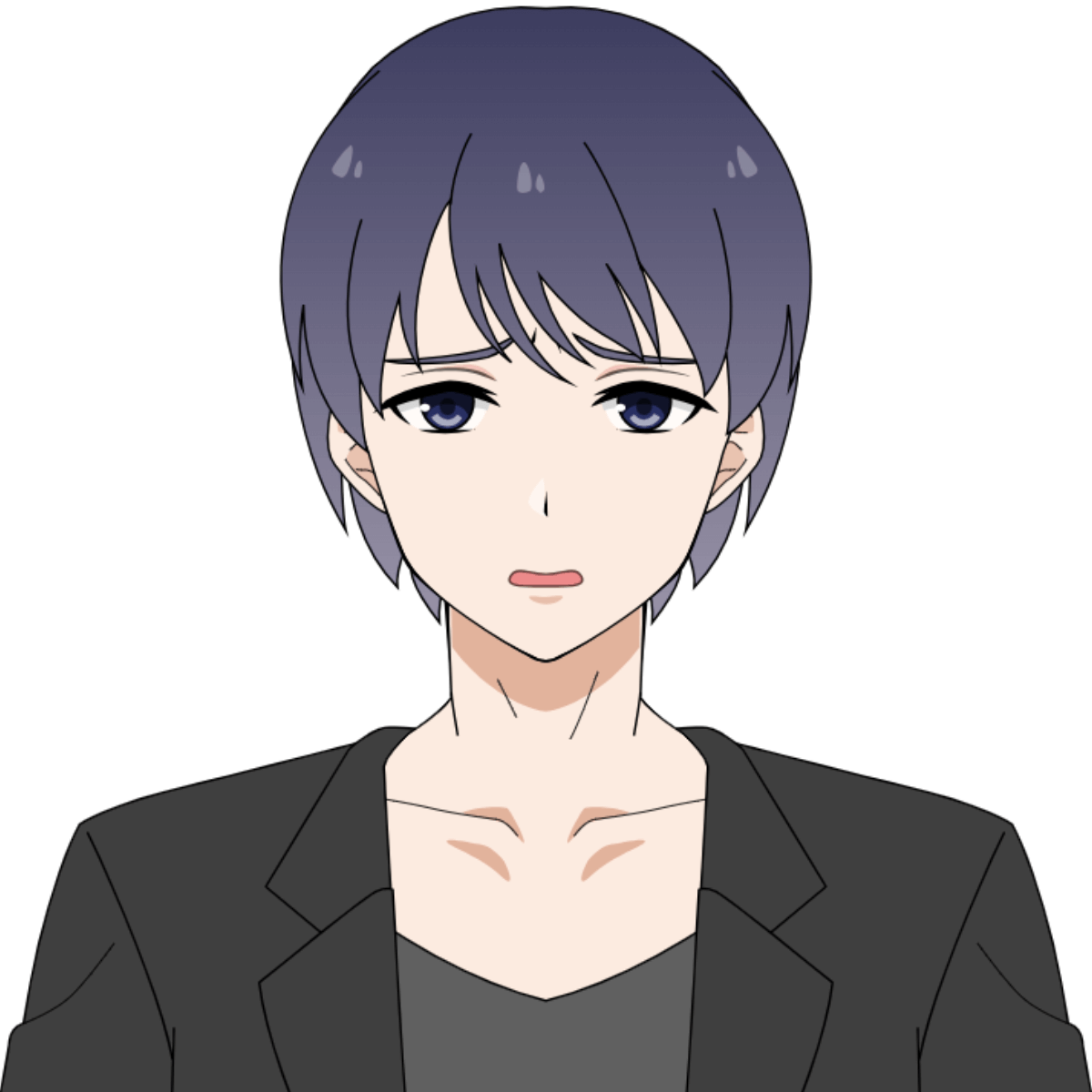
今は受付を設けないでアポがないと訪問もできないオフィスもあるよね
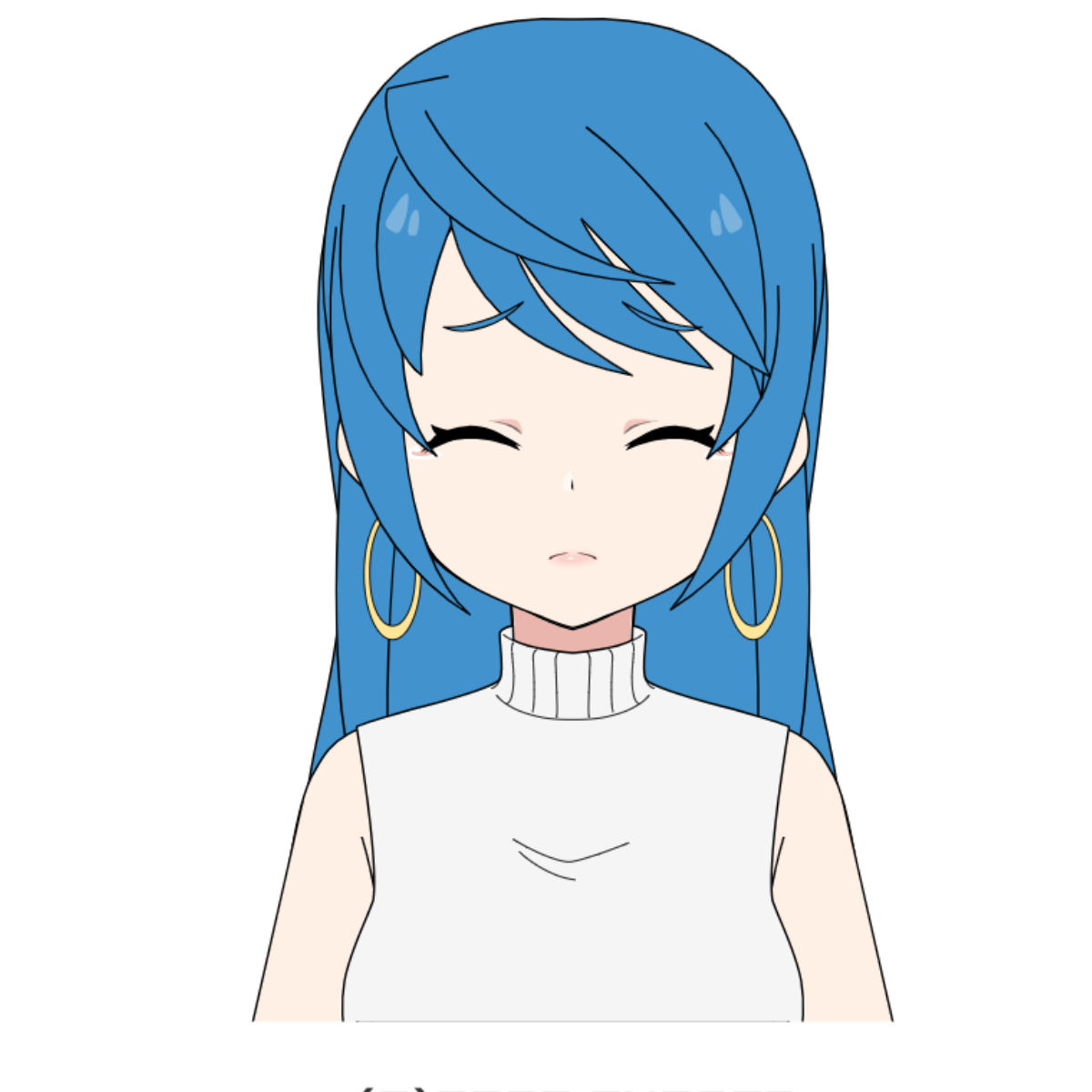
セキュリティ強化をされてしまっているケースは多いわね。ただ、飛び込みも未だに効果がある手法だから実施されているのよね。
こういった営業主導型の組織ではマーケティングやデジタル活用をを重要視せず、以下のような特徴が見られます。
- 営業部門が最も強い権限を持ち、マーケティング部門は営業のサポート的な役割にとどまる。
- 経営層は売上に直結する営業活動を重視し、マーケティングの重要性を十分に認識していない。
- リード獲得や育成は営業任せになっており、デジタル施策を活用する文化が根付いていない。
このような組織ではデジタルマーケティングの導入が進みにくく、DX推進が停滞する原因となります。
特に、営業担当者が「デジタル施策は自分たちの仕事には関係ない」と考えている場合、マーケティング施策の導入はさらに困難になります。
(しかし、残念ながらおおよそは経営層がデジタルやマーケティングの重要性を理解していないことが多いです)
マーケティング部が営業のサポート役になってしまう理由
BtoB企業において、マーケティング部門が営業の「サポート役」として扱われることが多いのは、企業の売上構造と深く関係しています。
ビジネスモデルにもよりますが、BtoBビジネスの特徴として「1件あたりの契約単価が高く、長期的な関係構築が求められる」という点が挙げられます。
そのため、企業の売上の大部分は地道な営業活動によって生み出されるケースがほとんどです。経営層としても、「売上に直結する営業活動を最優先する」という考えになりやすく、マーケティングはその補助的な役割に追いやられてしまいます。
この構造が続くと、以下のような問題が発生します。
- マーケティング部門が独自の戦略を持てず、営業からの指示待ち状態になる。
- 短期的な成果を求められるため、リード育成やブランド構築などの中長期的な施策が軽視される。
- 営業とマーケティングの連携が不十分で、リードの管理や活用が適切に行われない。
このような状況を打破するには、マーケティング部門が営業のサポートではなく、「売上を生み出す戦略的な機能」として位置づけられることが重要です。
そのためには、時間はかかりますが経営層がマーケティングの役割を正しく理解し、組織全体でマーケティング活動の価値を認識する必要をボトムアップで訴えていく必要があります。
プロストイックの上司代行(中間管理職支援)はこういった社内への説明や第三者視点での実行サポートも行っております。
中間管理職のマーケティング実行支援は
プロストイックが強い
DX推進企業ができていない縦割り企業の問題
またBtoB企業において、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している企業と、従来のアナログな営業手法に依存している企業では、組織の在り方に大きな違いがあります。
DXを推進している企業では以下のような特徴が見られます。
- マーケティング部門が営業と対等な立場で戦略を策定し、データを活用した施策を実施している。
- CRMやMAツールを活用し、リードの管理やナーチャリング(育成)を体系的に行っている。
- 営業とマーケティングのKPIが統合されており、部門間の連携がスムーズに行われている。
一方、対照的にアナログな企業や縦割りの企業では以下のような問題が顕著になります。
- データ活用が進んでおらず、営業の勘や経験に頼った属人的な営業手法が主流になっている。
- デジタルマーケティングの重要性が経営層に理解されておらず、十分なリソースが割かれていない。
- 営業とマーケティングの役割分担が不明確で、部門間の摩擦が発生しやすい。
このように、DX推進企業とアナログ企業の違いは「データ活用」「部門間連携」「経営層の意識」によって大きく分かれます。
DXを成功させるためには、企業文化そのものを変革し、デジタルを活用した営業・マーケティング体制を構築することが求められます。
デジタル活用が進まない企業の組織体制にありがちな特徴
デジタル活用が進まないBtoB企業には、共通する組織上の課題が存在します。繰り返しになる部分もありますが、課題をきちんと認識するために代表的なものとして、以下のような点を列挙します。
- 経営層のデジタル理解が浅くマーケティングの投資判断が遅れる。
- 営業部門が相対的に強い権限を持ちマーケティング部門の発言力が弱い。
- マーケティングが独立した機能を持たず営業の下請け的な立場になっている。
このような組織体制ではデジタルマーケティングを導入しようとしても、適切な活用ができずに形骸化してしまうケースが多くなります。
特に、営業部門がマーケティングの施策を理解せず、リードの活用やフォローアップが不十分な場合、成果が上がらないまま施策が中断されることも少なくありません。
デジタル組織の成功には、組織全体の文化や体制を変革することが不可欠です。(これは組織の規模が大きくなればなるほど大変で時間がかかります)。そのためには、経営層のリーダーシップと現場の意識改革が重要なポイントとなります。
成功するBtoB企業のデジタル組織体制とは
BtoB企業がデジタルマーケティングを成功させるためには、組織体制の抜本的な改革が不可欠です。
従来の営業主導型の組織ではデータ活用が進まず、マーケティング施策が形骸化しやすい傾向があります。デジタル時代においては、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが一体となった組織体制を構築し、データドリブンで意思決定を行うことが求められます。
本章では成功するBtoB企業のデジタル組織体制のポイントを解説します。
営業×マーケ×カスタマーサクセスが連携する理想の組織とは
BtoB企業のデジタル組織において、営業・マーケティング・カスタマーサクセス(CS)の三部門が密接に連携することは、顧客獲得とリテンションを最大化するために重要です。
従来のBtoB営業ではマーケティング部門がリードを獲得し、営業がクロージングを担当するという分業が一般的でした。
しかし、デジタル化が進む現代では、営業活動は「獲得」だけでなく、「育成」や「継続的なフォロー」にも重点を置く必要があります。ここで重要なのが、カスタマーサクセスの役割です。
理想的な組織では以下のような役割で各部門の連携が行われます。
- マーケティング:リードの獲得、育成(ナーチャリング)、コンテンツ戦略の推進(最初のきっかけ)
- 営業:ナーチャリングされたリードのクロージング、契約交渉(リード獲得後から契約まで)
- カスタマーサクセス:契約後の顧客フォロー、満足度向上、リピート促進(契約後~継続)
組織が人手不足の場合はマーケティングや営業部門の中にカスタマーサクセス機能が踏襲されるケースもあります
この3部門が連携することで、単発の取引ではなく長期的な顧客関係を築きやすくなり、LTV(顧客生涯価値)を向上させることができます。
DX推進のカギは「営業のデジタルリテラシー向上」
デジタルマーケティングを活用する上で、BtoB営業の現場において「デジタルリテラシーの低さ」が大きな課題となります。
当然、営業組織のほうが積極的にデジタルツール(CRMやMAなど)を活用している事例もありますが、営業担当者がデータ活用やデジタルツールの導入に消極的である場合、せっかくのデジタル施策も効果を発揮できません。
DX推進のためには、営業部門のデジタルリテラシーを高め、マーケティングと営業が共通言語・共通のリテラシーレベルで会話できる環境を整えることが重要です。具体的には、以下のような取り組みが求められます。
- CRMやMAツールの活用トレーニングを部署横断で実施する(ツール活用は属人化させない)
- 営業部門とマーケティング部門が定期的にデータを共有し、フィードバックを行う
- 営業担当者がデータを活用して、より適切なリードフォローを行える仕組みを作る
営業がデータを適切に活用できるようになれば、マーケティング施策のROI向上にもつながり、企業全体の成長を加速させることが可能になります。
デジタル組織改革に必要な人材と体制(上司代行の活用)
デジタルマーケティングを本格的に推進するためには、組織内に適切な人材を配置し、必要に応じて外部リソースを活用することが不可欠です。しかし、多くのBtoB企業では、「デジタル人材が不足している」「適切なリーダーが不在」**といった課題を抱えています。
こうした問題を解決するために、中間管理職支援(上司代行)の活用が効果的な選択肢となります。
上司代行とは、業務が集中してしまっているリーダーや中間管理職の直下にチームを創り施策の実行スピードを上げて、意思決定を素早く行い成果を通常の1.5倍の速さで出す体制のことです。
中間管理職がしなければならない社内業務や現場の指揮なども巻き取るため、管理職の方が「本来すべき業務に集中する環境」を作れることが一番の良さです。
また上司代行を活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- デジタルマーケティングの専門知識を即時に導入できる
- 社内のデジタルリテラシーを向上させ、長期的な組織改革につなげられる
- 部署間連携の橋渡し役も担うので短期間でマーケティングと営業の連携を強化し、売上向上に貢献できる
DXを推進する上で、デジタル知識を持つリーダーの存在は不可欠です。社内で適切な人材を確保できない場合は、上司代行のような外部リソースを活用することで、スムーズな組織改革を実現できます。
中間管理職のマーケティング実行支援は
プロストイックが実績No,1
データドリブン経営に不可欠なマーケ・営業の役割分担
デジタルマーケティングの成功には営業とマーケティングが明確に役割分担を行い、それぞれのKPIを設定することが不可欠です。多くのBtoB企業では営業とマーケティングが「どこまでリードを育てるべきか」「どのタイミングで営業に引き継ぐべきか」などの基準が曖昧になっています。
データドリブンな経営を実現するためには、以下のような仕組みを構築する必要があります。
- リードの温度感(ホットリード・コールドリード)を明確にし、営業が対応すべき範囲を定義する
- マーケティングのKPIと営業のKPIを統一し、部門間の摩擦を減らす
- データの可視化ツール(BIツールやCRM)を導入し、リアルタイムで状況を共有する
例えば上記で記述したように「営業がマーケティングのリードを活用して成約した件数」を共通指標にすることで、両部門の連携が強化される可能性があります。また、定期的なミーティングを設け、互いの視点や成果を共有することも有効な対策となるでしょう。
無論、既に摩擦が起きている場合、「部署間の連携」と一言で言ってもかなり大変で人手が足りていないことが多いです。(ここで言う人手不足とは「部署間の連携作業をやりたがらない」「やっている時間的余裕がない」ことも含みます)
このような取り組みを通じて、営業とマーケティングの間に明確な線引きを作り、効率的な連携を実現することが可能になります。
デジタルデータを活用して「見込み客の温度感」を可視化する方法
BtoB企業のデジタルマーケティングでは「リードの温度感」を正確に把握することが成約率向上の鍵を握ります。ではどのように見込み客の関心度や購買意欲を可視化し、適切なタイミングでアプローチを行うを可能にするのでしょうか。
利用しているツールによってやり方は分かれますがリードの温度感を可視化するためには、以下のような方法があります。
- Webサイトの閲覧履歴を分析し、どのコンテンツに関心を示しているかを把握する
- メールの開封率やクリック率を確認し、興味度の高いリードを優先する
- MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、スコアリングを行う
これらのデータをもとに、営業とマーケティングが連携し、適切なアプローチを行うことで、成約率を大幅に向上させることができます。
実際問題としてデータ計測ツールやMAツールは入れているが「活用できていない」「使える人材がいない」ということが多くの企業で課題となっています。
ツール活用のために正社員を雇用するよりも柔軟に動ける外部へアウトソースすることもぜひご検討ください。課題を放置するとますます競合他社との差が開き、課題が深刻化していきます。
マーケティング実行支援は
プロストイックが実績No,1
多くの企業で組織のサイロ化が深刻なレベルで根深い
少し組織間連携の文脈を深堀りしますが、皆さんは「サイロ化」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
サイロ化とは簡単に言うと「各部門が独立して連携が取れなくなる」ことを指します。
つまり営業とマーケ、ITシステム部門がバラバラに動いて連携が取れていない状態のことです。
組織のサイロ化が加速してしまう原因
営業とマーケティングが別々に動いている企業ではこの問題が特に顕著です。
なぜサイロ化は進んでしまうのか。その主な原因は以下の3つです。
① KPIの違いが連携を妨げる
営業は短期的な売上目標を追いマーケティングは中長期的なブランド構築やリード獲得に注力するため、両者のKPI(評価指標)が異なります。
例えば、マーケティングが「1ヶ月で500件のリード獲得」を目標としていても、営業が「今月の売上達成」にフォーカスしている場合、マーケティングが提供するリードの質やフォローアップのタイミングを巡って対立が生じます。
この結果お互いが歩み寄らず、業務が別々に進められてしまうのです。
② データ基盤の分断が情報共有を阻害する
営業とマーケティングが異なるツールを使っていることも、サイロ化を加速させる要因です。例えば、マーケティング部門はマーケティングオートメーション(MA)を使い、営業部門はCRM(顧客管理ツール)を使うケースが一般的ですが、これらが統合されていないと、以下の3つが発生します。
- マーケティングが獲得したリード情報が営業にうまく引き継がれない(未共有)
- 営業がどのリードにアプローチしたかがマーケティングに共有されない(未可視化)
といった問題が発生します。結果として、営業は「マーケのリードは質が悪い」と感じ、マーケティングは「営業がフォローしない」と不満を抱き、組織の連携がさらに悪化します。(未連携)
③ 部門間の文化・評価制度の違い
営業とマーケティングでは働き方や評価制度の違いもサイロ化を加速させます。
営業は個人の成果が重視され、成約件数や売上額が評価指標になります。一方、マーケティングは分業、役割制のことが多く個人評価ももちろんありますが、チームで施策を企画・実行し、認知度向上やリード獲得の数値をもとに評価されることが一般的です。
この違いが「営業 vs マーケ」という構図を生み、お互いの業務に関心を持たなくなる要因になります。
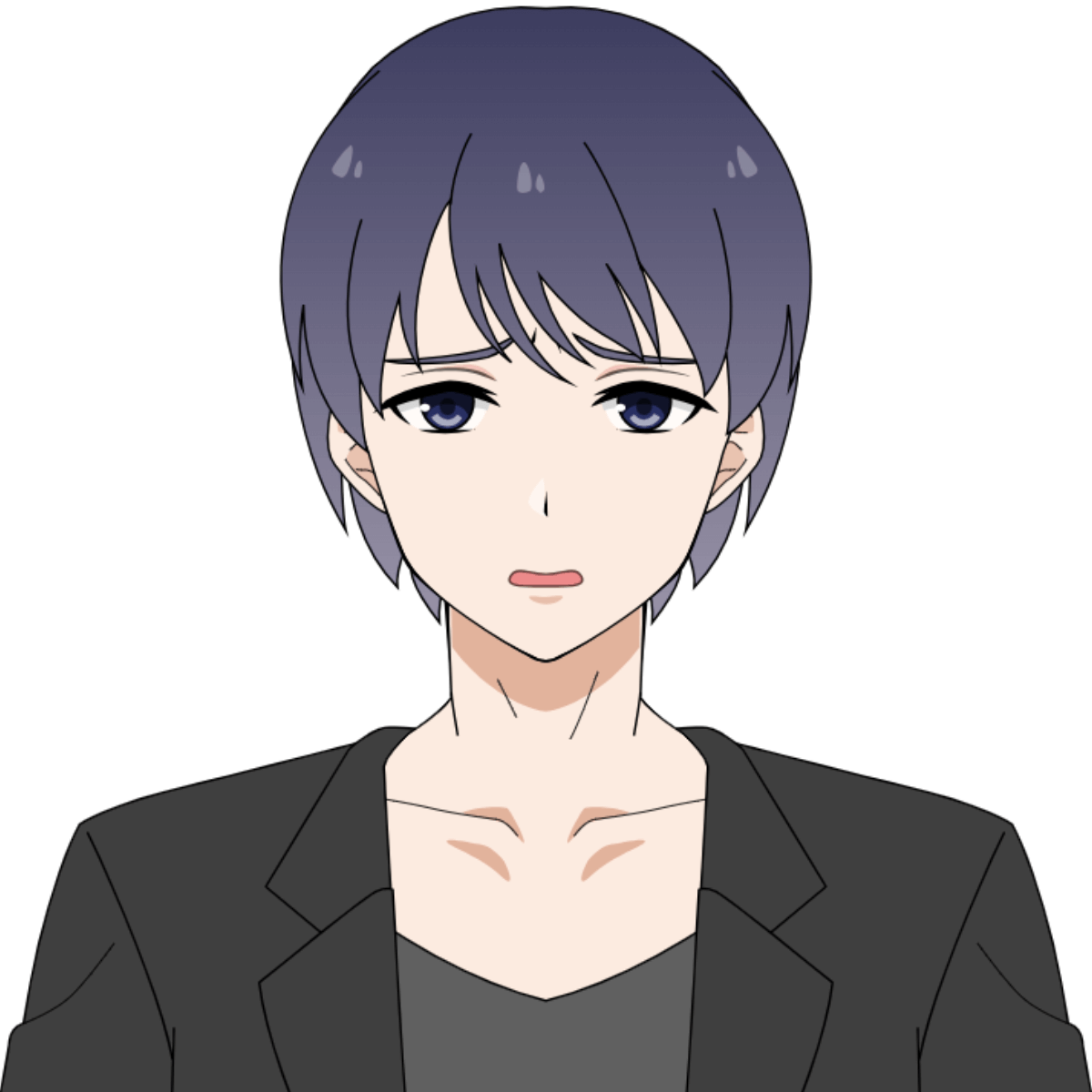
組織の中で一緒に平仄をあわせて動くって思っている以上に難しいのね
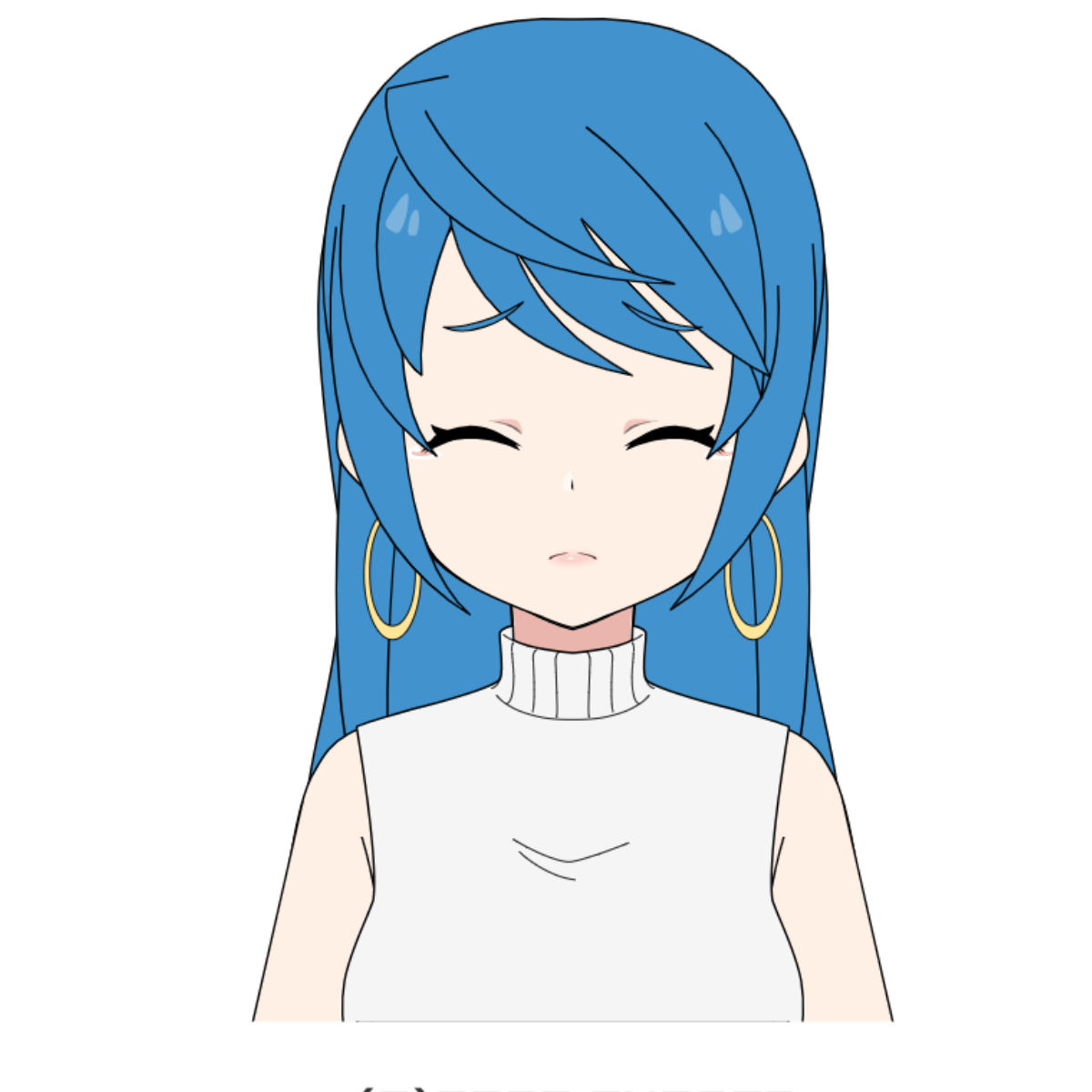
みんな自分の首を締めるようなことはしたくないのは当然よ。
サイロ化の予防とボトルネックを断ち切る方法
サイロ化が進むと営業・マーケティング・カスタマーサクセスが独立して動き、情報共有ができなくなります。
結果として、営業は「マーケのリードは質が悪い」と不満を抱き、マーケティングは「営業がフォローしない」と責任を押し付け合う状態に。
またサイロ化を防ぐには、発生してから対処するのではなく、事前に仕組みを整えることが重要です。特にBtoB企業では、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが密接に関わるため、早い段階でサイロ化の芽を摘む必要があります。
①KPIの統一と可視化
営業とマーケティングが別々のKPIを追っていると、どうしても対立が生まれます。
例えば、マーケティングは「リード数」、営業は「成約率」を指標にすると、マーケは数を増やすことを優先し、営業はリードの質に厳しくなるため、お互いの足並みがそろいません。
ここで必要なのは、「リードから成約までのコンバージョン率」や「顧客生涯価値(LTV)」といった、全体最適のKPIを設定することです。これにより、マーケティングも営業も同じゴールを目指すことができ、連携しやすくなります。
② 組織設計の段階で「連携」を前提にする
多くの企業では、営業とマーケティングが独立した(分断された)組織として設計され、結果としてサイロ化が発生します。
しかし、そもそも組織を「Revenue(収益)」という共通の目標で統一することができれば、部門の壁をなくすことが可能です。そのためには、最初から「Revenue Operations(RevOps)」を前提とした組織作りをすることが有効です。
③ 共通のデータ基盤を導入する
営業はCRM、マーケティングはMA(マーケティングオートメーション)、カスタマーサクセスはCSツールを使っている企業は多いですが、それぞれのツールが連携していないと、
- マーケティングが獲得したリード情報が営業に適切に伝わらない
- 営業が獲得した顧客情報がカスタマーサクセスに共有されない
という問題が起こります。
つまりデータの分断がサイロ化を引き起こす大きな要因なので、早い段階でデータ統合を進めることが重要です。例えば、CRM(Salesforce)、MA(Marketo、HubSpot)、BIツール(Tableau、Google Looker)を統合し、リアルタイムでデータ共有できる仕組みを構築することで、サイロ化を予防できます。
④ 部門横断チームの設置
組織の壁をなくすには、営業・マーケティング・カスタマーサクセスが同じチームとして動ける仕組みを作ることが効果的です。例えば、「レベニューオペレーションRevenue Operations(RevOps)」というチームを作り、各部門の連携を推進する役割を担わせることで、サイロ化を防ぐことができます。(レベニューオペレーションについては次の章で詳しく解説します。)
⑤ 経営層や管理職が主導して「文化」を作る
サイロ化はツールや組織設計だけで防げるものではありません。企業文化として「部門を超えた協力が当たり前」という価値観を浸透させることが重要です。そのためには、経営層が「RevOps」的な考え方を理解し、トップダウンで部門横断の連携を促すことが不可欠です。
組織のサイロ化解決なら
プロストイックが実績豊富
BtoB企業のデジタルマーケティングを成功させるためには、営業・マーケ・カスタマーサクセスの連携強化、営業のデジタルリテラシー向上、明確な役割分担、データ活用の強化が不可欠です。これらの施策を実行することで、企業の競争力を高め、売上の最大化を実現できるでしょう。
営業とマーケティングを統合的に管理する「Revenue Operations(レベニューオペレーション)」の導入
組織のサイロ化を解消し、営業とマーケティングを統合的に管理するための手法として「レベニューオペレーション:Revenue Operations(RevOps)」が注目されています。
レブオプス(RevOps)とは、営業(Sales)、マーケティング(Marketing)、カスタマーサクセス(Customer Success)を横断的に管理し、収益の最大化を目指す組織戦略です。
従来のように各部門が独立して動くのではなく、一つの「収益創出組織」として機能することを目指します。
なぜ今、レブオプス(RevOps)が必要なのか?
端的に言えばBtoBビジネスでは購買プロセスが複雑化し、顧客がオンラインで情報収集する割合が増えています。
そのため、マーケティング・営業・カスタマーサクセスがシームレスに連携し、顧客の意思決定をサポートすることが求められています。
しかし、サイロ化が進んだ組織では以下のような課題が発生しますが、レブオプス(RevOps)を導入すうることによってその課題を解決できるメリットがあります。
- マーケティングが獲得したリードのフォローが営業に適切に引き継がれない
- 営業が獲得した顧客情報がカスタマーサクセスに伝わらない
といった問題が発生し、結果としてビジネスの成長が妨げられます。
レブオプス(RevOps)導入のメリットと必要性
レブオプス(RevOps)を導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 組織全体で統一されたKPIを設定できる
「マーケはリード数、営業は売上、カスタマーサクセスはリテンション率」といったバラバラの指標ではなく、「リードから成約までのコンバージョン率」「LTV(顧客生涯価値)の向上」など、企業全体の収益を重視した全体最適の視点でKPIを設計できる。 - データ基盤を統合し、リアルタイムで可視化できる
CRM・MA・CSツールを統合することで、営業・マーケ・CSが共通のデータ基盤を持ち、リアルタイムで状況を把握できるようになります。これにより、顧客のフェーズごとに最適な対応が可能になります。 - リードから顧客維持までのプロセスを最適化できる
マーケティングが獲得したリードのうち、どのような属性の顧客が成約率が高いのかを分析し、より効果的なターゲティングが可能になる。 - 属人的な営業・マーケティングから脱却できる
従来のBtoB営業は「個人の経験や勘」に頼る部分が多かったですが、レブオプス(RevOps)の導入によってデータドリブンな意思決定が可能になります。
レブオプス(RevOps)を成功させるためのポイント
レブオプス(RevOps)を導入する際に重要なのは、「適切なツールの導入・運用」と「組織文化の変革」です。
- CRM・MA・BIツールの統合
Salesforce、HubSpot、Marketoなどのツールを連携させ、データを一元管理する。 - 各部門からの参加とシームレスな連携
初動は兼務になるが各部門からレブオプス(RevOps)チーム所属する人を集め各部門の意見を反映しやすくする - Revenue Operations専任チームの設置
収益最大化を目的とする専門チームを設け、各部門の連携を促進する。 - 経営層のコミットメント
レブオプス(RevOps)は部門横断の取り組みであるため、経営層が積極的に関与し、全社での実行を推進することが重要。
レブオプス(RevOps)はどんな組織にマッチするか
レブオプス(RevOps)は特に以下のような課題を持つ企業に適しています。
① 営業・マーケティングの連携が取れていない企業
「マーケのリードを営業がフォローしない」「営業のフィードバックがマーケに伝わらない」といった問題を抱える企業では、レブオプス(RevOps)が有効です。
② LTVを重視・サブスクリプション型ビジネスの企業
LTVを重視したり継続が前提のサブスクリプション系企業は「新規獲得→アップセル→継続利用」のプロセスを最適化することが重要です。そのため、マーケティング・営業・カスタマーサクセスが密に連携するレブオプス(RevOps)が適しています。
③ データドリブンな経営を目指す企業
レブオプス(RevOps)では、データを基に戦略を立て、PDCAを回すことが求められます。そのため、数値管理を重視する企業や、デジタル化を推進している企業にも適しています。
レブオプス(Revops)支援には中間管理職支援(上司代行)が非常にマッチする
レブオプス(RevOps)は既存の組織ではなく、部署・部門横断の新しい組織を創る必要があります。
基本的には各部門のメンバーが兼務で実行するのが初動の動きですが思うように進まないのが多くの企業の課題として挙げられます。
各組織間の意見を反映させて、組織の役割を機能として中間管理職がリードしていくことが求められますが、兼務の状況では難しいため中間管理職支援としてプロストイックが実行の支援もしております。
管理職の方の直下に実行支援のチームを敷くので方針や実施タスクに対して迅速に行動できますし目標達成に向けた合理的なアクションをチーム全体で行えます。
また各部門との調整も橋渡し役になるので、非定型タスクのマネジメント課題も解決可能です。
レブオプスの実行支援は
プロストイックが実績豊富
レブオプス(RevOps)でBtoB企業の成長を加速させる
営業とマーケティングの連携を強化し、組織のサイロ化を防ぐためには、レブオプス(RevOps)の導入が効果的です。
収益最大化を目的に、データの統合、KPIの統一、プロセスの最適化を行うことで、リード獲得から顧客維持までの流れをスムーズにし、BtoBビジネスの競争力を高めることができます。
今こそ、従来の部門主導型の考え方から脱却し、Revenue Operationsの視点で組織改革を進めるべきでしょう。
まとめ|営業とマーケティングが手を組めばBtoB企業の成長は加速する
ここまでの話をまとめるとBtoB企業がデジタル時代に競争力を維持し、成長を加速させるためには、営業とマーケティングが手を取り合うことが不可欠です。
従来は独立した部門として機能していた両者が、データとテクノロジーを活用して協力し合うことで、リード獲得から契約、さらにはカスタマーサクセスまでをシームレスに統合することが可能になります。
DXは営業とマーケの壁をなくす最大のチャンㇲ
BtoB企業の多くは長年にわたり営業とマーケティングを別々の部門として運営してきました。
しかし、デジタル化が進む現代では従来の分断された体制では競争に勝てません。DXを推進することで、営業とマーケティングの壁をなくし、よりスムーズな顧客対応が可能になります。
例えば、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入している企業は既に多いと思いますが、きちんと運用を行い部署間の連携を取り図ることができれば結果としてマーケティングが獲得したリードがどのようなコンテンツに興味を示したのか、営業がどのようなアプローチを行ったのかをリアルタイムで共有できます。
これにより、「リードの質が悪い」「営業のフォローが遅い」といった責任の押し付け合いを減らし、データに基づいた協力体制を築くことができます。
DXを営業とマーケティングの連携強化の機会と捉え、積極的に活用することで、企業全体の業績向上につなげることができます。
ツールや施策ではなく、「体制」こそ抜本的な仕組み(上司代行の活用)
デジタルマーケティングを導入する際、多くの企業が「ツールを導入すれば解決する」と考えがちですが、実際にはそうではありません。
最も重要なのは、営業とマーケティングが連携できる体制を整えることです。
例えば、CRMやMAを導入したものの、営業が活用できずに形骸化してしまったケースは少なくありません。これは、デジタルツールを使いこなせる人材が不足している、または組織全体として活用する文化が根付いていないことが原因です。
このような課題を解決するために、上司代行の活用が有効な手段となります。
上司代行は、デジタルマーケティングや営業支援の専門家が企業の中間管理職の役割を担い、組織の変革をサポートするサービスです。上司代行を導入することで、デジタル活用のノウハウを迅速に社内に浸透させ、営業とマーケティングの連携を強化することが可能になります。
上司代行は以下のような場面で特に効果を発揮します。
- デジタル施策を推進するリーダーが社内にいない場合
- 営業とマーケティングの連携をスムーズにしたい場合
- 社内にデジタルマーケティングの知見を蓄積したい場合
ツールを導入するだけではなく、実際に使いこなせる組織体制を構築することが、DX成功のカギとなります。
部署を超えたデータ活用が新たな成長戦略を生む
マーケティングの成功には部署を超えたデータ活用が不可欠です。
多くの企業ではマーケティング部門がリード獲得に関するデータを持ち、営業部門が顧客の商談データを持っているものの、それらのデータが統合されていないことが課題となっています。
例えば、マーケティング部門が獲得したリードのうち、どのような顧客が最終的に成約に至ったのか、そのデータが営業と共有されていなければ、次のマーケティング施策に生かすことができません。
逆に、営業がどのような情報を必要としているのかをマーケティング部門が理解できなければ、効果的なリード獲得施策を打ち出せません。
これを解決するためには、以下のような施策が必要です。(繰り返しになりますが、まとめとして改めてのお伝えになります)
- 営業とマーケティングが共通のKPIを設定し、データを共有する
- CRMやBIツールを活用し、部門横断的にデータを可視化する
- 定期的な会議やワークショップを開催し、データに基づいた意思決定を行う
データを部門間で共有することで、より精度の高いマーケティング施策が可能となり、営業活動の効率化にもつながります。
デジタル組織を変革し、BtoBビジネスの競争力を高めよう
デジタル化が進む現代において、BtoB企業が競争力を維持するためには、営業とマーケティングが連携し、データを活用する体制を整えることが不可欠です。
DXを推進することで、営業活動の効率を向上させ、マーケティング施策の精度を高めることが可能になります。
しかし、そのためには単にデジタルツールを導入するだけではなく、組織全体の意識改革が求められます。営業とマーケティングの役割を明確にし、部門間のデータ共有を促進することで、よりスムーズな顧客対応が実現できるでしょう。
また、デジタル変革をスムーズに進めるためには、社内に適切なリーダーが必要です。デジタル人材が不足している企業では、上司代行のような外部リソースを活用することで、変革を加速させることができます。
BtoB企業の未来は、営業とマーケティングの連携次第です。今こそ組織を変革し、デジタルの力を最大限に活用することで、企業の競争力を高めていきましょう。
BtoBのデジタル組織支援なら
プロストイックが得意
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック