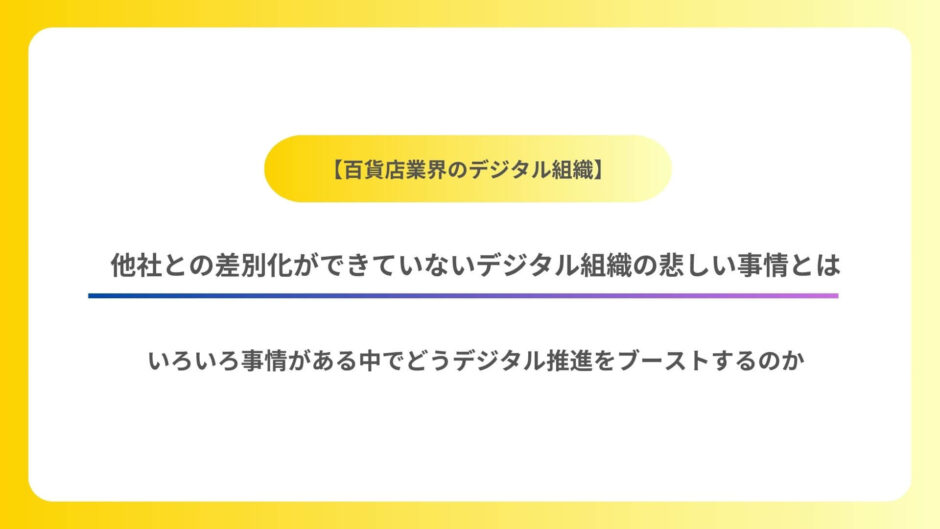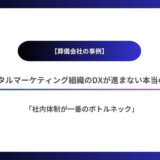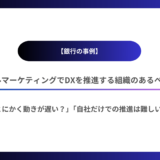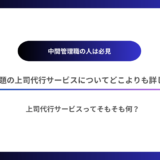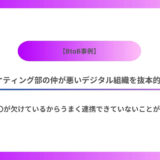皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
今回は百貨店のデジタル組織・デジタルマーケティング推進についてフォーカスを当てて解説をしていきます。
- 1.百貨店でデジタルマーケティング組織に属してる方
- 2.百貨店で働いていて、デジタル推進をしなければならない方
- 3.デジタル推進が百貨店内で遅れており外部の支援企業を探している方
ちなみに前回は葬儀業界や銀行などのデジタル組織事例について解説をしました。
百貨店業界のデジタルマーケティング組織はなぜ差別化できないのか
百貨店業界においてデジタルマーケティングの重要性は年々高まっています。
しかし、どの百貨店も似たような施策を打ち出しているため、消費者にとっての違いが見えにくくなっているのが現状です。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、競争力を高めようとするものの、ブランド力に依存しすぎた戦略では、本質的な改革には至りませんし、新規で顧客を獲得することが難しいように感じます。
本章ではまず百貨店業界が抱えるデジタルマーケティングの課題について掘り下げます。
どの百貨店も似たようなデジタル施策を打ち出している現状
現在、多くの百貨店がデジタルマーケティングに取り組んでいますが、その内容はユーザー目線ではどこも類似しているように感じます。
公式サイトでのキャンペーン告知、SNS運用、アプリでのクーポン配信など、基本的な施策はどの企業も共通しています。(無論、最低限の施策として上記で列挙したような施策は必須ではあります)
しかしここで提起したいのは
これでは、消費者にとって「この百貨店でなければならない」という理由が生まれにくいということです。
特に以下のような問題が具体的に見受けられます。
- ECサイトの差別化ができていない
百貨店のECサイトは、取り扱うブランドが似通っており、UIやUXの違いも大きくありません。そのため、消費者は価格比較やポイント還元率の違いで選ぶ傾向が強くなり、ロイヤルカスタマーの獲得が難しくなっています。 - SNSの発信内容が画一的
多くの百貨店がInstagramやX(旧ツイッター)を活用していますが、投稿内容が「新商品のお知らせ」や「期間限定セール」の告知に終始しているケースが目立ちます。消費者とのコミュニケーションを深める施策が不足しており、エンゲージメントが伸び悩んでいる企業も少なくありません。(一方的なセールの配信に留まっている) - オムニチャネル戦略の形骸化
店舗とオンラインを連携させるオムニチャネル戦略が重要視されていますが、実際には「ECと店舗で同じ商品を扱う」程度に留まっているケースが多いです。店舗ならではの付加価値(接客の質、体験型サービスなど)がデジタルと連携していないため、消費者にとっての利便性が十分に向上していません。
これらの問題を解決するためには、「単なるデジタル施策の導入」ではなく、企業としての強みを活かした独自の戦略が必要です。
ブランド力に依存しすぎてDXの本質を見失うリスク

百貨店業界は長年の歴史とブランド力を背景に成り立ってきました。
そのため、デジタルマーケティングにおいても「うちは有名百貨店だから自然とお客様が集まる」という前提のもと、DX推進が後回しにされているケースが見受けられます。
しかし、消費者の購買行動が変化する中で、ブランド力だけではもはや競争優位性を保てません。
ブランド力に依存することで、DXの本質を見失ってしまうリスクは次のような点に現れています。
- 既存の顧客層に頼り、新規顧客の獲得戦略が弱い
百貨店は長年の顧客を大切にする傾向が強く、新規層へのアプローチが十分に行われていない傾向にあります。(決算や経営戦略をみると企業によっては、対面接客に思いっきり舵を切っているケースもあります。) - データ活用の遅れ
DXの本質はデータを活用して顧客体験を最適化することにあります。しかし、多くの百貨店では、データの収集はしているものの、分析や活用に十分なリソースが割かれていません。購買データや顧客の行動データを活用し、パーソナライズドなマーケティングを展開できる企業はまだ限られています。 - テクノロジー導入が目的化している
DXの推進においては、新しいテクノロジーを導入することがゴールではなく、あくまで顧客体験を向上させるための手段であるべきです。しかし、一部の百貨店では「最新のECシステムを導入した」「AIを活用したチャットボットを設置した」など、施策自体が目的化してしまい、実際の業績向上に結びついていないケースが見られます。
こうした状況を打破するためには、ブランド力に頼るのではなく、消費者のニーズをデータに基づいて分析し、新しい価値を提供する姿勢が不可欠です。
そのためには、デジタルマーケティングの専門知識を持つ人材の育成や、上司代行のような外部リソースの活用が有効な選択肢となります。
百貨店業界におけるデジタルマーケティングはどの企業も似たような施策を展開しているため、消費者にとっての差別化が難しくなっています。また、長年のブランド力に頼ることで、DXの本質的な課題が見過ごされがちです。
今の百貨店業界に求められるのは単なるデジタル施策の導入(ネット上での値引きキャンペーン、ECでの商品販売)ではなく、消費者ニーズに即したデータ活用やパーソナライズドマーケティング(個別最適)の実施です。
百貨店業界が本格的なDXを成功させるためには、一例の方針として次のような取り組みが求められます。
- 独自のデジタル施策を構築し、競争優位性を確立する
- 既存のブランド力に依存せず、新規顧客の獲得戦略を強化する
- データ活用を推進し、消費者行動を可視化してマーケティング施策を最適化する
- デジタルマーケティングの専門人材を育成し、組織全体のデジタルリテラシーを向上させる
これらのポイントを実践することで、百貨店業界もデジタルマーケティングを活用した本質的なDX推進が可能になります。今こそ、デジタルを活かした競争力の強化に向けて、一歩踏み出す時です。
百貨店のデジタル推進なら
プロストイックにお気軽にご相談ください
百貨店のデジタル組織が抱える深刻な課題
百貨店業界では、デジタルマーケティングの重要性が増しているにもかかわらず、組織の構造や人材不足といった課題によってDX推進が進まない現状があります。
特に、人材不足や部署間の縦割り構造、経営層と現場の意識のギャップがデジタル戦略の足かせとなっています。本章では、百貨店のデジタル組織が抱える具体的な課題について詳しく掘り下げます。
DX推進を担う人材が圧倒的に不足している

百貨店業界において、DXを推進するための専門人材が極端に不足していることが、大きな障壁となっています。
デジタルマーケティングやデータ分析、オムニチャネル戦略を理解し、実行できるスキルを持った人材がいないため、DXの施策が形骸化してしまうケースが後を絶ちません。
また、多くの百貨店では、従来の業務を担う管理職がそのままDX推進の役割を兼任していることが多く、結果的に本来の業務負担が増加し、デジタル施策に十分なリソースを割くことができない状態に陥っています。
このような状況では、デジタル戦略を主導するリーダーの育成が急務ですが、現場の業務に追われている管理職にその余裕はありません。
こうした課題を解決する手段として、「上司代行」の活用が注目されています。上司代行とは、後ほど解説しますがデジタル組織の中間管理職として、業務のマネジメント支援や戦略策定、チームビルディング等をサポートする「中間管理職の方を支援」する体制を組むことです。
上司代行を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。
- DX推進を専門的に担う人材を確保し、デジタル戦略の推進と意思決定のスピードを加速
- 現場の管理職が本来の業務に専念できる環境を整備
- 中間管理職の直下に体制を敷くので社内のオペレーション業務は全て対応
DX推進を本格的に進めるためには、上司代行を活用し、適切な人材を確保することが重要なカギとなります。
部署間の縦割り構造がデジタル施策の連携を阻害
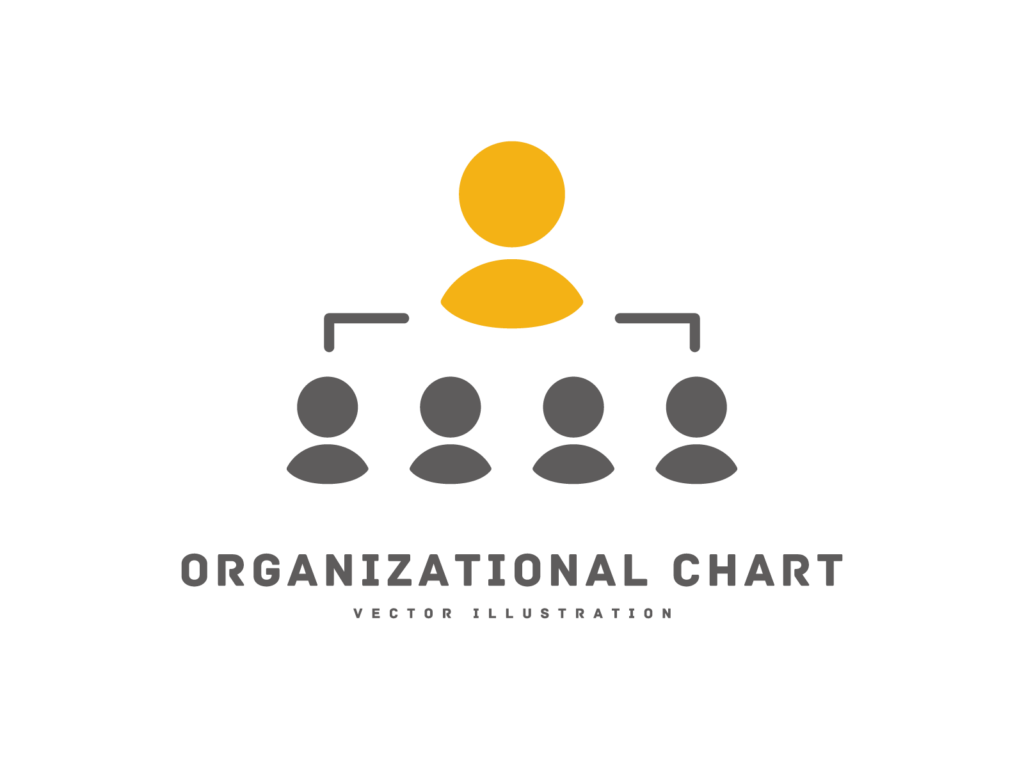
百貨店業界におけるデジタルマーケティングの課題の一つに、「部署間の縦割り構造」が挙げられます。マーケティング部門、EC部門、店舗運営部門、IT部門など、各部署が独立して運営されているケースが多いため、デジタル施策を横断的に推進することが難しくなっています。
たとえば、ECサイトの運営はIT部門が担当し、デジタル広告やSNS運用はマーケティング部門が行い、実店舗の販促は別のチームが管轄するというケースが一般的です。
このような状況では、部署ごとに異なるKPI(重要業績評価指標)が設定されるため、全社的なデジタル戦略が統一されず、顧客体験が一貫しないという問題が発生します。
具体的な問題としては、次のようなケースが見られます。
- ECと店舗で異なるキャンペーンを実施し、顧客が混乱
- データの連携不足により、顧客行動の一元管理・個別最適ができない
- 各部門が異なるツールを導入し、システム間の統合が進まない
この縦割り構造を解消するためには、部署横断的なデジタル推進チームを設置し、各部門の連携を強化することが不可欠です。また、上司代行を活用することで、部門間の橋渡し役として機能し、スムーズな連携を実現することも可能です。
デジタルマーケティングが現場主導ではなく経営主導になりがち
百貨店業界では、デジタルマーケティングの意思決定が経営層主導で行われる傾向があります。
本来、デジタル施策は顧客接点を持つ現場の意見を反映させながら設計すべきものですが
経営層が「DX推進をしなければならない」という意識だけで方針を決定し、実行面が現場の実態と乖離してしまうことが多々あります。
例えば、次のような問題が発生しています。
- 経営層が「最新のトレンド」として導入を決めたツールが実際には現場の業務と合わず活用されない(運用できない)
- 経営層が重視するKPI(売上向上・コスト削減)と、現場が求めるKPI(顧客満足度・エンゲージメント)が一致せず、成果が出にくい
- 店舗スタッフやマーケティング担当者の意見がデジタル戦略に反映されず、実行に対するモチベーションが低下
このような状況では、デジタル施策がうまく機能せず、「DXに取り組んでいるのに成果が出ない」という問題が生じます。
この課題を解決するためには、現場と経営層の間に立つ「デジタルリーダー」の存在が重要です。
デジタルマーケティングに精通したリーダーが、経営層と現場の間に入り、両者の意見を調整しながら戦略を策定することで、より実践的なDX推進が可能になります。しかし、百貨店業界にはこうしたデジタルリーダーが不足しており、戦略と実行のギャップが埋まらないケースが多いのが現実です。
ちなみに当社プロストイックの上司代行(中間管理職)支援サービスを導入すると外部の知見を取り入れつつ、経営層と現場の間に立つデジタルリーダーを確保することが可能になります。具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 経営層の意図を理解しつつ、現場の意見を戦略に反映する
- 最新のデジタル施策を把握し、適切なツールや手法を選定
- デジタル施策の成果を可視化し、経営層に対して納得感のある報告を行う
DXを本当に成功させるためには、構想を描く経営層とそれを実行する現場。そしてそのマネジメントや調整などを行う中間管理職の舵取りが非常に重要になります。当社プロストイックはその中間管理職の「意思決定」や「本来すべき業務への集中」をサポートします。(具体的には中間管理職の方のプレイヤー業務(手を動かす業務)をメインでサポートしていて短期的にも非常に効果を感じやすいと多くの企業から評価をいただいております)
経営主導の一方通行のデジタル戦略ではなく、現場の実態に即した柔軟なアプローチが求められます。そのためにも、デジタルに強い人材を確保し、組織全体でDX推進に取り組むことが不可欠です。
百貨店業界のデジタル組織伴走支援
ならプロストイックへ
DXを成功させる百貨店のデジタルマーケティング組織とは
百貨店業界においてDXを成功させるためには戦略や施策、ツール導入などを考えがちですが、適切な組織体制の構築が不可欠です。
つまり平たく言えば「誰が何を、どうするのか」の役割を組織的に体系立てることです。
しかし、デジタルマーケティングの推進にはさまざまな障壁があり、特にリーダー人材の不足や部門間の対立、デジタル人材の定着といった課題が存在します。本章では、DXを成功に導くために必要な組織のあり方について詳しく解説します。
DXを主導するリーダー人材の役割
百貨店がDXを成功させるためにはデジタル変革を牽引するリーダーの存在が欠かせません。
しかし、現実的にはデジタルマーケティングやDXの知識を持つ管理職が不足しており、現場と経営層の間で方向性が統一されないケースが多く見られます。
デジタルリーダーの役割は多岐にわたります。
- 経営層と現場をつなぐ架け橋となる(経営マネジメント)
- デジタルマーケティングの戦略を策定し、現場での実行をサポートする(現場マネジメント)
- 社内のデジタルリテラシーを向上させ、DXの定着を促進する(育成)
変革を阻む「デジタル部門 vs 既存部門」の対立

これは百貨店業界だけではないのですが、多くの企業ではデジタル部門と既存部門の対立がDX推進の大きな障壁となっています。特に、従来の営業・販売部門とデジタルマーケティング部門の間には、以下のような対立構造が見られます。
- デジタル部門:「データドリブンなマーケティングを推進すべき」
- 既存部門:「従来の接客・店舗販促が最も重要」
このギャップが埋まらない限り、DXはスムーズに進みません。
対立を解消するためには、両者の役割を明確にしつつ、共通のKPIを設定することが重要です。(たとえば、店舗とECの売上を総合的に評価する指標を設けることで、デジタル部門と販売部門が同じ目標に向かって協力できる環境を整える等。←これが一筋縄ではいかないのが組織なのですが)
デジタル人材の採用・定着に必要な組織文化とは

また百貨店業界ではデジタルマーケティングの専門人材を採用すること自体が難しく、仮に採用できたとしても長期的に定着しないケースが多く見られます。(採用費に数1,000万円かけても1年で離職されてしまえばかなりのコストの無駄になります)。
これは人間関係やキャリアなど様々な理由はありますが、百貨店の組織文化がデジタル人材とマッチしにくいことも原因の一つです。
デジタル人材が求める環境と、従来の百貨店の文化には大きなギャップがあります。
- デジタル人材:リモートワークや成果主義を重視
- 百貨店の文化:対面コミュニケーションや年功序列が根強い
このミスマッチを解消し、デジタル人材が働きやすい環境を整備するためには、柔軟な働き方の導入や評価制度の見直しが求められます。また、デジタル人材を孤立させない仕組みも重要です。
DX推進における外部パートナーとの効果的な連携方法(上司代行の活用)
百貨店のDX推進を成功させるためには外部パートナーとの連携が不可欠です。
しかし、多くの企業が代理店やコンサルティング会社に依存しすぎており、結果として自社にノウハウが蓄積されないという問題が発生しています。
効果的な外部リソースの活用方法として、内製的な体制を組みつつ、ノウハウも貯められる上司代行(中間管理職支援)の導入が挙げられます。
上司代行は従来のコンサルティングとは異なり、企業の中に入り込み(PCや座席、企業アカウントなどをお借りして)、実際の業務を担いながら組織を育成するという特徴があります。
また、上司代行は単なるアドバイザーではなく、社内での意思決定や部門間調整にも関与できるため、経営層と現場のギャップを埋める役割も果たします。(経営とのMTG参加、資料作成など)
特に百貨店業界のようにDXと従来の業務が複雑に絡み合う環境では上司代行のような実務レベルで動ける外部リソースの活用が効果的です。
百貨店業界で社内に入り込んだ
業務支援ならプロストイックまで
百貨店業界におけるDX成功のカギは、適切な組織体制を構築し、デジタル推進を担うリーダーを確保することです。しかし、現状ではDX人材の不足や部門間の対立が課題となっており、スムーズな変革が難しい状況にあります。
百貨店業界がDXを本格的に進めるためには、経営層と現場の連携を強化し、外部パートナーを戦略的に活用しながら、デジタルマーケティングの競争力を高めることが求められます。
百貨店業界の未来|DX推進で他社と差別化を図る方法
百貨店業界では従来のビジネスモデルのままでは競争優位性を維持することが難しくなっています。
消費者の購買行動がデジタルシフトする中、DXを活用した差別化戦略が求められています。
本章では、OMO戦略や会員制度のDX化、店舗スタッフのデジタル活用、KPI設定の方法について詳しく解説します。
OMO戦略でリアルとデジタルを融合
もう何十年も前から構想としては多くのリアル店舗をもつ企業が掲げているものではありますが、DXを推進する上で注目すべき戦略の一つが本質的なOMO(Online Merges with Offline)です。
これはオンラインとオフラインの垣根をなくし、シームレスな購買体験を提供する取り組みを指します。
(ここで言う「本質的なOMO」とは、現状垣根がなくなっていないことがほとんどでEC上での顧客体験を本質的に追求しようと提起しています。)
従来の百貨店は「店舗での接客と売上」が主軸でしたが、現代の消費者は「オンラインで情報収集し、店舗で体験し、ECで購入する」といった行動を取ることが一般的になっています。
この変化に対応するため、オンラインとオフラインを融合させた顧客体験の設計が必要になります。
あくまで一例で既に実施しているもの・できないものもあると思いますが具体的には、以下のような施策が考えられます。
- オンラインでの購買履歴や好みを分析し、店舗での接客に活かす
- アプリや会員サイトを活用し、来店前に商品情報を提供する
- 店舗在庫をリアルタイムで確認できるシステムを導入し、スムーズな購買体験を提供する
OMO戦略を成功させるには、データの統合管理が不可欠です。外部専門家を活用し、DXの知見を取り入れながら組織改革を進めることが重要になります。
リピーターを増やす仕組み
百貨店の強みの一つは長年の運営で築き上げたブランド力と、ロイヤルカスタマーの存在です。
しかし、従来のポイントカードや会員制度は「顧客主動」で来店と購入を積み重ねないとロイヤル化されない事がほとんどです。
来店による体験強化の前提として来店する顧客からしても遠方からくるだけでもかなりの体力を消費する(特に高齢者)のでそこに個別接客の余地を見出すことも検討に入るのかと思います。
- アプリと連携したデジタル会員証の導入(来店履歴や購買データの蓄積)
- 個別の購買履歴や来店数に基づいたクーポン配信(ECと連携し、再来店を促す)
- 会員ランクに応じたオンライン・オフライン統合型の特典提供(特別イベント招待、EC限定セールなど)
DX化のポイントは、単なるシステム導入にとどまらず、「会員データをどう活用するか?」というマーケティング視点を持つことです。
店舗スタッフがデジタルを活用できる環境を整備するには

百貨店のDX成功のカギを握るのは現場の店舗スタッフのデジタル活用です。
しかし、多くの百貨店では、デジタルマーケティングやデータ活用が「マーケティング部門やDX部門の仕事」となり、実際に顧客と接する店舗スタッフには十分に浸透していないケースが少なくありません。
デジタル施策を店舗で活用するためには、以下のポイントが重要になります。
- スタッフが直感的に使えるシステムの導入(難しい操作を求めない)
- 店舗業務と連携したデジタル施策の仕組み化(接客中に活用できるデータ提供)
- デジタルリテラシー向上のための研修の実施(実践的なトレーニング)
例えば、ある百貨店では、スタッフ向けのデジタル研修を導入し、接客時にタブレットを活用することで、顧客ごとの購買履歴を確認しながらパーソナライズドな提案を行う施策を実施しました。
その結果、売上向上だけでなく、顧客満足度の向上にもつながるという成果を得ることができました。
DXを進める際は上司代行を活用して店舗スタッフのトレーニングをサポートすることも有効です。外部のデジタル専門家が実践的な研修を提供することで、現場に即したスキルを習得できる環境を整えることができます。
DX推進のKPI設定と効果測定の具体的な方法
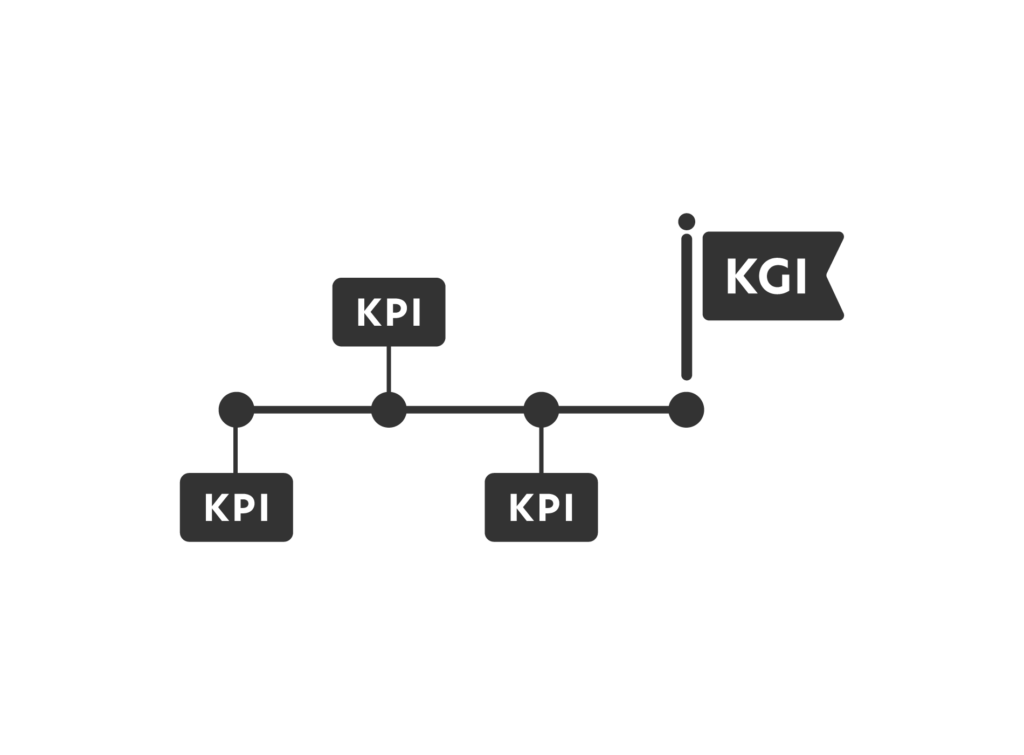
DXを推進する上で重要なのが、適切なKPIを設定し、効果を測定する仕組みを構築することです。しかし、多くの百貨店では、DXのKPI設定が不明確(あるけども体系化されていない)であり、結果としてDX施策が形骸化してしまう問題があります。
DXのKPI設定のポイントは、デジタル施策とビジネス成果を直結させることです。具体的には、以下のようなKPIが考えられます。これも既に取り入れている企業も多いと思うので、まだ未実施の企業を想定した一例になります。
- OMO施策のKPI例:ECサイト経由で来店した顧客数、オンライン予約後の購入率
- 会員制度のKPI例:アプリ会員の登録率、クーポン利用率、リピート率
- 店舗スタッフのデジタル活用KPI例:タブレット活用率、デジタル経由での売上比率
さらに、DXの効果測定を行う際には、短期的な指標だけでなく、中長期的な成長指標を設定することも重要です。
たとえば、OMO施策の効果を測定する場合、1ヶ月単位の売上変化だけでなく、半年〜1年後のLTV(顧客生涯価値)も考慮することで、より正確な評価が可能になります。
百貨店業界がDXを成功させるためには、OMO戦略の導入、会員制度のDX化、店舗スタッフのデジタル活用、KPIの明確化といった施策が必要不可欠です。しかし、DXを推進するには多くの課題があり、特にデジタル人材の不足や組織間の連携不足が大きな障壁となっています。
この問題を解決するためには、自社だけで推進を図るのではなく内製的な外部リソースの上司代行を活用し、外部の専門家と連携しながらDXの知見を取り入れることが有効な戦略となります。
百貨店企業のでデジタル施策
推進はプロストイックまで
まとめ|百貨店がDXで生き残るために今すぐ取り組むべきこと
百貨店業界は急速に進む消費行動の変化やEC市場の拡大により、従来のビジネスモデルが通用しなくなりつつあります。
今後、生き残るためにはDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、顧客体験を向上させる施策を講じることが不可欠です。本章では、百貨店がDXを成功させるために今すぐ取り組むべきポイントについて解説します。
旧来のビジネスモデルからの脱却が急務
百貨店業界は、長年にわたりブランド力と立地の優位性を活かした「待ちの商売」を展開してきました。しかし、ECサイトの台頭や消費者の購買行動の変化により、このモデルはもはや通用しなくなっています。
従来の百貨店のビジネスモデルは、主に以下の要素に依存していました。
- テナント収入に頼る運営形態(店舗が売上を上げることで収益を確保)
- 紙のポイントカードや従来型の会員制度による顧客管理
- 接客を重視したリアル店舗での体験価値の提供
しかし、現代の消費者はオンラインで情報収集を行い、価格や利便性を重視した購買行動を取る傾向が強まっています。
この変化に対応するためには、「百貨店のDX化=ECの導入」という単純な発想ではなく、リアル店舗の強みとデジタル技術を融合させたビジネスモデルへの変革が求められます。
例えば、OMO(Online Merges with Offline)戦略を活用し、顧客がオンラインとオフラインを自由に行き来できる仕組みを整備することが必要です店頭の在庫確認やオンライン注文の即日受取サービスを提供し、消費者の利便性を高めるなど家電量販店やアパレル店舗などで導入している施策なども有効です。
また、百貨店ならではの「接客力」をDXと組み合わせることも重要です。
例えば、AIを活用した顧客データ分析をもとに、パーソナライズされた接客を実施することで、従来の「誰にでも同じ接客をするスタイル」から脱却し、データドリブンな個別接客が可能となり1人あたりの体験や満足度が向上できます。
DX成功の鍵は「組織体制」と「人材育成」にある(上司代行の活用)
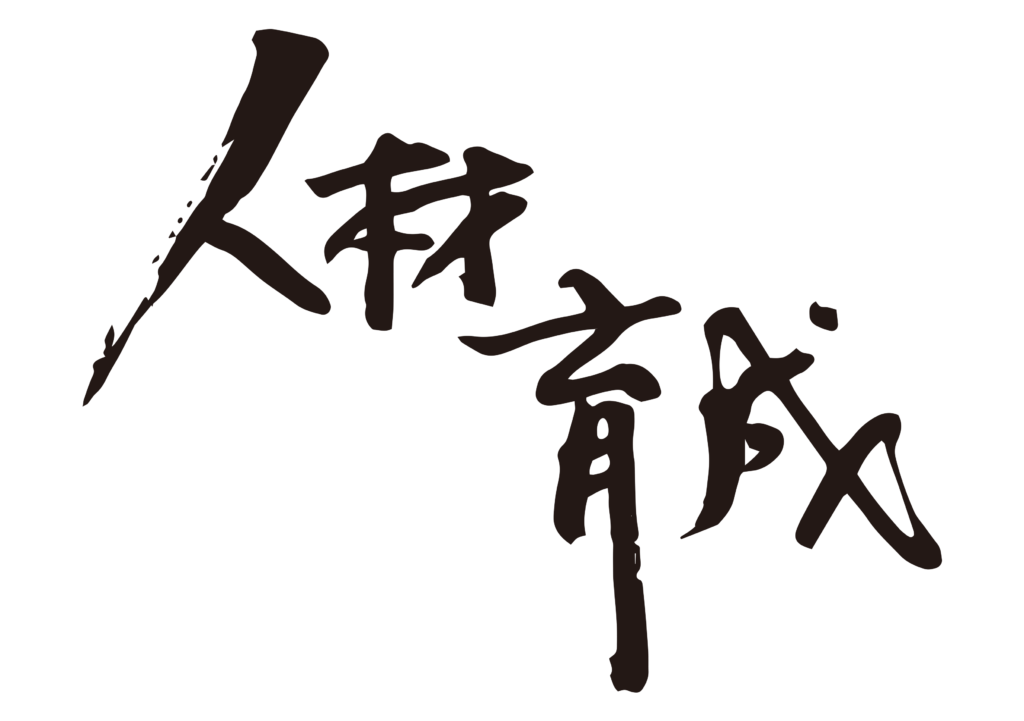
百貨店のDX推進が進まない大きな要因の一つに、「組織体制」と「人材不足」の問題があります。特に、DXをリードするデジタル人材が不足しており、マーケティング部門とIT部門の連携が不十分なケースが多く見られます。
DXを成功させるためには、以下の2つの改革が不可欠です。
- 組織の在り方を変える|DX専任チームの設置と役割の明確化
多くの百貨店では、マーケティング部門とIT部門が分断されており、デジタル施策の実行がスムーズに進んでいません。この問題を解決するには、DX推進チームを設置し、デジタル施策を一元管理できる体制を構築することが必要です。 - デジタル人材の育成と外部リソースの活用
百貨店業界では、DXを推進できる人材が社内に不足しているケースが多く見られます。この課題を解決するためには、内部の人材育成と外部リソースの活用を並行して行うことが重要です。
上司代行(中間管理職支援)はデジタルマーケティングのノウハウを持つ外部の専門家を組織(内製的)に取り入れる手法です。
これにより、社内にデジタルスキルを浸透させつつ、プレイングマネージャーの業務負担を軽減して意思決定のスピードを上げたり、本来すべきマネジャー業務に集中することが可能になります。
百貨店ならではの強みを活かしたデジタル戦略を構築しよう
百貨店業界のDX推進では、単にデジタル施策を導入するだけでは不十分です。
競争優位性を確立するためには、百貨店ならではの強みを活かしたデジタル戦略を構築することが重要になります。
ここまでをまとめると百貨店の強みには以下のような要素があります。
- 長年にわたるブランド力と信頼
- 高品質な接客サービスと顧客との関係性
- 富裕層や固定客の強いロイヤリティ
これらの強みを活かしながらDXを進めるためには、以下のような施策をぜひご検討にいれてみてはいかがでしょうか。既に取り組んでいるのであれば、より成果を図るために改善のスピードを上げていきましょう。
- 富裕層向けのパーソナライズドマーケティングの実施(AIを活用したターゲティング)
- VIP向けのオンライン接客や限定イベントの開催(OMO施策の強化)
- 高級ブランドとのコラボレーションによる独自ECサイトの展開
例えばVIP会員向けにオンライン限定のコンシェルジュサービス提供は、特別な商品提案を行うことで売上向上を目指します。このように、百貨店の持つリアルの強みをデジタルと組み合わせることで、他社との差別化を実現できます。
DXを推進し、百貨店の未来を切り開こう
百貨店業界のDXは単なるデジタル施策の導入ではなく、組織体制の見直しとデジタル人材の育成を含めた包括的な取り組みが求められます。
まとめになりますが今後百貨店が生き残るためには、以下のポイントに注力することが重要です。(参照の方針)
- 従来のビジネスモデルからの脱却(OMO施策の導入、デジタルとリアルの融合)
- DXを推進できる組織体制の構築(専任チームの設置、デジタルと既存部門の連携強化)
- デジタル人材の確保と育成(上司代行の活用、外部リソースの積極的導入)
- 百貨店ならではの強みを活かしたデジタル戦略の構築(高品質な接客とデジタル施策の融合)
当たり前のことを記載はしていますが、様々な社内事情でDXの推進は決して簡単ではないことが多いです。しかし、適切な組織改革と戦略を講じることで、百貨店の未来を切り開くことができるのです。
以上、既に取り入れている施策、これからの施策、検討している施策などそれぞれいろいろな構想はありますが、デジタル施策を推し進めるには「体制」と「各部門・現場」との連携が必要不可欠です。
業務が逼迫していて「中間管理職(プレイングマネージャー)」が業務過多になっている場合、ぜひ上司代行(中間管理職支援)をご活用ください。
プロストイックの上司代行(中間管理職支援)は管理職の方の直下に専属のチームを構築して、管理職のプレイヤー業務(社内のオペレーション業務や手を動かす業務)を巻き取り、マネジメント業務(部下の育成・現場マネジメント)を補佐します。
多くの企業で導入が進んでいるのでぜひご活用いただけますと幸いです。
百貨店企業のでデジタル施策
推進はプロストイックが強い
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック