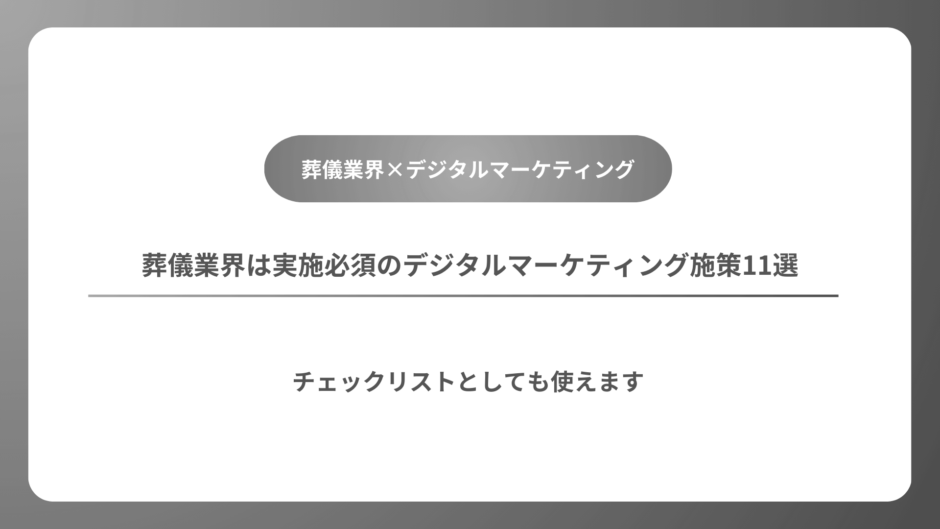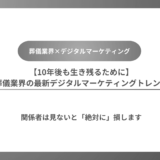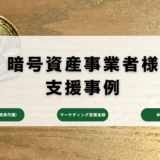本日は前回に続いて葬儀業界のデジタルマーケティングに関する記事です。
ちなみに前回はこちらの内容をご紹介しました。
この記事がおすすめな方
・葬儀業界でデジタルマーケティングをこれから推進する方
・葬儀業界でデジタルマーケティングを実施しているが施策が頭打ちの方
・どんなマーケティング施策が効果的か悩んでいる方
葬儀業界におけるデジタルマーケティングの施策について
葬儀業界は基本的に高齢層をターゲットとしていることが多く業界的に外部から見れば「やや暗い」という印象があるとのことですが、他業界と変わらず営業活動もするしマーケティング施策も実施しています。
多くの企業が未だに看板や新聞広告といった従来の広告手法を重視していますが、コロナ禍をきっかけにデジタルでのマーケティングを導入している企業が多くなっています。
今回は葬儀業界で必須となるデジタルマーケティング施策についてさまざまな視点から解説します。
未だに看板やラジオ、新聞広告を主流としている企業が多い

一方で「高齢層ターゲット=デジタルにタッチポイントがない=スマホ使わない」と考えるマーケティング担当者の方も多く、看板や新聞広告、ラジオといった広告手段はいまだに根付いていて地域密着型の葬儀会社が長年活用している定番の手法です。
特に地元の顧客層をターゲットとする場合、このようなアナログ広告は一定の効果を発揮します。
当人が葬儀の準備をする場合は「聞いたことがある」「見たことがある」とのことで目にした看板広告の葬儀会社が「想起」されて問い合わせをするというストーリーが確かにあります。
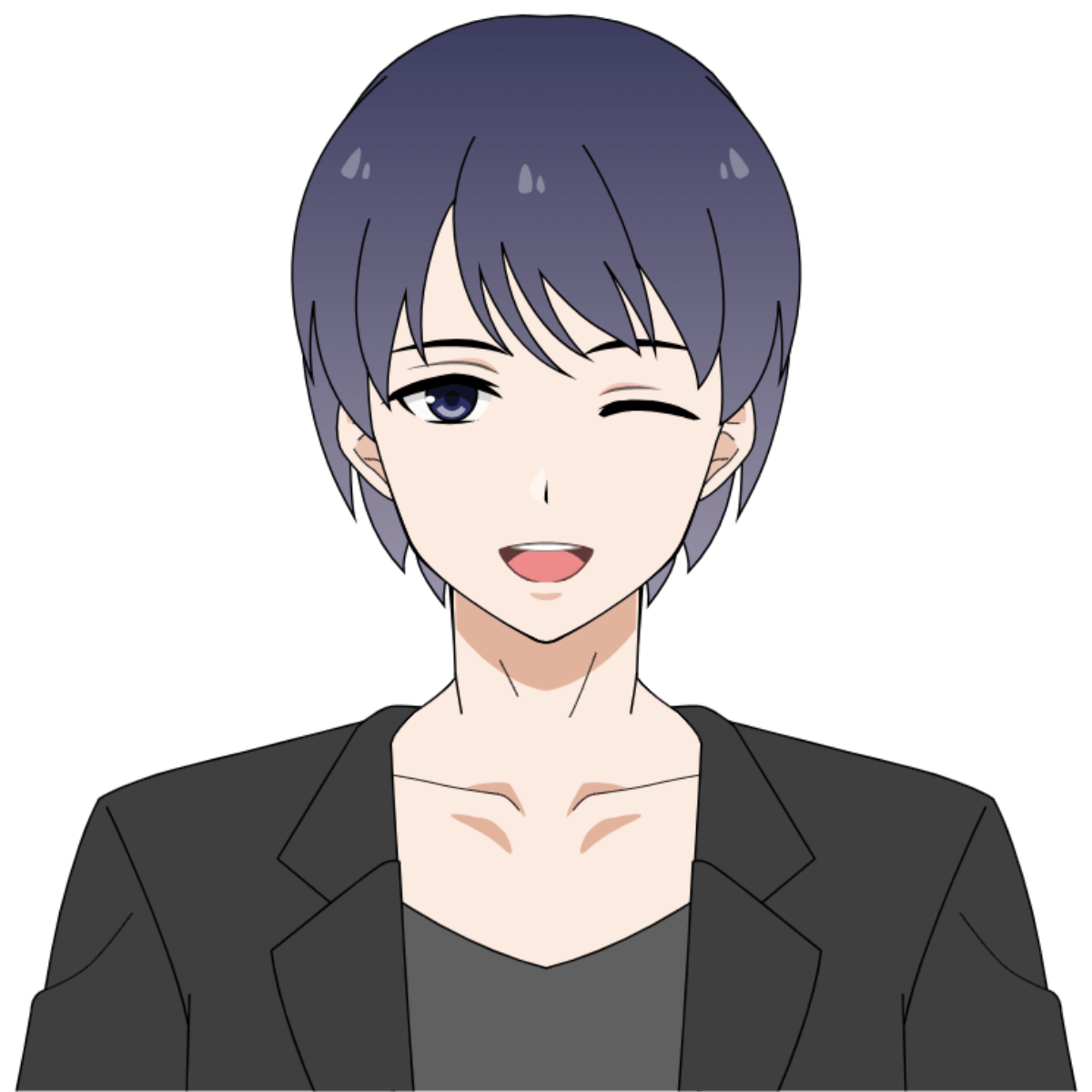
確かに僕も「バイト募集中時給5万円」の看板見つけてちょっと問い合わせしようか迷ったことある
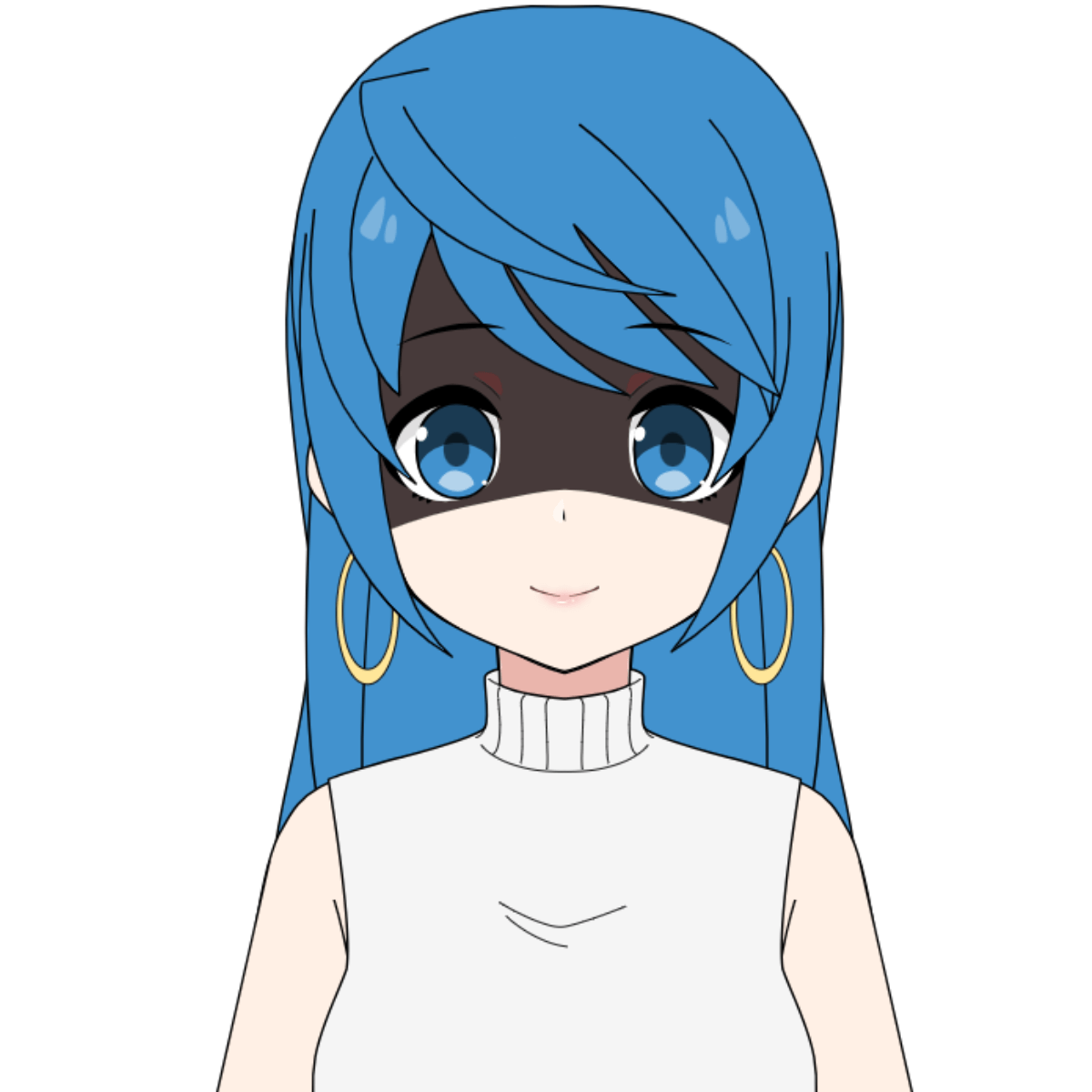
それ闇バイトではないかしら、、
しかし、時代の流れとともに情報収集の手段が多様化し、インターネットが主役となった現代においてはこれらの手法だけでは新たな顧客層にアプローチすることが難しくなっています。
例えば緊急で葬儀が必要になる場合、当人が調べられない場合ご家族が手配を行う際に「地名+葬儀」「緊急 葬儀」といったキーワードで調べて出てきたところに問い合わせをする流れもありますし、普通に当事者の方がネットで検索をすることもあります。
確かに看板広告やテレビCMも活用はしていいのですが、そこに一辺倒ではなくデジタル上にもタッチポイントを増やすことをした方がよいでしょう。
今も看板や新聞に頼りきっている企業は、一度現状を見直してみる必要があるかもしれません。
ターゲットとなる高齢層も実はスマホを使いこなしている

「高齢者はスマホを使わない」という認識はもう過去のものです。
総務省の調査によれば、高齢者のスマートフォン普及率は年々上昇しており、葬儀に関する情報をインターネットで検索するケースも増えています。
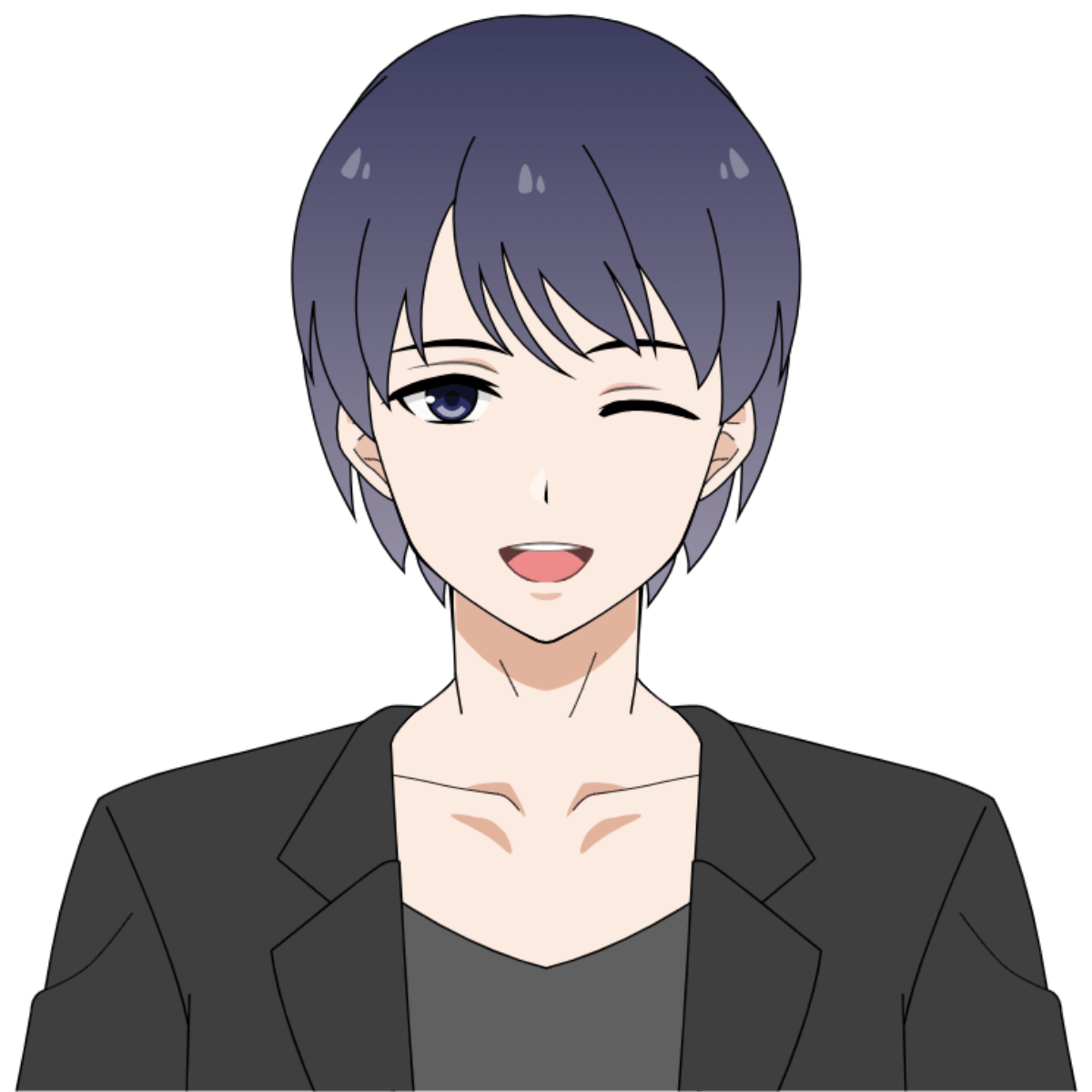
僕のおじいちゃんもめっちゃスマホ使ってるよ!tiktokとかイチナナとかよく見てるね
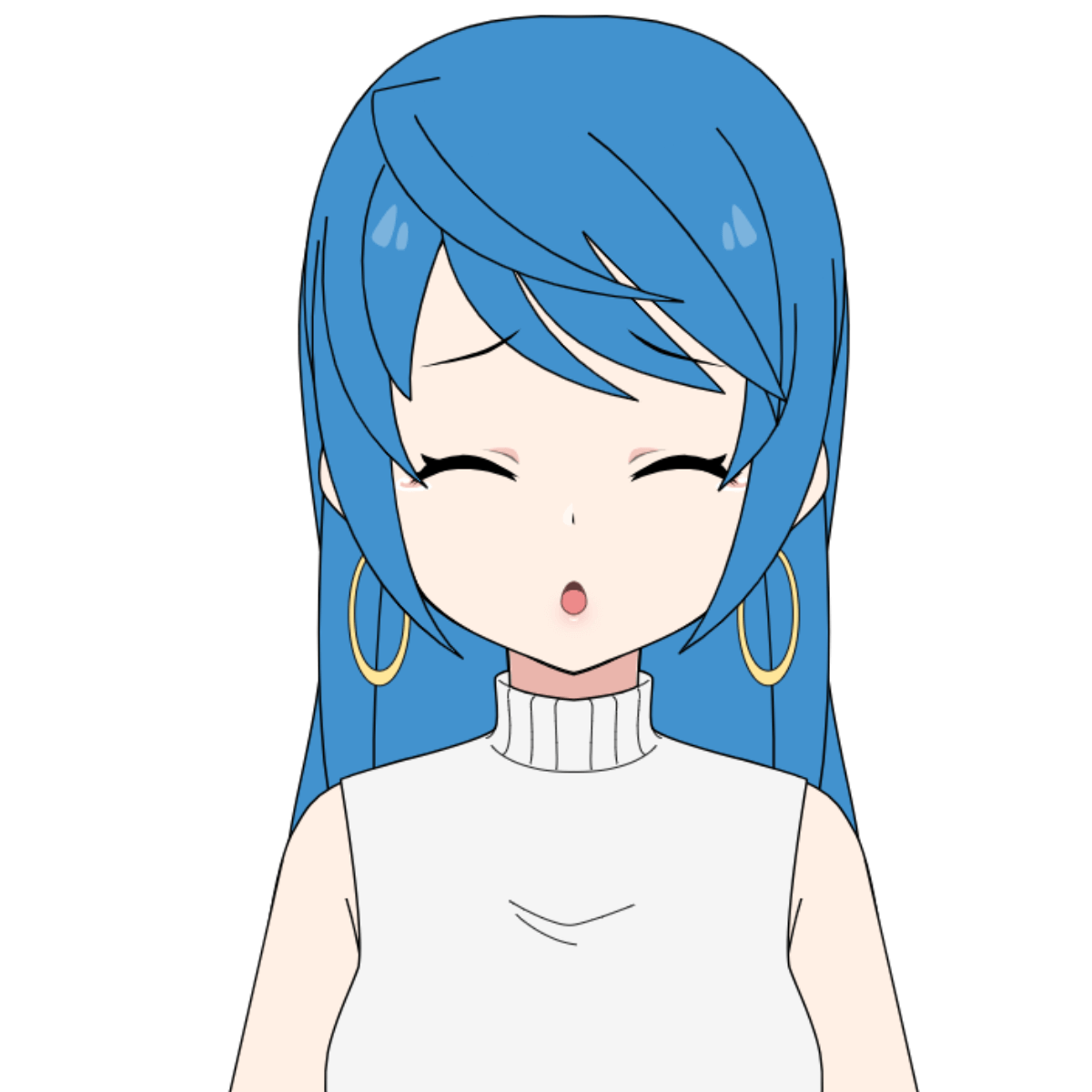
わ、若いわねあなたのおじい様
特に「家族葬 格安」や「地域名+葬儀場」といった検索キーワードは子世代だけではなくターゲットである高齢層が自分自身で検索をしている可能性が高いです。
このような背景を踏まえ、ターゲット層がスマホを使っていることを前提にしたデジタルマーケティング施策を立案することが求められます。
ぜひ葬儀業界の皆様はできてる・できてないをチェックしてください
自社がどれだけデジタルマーケティングに対応できているかを確認することは、業績向上の第一歩です。
本記事では他業界では一般的に取り入れられているデジタルマーケティング施策をご紹介します。
基本的なSEO対策やWeb広告、SNS活用ができていない場合、競合他社に遅れを取る可能性があります。「とりあえず看板を出しておけば大丈夫」という発想から脱却し、次のステップに進む準備を整えましょう。
Web広告
まずはweb広告です。web広告の強みは特定のターゲット層(年代、性別、地域など)にピンポイントでリーチすることができる非常に強力なツールです。
GoogleやYahoo、Microsoftの広告プラットフォームを活用することで、潜在顧客の目に留まる機会を格段に増やすことができます。Web広告の基本的な種類について見ていきましょう。
リスティング広告(Google・Yahoo・Microsoft)

多くの葬儀会社の方が既に取り入れられているのがこのリスティング広告かと思います。
リスティング広告は検索結果ページの上部や下部に表示される広告で、ユーザーが入力したキーワードに基づいて表示されます。
「葬儀 東京」「家族葬 格安」などのキーワードを設定し、潜在顧客に最適な情報を届けることが可能です。
また、クリック課金制であるため、広告費を効率的に管理できる点がメリットです。
葬儀業界でリスティング広告を活用する際には、地域名を含むキーワードや特定のサービスに特化したキーワードを設定することが重要です。たとえば、「練馬区 家族葬」や「火葬式 おすすめ」といったニッチなキーワードを狙うことで、競合を避けながら効果的な集客が可能です。
誤解がないようにお伝えするとリスティング広告やこの後ご紹介するディスプレイ広告も看板広告やチラシと異なり出して終わりではなくきちんと「運用」することで成果の向上が起こります。
(運用についてはこの後のパートでいやになるほど解説します)
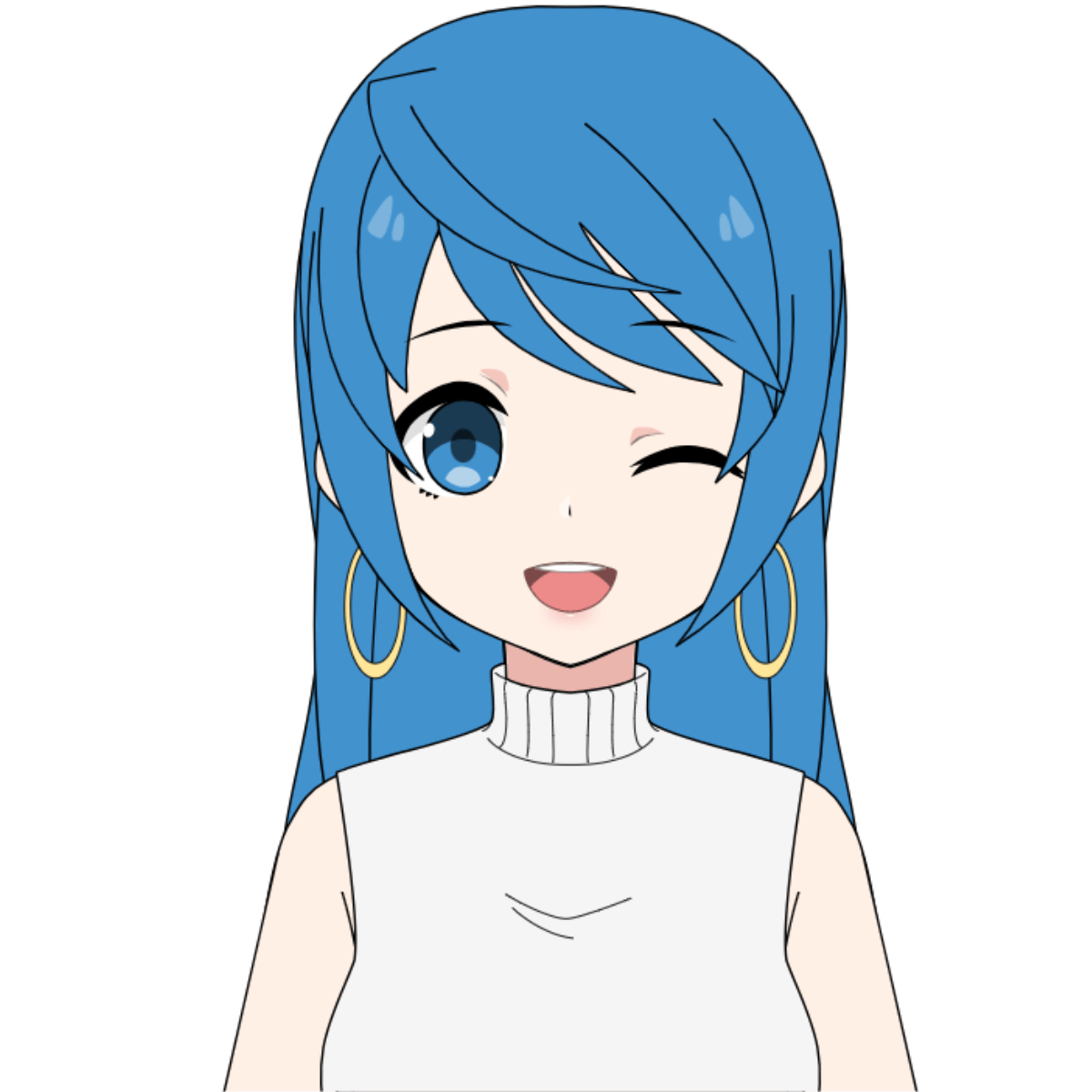
運用の重要性については後で詳しく解説しますね
ディスプレイ広告(Google・Yahoo・Microsoft)
ディスプレイ広告はWebサイトやアプリのバナーや画像広告として表示される形式です。
リスティング広告の文字だけと異なり、画像バナーで表示されるため視覚的に訴求力が高く葬儀場の雰囲気や価格プラン、ベネフィットを魅力的に伝えるのに適しています。
またリターゲティング広告として利用することで、以前に自社サイトを訪れたユーザーに再アプローチすることも可能です。
この手法は、認知度向上を目指す場合や、競合との差別化を強調したい場合に特に効果を発揮します。
葬儀業界では家族葬や直葬といった具体的なサービス内容を視覚的に伝えることで、ユーザーの関心を引きつけることができます。
ディスプレイ広告は多くのユーザーにアプローチできてインプレッション(表示回数)は取れるがコンバージョン(申し込み)が取れないという印象が多くあるようですが、そんなことはありません。
先ほどご紹介したリターゲティング機能を活用することはもちろん、GA4などを使った実際に訪問したユーザーが取っている行動分析、アトリビューション分析を行い本当に意味があるのかを把握する必要があります
ユーザーの行動やニーズが多様化している以上、直接的な成果だけではなく、多角的に成果を見る必要があります。
アフィリエイト

続いてはアフィリエイトです。アフィリエイトは広告主が提携メディアに自社の内容を掲載する代わりに報酬を支払う成果報酬型の広告手法です。
このアフィリエイト手法は実は取り入れていない葬儀会社・葬儀関連メディア企業が多い印象があり少し詳しく解説します。
まずアフィリエイトとは先ほども簡単に説明しましたが「成果報酬型の広告手法」です。
成果地点をどこに設定するのかにもよりますが、成果が発生した時点で報酬を支払うという仕組みなので、例えば「資料請求」「問い合わせ」「本申し込み」「メール仮登録」などいろいろな成果地点があります。
リスティング広告と比較するのであれば、リスティング広告は検索した検索結果上部に表示される広告ですが、アフィリエイトはポイントサイトや他メディアの記事内、あるいはアフィリエイターが記事用LPを作ってその広告内に掲載されることもあります。
掲載できる媒体はいろいろな媒体があるので次の見出しで詳しく解説していきます。
ポイントサイトやSEOメディア・広告メディアもある
ここではアフィリエイトの掲載媒体(メディア)について解説します。
まずはポイントサイトです。葬儀業界との相性は未知数ですが、アフィリエイトではポイントサイトを多く用いられます。
ポイントサイトはもっぴー、ハピタス、ポイントタウンなどがよく名前に上がり、ユーザーがポイントサイト経由で申し込みをすることで現金やマイル、クーポンなどに換金できる仕組みがあります。
ポイントサイトも成果報酬型のアフィリエイトなのでどれだけクリックをされても費用はかからず成果地点到達で報酬が圧制する仕組みです。なので、コストを抑えながら多くのユーザーにアプローチできる手法です。
またアフィリエイトはSEOメディアや広告メディアを通じて特定の検索キーワードで露出を増やすことも可能です。具体的にはSEOに強いメディアや広告でアフィリエイトをしながら稼ぐ媒体に依頼をすることになります。
このように、アフィリエイトはさまざまな選択肢を組み合わせて活用することで、集客の幅を広げることができます。
葬儀業界では特定のターゲット層にマッチしたメディアを活用することで効果的に集客することができます。
以降の見出しについても同様の流れで、各施策の具体的な解説を続けていきます。すべての施策を組み合わせて活用することで、葬儀業界でのデジタルマーケティング効果を最大化することができます。
マッチしそうなASPを探す
ここまででご紹介してきた内容は全てアフィリエイトを統括するプロバイバー(アフィリエイトサービスプロバイダー(通称ASP))に依頼をかけることで可能です。
選定する際には、葬儀業界と親和性の高いメディアを探すことが重要です。たとえば、終活情報サイトや地域特化型メディアは、ターゲットとなる顧客層に直接リーチできる可能性が高いです。
また信頼性の高いASPを選ぶことで、より質の高いトラフィックを確保できます。
SEO(コンテンツマーケティング)

SEO(検索エンジン最適化)は、デジタルマーケティングの中核をなす施策です。
葬儀業界においては実施している企業は半々で(この理由は後程解説)、関連キーワードで検索結果の上位に表示されることで多くの潜在顧客を獲得できます。
特に独自性のあるコンテンツと地域に特化した戦略が成功のカギを握ります。
ローカルキーワードの獲得がカギ
葬儀業界では、「地域名+葬儀」や「地域名+家族葬」など、ローカルキーワードの獲得が競争のポイントとなります。
たとえば、「横浜 家族葬」や「名古屋 葬儀 費用」などの検索は、地域の消費者が葬儀場を探している証拠です。これらのキーワードで上位表示されることで、地元での存在感を高められます。
また、地域の文化や風習に配慮したコンテンツを作成することも重要です。
たとえば、「○○市の葬儀でよく行われるお別れの方法」や「地域特有の法要の進め方」といった記事は、顧客にとって有益な情報となり、SEOの評価向上にもつながります。
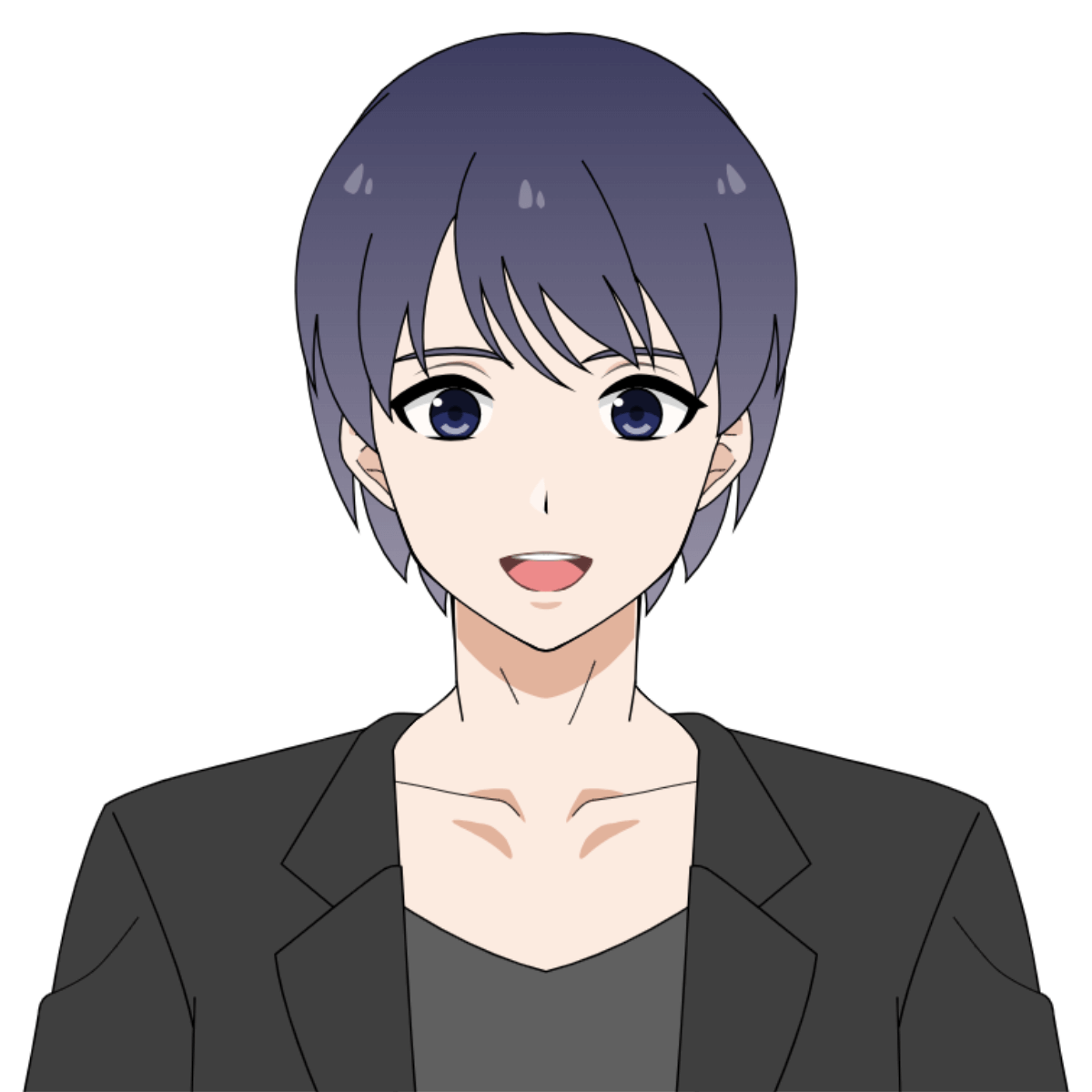
その地域特有のコンテンツを作ることができるのも地域に根づいているからの強みだね
みんなが意外と知らない「地元あるある」も実はあったりして
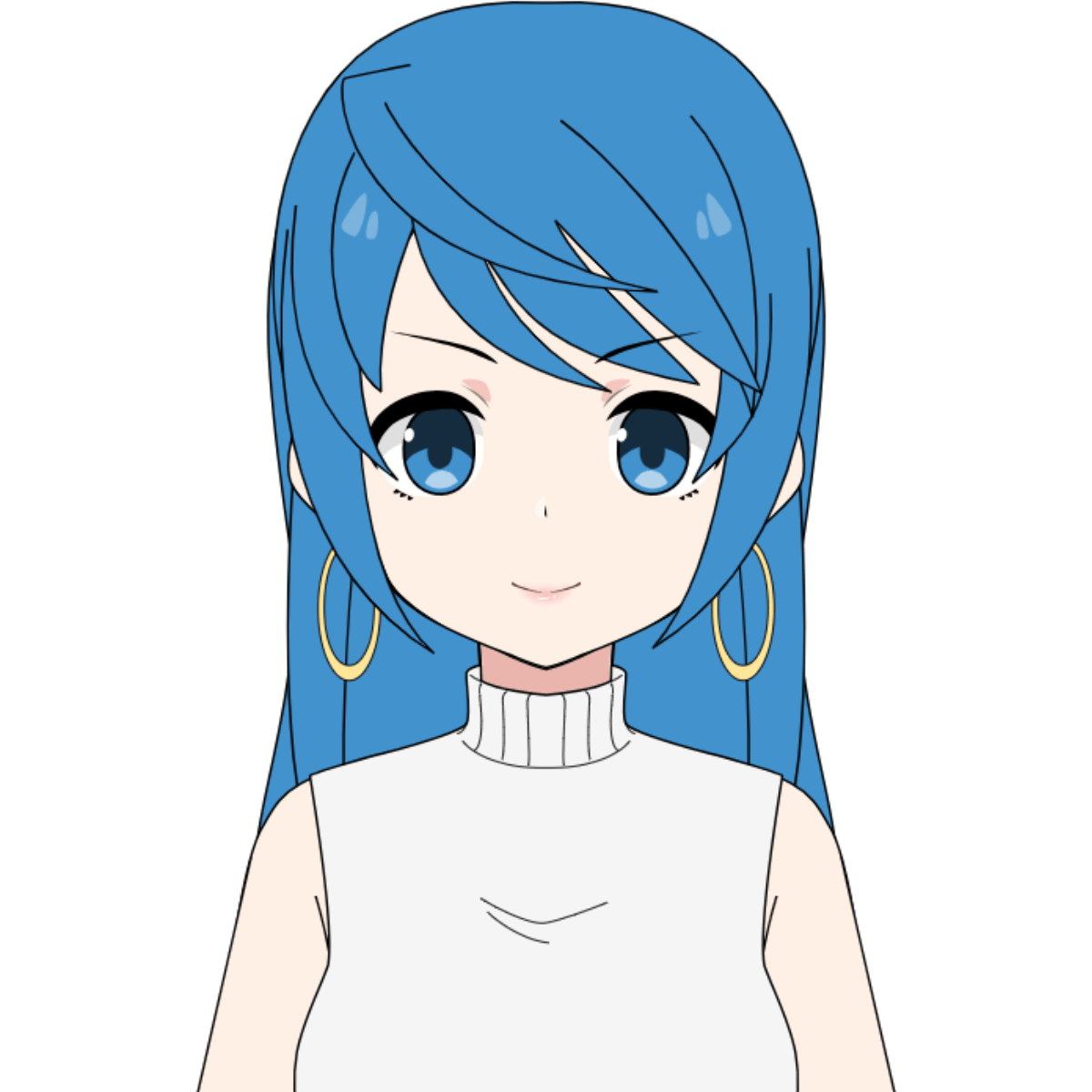
地元好きの方って以外と多いものね
一般的な説明記事より独自のコンテンツを創れるかが重要
一般的な「葬儀の流れ」や「家族葬とは」といった内容は、すでに多くの企業が取り扱っています。そのため、SEOで差をつけるには、独自性のあるコンテンツを創り出す必要があります。たとえば、「自社のスタッフが語る感動エピソード」や「顧客が実際に利用した葬儀プランの詳細紹介」といった具体的でオリジナルな内容が効果的です。
ただこの差別化が葬儀会社各社にとってはかなり難しいようです。具体的には「独自のコンテンツ作り」ができないようです。
本来であれば「自社での取り組み」などを外部に向けてアピールするべきなのですがコンプライアンス観点やリソース不足で足が重い企業が多いです。
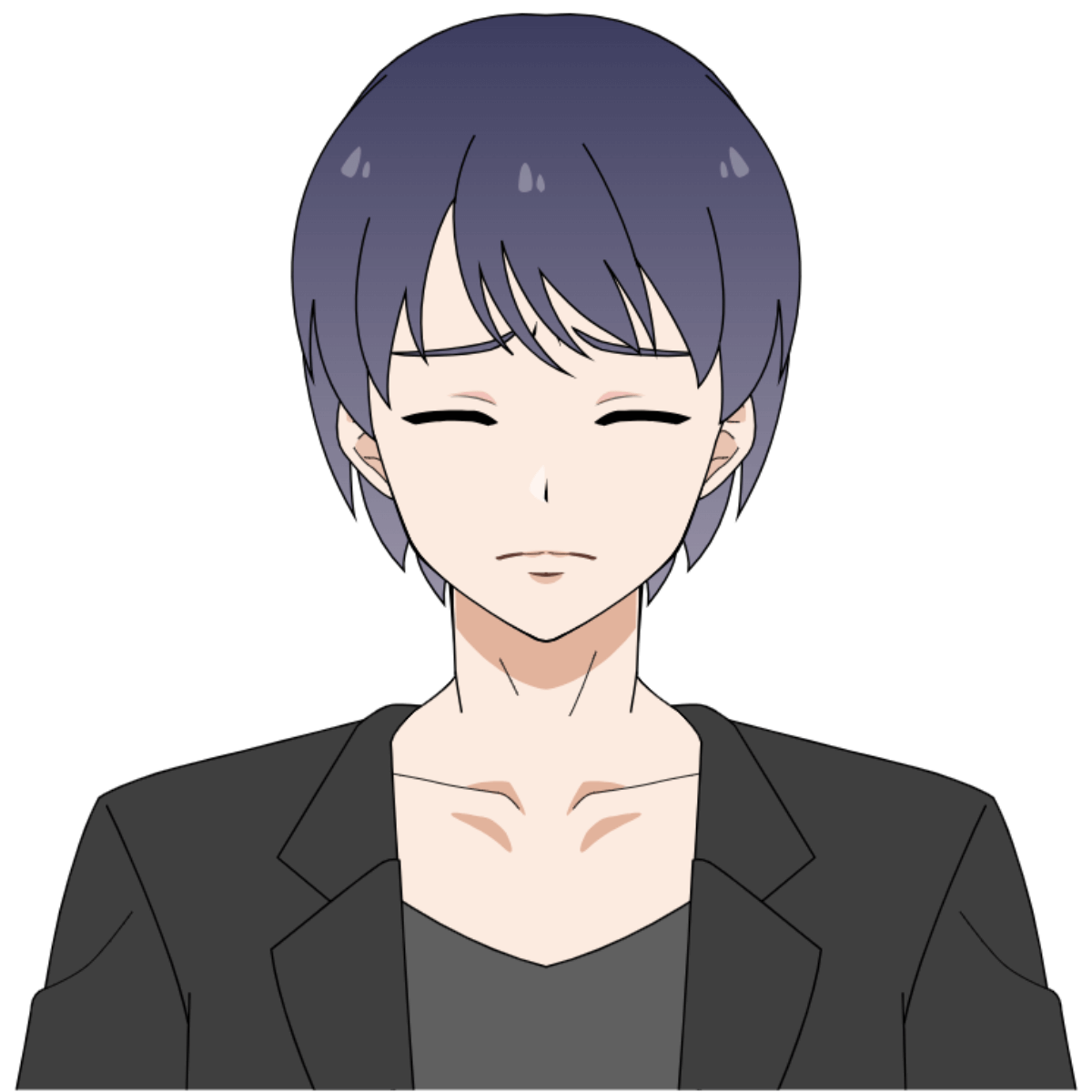
どの企業も色々な条件があって大変だよね
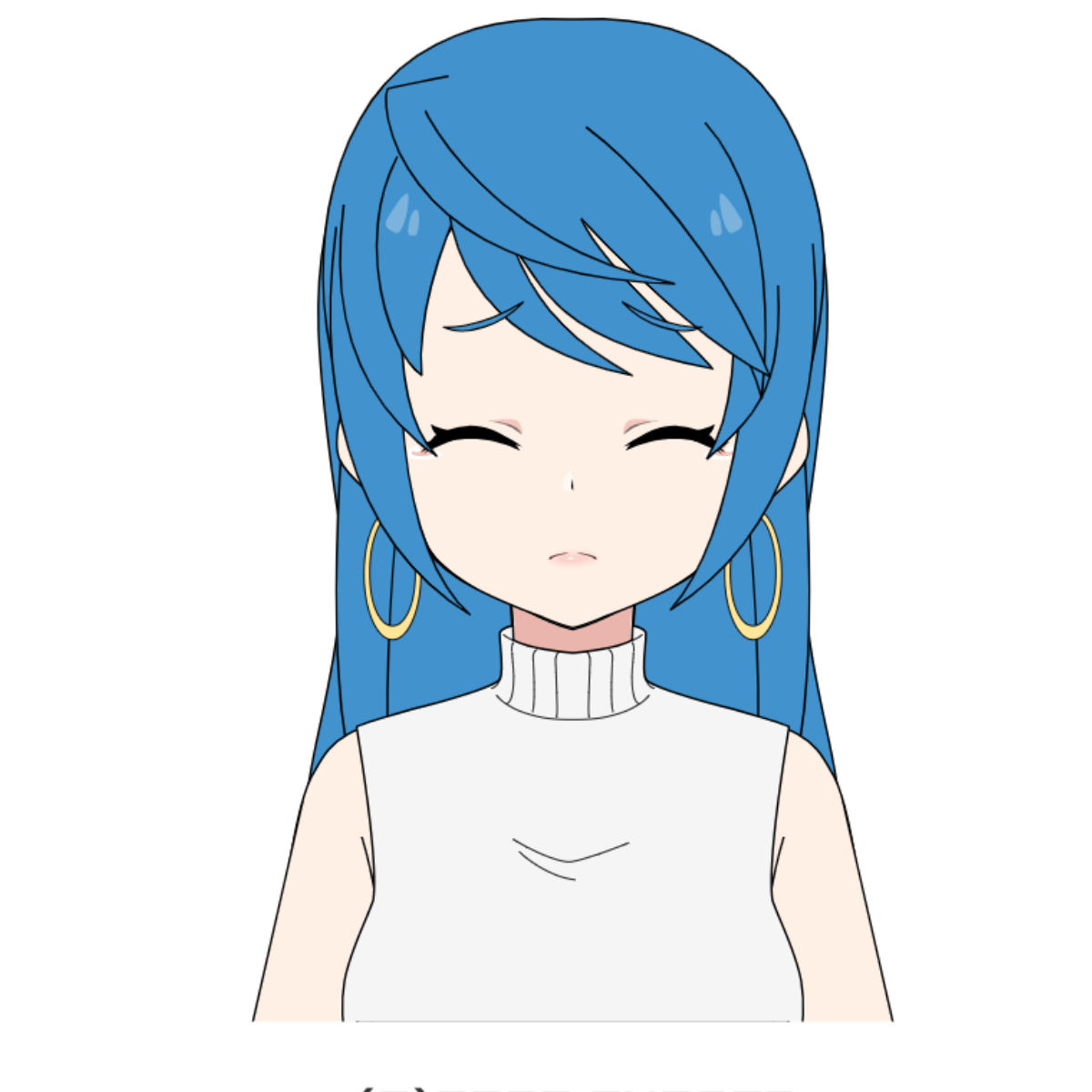
見えていない部分の苦労のほうが多いって言うわ
ブログ形式で記事を書くことも自社で取り組もうにも専門の人材を雇えるわけではないですし、外部に発注するにしても費用対効果が合わないとのことで途中で辞めてしまう企業が多い傾向にあるようです。
リスティング広告を解説した際にも挙げましたが、広告もSEOもデジタルマーケティング施策は基本的に「運用」が全てです。
どれだけ良い企画、施策を実施して効果が出ても「高級食パン」や「タピオカ」のように一過性で終わってしまっては意味がありません。
ブログで更新を続けることで検索エンジンからの評価が高まり、継続的にアクセスを集めることができます。コンテンツマーケティングは短期的な効果ではなく、長期的な信頼と成果を生む施策である点を意識しましょう。
MEO(口コミ)
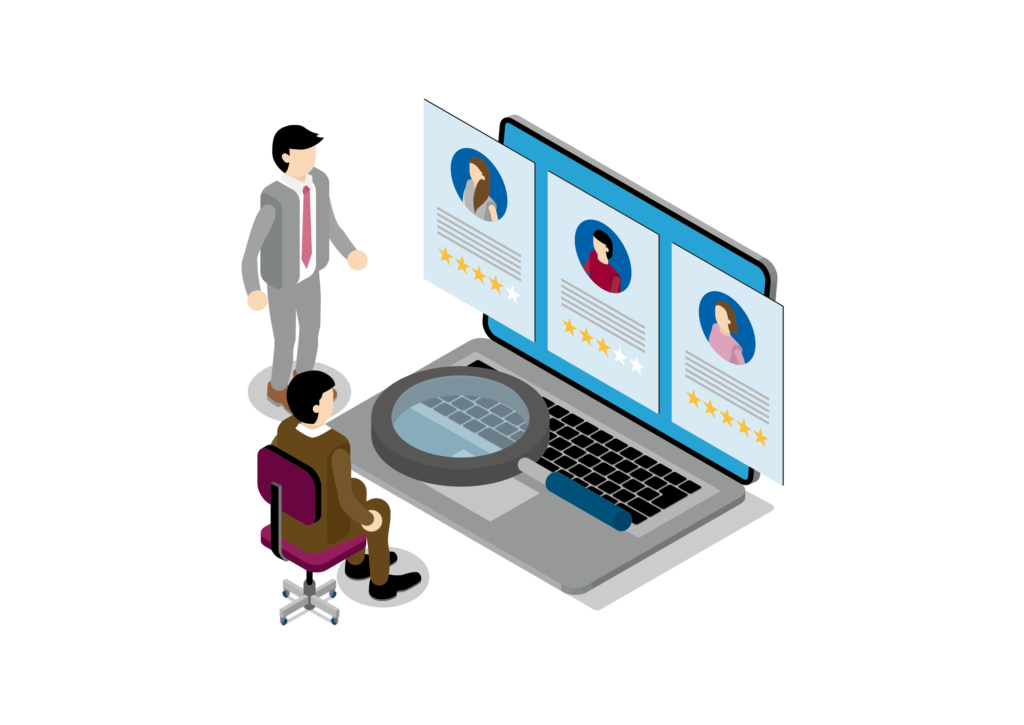
MEO(マップエンジン最適化)は、Googleマップでの露出を最大化するための施策です。
葬儀業界だけではないですが、美容品や食品を買う時には口コミが選ばれる理由の一つとして重要視されるため、MEO対策と口コミの活用はセットで考えるべきです。
口コミは地道な活動の成果指標の1つ
口コミは顧客満足度の直接的な表れです。
葬儀のようなサービスでは、信頼性が最優先されるため、口コミが非常に大きな影響力を持ちます。満足度の高いサービスを提供し続けることで、自然発生的に良い口コミが集まり、MEOの評価向上にもつながります。
(ここでいうMEOとはGoogle Map上での口コミ評価を指しています)
たとえば、Googleビジネスプロフィールでの評価が高い企業は、検索結果ページでも目立つ位置に表示されることが多く、新規顧客の獲得に繋がります。
口コミを増やすための施策はいくつかありますが、基本方針は「良いサービスを提供する」ことです。
他業界ではサービス終了後にお礼メールを送り、口コミ投稿を促すなどをしていますが、なかなか葬儀業界では業界慣習的に実施していない企業が多く、地道な努力が必要です。
塵も積もれば山となる
口コミの収集は、短期的な成果を求めるものではありません。1件1件の投稿が積み重なって、やがて大きな信頼へと繋がります。特に地方エリアでは口コミ数が少ない場合が多いため、少しの投稿でも相対的に大きな効果を発揮します。
悪い口コミが投稿された場合も、適切な対応をすることで、顧客に誠実さを伝えるチャンスと捉えることができます。このように、口コミを「地道な成果指標」として活用する姿勢が大切です。
CRM活用
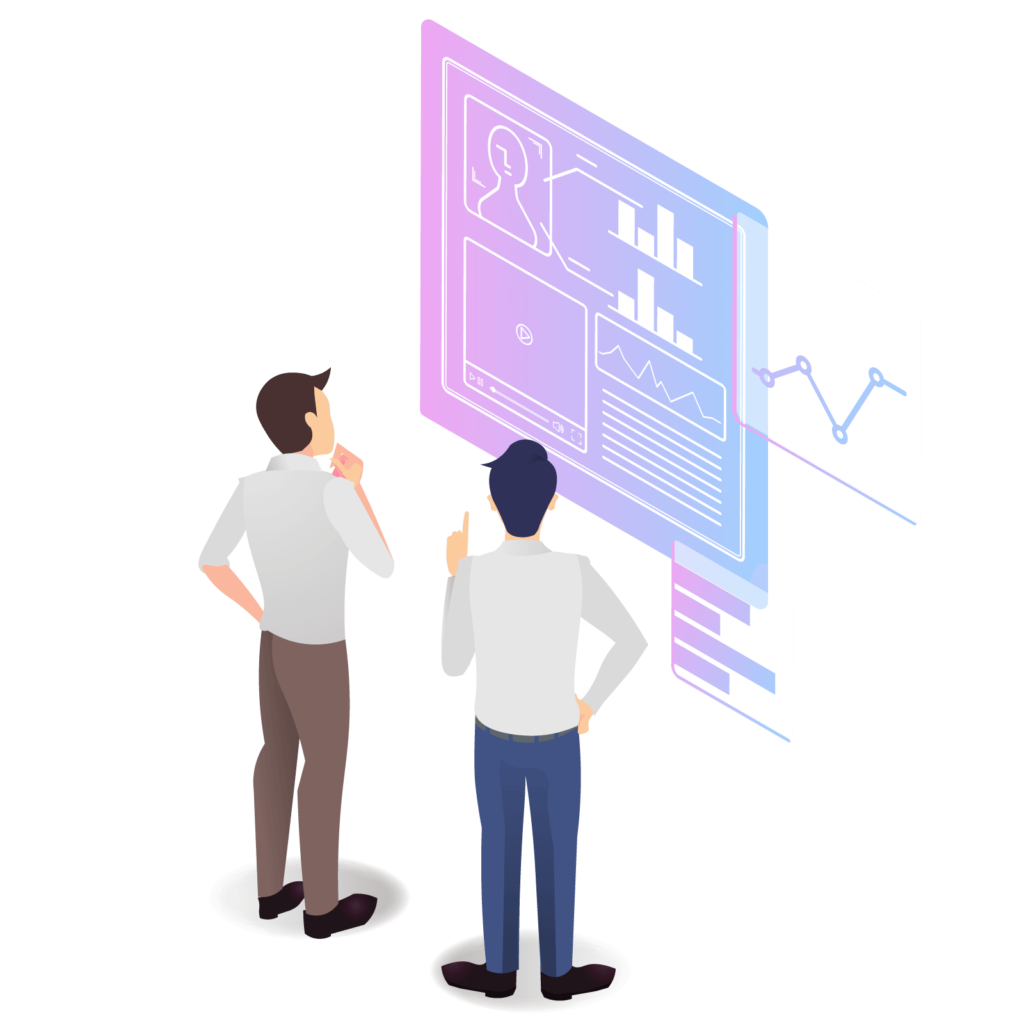
CRM(顧客関係管理システム)は、顧客情報を一元管理し、ニーズや行動を深く分析するためのシステムです。
葬儀業界においても多くの企業でHubspotやsalesforceなどのCRMを導入されていますがまだまだ活用できている企業は多くありません。CRMを活用することで、より個別化されたサービス提供が可能となります。
顧客一人一人のニーズや行動の分析
CRMは顧客の年齢、家族構成、過去の利用履歴などを分析するツールとして活用されます。
データとしては保有している企業は多いですが、そのデータを顧客最適化に生かしている企業は多くありません。
たとえば、以前に直葬を依頼した顧客が次に家族葬を検討している可能性が高い場合、最適なプランを提案することで次もご利用いただける可能性が高まります
また、問い合わせや資料請求の履歴を基に、どのタイミングでフォローアップすべきかを判断できる点もCRMの利点です。
顧客との接点を逃さず、適切なタイミングでアプローチすることで、成約率を向上させることができます。
MA(メールマーケティング)
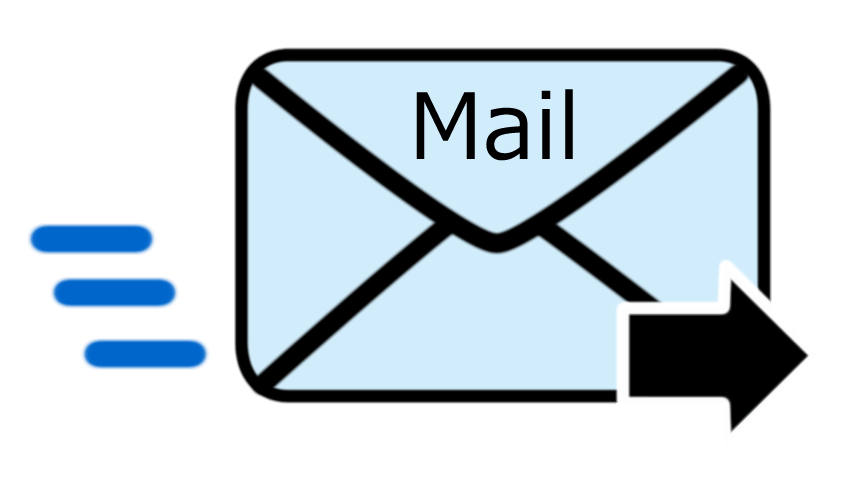
先ほどのCRM活用とも関連が強いのがMA(マーケティングオートメーション)です。MA(マーケティングオートメーション)は見込み客に対して効率的かつ効果的にアプローチするための手法として注目されています。
その中でもメールマーケティングは、葬儀業界における顧客とのコミュニケーションを深める重要な手段です。
顧客のニーズに応じたタイミングで情報を届けることで、信頼関係を築くことができます。
メルマガを登録された方に関連情報やキャンペーン情報を送ることはもちろん、無料の相談受付や質問などをMAのシナリオを設計して送付して顧客ナーチャリング(育成)を図ることは非常に葬儀業界でも非常に有効です。
ダイレクトに申し込みに繋がらなくても送れば認知は取れる
メールマーケティングの特徴は、必ずしも即時的な成果を求めるものではない点です。
「資料請求」「終活セミナー案内」などの情報を定期的に配信することで、顧客の頭の片隅に「信頼できる葬儀会社」というイメージを植え付けることができます。
たとえば、「家族葬の費用比較」「初めてのお葬式ガイド」といった役立つ情報をコンテンツとして送り続けることで、受信者がいざ必要になった際に第一候補として考える可能性が高まります。また、オートメーション化により、問い合わせや資料請求から一定期間後にフォローアップメールを送るなど、タイミングを逃さないアプローチが可能です。
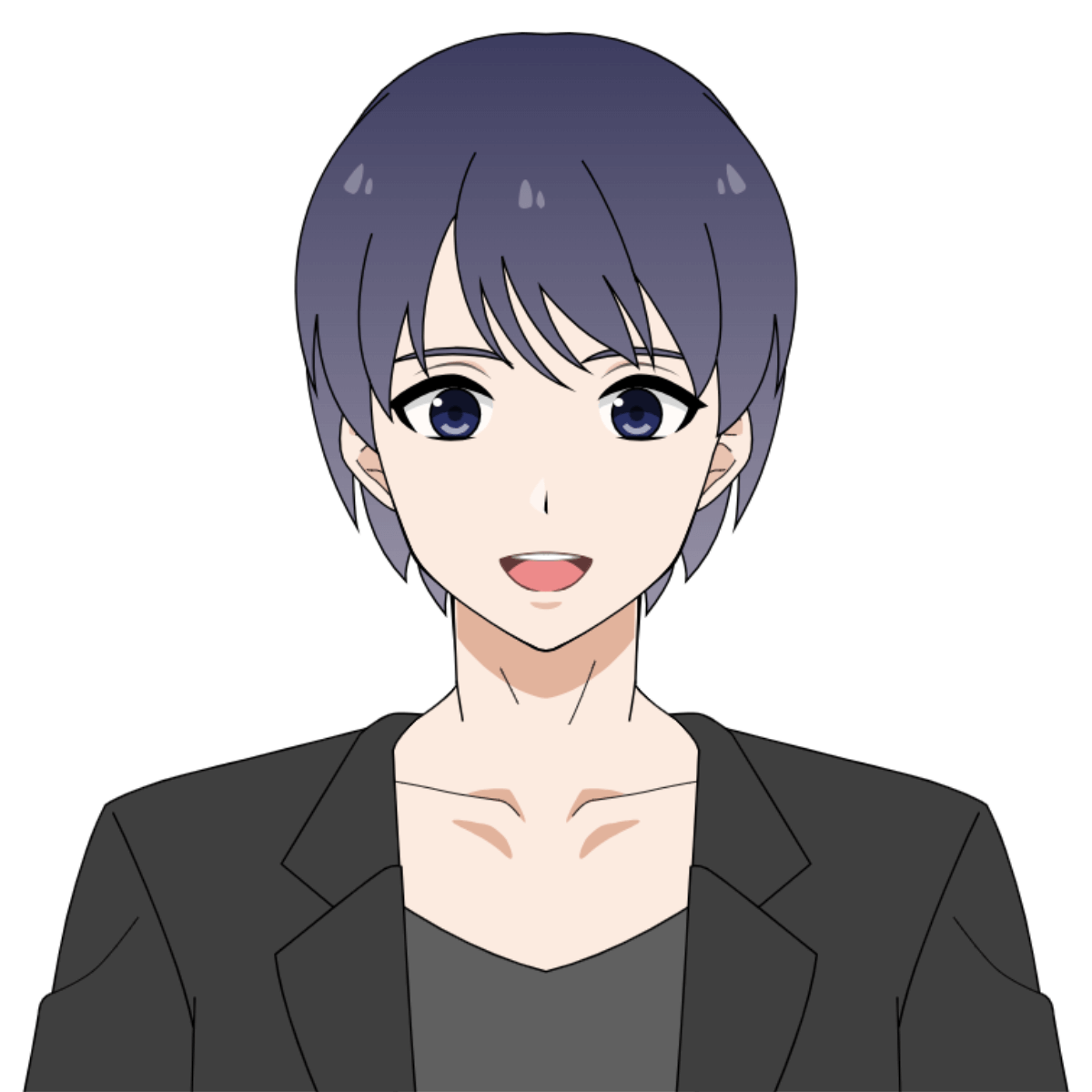
見ないけど、来てるメールって以外と覚えてるよね
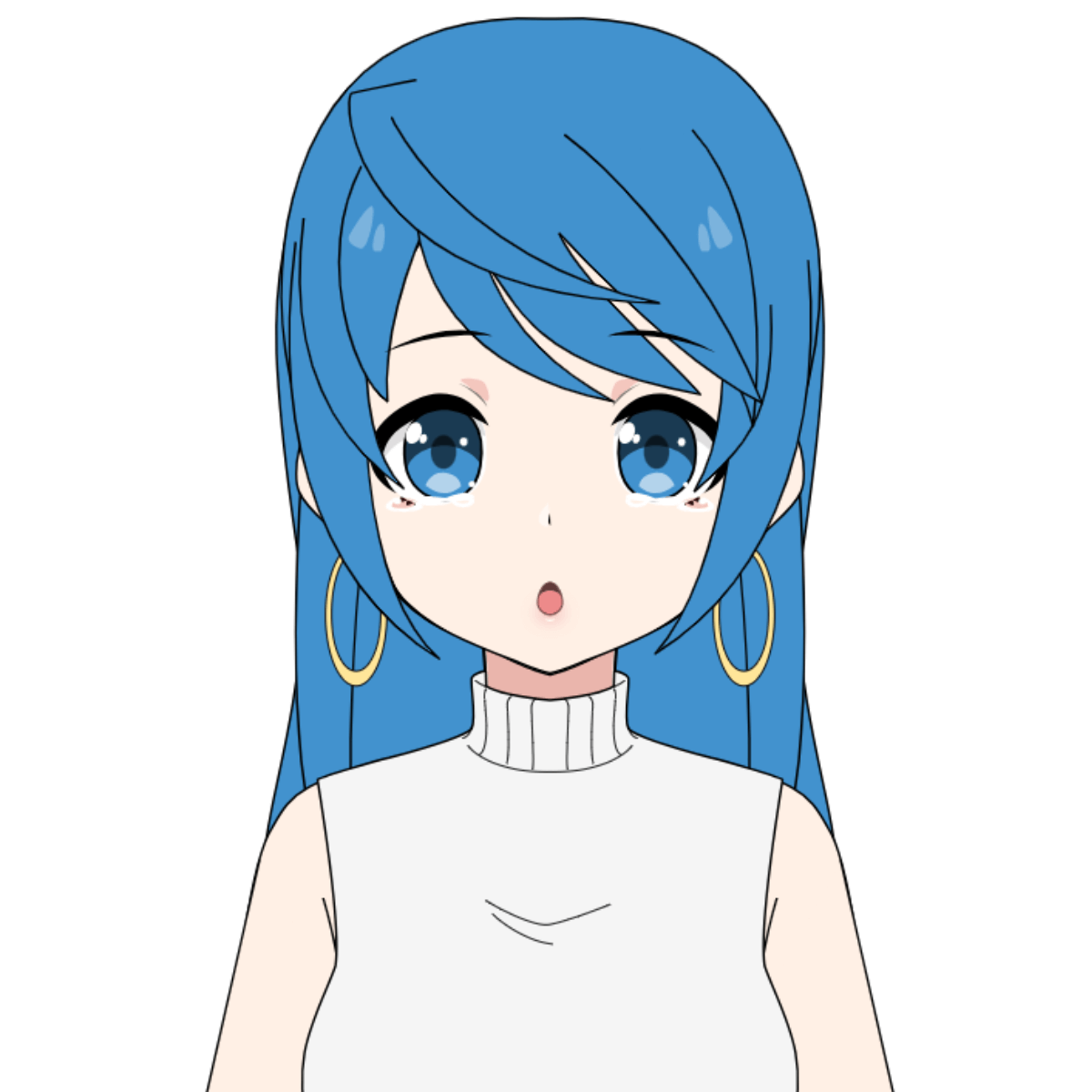
迷惑メールに入らなければ覚えてもらえる可能性もあるかもしれないわね
メールの内容を魅力的にするためには、プロフェッショナルなデザインや分かりやすい表現を取り入れることが重要です。一方で、情報が多すぎると逆に読まれないため、簡潔で心に響くメッセージを心がけましょう。
SNS

続いてはX(旧twitter)、Facebook、instagramなどのSNSです。SNSは、企業とユーザーを直接つなぐ強力なプラットフォームで本当に近頃は活用する企業が多く増えています。
葬儀業界においても、自社の信頼性や親しみやすさをアピールする場として一部のアドバイザーや葬儀会社の中で活用が広がっています。
特に、多様な年齢層が利用する現在のSNSでは、ターゲット層に応じた発信が成功の鍵となります。
若年層だけがSNSを利用しているわけではない
SNSは若年層だけのものというイメージがありますが、近年では中高年層の利用者が急増しています。
たとえば、Facebookは特に40代以上の利用者に人気があり、Instagramでは50代以上の層も増加しています。しかしもともとFacebookは若者に利用者が多いのがどんどん中高年に広がっていきました。tiktokも若者のユーザーが多い傾向にあるといわれていますが、現在では中高年層にも利用者が広がっています。
このように、年齢に関係なくSNSが日常生活の一部となりつつある現在、葬儀業界でもSNSを効果的に活用することで幅広い層にリーチできます。
自社を知ってもらうきっかけとして利用
SNSをどう企業のプロモーション・マーケティング活動に生かしていくかですが、SNSは消費者に自社を知ってもらう「入り口」として最適です。
葬儀業界では、葬儀場の温かみある写真や、プランに込めた想いを紹介する投稿が親しまれています。また、スタッフの日常や地域との関わりを伝えることで、親しみや信頼感を与えること可能かと思います。
さらに、ターゲティング広告を活用することで、特定の年齢層や地域に限定した情報を届けることが可能です。たとえば、「葬儀や終活の準備を始めたい方へ」といったメッセージを中高年層に届けることで、将来的な顧客を獲得する土台を築けます。
KARTEなどの接客ツール

ここまではプロモーション(集客)やブランディング・データ分析について解説してきましたが、デジタル上での接客ツールも求められている施策のひとつです。
接客ツールは顧客の行動をリアルタイムで把握し、最適なタイミングでのアプローチを可能にするツールです。いわばMA(マーケティングオートメーションのwebやアプリ版)と言っていいでしょう。
葬儀業界以外でも多くの企業で用いられているので、KARTEのような接客ツールを活用することで顧客体験を向上させ、成約率を高めることができます。
たとえば、KARTEを利用することで、サイトを訪れたユーザーの行動を追跡し、興味を持っているプランや問い合わせを予測することが可能です。
この情報を基にパーソナライズされた提案やフォローアップを行うことで、顧客の満足度を向上させられます。
動画マーケティング

動画マーケティングは情報を視覚的に伝える強力な手段です。
葬儀業界ではサービス内容をわかりやすく説明する動画や、葬儀場のバーチャルツアーなどが効果的です。
文章より動画の方がわかりやすい
特に初めて葬儀を検討する方にとって、文章だけの情報では何が何だか分かりづらい部分があります。
動画を活用することで、実際の葬儀場の雰囲気やサービスの詳細・ご利用・ご相談方法の流れを視覚的に伝えることができます。
また、作る動画の種類にも寄りますがは感情に訴えかける効果が高いため心に響くストーリーを作ることで、記憶に残るコンテンツを提供できます。
登録やいいねなどお気に入りに入れておいてもらう
動画の魅力は再生するだけでなく、後から見返すことが容易な点にもあります。
特に、YouTubeなどのプラットフォームを活用すれば、顧客がチャンネル登録やいいねなどをしておいてもらえれば思い出した時や見返したいタイミングで必要なときに確認できる環境を作れます。
デジタルサイネージ広告

続いてはマス系のプロモーション(広告)施策になります。
デジタルサイネージ広告は従来の看板やチラシに代わる次世代型の広告手法です。
都内だけではなく地方主要都市の駅や商業施設、病院など、人が多く集まる場所でも最近よく見かけます。デジタルサイネージは動的なコンテンツを表示することで、注目を集めやすくなります。
新宿の世界最長45.6mのデジタルサイネージやヨドバシカメラのサイネージ広告はかなり有名ですね。
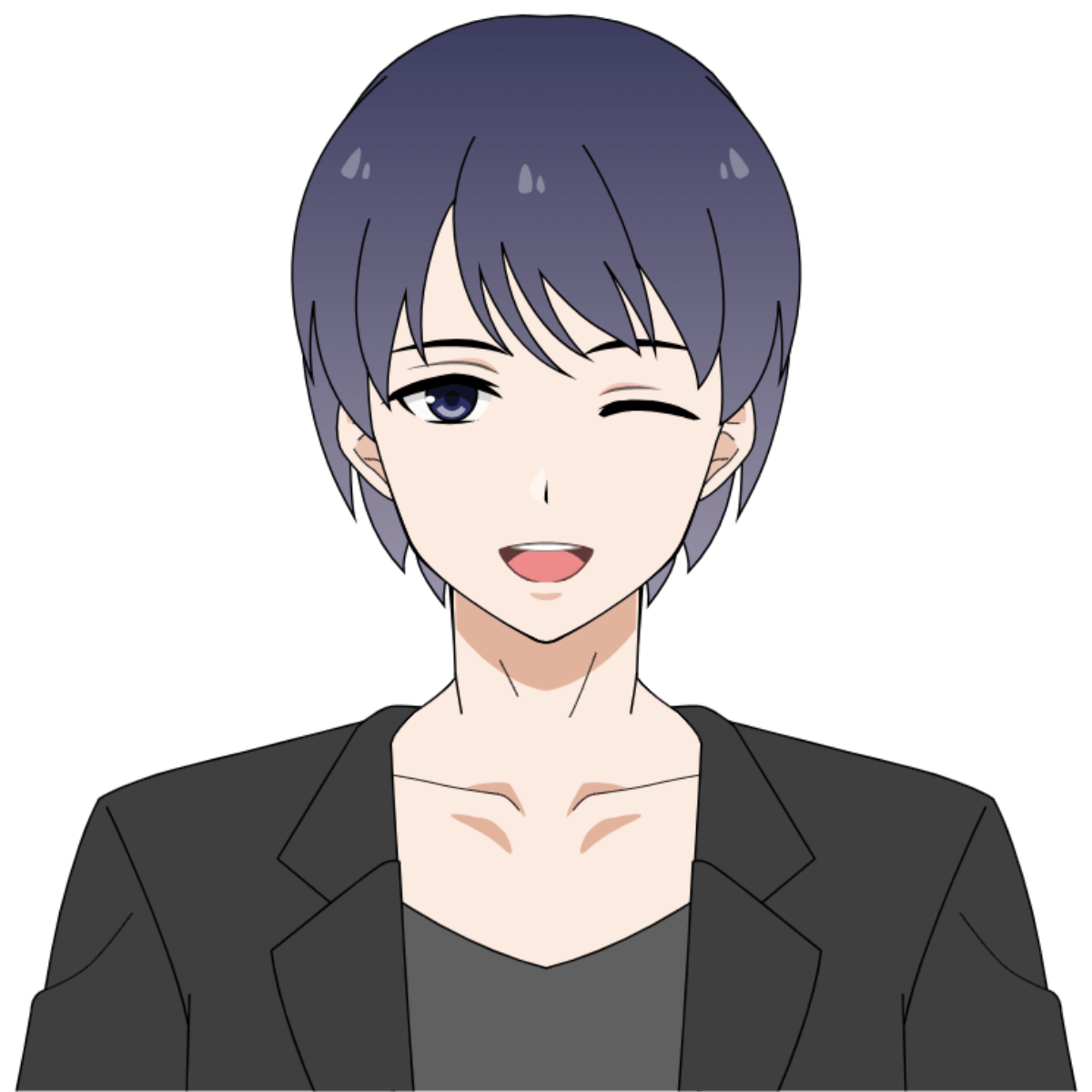
僕も見たことあるよ!
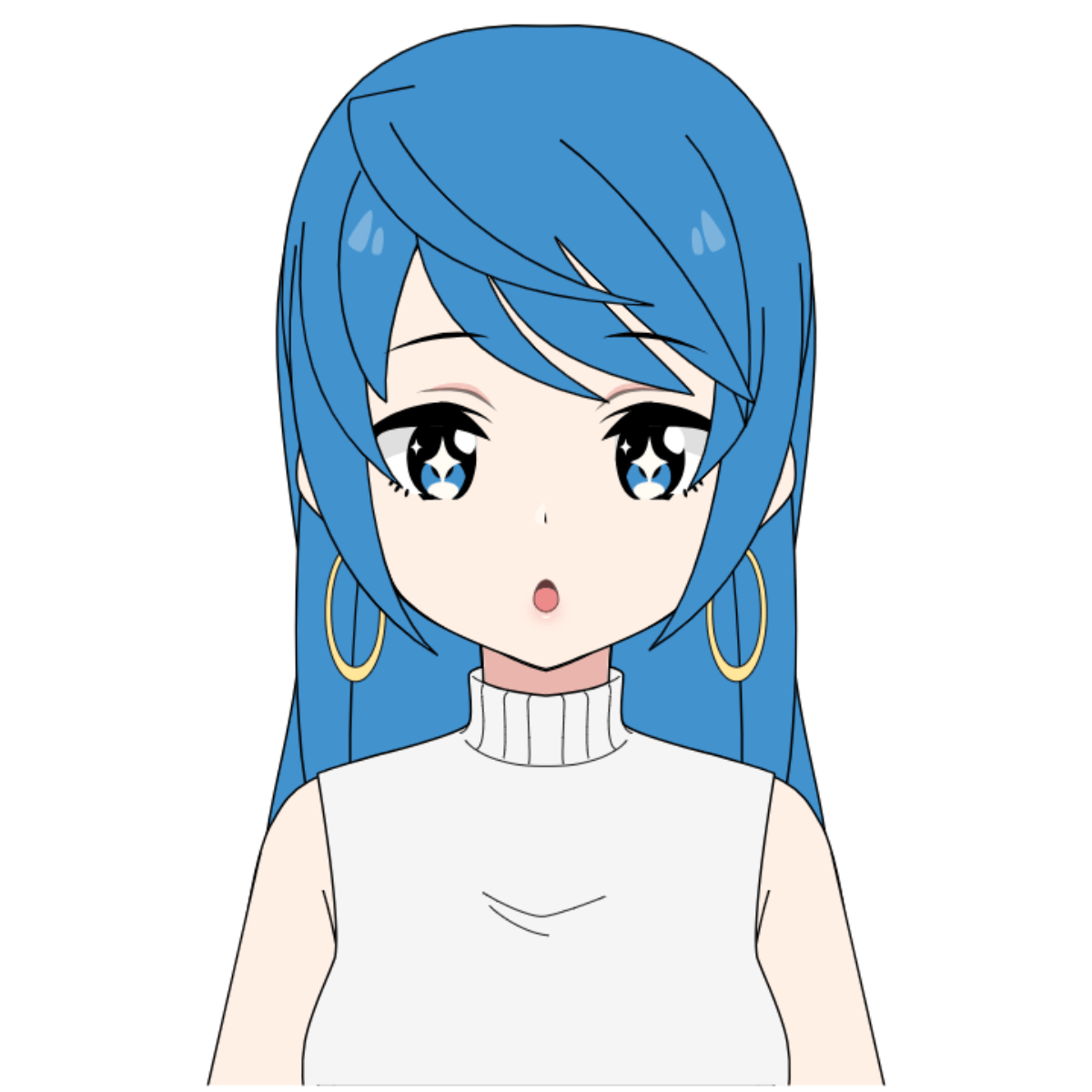
インパクトはすごいわよね
葬儀業界では地域密着型のサービスを強調し、視覚的にインパクトを与える広告が効果を発揮します。
看板やチラシと異なり効果を定量的に図れるものもある
デジタルサイネージは視認性が高いだけでなく、どのくらいの人が広告を見たかをデータとして記録できるのが大きな利点です。
サイネージ広告の種類によって計測できるものとできないものがありますが一部のサイネージでは通行量や視線の追跡データを基に、広告のパフォーマンスを定量的に評価できます。
葬儀業界においても、地域住民の注目を集めるだけでなく、効果を測定して改善を図ることで、費用対効果を最大化することが可能です。
とにかく目立たせることが役割なので、文字は最低限で注目してもらえるクリエイティブを作る必要があります。
よく看板広告やチラシなどを見かけると「これ文字量多くて運転中読めんよ」というものを高速道路で見かけます。
あるあるなのが広告クリエイティブの詰め込みすぎですね。伝えたいことが多いのはわかりますが、何を一番伝えたいのか絞れていないパターンの広告はかなり多いので伝えたいことを一言に絞るくらい凝縮して伝えましょう。
アクセス解析

アクセス解析はWebサイトの訪問者の行動を把握し、デジタルマーケティングの戦略を最適化するために欠かせないツールです。
よく用いられているのがGoogle analytics(GA4)やadobe analyticsなどが有名なツールです。
特に葬儀業界ではユーザーのニーズが多岐にわたるため、アクセス解析を通じてその行動を正確に理解することが重要です。
ユーザーの行動をきちんと分析
アクセス解析を行うことで、ユーザーがどのページを訪問し、どれくらい滞在したか、どこで離脱したかを詳細に把握できます。
たとえば、「家族葬の費用」ページで離脱率が高い場合、その原因を分析し、情報の追加やデザインの改善を行うことで、滞在時間を延ばせます。
また、アクセスデータを活用して、どの地域からの訪問者が多いかを分析することで、エリア特化型の施策を強化することも可能です。これにより、地域ごとのニーズに応じた柔軟な戦略が実現します。
思っている以上にユーザーはめんどくさがり屋と想定
ユーザーは情報をすぐに見つけられないと、簡単にサイトを離れてしまいます。
たとえば、「資料請求」のボタンが見つけづらい場合、せっかくの問い合わせ機会を逃してしまう可能性があります。
そのため、ユーザーが直感的に操作できるサイト設計を心がけ、必要な情報を目立たせることが重要です。
足らないコンテンツや探しているものをきちんと把握
アクセス解析はユーザーが求めているけれど見つけられなかった情報を明らかにするのにも役立ちます。
たとえば、「家族葬の進め方」や「火葬式の流れ」といった検索が多いにもかかわらず、該当するコンテンツが不足している場合、これを補完する記事を作成することでユーザー満足度を向上させられます。
葬儀業界問わずデジタルマーケティングは運用が全て
以上がデジタルマーケティングに関するよく用いられる施策一覧についてのご紹介です。
ここでまとめに入ります。
広告のパートでもお話したのですが、結局のところどの施策を実施するにも「運用」できなければ成果は持続しないということです。
改めてのお伝えになりますが「運用」とは一過性の成果ではなく持続的な成果を出すために日々仮説を立て、検証をして改善を図ることです。言うことはたやすいですが、やってることは非常に愚直なので地味なこともありますし多忙な中で疎かになることもあるでしょう。なのでみんなやりたがらないです。ですが、継続することで着実に成果を出す手法です。これは広告にしろ、SEO、SNSにしても同じことが言えます。多くの企業が疎かにしているので、継続することで逆に差別化することも可能です。
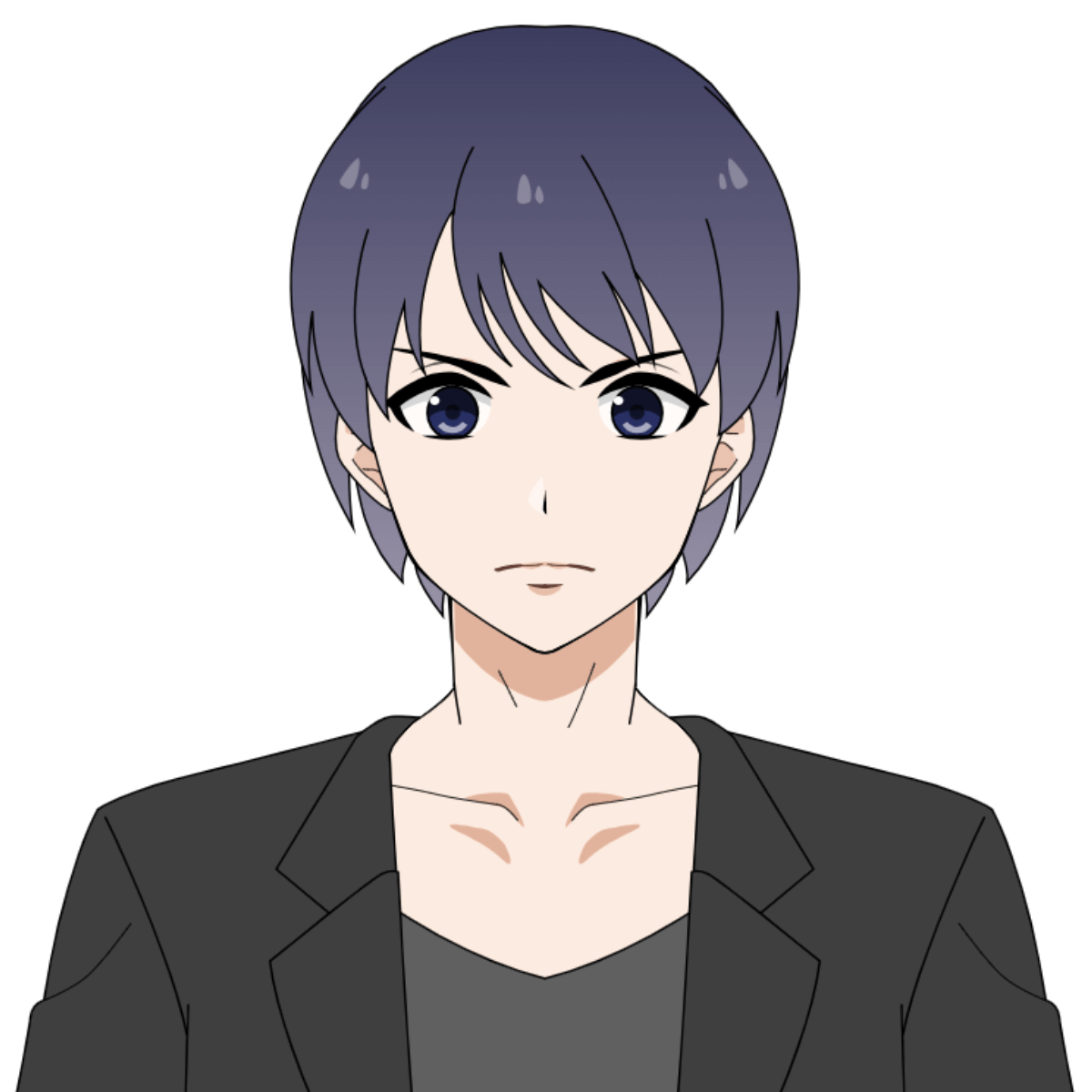
運用ってすごく地道だけど大事なことなんだね
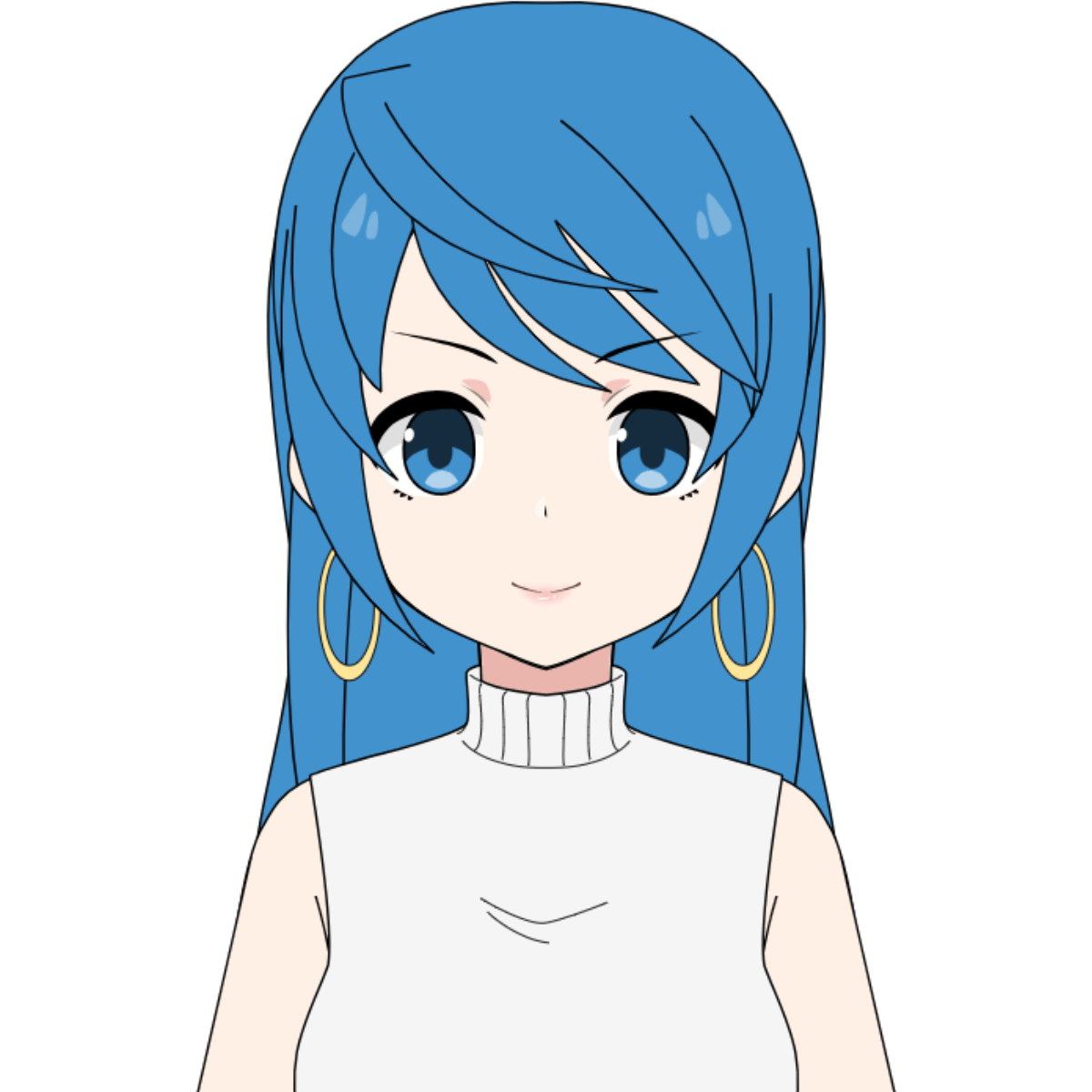
私もきちんと投稿が続いている(運用されてる)インフルエンサーはフォローしてるわ
葬儀業界のデジタル運用支援はプロストイックがとても強いです
デジタルマーケティングは葬儀業界に属する事業者様が今後の経営を左右・切り開く鍵です。
看板や新聞広告などの伝統的手法だけでは競争が激化する現代では生き残こることは難しく、SEO、Web広告、SNS、口コミ、動画マーケティングといったデジタル施策を組み合わせて活用することで、顧客との信頼関係を深め、長期的な成長を実現できます。
さらに、アクセス解析やCRMを駆使して顧客の行動を把握し、ニーズに応じたアプローチを行うことが成功への近道です。
デジタルマーケティングの可能性を最大限に引き出し、業界全体の発展に繋がる取り組みを行っていきましょう。10年後も選ばれる葬儀会社となるために、今こそその一歩を踏み出す時です。
不明点やお困りごと、運用に関するご相談はプロストイックまでお問い合わせください!
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック