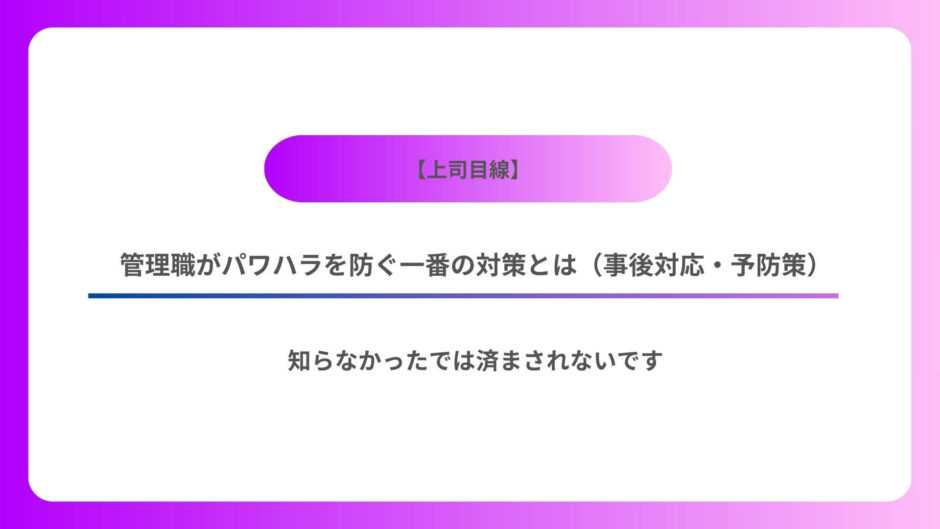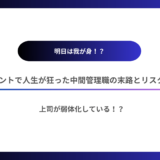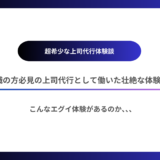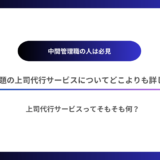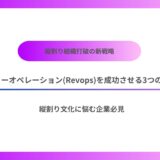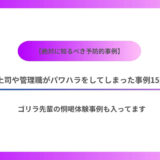皆さんこんにちは。株式会社プロストイックです。
今回のテーマはパワハラです。かなりセンシティブな内容ですが、だからこそ「他企業がどう扱っているのか」、「防ぐにはどうすればいいのか」、「パワハラをしてしまった事後の対応ってどうすればいいのか」等皆さんが知りたいことについて解説をします。
また今回はパワハラの加害者になってしまう可能性がある「管理職」や「上司」の方目線で解説をしていきます。
- パワハラをしてしまうリスクが(無意識的にも)ある管理職に着任している方
- 周囲でパワハラの被害・加害が最近勃発している方
- パワハラを事前に防ぎたい方
ちなみに関連する記事として過去こちらの記事も読まれております。
まだパワハラがなくならない理由とは?管理職・上司が知らない“本当の根本原因”

パワハラは社会問題として広く認知され、法整備や企業のハラスメント研修も進んできました。
それにもかかわらず、現場での発生件数は減少傾向にはありません。
これは、パワハラを“悪質な個人行動”として片づけてしまい、組織的な構造や文化にまで目が届いていないことが大きな原因です。
特に営業職が強い企業においては成果主義や短期の業績目標に追われやすく、現場の管理職や上司がプレッシャーを抱えたままマネジメントを行っているという構図が多く見られます。
この背景には管理職自身のリテラシー不足だけでなく、上司の孤立、教育体制の未整備、そしてジェネレーションギャップの深刻化など、複数の構造的問題が絡んでいます。
ここでは、「なぜこれほどまでにパワハラが根絶されないのか」という根本的な問いに対して、いくつかの視点から深掘りしていきます。
SNSで拡散されてもパワハラが絶えない背景

昨今、パワハラに関する情報は瞬時にSNSで拡散され、企業のブランド価値や採用力にも影響を及ぼす時代です。
しかし、それだけのリスクがあるにもかかわらず、現場ではいまだに「パワハラまがい」の言動が繰り返されています。
背景には、“発生したら対処する”という事後型のマネジメント文化が根強く、未然防止のための仕組みづくりが後回しにされている現実があります。
また、部下が声を上げたときに「それぐらいで?」「昔はもっと厳しかった」など、上司の側が感覚的に受け流してしまうケースも少なくありません。このような反応は、被害者側の沈黙を助長し、結果としてパワハラが可視化されずに温存される要因になっています。
管理職や上司がパワハラの定義を正確に理解していないことも問題です。
厚生労働省が示す「優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」という基準は抽象的で、現場での判断は難しく、つい感覚や経験で対処してしまいがちです。こうした曖昧な基準が、組織の中でパワハラの“グレーゾーン”を生み続けています。
「指導」と「圧力」の境界線が曖昧な現場の実情

パワハラの多くは「指導のつもりだった」という言い分から始まります。
つまり、当事者である上司や管理職にとっては善意であり、部下側にとっては威圧であるという、典型的な認識のギャップが根にあります。
特に営業現場などでは、「数字がすべて」という文化が色濃く残っており、上司がプレッシャーを部下に転嫁する構図が常態化しています。
問題はこの“圧力”が結果的に部下のモチベーションやメンタルヘルスを著しく損ない、離職や生産性の低下を招くという事実に、上司自身が気づきにくいことです。
これまでの成功体験や「自分もこうして育った」という感覚に頼ってしまうことで、マネジメントが“アップデート”されず、結果としてパワハラ的な言動が「自分の中で」正当化されてしまいます。
こうした事態を防ぐためには、管理職一人ひとりが指導と圧力の違いを明確に認識し、チームビルディングや信頼関係構築のスキルを身につける必要があります。
近年では既に先見の明がある企業が続々と、上司代行のような専門サービスを活用して、第三者の視点からマネジメントの質を見直す企業も増えつつあります。
これは単なる事後対応ではなく、根本的な予防策としての意味を持ちます。
上司と部下の“ジェネレーションギャップ”が火種に

世代間ギャップはパワハラが起きる要因の中でも特に見落とされやすいポイントです。
たとえば、団塊ジュニア世代の管理職がZ世代の若手社員を指導する場面では仕事観、価値観、働き方に対する認識が大きく異なります。
前提がまるで違う中で、上司が“常識”と思っていることが、部下にとっては“理不尽”に映る。そのズレが職場の空気を悪化させ、パワハラと捉えられる行為に発展するケースが後を絶ちません。
管理職側に悪意がなくても、言葉選び一つ、コミュニケーションの取り方一つで、相手には強い圧力として伝わってしまう。
これは、個人の資質というよりも、時代の変化に対するアップデート不足の問題です。
定期的なリーダーシップ研修や外部コーチの導入だけでなく、世代間の価値観ギャップを理解し、調整する力が求められています。
その観点からも、上司代行サービス(中間管理職支援)のように、外部のプロがチームやマネジメント体制の設計に関与する取り組みは非常に有効です。
年齢や経験の違いを超えてチーム全体の関係性を再構築し、共通言語で動ける組織づくりを支援する動きが注目を集めています。
管理職が知っておくべきパワハラの基礎知識
現場でのパワハラ防止は感覚や経験ではなく「知識と理解」によって支えられるべきです。
しかし実際には多くの管理職や上司が「どこからがパワハラなのか分からない」「昔はこれが当たり前だった」といった曖昧な基準で行動しています。
その結果、意図せずして部下を追い詰めたり、組織の信頼を損なったりする事態につながってしまいます。
パワハラは発言や行動が相手の主観によって受け止められるため、判断が難しい場面が多いのも事実です。
だからこそ、まずはパワハラの正式な定義と6つの類型、そして法律・企業のガイドラインの違いといった「最低限知っておくべき基礎知識」を、管理職は正確に把握する必要があります。
上司という立場である限り「知らなかった」では済まされない現実がそこにはあります。
パワハラの6類型とは?知らなかったでは済まされない分類
こちらは厚生労働省が定めるパワハラの6類型は現場の上司や管理職がまず理解すべき基本情報で、以下のように分類されています。
- 身体的な攻撃(殴る・蹴るなどの暴力行為)
- 精神的な攻撃(人格否定、侮辱的な発言)
- 人間関係からの切り離し(隔離、無視、集団での排除)
- 過大な要求(遂行不可能な業務量を課す)
- 過小な要求(業務を与えずスキル低下を誘導する)
- 個の侵害(私生活への過度な干渉)
この分類を知らない管理職が多いのは研修が形式的で終わってしまっているからです。
しかし、例えば「目標未達の部下に皆の前で叱責する」ことが、本人にとっては当然の指導でも、実は「精神的な攻撃」に該当する可能性がある。
こうしたギャップを正しく埋めるためには分類を理解したうえで日々のコミュニケーションを見直す視点が求められます。
また、これらの行為は一回限りでも成立し得るため、「何度も繰り返していないからセーフ」、「状況が状況なだけに仕方がなかった」等という自己判断は危険です。
こういった懸念が少しでもある会社・管理職の方は上司代行(中間管理職支援)のような外部支援を受けながら、自らの言動を客観視する体制も、今後は必要になっていくでしょう。
起こってしまってからでは遅いので管理職の方を守るために強めに警告をしておりますが、これは事後対応では時すでに遅しです。刑事罰に処されることもありますし、謝罪で済まないケースも実際に発生しています。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
法律と企業のガイドラインの違い|最低限守るべき基準とは
「法律で決まっていないから大丈夫」という思い込みは管理職にありがちな誤解の一つです。
確かにパワハラに関する法的整備は2020年の改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)によって企業に義務付けられるようになりましたが、これはあくまで「防止措置義務」の話であって、行為そのものにすべて刑罰が科されるわけではありません。
つまり法律は「最低限のライン」を示しているだけであり、実際の職場運営においては、企業ごとのガイドラインや就業規則の方が、より実効的な行動規範として機能します。
企業によっては業務指導に関するマナーや言葉遣い、報告の受け方にまで踏み込んだマニュアルを整備しているところもあります。
ここで重要なのは「自社の基準を把握しているかどうか」です。管理職や上司がこの点を見落としていると、本人のつもりでは“適正な指導”でも、社内ルール上ではアウトということが起きかねません。
逆に、企業としてのポリシーを明確に示すことで、現場の判断もブレなくなります。
上司代行の現場ではこうした企業内規定を再設計するサポートも行っています。
特にデジタル組織ではリモート環境下でのハラスメント対策が求められるようになっており、画面越しでも「圧」を感じさせないコミュニケーション設計が重視されています。
パワハラになりやすい言動チェックリスト

理論は分かっていても、日常の言動がどこまでリスクを含んでいるかはなかなか判断が難しいものです。
パワハラの加害者となる多くは、「そんなつもりはなかった」と言います。その“つもり”が誤解を生み、職場の空気を壊すのです。
以下に挙げる言動は実際にトラブルに発展しやすいものとして、数多くの労働相談事例でも取り上げられている典型的なパターンです。
- 人格否定:業務報告の遅れを叱責する際に、「何度言えば分かるんだ」「お前には期待していない」といった人格否定の言葉を使う
- 叱責:周囲の前でミスを責め立て、「みんなの迷惑になる」と過度にプレッシャーをかける
- 陰湿ないじめ:部下を会議や連絡網から意図的に外し、情報を与えない
- 職権乱用:能力に見合わない業務を一方的に押し付け、できなければ評価を下げると脅す
- 業務時間外労働:勤務時間外や休日に私用の連絡を強要する
これらは一見業務の延長に見えてしまうケースも多く、だからこそパワハラと認識されにくいのです。
重要なのは言われた側がどう感じたかという“受け取り手の視点”を持つこと。
日々の言動を点検するためには、定期的なフィードバックの場や第三者の視点を取り入れる仕組みが欠かせません。
上司代行ではこうしたチェックリストを基に、実際のマネジメント言動の見直しや、対話力を高めるトレーニングも実施しています。
言葉が組織文化をつくり、文化が業績を左右する時代において、上司のふとした一言がパワハラに転じるリスクを軽視してはいけません。
【被害者対応の初動が命取り|やってはいけない3つの対応例】

パワハラが発覚した瞬間管理職の対応が組織全体の信頼を左右すると言っても過言ではありません。
特に初動での被害者対応は、その後の経過に大きな影響を与えます。
大手企業では実施にハラスメント認定された管理職の「減給」や「降格」「出勤停止」などを厳しく実施して、社内掲示板で懲戒を出しているケースも多数あります。
残念ながら、ここで誤った行動を取ってしまう上司がまだ多く、結果的に二次被害や問題の深刻化を招くケースも少なくありません。
ありがちな誤対応の一つが「相手も悪かったんじゃないか?」と被害者に非を求める言動です。
たとえ事実確認前であっても、この一言で被害者は“信頼されていない”と感じ、口を閉ざすことになります。
次に多いのが、「今は忙しいから、後でゆっくり話を聞く」といった先延ばし。時間が経てば経つほど証言は曖昧になり、問題の核心がぼやけます。
そして三つ目は、「加害者とすぐに話して丸く収めようとする」対応。これは被害者にとって“黙っていろ”という圧力になりかねません。
パワハラというキーワードは管理職自身が無自覚に加担するリスクもあるという現実を突きつけます。
だからこそ、初動ではまず被害者の安全確保と心理的ケアを最優先に。事実確認や処分の前に、「あなたの声はきちんと受け止められている」と伝える姿勢こそが、信頼回復への第一歩になります。
社内ヒアリングのポイントと第三者機関(上司代行・管理職支援)との連携

パワハラの訴えがあった際社内でヒアリングを行うのは当然のプロセスです。
ただし、ここでの調査が形式的だったり、偏った聴き取りだったりすると、真実は表に出てきません。
むしろ、調査そのものが新たな火種になることもあります。だからこそ、ヒアリングは「聞く内容」と「聞く姿勢」がすべてです。
まず押さえるべきは被害者・加害者の主張をそれぞれ個別に、第三者的な立場で聞くということ。
複数人での聴取や、片方の言い分に引っ張られた質問は避けるべきです。また、ヒアリングの記録は感情や印象で書かず、できるだけ客観的な言葉を使って記述する必要があります。さらに、周囲の関係者や目撃者にも聴取を行い、組織全体の空気や人間関係の構造も捉える視点が重要です。
このように、ヒアリングには高度なスキルと中立性が求められます。
そこで近年活用が広がっているのが、上司代行などの第三者企業との連携です。
プロストイックが主導する上司代行(中間管理職支援)では管理職の業務支援やマネジメント支援の一環として、客観的立場からヒアリングに介入し、利害のないフィードバックを提供します。(実際に部署に入り込んで業務をしつつ、マネジメントも行うので違和感なく部署に溶け込みます)
先ほど述べた「初動ではまず被害者の安全確保と心理的ケアを最優先」というのも実際問題として「パワハラ」なんて言われてしまって冷静な判断なんてできる状況ではありません。
管理職の多くは多忙を極めて常に高いストレスにさらされています(無意識的にも)。
特にデジタル組織や複雑なチーム体制では外部の視点を入れることで初めて、組織の歪みに気づけることもあります。
ヒアリングを単なる“聞き取り作業”で終わらせないためにも、管理職は自らの聴き方を見直すとともに、必要に応じて専門家と連携する柔軟さを持つことが不可欠です。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
組織としての再発防止策をどう打ち出すか
パワハラが発覚した組織に最も求められるのは「なぜ起きたのか」を明確にし、「二度と起こさない」ための仕組みを作ることです。
個人の問題として処理してしまえば、次のパワハラは時間の問題です。組織的な構造や文化に根ざした問題であればあるほど、管理職や上司だけの力では限界があります。
再発防止策はまず問題の本質を把握するところから始まります。
例えば「指導の一環だった」と加害者が主張する場合、その背景に業績プレッシャーや評価制度の偏りがあったのかもしれません。逆に、部下が過度に防衛的だった場合には、上司との信頼関係構築に課題があったとも考えられます。
こうした全体像を踏まえたうえで、制度・仕組み・文化の3点を見直す必要があります。
具体的には明確な行動基準の設定と「浸透」、「機能する」匿名相談窓口の設置、マネジメント研修の定期実施などが挙げられます。
(重要なワード部分を黒字にしていますが、既に行動規範や相談窓口は設けている企業が多いですが「浸透」や「機能させる」ことができていないケースが多いのでどう組織に溶け込ませるかが重要です)
また、評価制度を「結果主義」から「プロセス評価」へとシフトするだけでも、過度なプレッシャーからくるパワハラを抑止する効果が期待できます。
特に管理職支援の現場では「言葉の再教育」が重要視されています。つまり、リーダーがどんな言葉でチームを動かすか。それが再発防止の第一歩であり、組織文化を変える核心です。
パワハラの再発防止は一時的なキャンペーンではなく、組織に根づく“仕組み”と“姿勢”の再構築から始まります。
それを本気で取り組むかどうかが、次世代の組織づくりの分かれ道になるのです。
【予防策編】パワハラを未然に防ぐ管理職のマネジメント術

パワハラの事後対応が重要なのは言うまでもありませんが本当に求められるのは“起きない組織”を作ることです。
つまり、管理職が日々のマネジメントでどう立ち回るかが、職場環境を左右します。
多くの上司は「パワハラするつもりはなかった」と言いますが、それはつまり“無意識にやっていた”ということです。この無自覚な圧力を防ぐには、マネジメントのやり方そのものをアップデートする必要があります。
ここでは、日常業務に組み込める具体的な予防策を解説します。
指示を“伝える”から“理解を促す”へ
部下への指示は、上司として欠かせない仕事です。しかし、ここでパワハラの芽が生まれやすいのも事実です。
なぜなら、「ちゃんと伝えたのに」「なんで分からないんだ」という苛立ちは、知らず知らずのうちに高圧的な言動につながるからです。
これまでの管理職はタスクの内容や納期を“伝える”ことで仕事を回してきました。
しかし、パワハラを未然に防ぐためには、“伝えた”かどうかではなく、“理解されたか”に軸足を置く必要があります。そのためには、指示を一方的に出すのではなく、確認のプロセスが重要です。
たとえば、「ここまでの説明で分かりにくいところある?」と相手の理解度を見ながら進めたり、「なぜこれをやるのか」を丁寧に共有したりすることで、納得感を持って動いてもらえるようになります。
上司という立場である以上、命令ではなく対話でリードするスタイルに切り替えることが、パワハラの予防につながります。
1on1の導入だけでは不十分?信頼関係の築き方
最近では多くの企業が1on1ミーティングを導入していますが、「やっているのにうまくいかない」「本音が引き出せない」という声もよく聞きます。
1on1はあくまで“枠”にすぎません。信頼関係を築くには、その中身と運用の仕方がカギになります。
たとえば、1on1を“業務進捗の確認の場”にしてしまうと、部下にとっては「また詰められる時間」となり、逆に心を閉ざしてしまいます。信頼構築のためには、個人の考えや感情に耳を傾ける時間が不可欠です。
つまり、「今、仕事で悩んでることある?」「最近うまくいったことって何かある?」といった問いかけが自然とできるかどうかが分かれ目です。
管理職が“聞く姿勢”を持つことで、部下は徐々に心を開きます。
そして信頼が醸成されれば、多少厳しい指摘をしてもパワハラにはなりません。1on1の導入自体が目的化しないように、まずは“信頼の土台”を意識することが重要です。
チームの心理的安全性を高める日常的な声かけとは
「うちの職場はなんとなくピリピリしている」「発言すると否定される雰囲気がある」――このような職場では、パワハラが表面化しにくく、根深く残る傾向があります。
だからこそ、管理職が“心理的安全性”を日常的に作り出す工夫が求められます。
とはいえ、特別なことをする必要はありません。
実は、ちょっとした声かけが効果的です。たとえば、「ありがとう、助かったよ」と感謝を言葉にしたり、「その考え、面白いね」とフィードバックしたりするだけでも、部下の発言意欲や安心感は大きく変わります。
(管理職目線だと分かりづらいかもしれませんが、部下の方ってかなり管理職の声を聴いています。「このシーンでありがとうと言われた」というのも覚えています。なので、細かな気配りが徐々に効果を発揮します)
また、「これってどう思う?」と意見を聞く習慣も大切です。
上司が積極的に意見を求めることで、「ここでは自分の意見を言っていいんだ」という雰囲気が生まれます。こうした積み重ねがチーム全体の空気を変え、パワハラを生みにくい環境づくりにつながります。
心理的安全性はツールや制度ではなく空気でつくられます。
その空気を動かせるのは、日々のコミュニケーションを担う上司自身です。
上司代行(管理職支援)の活用でマネジメントを分化する

すべてのマネジメントを一人で背負い込む時代は終わりつつあります。
特にデジタル組織ではプロジェクト数やチームの構造が複雑化しており、従来の管理職像では対応しきれないケースが増えています。そうした背景から注目されているのが、上司代行(中間管理職支援)という支援サービスです。
上司代行とは企業の中間管理職業務を一部代行・サポートするもので、具体的には、メンバーのマネジメント、1on1実施支援、パフォーマンスの可視化、マネージャー向け研修などを通じて、管理職の負担を分散します。
(特にプレイングマネージャーに対して効果を発揮して「プレイヤー」業務と「マネージャー」業務を二重負荷で抱えている企業様に対して業務を分化させて、「本来すべき業務」や「意思決定のスピードを上げて目標到達を現実化する」体制を創ることを目指しています)
これにより、上司自身はマネジメント業務として「聞く」「支える」ことに専念でき、強いリーダーシップと温かいマネジメントの両立が可能になります。
また、上司代行は外部の目として、パワハラにつながりやすい構造や言動を早期に発見する役割も担います。管理職が孤立せず、組織として支援体制を整えることが、パワハラ予防の土台になります。
マネジメントを“個人技”から“チームプレイ”に変える。そんな発想の転換が、これからの組織に求められているのです。
上司代行支援なら
プロストイックが実績No,1
成功企業の事例に学ぶ、パワハラを防ぐ組織づくり
パワハラを防ぐには、個人の意識だけでなく組織全体の仕組みが問われます。
特に、管理職や上司の行動だけを正すだけでは限界があります。
むしろ、パワハラが“起きにくい環境”を構造的にどうつくるかが、企業としての本質的な課題です。
実際に成果を上げている企業は、制度設計や組織文化の作り方において共通する工夫をしています。ここでは、管理職が学ぶべきリアルな成功事例を通して、パワハラを未然に防ぐためのヒントを探っていきます。
上司研修だけでなく「部下からのフィードバック制度」を導入
多くの企業で実施されている上司向けのパワハラ防止研修。
たしかに知識を得る場としては有効ですが、それだけで現場が変わるわけではありません。
あるIT系企業では研修に加えて「部下から上司へのフィードバック制度」を正式に導入し、大きな変化を生みました。
この制度では、年に数回、部下が匿名で上司のマネジメントについて意見を伝えることができます。
たとえば「指示が一方的すぎる」「発言しづらい空気がある」といったリアルな声が、直接では言いにくいことも含めて集まります。
ポイントはそのフィードバックが人事評価とは切り離されていること。
上司にとっては安全に自己改善できる材料となり、部下にとっては声が届く実感が持てる仕組みです。
この企業では、制度導入から1年で「職場の風通しが良くなった」「上司が話を聞いてくれるようになった」といった声が多数寄せられました。
パワハラの兆候を早期に察知する仕組みとしても有効で管理職のマネジメントが変わるきっかけにもなっています。上司自身が成長し続けられる環境こそ、健全な組織の土台なのです。
年次・役職を問わないフラットな対話文化が根付いた理由
次に紹介するのは、広告代理店での事例です。
この会社は役職が上がるほど会話の距離も広がってしまうという典型的な“ヒエラルキー文化”に悩んでいました。そのため、部下がミスをしても言い出せず、上司からの指摘が厳しくなり、結果としてパワハラのリスクが高まっていたのです。
そこで取り入れたのが、「階層を越えたダイアログの場」を定期的に設ける取り組みでした。
これは、役職や部門の枠を外して少人数の対話の場を設定し、テーマに沿って自由に意見を交わすものです。例えば「最近気になっている職場の空気感」「上司に期待したいこと」など、少し踏み込んだテーマを扱うことで、普段言えない本音が出やすくなります。
こうした場が継続されることで、日常のやりとりにも影響が出るようになった点です。
会議での発言が増え、雑談の中でも役職に関係なく意見を交わせる雰囲気が生まれました。管理職も「自分の言い方が強すぎたかもしれない」と気づける場になり、自然とパワハラのリスクが減ったといいます。
この成功の背景には“対話は制度ではなく文化”だという考え方があります。
形式だけを整えても意味はなく、継続して「聞き合う」経験を積ませることで初めてフラットな文化が根づくのです。上司と部下の信頼関係を築くには、日々の対話の質こそが鍵になります。
外部相談窓口の設置で社員の安心感が向上(上司代行の活用)
パワハラ対策として、社内窓口を設けている企業は多いですが、「どうせ何も変わらない」「相談したら不利になるかも」という不信感から実際に活用されないケースも少なくありません。
そこである企業が導入したのが外部の中立的な相談窓口でした。特に効果を発揮したのが、上司代行(中間管理職支援)の活用です。
上司代行(中間管理職支援)とはプレイヤー業務と管理職業務の二重負荷になっている方を主な対象としたサービスで、通常のマネジメント業務に加え社員の声を拾い上げる役割も担います。
この企業では上司代行が定期的に現場と対話をし、そこで上がった声を人事や経営層にレポートする体制を作りました。
匿名性と専門性が担保された外部窓口だからこそ、社員も本音で話すことができ、「ようやく誰かが自分のことを見てくれている」と感じられたといいます。
この取り組みによって、パワハラの兆候が事前に検知され、実際に早期対応できたケースもありました。
管理職側も外部のプロが入ることで「自分のマネジメントが客観的に見られる」環境に置かれ、改善の意識が高まりました。
安心して声を上げられる体制づくりは、被害者を守るだけでなく、上司自身を守ることにもつながります。
上司代行(中間管理職支援)という外部リソースを活用することはこれからの組織にとって“賢い選択肢”の一つです。パワハラを未然に防ぐには、社内外を巻き込んだ支援の仕組みが必要です。
上司代行支援なら
プロストイックが実績No,1
現代の管理職が持つべき“新しい上司像”とは?

時代は確実に変わっています。
かつての「強く引っ張るリーダー像」では、組織も人も動きません。特にパワハラが社会問題化して以降、上司に求められる役割は、支配者から伴走者へと大きくシフトしました。
マネジメントとは命令することではなく、信頼される関係を築きながらチームを成果へと導く技術です。これからの管理職に必要なのは、単なる管理能力ではなく、“人と人をつなぐ力”です。
「恐れられる上司」から「信頼される上司」へ
もう「威圧的な上司」が通用する時代ではありません。
声を荒げて部下を動かすことは、組織の空気を重くし、心理的安全性を奪います。社員が意見を言えない空気の中で生まれるのは、ミスの隠蔽と不信感だけです。
一方、信頼される上司は自らを飾りません。
わからないことはわからないと言い、部下の話にきちんと耳を傾けます。
指示の前に「なぜそれをやるのか」を丁寧に共有し、納得感を与えることを怠りません。
こうした上司のもとでは、自然とチーム内に対話が生まれます。怖さではなく信頼で人が動く職場をつくることこそが、これからの管理職の仕事です。
指示待ち部下を育てない“問いかけ”型コミュニケーション(受け身な部下が多いという課題)
多くの管理職が悩むのが、「受け身な部下が多い」という課題です。
しかしその原因をたどると、上司の“指示出しスタイル”にあることが少なくありません。「こうして」「次にこれ」と細かく指示を出し続けるほど、部下は自ら考える力を失っていきます。
そこで効果的なのが、“問いかけ型コミュニケーション”です。
たとえば「この提案の目的は何だと思う?」「どの進め方が一番効果的だと感じる?」と問いを投げることで、部下自身の思考を促すのです。最初は時間がかかっても、自分の頭で考える習慣が根づけば、次第に指示を待たず動ける人材に育ちます。
マネジメントとは、人を「育てる仕事」でもあります。目先の成果だけにとらわれず、問いかけを通じて思考力を養うことが、長期的にはチームの生産性を押し上げる最良の手段です。
一方でそこまで個別にケアできるほどの余力がないというのも現状あるかと思います。それは既に体制を見直す局面にきているということです。課題を棚に上げて優先順位をつけて仕事をしているかとは思いますが、向き合うべきは部下であり、部下のモチベーションが上がることで部署全体の生産性も上がります。
部下からの評価も“マネジメント力”の一部と捉える
「上司は部下を評価する側」という固定観念は、もう古いと言わざるを得ません。これからの管理職には、部下からどう見られているかを正しく把握し、そのフィードバックを自らの成長材料として活かす視点が求められます。
たとえば、360度評価の導入や、定期的なフィードバック面談を通じて、上司が自分のマネジメントスタイルを点検する機会を設ける企業も増えています。
特に、上司代行や外部支援による第三者視点が入ることで、組織としてのマネジメント改善が一気に進むケースもあります。
部下からの評価を「攻撃」ではなく「改善のヒント」として受け止められる上司こそ、これからの時代に求められる存在です。
信頼され、支えられるリーダーは、まず自らが学び続ける人であることが大前提なのです。今こそ、“新しい上司像”を体現できる管理職が組織の未来を担っていくべきです。
まとめ|パワハラを防ぐ鍵は“日常”にある
パワハラ防止に特効薬はありません。
ルールを設けても、研修をしても、それだけでは根本的な解決にはつながりません。
真に意味のある対策とは、日々の言動、対話、マネジメントスタイルの中に宿る“習慣”の中にあります。管理職一人ひとりが、「普段の接し方」そのものを見直すこと。
これが最も強力で現実的な予防策です。今の時代、パワハラは“意図していなかった”では済まされません。だからこそ、「気づける上司」「軌道修正できる組織」を日常的につくっていくことが重要です。
管理職自身の意識改革が最も強力な予防策

マネジメントで起こるトラブルの多くはスキルよりも“スタンス”の問題です。
知識があっても、「自分は正しい」と思い込み、相手に耳を傾けなければ、パワハラは防げません。
だからこそ管理職自身が「自分の関わり方」を客観視し、柔軟にアップデートしていく姿勢が必要です。
パワハラを防ぐ上で最も効果があるのは、「変わる意思」を持つことです。信頼関係は一朝一夕では築けませんが、上司が自らの言動を見直し、誠実に部下と向き合うことで、確実に空気は変わります。それができる人こそ、これからの時代に必要とされる管理職です。
合わない”と割り切ることも最終的には必要
全ての部下と完璧な関係を築けるわけではありません。
価値観や働き方の違いから、どうしても“合わない”部下もいます。
そういった相性の問題は、無理にねじ伏せようとすると逆効果です。
(これ非常に重要です。特にキャリアを築いてきた管理職・上司の方は自分の実力で部下をねじ伏せようとしますが絶対に逆効果なので辞めた方がいいです)
お互いのストレスが溜まり、やがてパワハラに転じるリスクすらあります。
だからこそ、「関係を変えようとしすぎない」という選択も時には正解です。
例えば、部下の異動やプロジェクトの再配置、あるいは第三者的な上司代行サービスを活用することで、無理なく環境を調整することができます。問題を抱え込むのではなく、冷静に対処する視点が管理職には求められます。
組織全体で“パワハラゼロ”を目指すには
個人の努力だけでは限界があります。
だからこそ必要なのは、組織全体で「パワハラゼロ」を当たり前にする文化づくりです。
上司と部下の関係性だけでなく、人事制度、フィードバック体制、相談窓口など、組織構造として“安心して働ける土台”を整えることが欠かせません。
特に効果があるのは、現場の中間管理職を支援する体制です。
管理職は孤独になりがちですが、そこに外部の支援や上司代行のような第三者が入ることで、冷静な判断や相談が可能になります。組織全体で管理職を支える仕組みがあってこそ、パワハラは防げるのです。
「変わる上司」こそ、これからの組織の要
最終的に組織を良くする力を持っているのは“上司”です。
上司が変われば、部下も変わり、チームも変わります。かつてのように「強くあれ」「結果を出せ」とだけ求められる時代は終わりました。
これからは「信頼される上司」「人を育てる上司」こそが、組織の要になります。
パワハラを防ぐのは、制度やマニュアルだけではありません。
一人ひとりの上司が、日常の関わり方を見つめ直し、変化を恐れずアップデートし続けること。小さな変化の積み重ねが、組織全体を変える大きな力となります。今、必要なのは“変われる上司”であること。その一歩が、パワハラのない、健全な職場をつくる第一歩です。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック