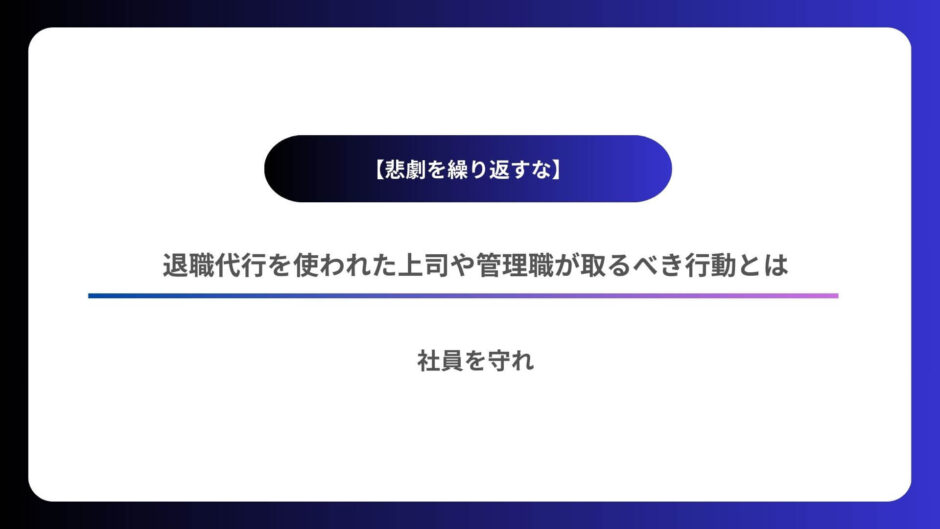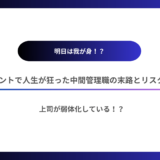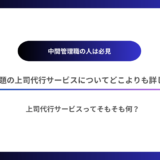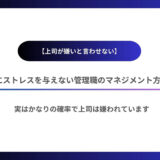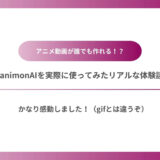皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。
本日は今話題の退職代行についての記事ですが、使う側ではなく「部下や社員に使われてしまった企業側」目線での解説記事となります。
- 自分の部下が退職代行を使い退職してしまい自分のマネジメントに自信がない
- 退職代行を使われ、他の部下も退職するリスクを抱えている
- 退職代行を使われない職場にするための手段や対策
当サイトでは上司のマネジメント系に関する悩みの記事が非常に多く読まれています
退職代行を使われる理由とは(上司との関係性・職場風土)

「突然、あの部下が退職代行を使って辞めた」という話はもはや珍しくなくなりつつあります。
以前は一部の若年層に限られた現象と見られていた退職代行ですが今ではどの業種・職種でも起きうるリアルな問題となりそうです。
そしてその背景にはただの「逃げ」や「甘え」では済ませられない、上司や管理職との関係性や、職場の空気感といった深い問題が潜んでいます。
ちなみに上司や人事の方で社員が退職代行を使うのは「若気の至り」や「単純な逃げ」と捉えている方はおそらくマネジメントや人事に向いていないので今すぐ考えを改めてください。
(煽っているわけではなくこの記事を読んでぜひ見直す「きっかけ」にしていただきたくやや語尾を強めに書いています。当社でも管理職やチームリーダーの方を支援していますが、ご自身の考え方・価値観を突然変えるというのは非常に難しく時間もかかります。ぜひ本記事を通じて考え方を変える「きっかけ」を掴んでいただきたく存じます)
まず本見出しでは「なぜ人は退職代行を選ぶのか」。その決断の裏側にある“上司との距離感”や“辞めづらい組織の構造”について深掘りしていきます。こうした構造的な課題に気づかずただ「またか」と流してしまえば、同じ悲劇は何度でも繰り返されるでしょう。
ハラスメント・人間関係への不安
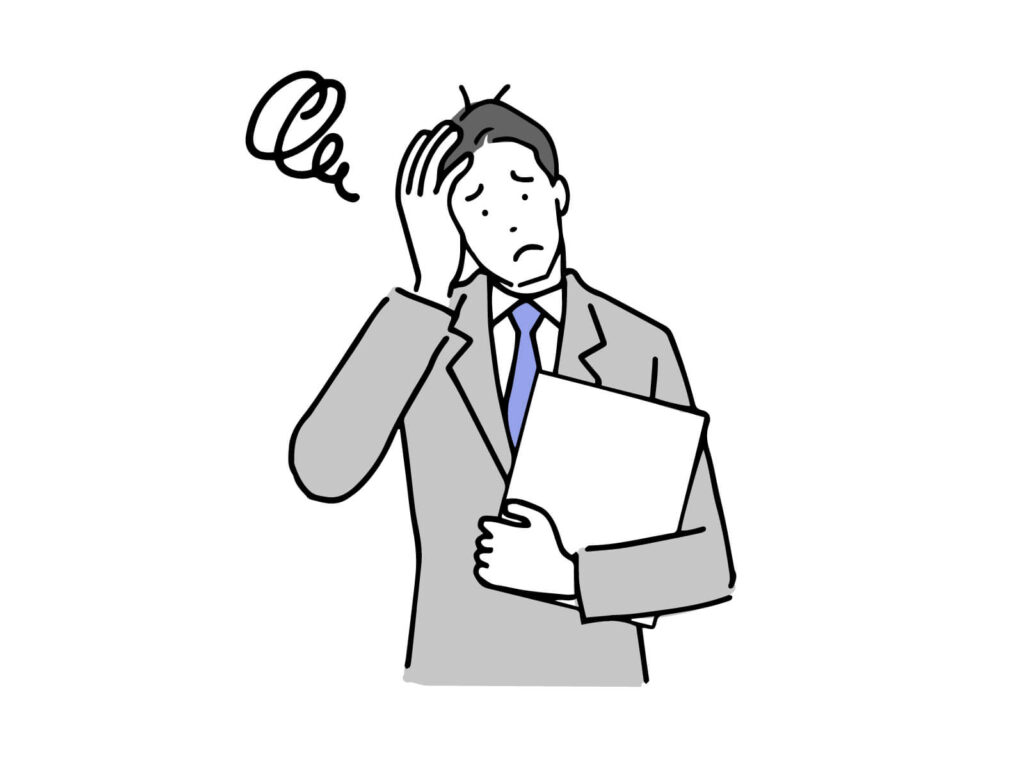
退職代行が選ばれる理由の中で、最も多く挙がるのが人間関係のトラブルや職場でのハラスメントです。
厚生労働省の統計でも若年層の離職理由として「職場の人間関係」が常に上位にランクインしています。
特に、直接的に言いづらい、抗議しづらい環境がある場合、退職代行を“唯一の脱出口”と捉えるケースも多くなります。
筆者が間接的に直面したケースではある20代の社員がパワハラに近い叱責を受け続けた末に、言葉を発することすら怖くなり、会社との連絡も断ち切って退職代行にすべてを委ねたという事例がありました。上司との信頼関係がゼロに等しくなったとき、人は対話を諦めるのです。
「ただ厳しく指導しただけ」「昔はこれが当たり前だった」——そんな言い分が今でも管理職の中には根強く残っています。しかし、それが相手にとってどれだけのプレッシャーになるか、どれほど精神的に追い詰めるかを、自分では気づけないのがこの問題の厄介なところです。
退職代行という行動には単に会社を辞める以上の意味があります。
それは「自分の声をもう直接伝える手段が残っていない」という、最後のメッセージでもあるのです。管理職がこの“沈黙のメッセージ”をどう受け取るかが、今後の組織の健全性に大きく関わってきます。
退職を言い出せない組織の空気

退職代行が利用される背景には必ずしも個別のトラブルだけではなく、職場全体の空気感も深く関係しています。特に退職を「裏切り」「甘え」と捉える文化が強い職場ほど、社員が辞めたいという本音を口に出せず、追い詰められていく傾向が見られます。
ある企業で実際にあった事例では、退職を申し出た社員に対して上司が「こんなタイミングで辞めるのか」「根性がない」と詰め寄り、結果的にその社員は退職の意思を撤回しました。
しかしその数週間後、同じ社員は退職代行を使って姿を消しました。なぜなら、一度圧力を受けた経験によって、“もう話し合いは通じない”と判断したからです。
このように、「言えない雰囲気」こそが退職代行を選ばせる最大の要因になることもあります。そしてこの空気感は上司や管理職が無意識に作り出していることが多いのです。
たとえば、「誰も辞めたがらない」「ウチは仲が良い職場だ」と言いながら、実際には“辞めにくい職場”になっているという矛盾がよく見受けられます。これは評価制度や感情論が辞意の表明を妨げている証拠でもあります。
「退職代行=逃げ」ではなく、「話し合いの扉が閉ざされた結果」だと捉えることが、これからの上司や管理職に求められる視点です。
「辞めにくさ」を生む上司の無自覚な態度

上司や管理職の言動が知らず知らずのうちに「辞めにくい職場の空気」を作り出していることがあります。
それは明確なパワハラでなくても、何気ない一言、ちょっとした態度の積み重ねで、部下は「この人には退職の話を切り出せない」と感じてしまうのです。
たとえば、「若者はちょっと苦労するべき」「俺の時代は〇〇」「お前が抜けたら回らないぞ」といった言葉。
(極論ではなく現実的な話として今の40代、50代の方が若いときに上司から言われていた言葉は今の若者にとってはたいてい「うざい」と感じていると捉えてもらったほうがいいです)
これらは冗談や軽いプレッシャーのつもりでも、受け取る側にとっては非常に重たい言葉です。特に20代の若手社員や、繊細な性格の部下にとっては、「辞めたら裏切り者になる」と感じてしまうきっかけになりかねません。
筆者が相談を受けた中には直属の上司が「本音で話していいよ」と言いながら、部下の悩みに対して毎回“論破”する癖があったというケースがありました。
(だから二度と本音で話さないし、「本音で話をしていいよ」といきなり切り出す人に限って裏があり、本音で話しづらいということもわかっています)←じゃあどうすればええねんという対策を本記事で解説します。
結果として、部下は相談すること自体をやめ、最終的には退職代行を選びました。「話すだけムダだ」と思わせるような対応は、対話の断絶を生む第一歩なのです。
上司の側に悪気がなくても、態度の裏にある「押し付け」「過干渉」「自己正当化」が、部下にとっては圧力となってしまうことが少なくありません。管理職は「何を言ったか」だけでなく、「どう伝わったか」を常に意識する必要があるということです。
退職代行が使われたという事実を、ただの“突然の退職”と受け止めるのではなく、「辞められる前に、何かできたことはなかったか?」と自省する姿勢が、次の悲劇を防ぐ鍵になります。上司の無自覚が、部下の沈黙と退職につながる。その現実を、今こそ直視すべき時です。
退職代行を使われた体験談:ある日突然、社員がいなくなった
「出社してこないと思ったら、まさか退職代行だった」——この衝撃的な経験は今や管理職や上司にとって決して他人事ではありません。退職代行の利用者数は年々増加しておりもはや“特殊な辞め方”ではなく、誰にでも起こり得るリアルな現象になりつつあります。
ここでは実際に退職代行を使われた上司や現場がどのような混乱に直面したのか、そしてそれが管理職にどんな心理的影響を与えたのかを、体験談をもとに掘り下げていきます。「退職代行」「上司」「管理職」「悲劇」というキーワードが交錯するリアルなエピソードから、同じ事態を繰り返さないためのヒントが見えてきます。
見知らぬ番号からの電話。退職代行業者からの通告

ある朝、いつものように出社した上司(管理職Aさん)のもとに、見覚えのない携帯番号から着信がありました。迷惑電話かと思いながらも一応出てみると、相手は「〇〇退職代行センター」(仮称)と名乗り、「貴社に勤務中の〇〇さんより、退職の意思を承りました。本日をもって出社はありません」と伝えてきました。
上司(管理職Aさん)は一瞬、意味がわからず沈黙。つい昨日まで普通に会話していた部下が、今日から突然いなくなるという現実。
その上司(管理職Aさん)から思えば比較的良好なコミュニケーションを取れていると思っていました。
確かにミスしたときは注意をするけど一方的な叱責なんてしてないし再発防止の改善や対策を一緒に考えていたし、部下から飲み会にも誘われたから行っておごりもしました。
日常的に会話もしていて、プライベートな話とかもオフィス内でしていました。
なのに退職代行、、、、頭が真っ白になりました。
しかもその事実を、本人ではなく第三者の退職代行業者から知らされるのです。これが、退職代行がもたらす“断絶の始まり”です。
このような状況では、驚きや動揺だけでなく、「なぜ本人から何も聞いていないのか?」「いつから決まっていたのか?」という疑問とショックが一気に押し寄せてきます。
上司(管理職Aさん)の中には、「最初は詐欺電話かと思った」「ドッキリ企画かと思った」と本気で混乱していた人もいました。
「退職代行」という手段には本人と職場との関係を完全に遮断する強烈な性質があります。
電話一本で事実だけを告げられるその冷たさが、上司にとっては「自分が拒絶された」という強い感覚として残りやすく、感情的な混乱を長引かせる要因にもなります。
引き継ぎゼロ、本人と連絡もつかない現場の混乱

退職代行を通じて退職の連絡が来た場合、最も現場を混乱させるのが引き継ぎの完全な不在です。
通常であれば、退職者は後任への業務説明や資料整理を行い、一定の期間をかけてスムーズな離脱を目指します。しかし退職代行が介入する場合、その流れは完全に断たれてしまいます。
先程の管理職Aさんの場合は別の社員の方を通じて引き継ぎをさせてもらったようですが、引き継ぎ(業務・有給消化・PC返却)についても当人とではなく弁護士などを通じてやり取りをします。
(ちなみに賢い人は引き継ぎのフォルダを社内のクラウドサーバーに残して、PCも会社のロッカーに入れてから辞めていくようです。)
当人と連絡が取れないケースに関しては社内が非常に混乱します。関係部署に辞めた当人の業務内容を確認しても、「本人しか把握していなかった」「メモが一切残っていなかった」という状態で、業務のブラックボックス化が露呈します。
また、本人と一切の連絡が取れないことで、「何を聞いても誰も答えられない」「顧客からの質問にも対応できない」といった問題が次々に起こります。(社内だけの業務であればよいですが、クライアントワークしていて何10社もクライアントを担当していた際には対応は相当大変です)
管理職としては現場を守るために対応に追われながら、「なぜここまで事前に気づけなかったのか」と自責の念にかられるケースも少なくありません。
「退職代行」という選択肢は個人間だけで済む話ではなく、組織としての対応を極端に難しくする側面もあります。この“突然の不在”によって、残されたチームメンバーにも影響が波及し、次なる離職リスクの火種にもなりかねません。
「自分が悪かったのか?」と悩む上司・管理職の声
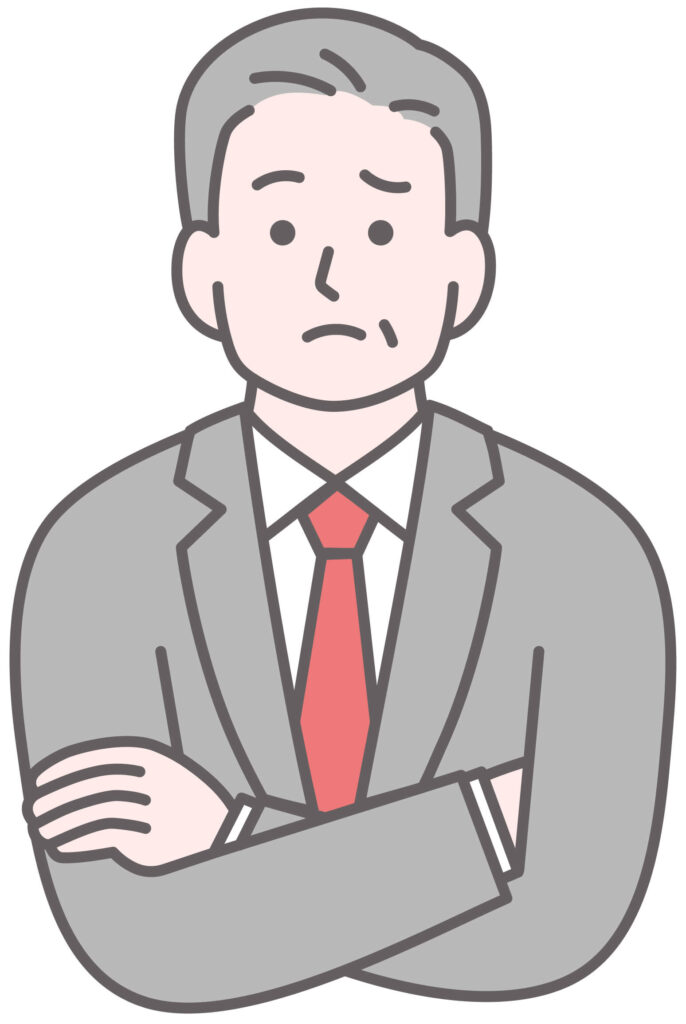
退職代行を使われた上司の多くが、その後に抱える共通の悩みがあります。
それは、「自分の接し方に問題があったのかもしれない」「もっと早く異変に気づけていたら、違う結果になっていたのではないか」という、自己否定に近い思考です。
ある50代の課長職は10年以上管理職として部下を育ててきた自負がありました。
そんな彼が、ある日突然部下から退職代行を通じて辞職を知らされたとき、最初は怒りよりも「なんで直接話してくれなかったんだ」という深い寂しさと無力感に襲われたと言います。
後日、残された社員に状況を確認したところ、「辞めた本人は、課長に何を言っても“気合で乗り切れ”と返されるから話せなかった」と言っていたことを知らされました。その言葉を聞いて自己嫌悪で数日間眠れなくなったと語ってくれました。
退職代行が突きつけるのは、ただの人員欠如ではなく、信頼の欠如です。そして、それが上司自身の言動や態度の結果だったかもしれないという可能性が、精神的なダメージとして残ります。
もちろん、すべての責任が上司にあるわけではありません。
けれども、「自分は何を見落としていたのか」を振り返る姿勢がなければ、同じ状況はまた繰り返される可能性があります。管理職が“反省できる大人”であるかどうかが、次の世代との信頼構築に直結しているのです。
退職代行は一方の退職者にとっては「最終手段」であると同時に、もう一方の上司・管理職にとっては「突然の断絶」として突きつけられるものです。
そこにある感情は怒りではなく、困惑、そして「自分はどうすべきだったか」という問いです。
この問いを放置せず、自ら考え、行動を変えることでしか、悲劇の再来は防げません。
退職代行を使われた上司・管理職が取るべき行動とは
退職代行を使われた瞬間、上司や管理職の立場からすれば混乱と感情の揺れは避けられません。「なぜ本人から何も言ってくれなかったのか」「自分は嫌われていたのか」と思い悩むのも当然です。
しかし、そこで思考停止してしまうと、現場ではさらに混乱が広がり、最悪の場合“連鎖退職”という二次災害にもつながりかねません。
この見出しでは退職代行という出来事が発生した直後から、上司・管理職が現実的に取るべき行動をステップごとに整理します。単なる感情論ではなく、「これをやっておくことでチームと職場の未来を守れる」という視点から、今後の対応を考えていきましょう。これは同じ悲劇を繰り返さないための、最初の一歩です。
まずは冷静に現実を受け止める

退職代行の連絡が入った瞬間、ほとんどの上司が「まさかあの子が?」とショックを受けます。
突然の報告、引き継ぎなしの事実、そして一切の相談がなかったことへの戸惑い。ここで焦って動いてしまうと、さらに状況を悪化させかねません。まず必要なのは、冷静に現実を受け止めることです。
筆者が直面した事例では上司が感情的になって他のメンバーに「あいつは逃げた」「裏切り者だ」と言ってしまい、結果的に職場全体の空気がさらに悪化。
残った社員からの信頼も失うという“二重の失敗”に陥っていました。
ここで意識したいのは、「今ここにいるメンバーを守る」ことが上司の役割であるという事実です。
辞めた社員への怒りや悲しみを感じるのは自然ですが、それを周囲に見せたり、発散したりするのは職場全体の士気にマイナスです。
退職代行は「その社員がもう会話を選べなくなった末の手段」だったかもしれません。であればこそ、上司自身が冷静であることが、組織の信頼を守るカギになります。ここでの対応次第で、チームの空気は大きく変わるのです。
チームや残った社員への影響を最小限に

退職代行がもたらすのは単なる一人の退職ではありません。
そこには、「次は自分かもしれない」「あの上司には本音が言えないかも」といった、チーム全体に漂う不安がセットで付いてきます。これを放置しておくと、残ったメンバーのモチベーションが低下し、結果的に連鎖退職につながる危険があります。
また1人が退職代行を使うということは潜在的にも「本音を言えば退職したい」と思っている方もいる可能性が高いです。
なので管理職としてまず行うべきは、今いるメンバーの不安を拾い上げることです。
たとえば、個別面談を設けて一人ひとりに現状の負担や気持ちを確認したり、「〇〇さんが突然辞めたことで、困っていることはあるか」と声をかけたりするだけでも、部下の安心感はまったく違ってきます。
筆者が取材した企業では退職代行で社員が辞めた翌週に、マネージャーがチーム全員と一対一で対話の時間を設けました。その結果、「実は自分も辞めようか迷っていたが、ちゃんと話を聞いてもらえて踏みとどまった」という声が複数上がったそうです。
上司が逃げずに向き合ってくれる姿勢を示すこと。それが、組織内の信頼を維持し、残った社員が安心して働き続ける環境を守るために、何より重要なのです。
本人と連絡が取れないときの対応マニュアル
退職代行を通じての退職では本人と一切の連絡が取れないという事態が頻繁に起こります。
ここで焦って個人連絡を繰り返す、SNSを探す、家族に連絡するといった行動は逆効果であり、法的・倫理的にもトラブルの元となりかねません。
対応の基本はあくまで「会社」としての手続きを、冷静に、丁寧に進めることです。
労務・人事と連携して、退職届の代替確認、備品の返却依頼、未払い給与や有給消化の確認といった、必要最低限の事務処理を行います。
筆者が実際に見た良い対応例では退職代行業者とのやり取りにすべてを委ね、社員には「本人とは今後直接の連絡を控えてください」と伝える一方、引き継ぎ資料が存在しない場合には、残されたログや業務記録からチームで再構築を進めていました。
過去にしがみつかず、未来の再構築に集中する姿勢が印象的でした。
「退職代行=非常識」と捉えて相手に感情をぶつけたくなる気持ちも理解できますが、現実には「もうその社員はこの場にいない」という事実を踏まえた、非感情的・事務的な対応が求められるのです。
二次災害(次の利用者)を防ぐための部署内のケア
退職代行が一人に使われると、「次は誰が辞めるか」と組織内に妙な緊張感が走ることがあります。いわゆる“連鎖退職”や“退職代行の連鎖”を防ぐには、部署全体への心理的ケアが不可欠です。
ここで重要なのは「〇〇さんが辞めた件について、どう受け止めているか」を部下一人ひとりとすり合わせる機会を持つことです。
直接的な理由を問いただす必要はありませんが、「最近仕事の負担が増えていないか」「不安に感じていることはないか」といった、相手の心を“聴く姿勢が鍵になります。
また、普段から業務を一人で抱え込まないようにする工夫も重要です。属人化を防ぎ、誰かが抜けてもカバーできる体制があれば、「抜けたら困るから辞めにくい」→「辞めづらさから逃げ道を探す」といった流れも生まれにくくなります。
「退職代行=個人の問題」ではありません。むしろ、チーム全体に関係する空気や構造がそうさせた可能性がある以上、部署単位での対話とメンテナンスが求められます。それこそが、次の“悲劇”を防ぐ唯一の手段です。
二度と“退職代行される職場”にしないために
最後にもっとも本質的なポイントに触れます。
それは、「退職代行を使われない職場とは、どういう組織なのか?」という問いです。
答えはシンプルで、辞めたいときに“直接言える”空気がある職場です。
辞めること自体は悪ではありません。問題は「辞めることを言い出せない」空気があること。
これを変えるには上司が「辞める相談も、業務の一部」と捉えるマインドにシフトする必要があります。
たとえば「最近どう?迷ってることがあれば今じゃなくてもいいので教えてくれると嬉しい」「もし将来のキャリアに迷ったら、他社を視野に入れてもいい」といった、出口も含めたオープンな対話ができることが、職場への信頼に直結します。
筆者が出会ったある理想的な管理職はこう言っていました。「辞める相談すらできないような職場で、人は安心して働き続けられない。だからこそ、退職の相談を受けられる上司でいたい」と。
退職代行が一度でも起きた職場はそこに原因がある限り、何度でも繰り返されます。そうならないために、まずは“言いやすい雰囲気”をつくるのが上司の仕事です。そしてそれが、真に健全な組織をつくる第一歩でもあります。
上司や管理職が退職代行を使われたときにしてはいけないNG対応
退職代行を使われたとき、上司や管理職として冷静に対応することは非常に重要です。
しかし、突然の事態に感情が先走り、誤った言動をしてしまうケースも少なくありません。こうした“NG対応”は、本人との関係をさらに悪化させるだけでなく、残った社員の信頼を損ない、職場全体の空気に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この見出しでは退職代行という手段を使われた際に、上司・管理職が絶対に避けるべき行動を明確にしつつ、どうすれば適切に対応できるかを、実務的かつ法的観点も踏まえて解説します。悲劇を繰り返さないために、感情ではなく「正しい判断力」を持つことが、管理職に求められているのです。
労務対応で必要な記録と手続き
退職代行を使われた場合、まずやるべきは「本人に直接連絡を取ること」ではなく、会社としての正当な労務手続きを淡々と進めることです。ここで感情的に動き、「なんで急に?」「本人に確認しないと処理できない」と混乱することは、労務トラブルの火種になります。
退職の意思表示は法律上、本人の自由です。たとえ退職代行業者を介していたとしても、本人の意思が明確であれば退職は成立します。そのため、まず対応すべきは、以下のような記録と手続きの整理です。
- 退職代行業者とのやり取りはすべて記録(メールや書面)として保管
- 本人からの意思表示があった日付を起点に、退職日を確定
- 有給休暇の残日数確認と、退職日までに消化されるかの調整
- 雇用保険・社会保険の資格喪失手続き、源泉徴収票の送付手続き
- 貸与品(PC、制服、IDなど)の返却方法を明文化して送付
筆者が直面した企業では退職代行の連絡を受けた翌日に社労士と連携を取り、速やかに労務対応を始めたことで、本人と一切の連絡が取れない中でも、トラブルなく退職処理を完了できたといいます。
逆に「本人と直接話さないと手続きできません」と対応を保留した結果、退職の効力発生日が曖昧になり、給与や社会保険の計算で混乱を招いたケースもありました。
上司や管理職が陥りがちなNG対応は個人感情を先行させて手続きを後回しにすることです。どれだけ納得いかない退職でも、労務は“感情抜き”で正確に行う。これが、職場の信頼を守る最初の一手となります。
退職代行は合法?違法?
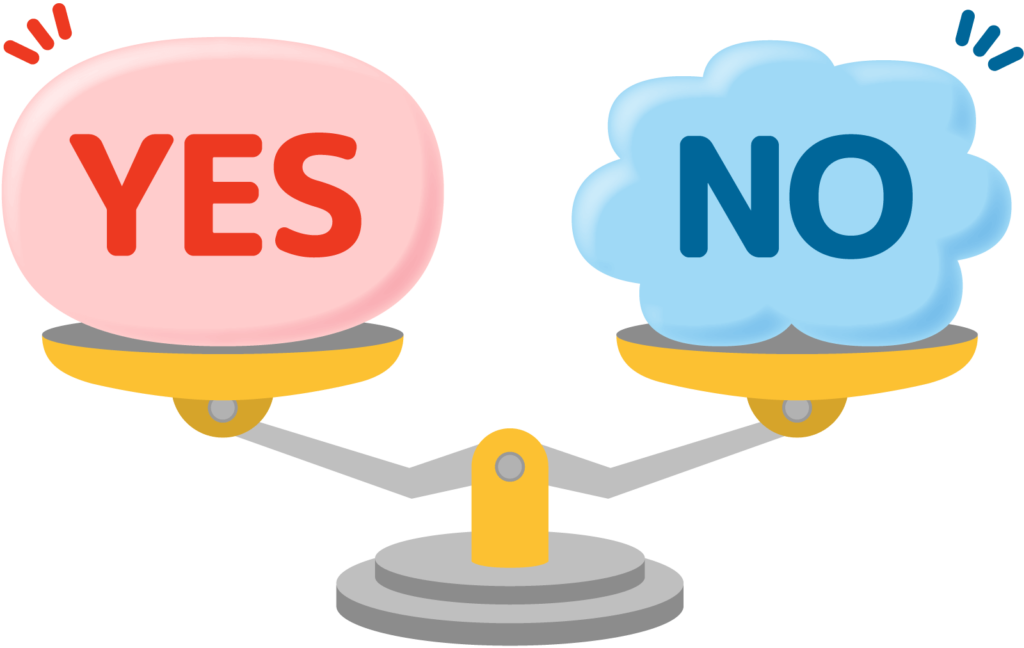
退職代行を初めて利用されたとき、多くの上司や管理職が抱く疑問の一つが「これってそもそも合法なのか?」というものです。
結論から言うと、退職代行そのものは合法です。ただし、提供する側の業者がどのような行為をするかによって、合法・違法の線引きが変わってくる点には注意が必要です。
まず、退職の意思表示自体は、労働者に完全な自由が認められています。これは民法627条に基づき、正社員でもパートでも「2週間前に意思表示すれば、理由を問わず辞められる」という原則があるため、本人が直接言うか、誰かを通じて言うかに関係はありません。
(2週間前の意思表示なので、有給が残っている人は使えるケースが多いですが、残っていない場合は無休で退職となります。(厳密には有給ゼロの場合、退職日は社内では2週間後で2週間は無休での休暇という扱いになり一応は在籍していることになります))
問題になるのは退職代行業者が“交渉行為”に踏み込んだ場合です。たとえば、「退職金の増額交渉」や「有給消化を強く要求する」など、法律的に“非弁行為(弁護士でない者が法律業務を行うこと)”にあたる場合、それを行った業者が違法と判断されることがあります。
したがって、退職代行を使われた企業側としてNGなのは「退職代行は違法だから無視する」「非弁行為だから本人と直接連絡しなければダメだ」といった独自判断をすることです。あくまで会社としては、「本人の退職意思が明確かどうか」に基づいて処理を進めるのが基本です。
対応に慣れていない上司が「退職代行は認めない」と突っぱねた結果、本人側から弁護士を通じて抗議を受けたとのこともあるようです。
「退職代行=違法ではない」「本人の退職意思を尊重するのが法的にも正解」——この認識を正しく持つことが、余計なトラブルを防ぐための管理職の“知識リテラシー”です。
退職代行を使われた瞬間、上司や管理職が取る行動はその後の組織運営や社内信頼に大きな影響を与えます。「不誠実だ」「非常識だ」と感じるのは当然かもしれませんが、その感情をどう処理するか、どこで線を引くかが、次の信頼構築に繋がっていきます。
個人への怒りではなく組織としての正しい手続きと対応を。その積み重ねこそが、二度と“退職代行される職場”にしないための基礎となります。
管理職・上司としてのふるまいに限界がある場合は上司代行(中間管理職支援)の活用も視野に
退職代行を使われた経験がある上司や管理職は「もっと自分がちゃんとしていればよかったのではないか」と必要以上に自分を責めがちです。
確かに、部下とのコミュニケーション不足や態度の見直しが求められる場面もあります。
しかし一方で、すべてを個人の責任として抱え込むことにはリスクがあります。
なぜなら、そもそも上司や管理職という役割には、マネジメントできる範囲に物理的な“限界”があるからです。
ここでは、現場で求められる上司のふるまいと、その負荷の実態を正しく見つめ直した上で、近年注目されている「上司代行(中間管理職支援)」という新たな支援の選択肢について紹介していきます。
詳しい解説についてはこちらの記事で細かく解説していきます。
悲劇を繰り返さないために必要なのは「上司が完璧であれ」というプレッシャーではなく、「必要な支援を受けながらチームを守る」という新しい発想です。
上司・管理職のマネジメント範囲も限界がある
管理職という立場には日々の業務指導、評価、採用、部下育成、メンタルケア、そして時には離職対応まで、実に多くの責任がのしかかります。
それに加えて自らの業務目標も背負っているのが、現代の管理職のリアルです。
筆者がヒアリングしたある課長職の方は、「部下が辞めたあと、残ったメンバーの不満対応をしていたら、自分のプロジェクトの進行が1週間遅れた」と話してくれました。
さらに、その遅れが原因で本部からプレッシャーを受け、「何のために部下を守っているのかわからなくなった」とまで語っていました。
このように、上司という立場には“プレイヤーであり、マネージャーでもある”という二重の負荷が常に存在します。全員のコンディションを気にかけながら、自分自身も評価にさらされている構図は、どこかで必ず破綻が生まれます。
さらに、近年ではハラスメント対策や多様性配慮、メンタルヘルス対応など、「専門家でなければ難しい」領域のマネジメントまで求められがちです。いくら優秀な上司でも、“全方位完璧”は不可能に近いのが現実です。
だからこそ、今必要なのは「上司が弱音を吐いてもいい」という風土づくりです。そして、マネジメントの限界を感じたときに、「上司代行」「外部の中間管理職支援サービス」といった選択肢を柔軟に使える環境です。
上司代行(中間管理職支援)とは心理的安全性のある中立的な第三者が、部下との間に入ってヒアリングを行ったり、メンタル支援をしたりする新しい取り組みです。
専門的な知見を持つ人材がサポートに入ることで、“部下が本音を言える場”を上司の代わりに確保することが可能になります。
こうしたサービスを導入する企業も増えており、実際に「部下が安心して相談できるようになった」「上司の孤独が減った」といった声も聞かれます。
「自分がもっと頑張らなきゃ」ではなく、「足りないところは頼っていい」という意識こそが、管理職を燃え尽きから救い、結果的に退職代行のような悲劇を防ぐ根本対策になるのです。自分一人で抱え込まない、それがこれからの上司の在り方ではないでしょうか。
退職代行を“きっかけ”に職場を進化させる

退職代行を使われることは上司や管理職にとって衝撃的な体験です。突然の連絡、何の前触れもなく去っていく部下、そして残されたチームの混乱。心が追いつかず、「なぜこんなことに…」と自問し続ける方も多いでしょう。しかし、この“苦しい現実”は、ただの後悔で終わらせてはいけません。
実は、退職代行を使われたという事実こそが、組織の課題が表面化したサインであり、そこに向き合うことで職場は“進化”することができます。
この記事の締めくくりとして、この痛みをどう糧にし、よりよいチームへと再構築していくか。その具体的なヒントを3つの観点から整理していきます。悲劇をチャンスに変えるために、今こそ行動が求められています。
辛い経験をどう組織改善に活かすか
退職代行が使われた瞬間、管理職が感じるのは多くの場合「裏切られた」「信頼されていなかった」というネガティブな感情です。それは決して間違っていません。
しかし、そこで終わってしまえば、同じ問題は繰り返されるだけです。大切なのは、「なぜ話してくれなかったのか」「何が辞める決断を後押ししたのか」といった背景をチームで共有し、構造的な改善に繋げることです。
筆者が支援したある企業では退職代行をきっかけに、社員の声を拾う匿名アンケートを導入しました。
これは直属の上司が一切関与しない第三者の調査機関からのアンケートになります。
その結果、「直属の上司には相談しづらい」「叱責のトーンがきつくて本音が言えなかった」という具体的な声が多数寄せられ、マネジメント層の研修内容が根本から見直されることに。
こうした取り組みに共通しているのは、“個人の問題”ではなく“組織の課題”として捉える姿勢です。
退職代行はあくまで“結果”であり、その背後には職場環境の歪みが必ず存在します。だからこそ、逃げずに直視し、事実をもとに改善へとつなげる。その姿勢こそが、組織の進化に必要な第一歩です。
「辞めたい」と言える職場が健全な理由

「退職を申し出たら怒られる」「評価が下がる」「話を聞いてもらえない」——そんな空気の中で、人は本音を封印し、限界を迎えたときに“退職代行”という手段に走ります。つまり、本当に必要なのは、退職を“言える環境”を日頃から作っておくことです。
辞めたいと思うこと自体は、誰にでも起こり得る自然な感情です。キャリアの方向性が変わることもあるし、価値観がズレてくることもあります。そのときに、「一度ちゃんと話そう」と言える場があるだけで、退職の在り方はまったく違ったものになります。
筆者が支援しているベンチャー企業では、「面談」を第三者を通じて頻度高く実施しています。実際にその面談を通じて、異動や役割変更をしたいという声も多く実際にキャリアチェンジを社内でして活躍する社員も多く、「選択肢の一つ」として前向きに捉える文化が根付きつつあります。
上司や管理職が「辞める話を聞くのは怖い」と感じるのは当然ですが、言えない職場こそが危険なのです。なぜなら限界まで我慢した結果、ある日突然いなくなる“退職代行”という形で爆発するからです。
「辞めたい」と言ってもいい職場。そこには安心感、信頼、そして“対話の文化”が息づいています。そんな土壌を作れるかどうかが健全なチームづくりの分水嶺です。
離職を防ぐ上司・管理職のあり方とは
離職を完全にゼロにすることは不可能です。
人には人生の転機があり組織と価値観が合わなくなることもある。ただ、“突然辞めるしか選択肢がない”状態を防ぐことはできるのです。その鍵を握るのが、日頃からの上司・管理職のあり方にあります。
大事なのは「話を聞いてくれる人だ」「弱音を吐いても否定しない人だ」という印象を持たれているかどうかです。立場上、指導や評価は避けられませんが、その一方で“安全基地”のような存在であることが、現代の上司には求められています。
筆者が印象に残っているのはある上司のこの一言です。
「辞めるかどうかの決断は最終的に本人がすること。でも、その決断の前に、一回は“相談してみよう”と思える上司でいたい」。その言葉の通り、部下が辞めるときも必ず話をしてくれ、「この上司には最後まで誠実に向き合いたい」と思って去っていくのが常だったそうです。
離職は止めることだけが正解ではありません。むしろどう辞めていくか、辞め方が“きれいかどうか”で、その組織の本質が見えてくるのです。
退職代行を選ばせないために、普段から“言える空気”を作り、誠実な対話を心がける。これが、離職を最小限に抑えるための、上司・管理職としてのスキルです。
退職代行という出来事を、ただの「突然の退職」と受け止めるか、それとも“職場を進化させるきっかけ”と捉えるか。
それが、これからの組織の未来を分ける判断になります。苦しさの中にある学びに目を向けることで、よりよいチーム、より信頼される上司へと変わっていける。その第一歩は、「対話を恐れない」姿勢から始まります。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック