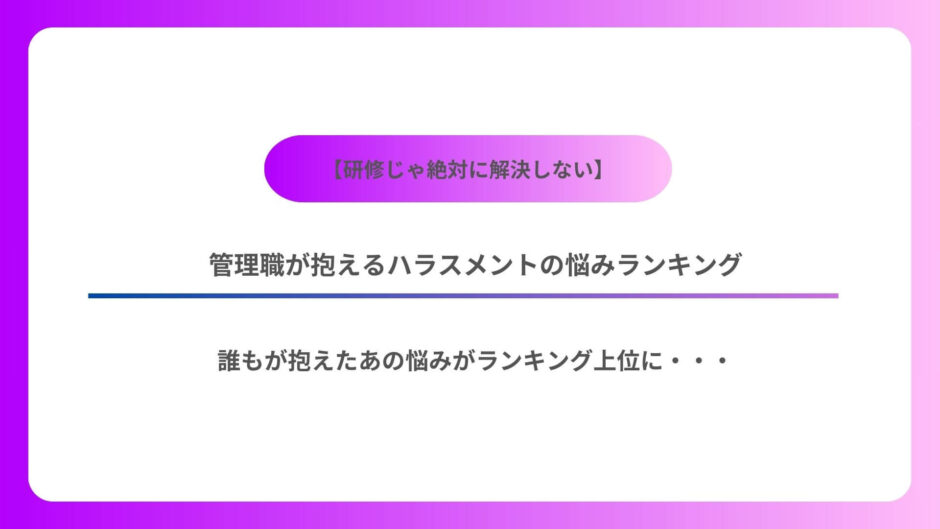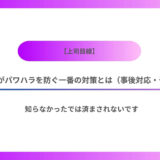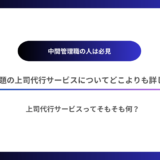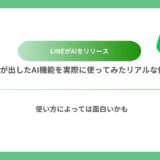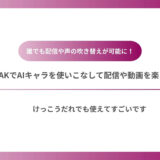皆さんこんにちは。株式会社プロストイックです。
今回のテーマも前回に続き「ハラスメント」です。最近かなり当社へ「ハラスメントの相談」が増えており、上司代行(中間管理職支援)の活用の幅も広がっています。
ハラスメント自体はかなりセンシティブな内容ですが、管理職だけではなく社会で働くひとであれば絶対に知っておくべき内容なので、今回は管理職が抱えるハラスメントの悩みをランキング形式で解説をします。
- パワハラをしてしまうリスクが(無意識的にも)ある管理職に着任している方
- 周囲でハラスメントの被害・加害が最近勃発している方
- 組織全体でハラスメントを事前に防ぎたい方
ちなみに前回執筆したこちらの記事も読まれております。
なぜ“研修だけ”ではハラスメントはなくならないのか?

多くの企業が「ハラスメント対策」として真っ先に導入するのが研修です。
eラーニングでの座学、定型パターンのケーススタディ、そして「やってはいけない言動」の確認――形としては整っています。しかし、それだけで職場から本当にパワハラがなくなるのでしょうか?答えはNOです。
(無論、研修を主動する人事・労務の方々も研修だけで全て解決するとは思っていないと存じます。ただ実情としてハラスメントをボトルネックから解決するのは様々な制約があり難しく研修という形にとどまっているのが大半かと)
現場の管理職や上司が感じている“本当の悩み”は、研修では触れられない領域にあります。
研修で提示されるのは理想的な対応ばかりで、現実の感情の揺れ、部下との微妙な距離感、成果を出さなければならない圧力――そういったリアルな葛藤に対する具体的な処方箋は、ほとんど提供されていません。
ここからは、「なぜ研修だけでは不十分なのか?」を掘り下げます。
実際の事例や管理職の本音に触れながら、対話ではなく一方通行で終わっている従来の対策の限界を明らかにしていきます。そして、「上司代行」のような新しい支援体制の必要性にも自然とつながっていきます。
ハラスメント研修をしても現場で何も変わらない3つの理由

企業でハラスメント研修を行っても、実際の職場での言動や関係性が変わらない――そう感じている管理職は少なくありません。その大きな原因は、研修が“実践の場”と切り離されているからです。
第一に、研修内容が「理想論」に終始している点があります。
たとえば、「感情的にならず冷静に指導を」と言われても、納期が迫り部下がミスを連発している状況で、感情を完全に切り離すのは非現実的です。パワハラはそうした“現場のテンション”の中で発生します。
第二に、研修後のフォローアップが機能していないこと。
研修で何かを学んでも、現場での行動変容につなげるには、継続的な支援やフィードバックが必要です。しかし多くの企業では、研修を“やったことにする”だけで終わってしまっています。
第三に、管理職や上司の「自分が悪者にされる恐れ」がある点です。
たとえば、研修で「部下に配慮を」と言われた一方で、「成果を上げろ」と現場では詰められる。こうした矛盾が、管理職を迷わせます。
上司代行の現場では、こうしたギャップを埋めるために、業務支援とマネジメント教育をセットで提供しています。つまり、実践に根ざした支援があってこそ、パワハラを防ぐ現場は動き出すのです。
管理職や上司が抱える“誰にも言えない”葛藤とは

パワハラを起こしたくて起こしている上司など、ほとんどいません。それでも、問題が起きてしまうのは、管理職自身が「言えない悩み」を抱えているからです。
たとえば、「部下を注意したいけど、パワハラと言われるのが怖い」「甘くなっても成果が出ないし、厳しくすれば不満が出る」。
このような板挟みの状況は、どこの職場にも存在します。あるIT企業の管理職は、部下との1on1のたびに“正しい言い方”を意識しすぎて、結局言いたいことを伝えられず、関係がギクシャクしてしまったという事例もあります。
こうした葛藤は、研修では扱われません。「感情を抑えて対応しよう」と言われても、人間である以上、完全に感情を切り離してマネジメントすることは不可能です。
むしろ、それを「言ってはいけない空気」が、さらに管理職を孤立させていきます。
だからこそ、現場で管理職が孤立しない体制が必要です。上司代行のような存在が、第三者的に支援に入ることで、管理職は“人として”の感情を持ちながらも冷静に対処する余裕を取り戻せます。
パワハラの予防には、管理職の“安心”が不可欠です。問題の根本には、「誰にも相談できない上司の孤独」が横たわっているのです。
本音と建前のギャップがハラスメントを温存する
研修で語られるのは「建前」です。
公平であれ、冷静であれ、感情的になるな――どれも正論に聞こえます。けれど、現場の「本音」はそんなにきれいごとでは片づきません。そこにあるギャップこそが、パワハラの温床になっています。
実際、ある人材系企業の現場では、「チームの目標達成が危ないから、多少厳しく接してでも引き上げたい」と思う上司と、「そんなふうに言われると追い詰められる」と感じる部下とのすれ違いが頻発していました。
上司としては“育てたい”気持ちで接していても、受け手にとっては“抑えつけられている”と映る。まさにこの感覚のズレが、事例となってパワハラに発展します。
そのズレを修正するには、建前だけを並べた研修ではなく、「実際の現場で起きていること」を冷静に分析し直す視点が必要です。
つまり、現場目線でマネジメントの“翻訳”をしてくれる存在が求められるのです。
ここで上司代行のような役割が活きてきます。建前ではなく、本音のぶつかる現場で、間に立って双方の意図をつなぎ直す。そうした支援があって初めて、パワハラの芽は摘まれるのです。
上司代行については本記事後半でも解説しています。関連する記事であればこちらも合わせてご確認ください。
管理職が抱える本音と、企業が求める建前。このギャップを埋める仕組みを持てるかどうかが、パワハラ防止の成否を分けるカギになります。
【ランキング】上司や管理職が本当に悩んでいるハラスメントランキング
表面的な研修やマニュアルでは見えてこない、現場の“生の声”。
管理職や上司が日々感じているプレッシャーや葛藤には、思った以上にリアルで深刻な悩みが詰まっています。
この記事では、上司・管理職向けのマネジメント支援を行っている現場から寄せられた声をもとに、「ハラスメントに関するリアルな悩みランキング」をご紹介します。
すべてが日々の業務の中で「今まさに起きている」ものばかりをランキング化しています。だからこそ、自分の職場や立場と重ね合わせながら読んでいただける内容です。
特に「パワハラ」や「上司代行」のようなキーワードで検索される方は、今まさに管理職として“壁”にぶつかっているのではないでしょうか。このランキングは、そうした悩みに対して「一人じゃない」と思えるヒントにもなるはずです。
このランキングを通じて知ってほしいことは「悩みの内容」「どう対処・対策しているのか」の2点です。
【第7位】部下のメンタル不調に“どう接していいかわからない”
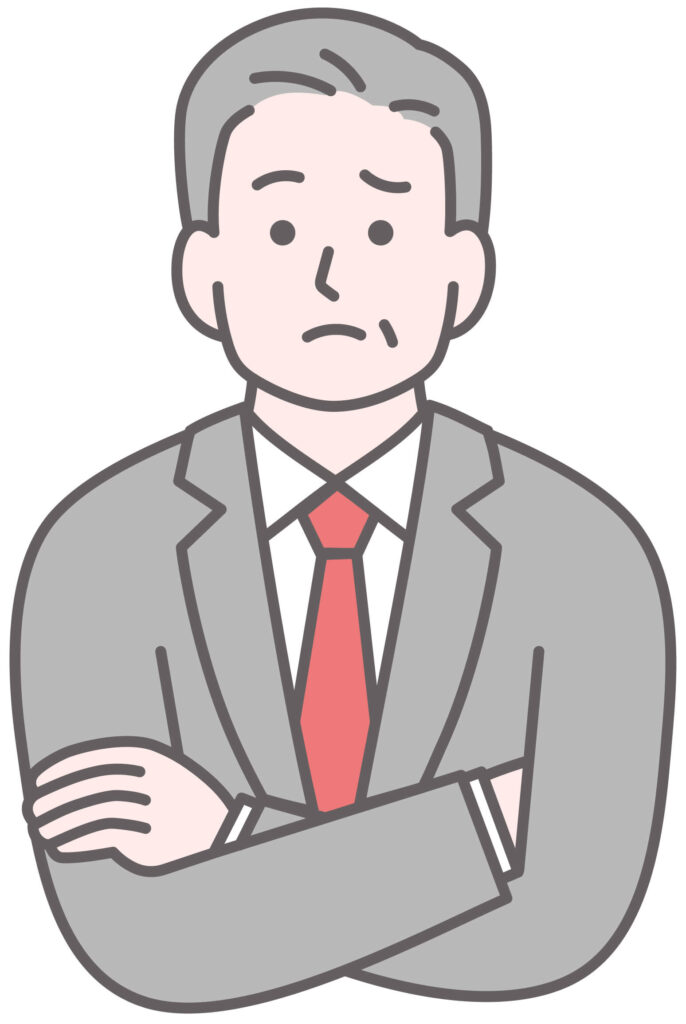
今、上司や管理職の間で最も増えている相談の一つが、「メンタル不調の部下への対応」です。
無理をさせてもダメ、干渉しすぎても逆効果。声をかけるべきか、そっとしておくべきか――その判断に悩む人は非常に多くいます。
ある企業では上司が気を遣って「仕事量を減らす」配慮をしたところ、逆に「干されている」と受け取られてしまい、人事を巻き込むトラブルになったという事例もあります。
(「じゃあ、どうすればええねん」という声も多いようです)
パワハラを避けようとしても、接し方ひとつで逆効果になるという難しさがあります。
こういった事案は人事・労務が対処すべきとの声がありますが、結局は現場の管理職が直接対応していることも多いのが現状です。
管理職の立場としては、業務の責任と人としての思いやりのバランスを取るのが非常に難しい。
上司代行サービスではこうした繊細な状況下での対応方法や、部下との間に立って調整する役割を担うことで、管理職の精神的負担を軽減しています。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
パワハラではなく“気遣い”として伝えるには言葉の選び方だけでなく、タイミングや背景の理解が不可欠です。その判断を一人で抱えるのではなく、組織として支える体制が求められています。
【第6位】管理職がやってしまいがちな部下への無言の圧力がハラスメント化

部下との関係がギクシャクしたなかで生まれる「無言の圧力」にもパワハラの火種は潜んでいます。特に部下と上司の関係がうまくいっていないケース(意見の対立や仕事の期待に届かない成果量)から生まれる“無言の圧力”が存在すると、非常に危険です。
ある事例では会議で反対意見を述べた部下に対して管理職が取った行動は以降業務上の相談一切しなくなったというケースが報告されました。
これは明確な言動がなくても、ハラスメントとして問題視される典型例です。上司と部下との関係性が悪化すると、チーム全体の風土にも悪影響を与えます。
こうした状況では当事者が「気づかないふり」をしてしまいがちです。
しかしそれこそが、パワハラが根を張っていく土壌になります。
上司代行を通じた外部支援の中ではこのような関係性の調整にも介入し、冷静な対話のきっかけをつくる取り組みが行われています。
管理職は孤立したときほど、立場を守ろうと攻撃的になりがちです。
だからこそ、上下という関係でなく”業務上における信頼関係”こそ今後のハラスメント防止の鍵になるのです。
【第5位】人事異動・査定など“権限行使”が誤解を招く
管理職という立場上、どうしても避けられないのが人事や査定に関わる判断です。
しかしこの“権限行使”が、意図しないパワハラと受け取られてしまうケースも後を絶ちません。
たとえば、組織体制の変更が根本的な背景ではありますが部下に部署異動を伝えた際に、部下が「自分に対する懲罰だ」と思い込み、メンタル不調に陥ったという事例があります。
実際には業務適性やチーム構成の問題も大きく人事異動を言い渡したのですが、説明の仕方や日頃の信頼関係によって、捉え方は大きく変わってしまいます。
特に、上司からの評価が直接昇進や処遇に反映される企業では、些細な発言も「査定に響くのでは」と部下が過敏に反応します。
(実際に管理職が評価・査定を決めるので査定の時期になると「スッと」大人しくなる部下もいるようです)
管理職の側にも緊張感があり、説明が不足してしまうと、それがパワハラと認定されるリスクにもつながります。
【第4位】ジェンダー・世代間の価値観の違いによるすれ違い(セクハラ事例)
パワハラの多くは、「悪気がなかった」という言葉から始まります。特にジェンダーや世代間の価値観の違いは、無自覚な言動を生み出しやすく、本人の意図とは裏腹にトラブルを引き起こす原因となっています。
たとえば、「女性だから家庭との両立を考えて配置を決めた」「最近の若い女の子は打たれ弱い」など、一見“配慮”のつもりでも、相手にとっては差別的・決めつけ的な発言と捉えられる場合があります。こうした発言が積み重なることで、信頼関係が崩れていくのです。
ある企業では、男性上司が「女性に夜遅い業務は任せられない」と発言し、当該社員から「チャンスを奪われた」と抗議を受け、ハラスメントに至ったこともあります。
(これは夜に仕事をさせなかったからではなく、「男女」という性別で業務を分類したことが問題だったということです。)
世代や性別の違いは、今や無関心では済まされないテーマです。
管理職がこうした多様性に対応するには個人の感覚だけで判断するのではなく、対話と仕組みで支える必要があります。
【第3位】人によって捉え方が違いすぎるコミュニケーション
続いては第3位です。第3位は「コミュニケーションのすれ違い」です。
同じ言葉でも人によって受け取り方はまったく異なります。これが、パワハラをめぐるトラブルで最も誤解が生まれやすいポイントです。
「それ、早くやってね」という指示がある人には普通でも、別の人(まだ関係値が築けていない人)には“急かされた”“責められた”と感じられることがあります。
つまり、言った側の意図ではなく、受け手の主観で判断されるのがパワハラの特徴なのです。
ある職場では指導的立場の上司が「もっとちゃんとやって」と言ったことが、部下にとっては人格否定と受け止められ、ハラスメントの相談にまで発展しました。(1回、2回ではなく慢性的な圧力に取れる言動が他にもあって)
この事例では上司が「そんなつもりじゃなかった」と反論しましたが、対応のまずさが事態を悪化させました。
コミュニケーションの“受け取り方の幅”をどう受け止めるかは管理職の重要な役割です。
上司代行では会話のログや部下の反応を定期的に分析し、「伝え方と受け取り方のズレ」を修正する支援も行っています。
パワハラを防ぐには言葉そのものよりも「どう受け取られるか」を軸にマネジメントを考える視点が不可欠です。
関係性は築くのは大変ですが、崩れるのは一瞬です。
上司代行(中間管理職)支援なら
プロストイックが実績No,1
【第2位】部下から“逆パワハラ”で訴えられそうな恐怖

続いては第2位です。近年、急増しているのが「逆パワハラ」の懸念です。部下が管理職に対して過度に“パワハラ”という言葉を使い、上司が指導や助言を躊躇してしまう――そんな現場が目立っています。
ある中堅企業では業務改善を求めた上司に対し、部下が「それってパワハラですよね?」と口頭で詰め寄り、社内調査が入った事例がありました。
結果的にはパワハラと認定されなかったものの上司はその後部下への指導を避けるようになり、チームの生産性は大きく下がったといいます。
(実際に「それってパワハラですよね?」と部下から詰め寄られる時点でもう関係性は大きく損なわれてしまっていて、修復するのが困難になってしまっています)。
こうした状況では管理職が“何も言えなくなる空気”に陥るリスクが高まります。
(実際に既に「もう怖くて何も指導できない」と心のなかで訴えている管理職・上司の方も多いです)
逆パワハラに怯えず、適切なマネジメントを続けるためには、「正しく指導する力」と「証拠を残す仕組み」がセットで必要です。(後半で対処法や事前防止策を解説)
【第1位】どこまでが指導?どこからがパワハラ?の線引き問題

そしていよいよ第1位です。
第1位はパワハラに関する管理職の最大の悩み、それは「指導」と「ハラスメント」の境界があまりにも曖昧だということです。
「これは厳しく言ったほうがいいのか?」「この指摘は嫌がられるのでは?」と自問自答しながら発言する上司がほとんどです。上司の方はどう伝えたらいいのか、本当に毎日悩んでいるのではないでしょうか。
ときには、その迷いが指導のタイミングを逃し、チーム全体のパフォーマンスにまで影響を与えることもあります。
たとえばある教育系企業では上司が何度も注意をためらい、ミスを繰り返す部下に対して適切な指導ができず、
最終的にクレーム対応までこじれてしまったという事例が報告されています。指導の“ブレーキ”が、別のリスクを招いたのです。
一方でその線を超えて指導してしまい、もう修復が不可能な関係になってしまった上司と部下もいます。
この線引きの不安を取り除くには、「これはパワハラに当たるのか」を一人で判断するのではなく、第三者の視点を入れてマネジメントをチューニングする体制が必要です。まさに、上司代行のような支援体制がそれを可能にします。
パワハラという言葉に怯えるのではなく、“伝えるべきことを、伝え方に工夫して届ける”――それが今、上司に求められるマネジメントの姿です。
いかがだったでしょうか。ここまでのランキングで上司・管理職の皆さんがこれまで感じたこと、今も抱えているお悩みはありましたか?
皆さんが抱えているお悩みは実際に他の上司や管理職の方も抱えている悩みなことが多いです。
しかし悩みを抱えているだけでは問題が慢性化するし、事後対応では時はすでに遅いので、どうハラスメントを上司や管理職の方が予防すべきなのかをお伝えします。
上司・管理職が今日からできる!パワハラ予防の対策アクション
パワハラを防ぐためには、特別な制度改革や大がかりな研修だけでは不十分です。
むしろ日々のコミュニケーションや行動の中にこそ、改善できるヒントが詰まっています。
実際、深刻な事例に至る前に、小さな気づきと行動で“予防”できたケースは数多く存在します。
ほんとうに予防できることは多いです。ただ「変にムキになったり」「間違った対応方法」を取ってしまうことで問題がよりひどくなるケースが跡を絶ちません。
このパートでは、上司や管理職が「今日からすぐに取り入れられる」具体的なアクションを取り上げます。難しいことではありません。ただ少し視点を変えるだけで、職場の空気はぐっと変わります。
パワハラという言葉に敏感になる前に、信頼を築ける言動ができているか。上司代行の支援現場でも推奨されている基本のアプローチを、今あらためて見直していきましょう。
1on1や面談で「相手視点」を意識する管理職の会話術
1on1や面談はパワハラ予防の最前線です。既に多くの企業で上司や管理職と部下が1on1を導入しています。
(そもそもまだ「1on1すらできていない」、「忙しくて時間が取れない」、「あの子とはやってもムダだから」というのは問題から目を背けている典型例です。
とはいえ、ただ「時間を取ればいい」というものではありません。
重要なのは、上司が“話す”のではなく、相手の話を“引き出す”ことに主眼を置くことです。
たとえば、ある企業では、1on1で上司が「業務の進捗どう?」とだけ聞いて終わらせていたところ、部下は「自分の意見を言う場じゃない」と思い込み、心理的距離が縮まらなかったという事例がありました。ここで重要なのは、問いの立て方と、沈黙に耐える姿勢です。
「最近、気になってることはある?」「困ってることがあればどんなことでも言っていいよ」といったオープンな問いを投げかけ、じっくり相手に話してもらう。これが、信頼を深める会話術の基本です。
またここで注意なのがプライベートの話に踏み込むのかどうかです。相手との距離感を掴むのが苦手な上司な方はいきなりプライベートな話からはいってしまいがちですが、逆に距離感が遠のいてしまうのでやめてください。
(ここは感覚的な部分もあるので、線引が難しいですがまだ関係値ができていない場合、プライベートな話をする合図は「相手(部下)がしてきたら」自分も話すのを心がけましょう。
自分からいきなりプライベートな話をしても相手も同じ話に乗っかってよというのはあ受け手側からすればかなり横暴ですし、いきなり自分のパーソナルスペースに入られたような感覚になります)
上司代行でも、1on1での“相手主導”を強く推奨しています。管理職がパワハラを避けるには、まず部下の心の動きを言葉として引き出す力が必要です。それは、会話のテクニックではなく、相手を尊重する姿勢の表れでもあります。
相手の受け取り方を基準にするコミュニケーション法
上司や管理職が意識している以上に、部下は言葉や態度に敏感です。
なぜなら、力関係がある以上、上司の発言には“評価や処遇につながる圧力”が無意識に含まれてしまうからです。
(部下目線で言えばいい意味でも悪い意味でも上司・管理職は「権力」を持っているということです
そのため、指導やフィードバックの場面では、「自分が何を言ったか」ではなく「相手がどう受け取ったか」を基準に考えることが不可欠です。
たとえば、「もっと頑張ってくれ」と伝えたつもりの上司が、部下から「追い詰められた」と感じられたという事例は決して珍しくありません。言葉そのものではなく、言い方・場面・関係性の文脈によって印象は大きく変わります。
上司代行の現場でも、「発言の受け取り方」についてのアドバイスやフィードバックが多く寄せられます。これは、管理職が持っている“つもり”と、部下が受け取っている“実感”のズレが、ハラスメントの温床になっている証拠でもあります。
伝える力よりも、届いているかどうかを確認する力。これこそが、パワハラを未然に防ぐための管理職の基本姿勢なのです。
ハラスメントを“未然に防ぐ”ために管理職すべき習慣術
パワハラが問題化したとき「なぜもっと早く気づけなかったのか」と振り返る場面は多くあります。
ですが実際には、その“予兆”は日常の中に存在していたはずなのです。ただ、それを見落としてしまうのが現場のリアルであり、忙しさやプレッシャーに飲まれやすい管理職の現実です。
だからこそ、重要なのは「起きてからの対応」ではなく、「起きる前の対策」です。
つまり、日々のコミュニケーションや働きかけの中に、パワハラを未然に防ぐ視点を組み込んでおく必要があります。
このパートでは、上司や管理職が今日から意識すべき“予防のための行動”を整理して紹介します。パワハラ、上司代行、事例などのキーワードが示す通り、問題の芽は日常に潜み、そして日常の工夫や習慣によってこそ防ぐことができるのです。
管理職自身の言動をチェックする“モニタリング習慣”
管理職が「自分の言動がどう見えているか」を客観的に振り返る習慣はパワハラ予防に極めて有効です。
というのも、パワハラの多くは“意図しない加害”として起きており、本人にとっては「普通の指導」でも、相手には「精神的圧力」に映ることが多いからです。
ある企業では、週1回「上司セルフチェックシート」を記入する取り組みを導入しました(一旦1ヶ月のみ)。
結果、「言いすぎたかも」「あの言い方は強かったかもしれない」といった気づきが増え、部下との関係が改善されたという報告があります。
特にプレッシャーがかかる局面では知らず知らずのうちに言動が強くなりがちです。だからこそ、「今日は自分がどんな言葉を使ったか」「どんな空気を作ったか」をモニタリングする習慣が、パワハラの芽を摘み取るために重要なのです。
上司代行では、こうしたセルフチェックの習慣化に加えて、客観的なフィードバックを管理職に提供する仕組みも取りいれておりマネジメントをゼロベースから見直す取り組みを行っています。
ハラスメントの「予兆」に気づける習慣を身につける
パワハラが顕在化する前には必ず「小さな違和感」や「予兆」があります。
たとえば、部下の発言が少なくなる、報告の頻度が減る、いつもより表情が乏しい――そうした変化に気づけるかどうかが、管理職の真価を問われる場面です。
ある企業のケースでは部下の様子が明らかに変わったにもかかわらず、「忙しいから後回し」にされ、結果的に休職にまで至ったという事例がありました。上司は「気づいてはいたけど、あえて触れなかった」と後悔を語っています。
このような“予兆”は、行動の中だけでなく、チーム全体の雰囲気や雑談の端々にも表れます。だからこそ、管理職は「気づく目」を養う必要があります。それは特別なスキルではなく、日々の観察と小さな声に耳を傾ける姿勢です。
上司代行では、部下の心理的安全性を高めるために、こうした「変化に気づくための習慣」を仕組みとして組み込む支援を行っています。パワハラは、いきなり起きるのではなく、予兆の蓄積で発生します。それに気づけるかどうかが、未来を左右するのです。
上司・人事と連携し、“一人で抱え込まない”環境を整える
管理職が最もハラスメントに近づく瞬間とは、「一人で抱え込んだとき」です。
部下とのトラブル、評価に対する不満、言葉の行き違い――こうした状況を、周囲に相談できず、独断で判断した結果、問題が悪化してしまうことが少なくありません。
ある中規模の企業では、部下からのクレームに対して上司が単独で対応し続けた結果、情報が歪んだまま上層部に伝わり、事実と異なるパワハラ認定がされたという事例がありました。もしこのとき、早期に人事や他の上司と連携していれば、異なる結末になったはずです。
管理職は孤独になりがちです。特に、実力主義や成果主義の文化が強い職場では、「弱音を吐けない空気」が強くなります。
だからこそ、「共有できる場」と「相談できる相手」を職場の仕組みとして持つことが、パワハラを防ぐセーフティネットとなります。
上司代行がその役割を果たす場面も増えてきています。外部から中立的な視点を提供することで、判断の精度を上げ、抱え込みによる誤判断を未然に防ぐ。そうした支援の仕組みは、管理職にとっての“見えない味方”になるのです。
形式的な研修から脱却!本当に機能する仕組みづくりへ
ここまで、上司や管理職が抱えるパワハラに関するリアルな悩みや、その背景にある構造、さらには“未然に防ぐ行動”について紹介してきました。そして浮かび上がるのが、「形式的な研修では、限界がある」という事実です。
多くの企業が年に一度、もしくは新任管理職向けに実施しているハラスメント研修。しかし、その多くが「座って受けるだけ」「聞き流すだけ」で終わっているのが実態ではないでしょうか。
パワハラがなくならないのは、意識の問題ではなく、“習慣や仕組み”の部分が手つかずだからです。
このパートでは、「本当に意味のある仕組みとは何か?」に焦点を当て、研修のあり方と支援体制の見直しについて具体的に触れていきます。上司や管理職の立場を「個人の責任」にせず、組織全体で支えるにはどうするべきか――ここからが、真の対策のスタートです。
ハラスメントを「自分ごと」にする継続型研修のススメ
研修でありがちなのが、「一度受けたら終わり」「義務として済ませるだけ」という形式的な取り組みです。しかしパワハラを本当に防ぐには、管理職自身が「これは自分にも起こりうること」と捉えられる、“自分ごと化”が不可欠です。
ある企業では月に1回15分のミニ研修をオンラインで実施し、過去の社内事例をもとに短く議論する取り組みを導入しました。すると、受講者の「自分の言動を振り返る回数が増えた」というフィードバックが多く寄せられ、社内の相談件数も早期段階で増加――つまり、トラブルの芽が早く表面化するようになったのです。
このように、“量より継続”のスタイルであれば研修形式においてもパワハラの防止においては効果的です。(ただ、問題はこの研修をする時間を継続的に取れないということです)
管理職が忙しい中でも負担なく続けられる形式を工夫し、「知る」→「気づく」→「行動が変わる」のサイクルをつくることが重要です。
上司代行による支援の中でも、こうした継続型の教育プログラムを導入する企業が増えており、現場の言動が確実に変わり始めています。研修は“一度きりのイベント”ではなく、“変化を起こす仕組み”として再構築する必要があるのです。
実例ベースで議論するケーススタディ型研修とは?
パワハラ研修で多くの管理職が口にするのが、「内容が現場とずれている」「リアリティがない」といった声です。これは、理想論や抽象論だけが先行し、実際にどう動けばよいのかが見えないことが原因です。だからこそ、現場の声に根ざした「ケーススタディ型研修」が注目されています。
たとえば、実際に自社や業界内で発生したパワハラ事例を匿名で紹介し、その上で「なぜ起きたのか」「どう防げたのか」を複数の視点から議論する形式。これにより、“正解を教える”のではなく、“考える力を育てる”ことができ、研修への納得度も高まります。
ある企業では、ケーススタディ形式の研修を通じて、「部下がなぜ傷ついたのか」を具体的に理解できたという上司が増え、実際の会話やフィードバックが格段に柔らかくなったという変化が報告されています。
また、上司代行の支援現場でも、こうした事例ベースのディスカッションを導入しており、「マニュアルには載っていない、リアルな判断力」を育てる取り組みが進んでいます。現実の職場で迷わず行動できる力をつけるには、“現実の事例”こそ最高の教材なのです。
上司代行(管理職支援)を活用することで管理職への属人化を防ぐ
どれだけ研修を行っても、どれだけ意識を高めても、最終的にすべてを“個人の判断と責任”に任せてしまっては限界があります。特に中間管理職のポジションは、プレッシャーの割に孤立しやすく、属人化によるリスクが高くなりがちです。
そこで有効なのが、上司代行という仕組みを活用し、マネジメントの一部を「外から見える体制」に変えることです。
上司代行とは管理職が本来すべき業務に集中できる体制を構築してマネジメントやプレイヤー実務を完備する仕組みで、大手企業・組織を中心に導入が広がっています。
上司代行についての詳しい解説はこちら
たとえば、部下との1on1や、評価面談の場に“もう一人の視点”として上司代行が関与することで、判断が偏らず、パワハラのリスクも下がります。ある企業ではチーム体制の見直しを上司代行と連携して行った結果、部下の満足度と上司の精神的負担の両方が改善されました。
パワハラは知識だけでは防げません。支援の仕組みと、人に頼れる環境を作ることが必要です。属人化しないマネジメント体制を持つことは、これからの組織にとっての“安全装置”となります。
 株式会社プロストイック
株式会社プロストイック